オルガン男さんにボリュームの分解清掃のやり方についてコメントをいただきました。コメント欄に返信を書いていたのですが、妙に長い文章になってしまったので、こちらに新規投稿という形でカキコ。
ボリュームのガリは、古いモデルでは必ずといっていいほど発生します。どのような方法がベストかはわかりませんが、私の自己流清掃方法は以下のとおり。
A 完全に分解できるタイプのもの(基本の清掃方法)
1 アルコールに浸した綿棒で扇動子とカーボン面を清掃
2 カーボン面にタミヤの接点グリス 塗布
塗布
B ある程度までしか分解できないタイプのもの
1 アルコールに浸した綿棒でカーボン面を清掃
2 扇動子とカーボンの隙間にアルコールで濡らした紙を挿し込み、これを前後にスライドさせて扇動子の汚れを溶かす
3 更に乾いた紙で同じ事を繰り返し、汚れを取り除く
4 カーボン面に接点グリス塗布
C 全く分解できないタイプのもの&分解するのが面倒くさいタイプのもの
1 隙間からエレクトロニッククリーナー を噴射、シャフトをグリグリ回転。
を噴射、シャフトをグリグリ回転。
2 隙間から接点復活剤 を少量噴射、シャフトをグリグリ回転。
を少量噴射、シャフトをグリグリ回転。
3 最後にエアダスターで余分な接点復活剤を除去(接点復活剤は揮発性が全く無いため)。
以上のことをやってもガリが取れない場合、超音波洗浄器 にぶち込むという荒業もやったことがあります。
にぶち込むという荒業もやったことがあります。
ちなみに自分はカーボン面に鉛筆の芯(これもカーボン)を塗るってことはやってません。あれ、プラグ等の動かさない部分には有効かも知れませんが、ボリューム等のスライドする部分では塗りムラが心配ですし、また、芯粉が定着せず扇動子で削れてしまうからです。
ご参考になりましたでしょうか・・・・?
ボリュームのガリは、古いモデルでは必ずといっていいほど発生します。どのような方法がベストかはわかりませんが、私の自己流清掃方法は以下のとおり。
A 完全に分解できるタイプのもの(基本の清掃方法)
1 アルコールに浸した綿棒で扇動子とカーボン面を清掃
2 カーボン面にタミヤの接点グリス
B ある程度までしか分解できないタイプのもの
1 アルコールに浸した綿棒でカーボン面を清掃
2 扇動子とカーボンの隙間にアルコールで濡らした紙を挿し込み、これを前後にスライドさせて扇動子の汚れを溶かす
3 更に乾いた紙で同じ事を繰り返し、汚れを取り除く
4 カーボン面に接点グリス塗布
C 全く分解できないタイプのもの&分解するのが面倒くさいタイプのもの
1 隙間からエレクトロニッククリーナー
2 隙間から接点復活剤
3 最後にエアダスターで余分な接点復活剤を除去(接点復活剤は揮発性が全く無いため)。
以上のことをやってもガリが取れない場合、超音波洗浄器
ちなみに自分はカーボン面に鉛筆の芯(これもカーボン)を塗るってことはやってません。あれ、プラグ等の動かさない部分には有効かも知れませんが、ボリューム等のスライドする部分では塗りムラが心配ですし、また、芯粉が定着せず扇動子で削れてしまうからです。
ご参考になりましたでしょうか・・・・?

















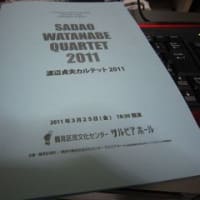

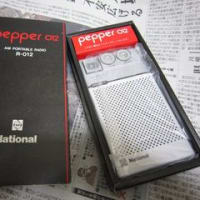

参考にさせて頂きます。ありがとうございます。
接点グリス、エレクトロニックスプレー等、自分に道具が欠如しておりました。
早速手配してみます。
鉛筆芯のムラの件、言われて見ればその通りですね。
東芝Walkyチューナーパック付
恐らく初代Walkyだったのではないですか?
当方も先日から初代カセットボーイと格闘中ですが自分の低レベルでは難しくかなり苦戦してます…
拝見させて頂いたところWalkyのメカの方がシンプルに仕上げていて良いですね。
この手の初代物もでかくて格好良いと思いますいます。
コンデンサ交換、メカ調整などフルオーバーホール並みにやることが沢山ありますが
後継機を見るにつけ、
進化の過程が垣間見えて大変興味深いです。
今回のWalkyはかなりでかいんですが、自分はこういうタイプのほうが好きなんです。ガム電池以降のやつには思い入れがなくて・・・しかし、修理っていう点ではガム電池タイプのほうがやり甲斐ありそうですね。F707、お疲れ様でした。カッコイイですね、あの機種。
また最初は両耳聞こえていたのに突然左チャンネルが全く聞こえなくなりました。。。
手持ちのコンデンサを使って交換しましたが
100uf3つのコンデンサあたりが原因でしょうか?
F707~格好良さが分かって頂き大変嬉しいです。
色々つぃ安いと言って薄型のヘッドホンステレオも買ってしまぃますが、個人的には
F707はウォークマン至上最後?の格好良いデザインのモデルだと思います。
左チャンネルの音が全く出なくなったということですが、こういうトラブルの場合、原因がコンデンサである可能性は少ないと思います(ゼロではありませんが)
セラミックイヤホン(ゲルマニウムラジオなんかで使うやつ。クリスタルイヤホンともいう)で信号がどこで途切れているかを確認するのも手です。拙ブログの「National RX-1830」もこれで故障箇所を特定しました。ご参考までに。
カセットボーイ記事にしてみたので宜しければチェックお願いします。。。