前回KX-640の記事をアップしましたが、あれは引っ越し前のブログ(FC2。現在は閉鎖)に今年5月に書いたものの再アップバージョンでした。で、その後数カ月も放置していたこのKX-640ですが、昨日から修理を再開。
手順としては、1.コントロール系の修理、2.ディスプレイの修理、3.各種調整です。

コントロール系がダメダメなのはタクトスイッチの劣化がまず疑われます。んで、全て取り外し。
通常ならば新品交換するところですが、生憎この2本足タクトは手持ちがありません。今から通販してもモノが届くのは年明けになってしまうので、取り外したタクトを私が独自に開発(大袈裟)したリフレッシュ方法で再生することにしました。
手順はとても簡単。サルキャン(猿でもできる)です。
1.タクトをクリンボーイまみれにする。
2.数時間後、超音波洗浄機でクリンボーイを除去する。
3.今度は接点復活剤まみれにする。
4.再度、超音波洗浄機にかけ接点復活剤を除去する。
5.エアスプレーでタクト内部の水分を吹き飛ばす。
6.自然乾燥させる。

(注)料理ブログではありません。
このリフレッシュ大作戦により、見事タクトスイッチ復活!基板に取り付けたところ、ストレスなくコントロールできるようになりました。YATTANE!!
さあ、調子が出てまいりました。お次はディスプレイだ!!

あれ、なんか焦げてる・・・

ディスプレイ不点灯の理由は麦球のタマ切れ。かなり熱を発するんですねー。煤で黒くなっていました。私のアタマもこのくらい黒いといいのですが・・・

麦球はどうしてもタマ切れしてしまうので、一瞬、LEDに交換しようかなと思いましたが、電源がACなので整流回路が必要。自作するのもメンドーなので、ここは素直に麦球を使います。手持ちのリード線付12V麦球を取り付け。しかしどうも輝度が足りません。テスタで電源電圧を測ったところ、AC7Vちょいだったので耐圧8Vの麦球に変更します。

リード線が付いてない麦球でしたので、取り付けが超メンドーでした。ちなみに8Vの麦球にすると明るさはアップしますが耐久性は12Vに劣ります。

点灯式。おー明るい。
最後に天板以外を組み上げ、テストテープを使って各種調整。まずはテープパスから。

問題ありません。まあ今回はピンチローラー交換等はしてませんから当然っちゃー当然。
はい次。テープスピードとアジマス調整。

スピードがちょっと速かったのでモーター裏の半固定ボリュームをグリグリ。アジマスもヤバいほど狂ってましたので、写真のようにリサージュが右肩上がりになるよう調整しました。ちなみに私はオシロスコープを持っていませんので、efu様が作成した超有名フリーソフト「Wave Spectra」を使わせていただいております。非常に便利。efu様、ありがとうございます。

左右の再生バランスが若干ずれていましたので、再生AMPの半固定ボリュームを弄ります。この機種は基板に各部品の機能が記載されているのでありがたいです。

仕上げとして、CDを録再してみて音質に問題がないか確認します。一緒に写っているのはポータブルCDプレーヤーの1号機、ソニーのD-50(希少)。

はい修理完了。パチパチパチ。
修理が終了しましたので、また放置プレイです。この機種はそーゆー運命にあるのです。グッとくるものがないとウチのメインシステムにはなりえません。アデュー。
手順としては、1.コントロール系の修理、2.ディスプレイの修理、3.各種調整です。

コントロール系がダメダメなのはタクトスイッチの劣化がまず疑われます。んで、全て取り外し。
通常ならば新品交換するところですが、生憎この2本足タクトは手持ちがありません。今から通販してもモノが届くのは年明けになってしまうので、取り外したタクトを私が独自に開発(大袈裟)したリフレッシュ方法で再生することにしました。
手順はとても簡単。サルキャン(猿でもできる)です。
1.タクトをクリンボーイまみれにする。
2.数時間後、超音波洗浄機でクリンボーイを除去する。
3.今度は接点復活剤まみれにする。
4.再度、超音波洗浄機にかけ接点復活剤を除去する。
5.エアスプレーでタクト内部の水分を吹き飛ばす。
6.自然乾燥させる。

(注)料理ブログではありません。
このリフレッシュ大作戦により、見事タクトスイッチ復活!基板に取り付けたところ、ストレスなくコントロールできるようになりました。YATTANE!!
さあ、調子が出てまいりました。お次はディスプレイだ!!

あれ、なんか焦げてる・・・

ディスプレイ不点灯の理由は麦球のタマ切れ。かなり熱を発するんですねー。煤で黒くなっていました。私のアタマもこのくらい黒いといいのですが・・・

麦球はどうしてもタマ切れしてしまうので、一瞬、LEDに交換しようかなと思いましたが、電源がACなので整流回路が必要。自作するのもメンドーなので、ここは素直に麦球を使います。手持ちのリード線付12V麦球を取り付け。しかしどうも輝度が足りません。テスタで電源電圧を測ったところ、AC7Vちょいだったので耐圧8Vの麦球に変更します。

リード線が付いてない麦球でしたので、取り付けが超メンドーでした。ちなみに8Vの麦球にすると明るさはアップしますが耐久性は12Vに劣ります。

点灯式。おー明るい。
最後に天板以外を組み上げ、テストテープを使って各種調整。まずはテープパスから。

問題ありません。まあ今回はピンチローラー交換等はしてませんから当然っちゃー当然。
はい次。テープスピードとアジマス調整。

スピードがちょっと速かったのでモーター裏の半固定ボリュームをグリグリ。アジマスもヤバいほど狂ってましたので、写真のようにリサージュが右肩上がりになるよう調整しました。ちなみに私はオシロスコープを持っていませんので、efu様が作成した超有名フリーソフト「Wave Spectra」を使わせていただいております。非常に便利。efu様、ありがとうございます。

左右の再生バランスが若干ずれていましたので、再生AMPの半固定ボリュームを弄ります。この機種は基板に各部品の機能が記載されているのでありがたいです。

仕上げとして、CDを録再してみて音質に問題がないか確認します。一緒に写っているのはポータブルCDプレーヤーの1号機、ソニーのD-50(希少)。

はい修理完了。パチパチパチ。
修理が終了しましたので、また放置プレイです。この機種はそーゆー運命にあるのです。グッとくるものがないとウチのメインシステムにはなりえません。アデュー。

















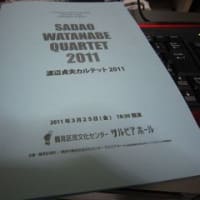

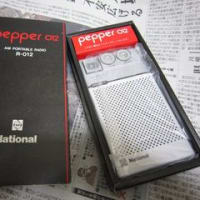






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます