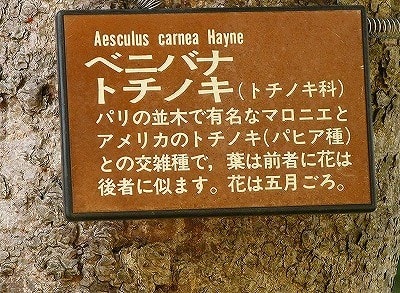2024年版 渡辺松男研究29まとめ(2015年7月実施)
【陰陽石】『寒気氾濫』(1997年)100頁~
参加者:S・I、M・S、渡部慧子、鹿取未放
レポーター:渡部 慧子 司会と記録:鹿取 未放
237 ささやきのごとくに若葉揺れあいて樹々の秘密はあかるかりけり
(レポート)
揺れあいの原因の風については描かれておらず、そこに作者や「揺れあい」の相手が考えられる。「ささやき」「秘密」「あかるかりけり」と言葉を繋いで、作者の回想に落ち着いているのは若やかな恋を思ってのことだろう。(慧子)
(当日意見)
★何か希望のあるようなおしゃれな感じですね。(S・I)
★さりげない歌ですが、随分あまやかですね。若い二人を取り巻いて若葉がささやきの
ように揺れているという。〈われ〉らの恋だけではなく、樹々そのものの存在の秘密
がなんかあっけらかんとむき出しになっているような面白さを感じたのでしょうか。
助動詞「けり」は 過去の他に詠嘆をもあらわすので明るい事よ、と現在の詠嘆か
もしれませんね。(鹿取)
【陰陽石】『寒気氾濫』(1997年)100頁~
参加者:S・I、M・S、渡部慧子、鹿取未放
レポーター:渡部 慧子 司会と記録:鹿取 未放
237 ささやきのごとくに若葉揺れあいて樹々の秘密はあかるかりけり
(レポート)
揺れあいの原因の風については描かれておらず、そこに作者や「揺れあい」の相手が考えられる。「ささやき」「秘密」「あかるかりけり」と言葉を繋いで、作者の回想に落ち着いているのは若やかな恋を思ってのことだろう。(慧子)
(当日意見)
★何か希望のあるようなおしゃれな感じですね。(S・I)
★さりげない歌ですが、随分あまやかですね。若い二人を取り巻いて若葉がささやきの
ように揺れているという。〈われ〉らの恋だけではなく、樹々そのものの存在の秘密
がなんかあっけらかんとむき出しになっているような面白さを感じたのでしょうか。
助動詞「けり」は 過去の他に詠嘆をもあらわすので明るい事よ、と現在の詠嘆か
もしれませんね。(鹿取)