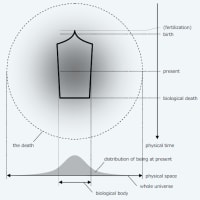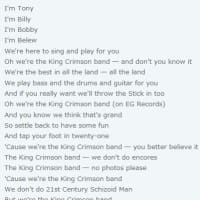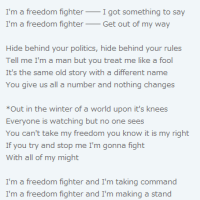第8章 人権(human rights)
8-5 言論の自由の権利
絶対的な消極的権利の最小リストを作ることができると言った。その議論を導くために、基本的な消極的権利、言論・表現の自由ということがあらゆる人権の理論によって一般に合意されているものかどうかを確認してみようと思う。この議論はわたしにとって消極的な権利と積極的な権利の区別を明確にすることを可能にするものでもある。なぜ社会は言論の自由を認める(grant)べきなのか?わたしには、言論の自由についてなされている現実の主張は嫌になるほど弱いものだと思える。ふたつの型の主張がある。ひとつは言論の自由は神様から授かりしものであり、したがって尊いものでなければならないというものである。もうひとつは、言論の自由は功利主義的な基礎のもとで正当化されるというものである。後者の立場からなされた最も有名な文書はミルの「自由論*」である。
ところで、合衆国における権利についての議論で奇妙なのは、それらがしばしば問題の憲法の条文を示すことで端折られてしまいがちだということである。だから多くのアメリカ人にとって言論の自由の正当化ということは憲法修正第一条で保証された権利だという、ただそれだけのことになってしまっている。何が議論か、世も末(end of discussion)である。ドレイ制度の何が間違っているのか、それは修正第十三条に反する、それだけだと言わぬばかりである。もしもこれらの議論の目的が、いずれの場合においても問題の権利についての適切な正当化は存在しないということなのだとしたら、と仮定してみる。それは合衆国における権利の議論を端折ることができて政治的に有用だということなのかもしれない。だがそれは哲学を満たすものではない。神の権威に訴えることについても同じことが言える。権利が授かった地位機能の形態ならば、それらは合理的な基礎のもとに正当化されなければならない。今からわたしは言論の自由についてその正当化を確認してみる。
権利の功利主義的な正当化は嫌になるほど不適切なものである。特に言論の自由の場合は、これ以上ひどいものはないくらいである。もしわたしの言論の自由の権利が、わたしが言論の自由を行使することが最大多数の最大幸福を導く(conduce)という事実から導かれるものだとしたら、その権利の存在と行使はまったく最大多数の最大幸福という特定の事実に依存することになる。その場合、わたしが言論の自由を行使することによって最大多数の最大幸福をもたらさないなら──たとえばそれが、わたしの属する共同体の成員にとって胸糞の悪い、乱暴な言い草であるような場合、わたしは言論の自由を失う[左様ナ事ヲ言ッテハナラヌ]ということになる。それはバカ気た結論であり、そういうことになってしまう理論は何かが間違っているのでなければならない。
さらに、規則功利主義(rule utilitarianism)に訴えたとしてもその理論を救跋することはできない。功利主義的な正当化の標準的な規則の場合を考えてみればわかる。わたしが一般的な功利主義者ないし帰結主義(consequentialist)の立場に立って一日に2回歯を磨くという規則に従っているとする。つまりわたしは日に2回歯を磨く方がましだ(better off)と思っているということである。しかし何らかの特別な理由で、わたしの歯にカタストロフィックな帰結が生じたとしたら(たとえばわたしの歯が突然放射能を帯びて、歯を磨いたら街ごと吹っ飛んでしまうとか)、歯を磨くべしの規則を求める独立した強制力は何もないことになる。守るべきはわたしの歯なのか、この街なのか、功利主義的な究極の選択になってしまう。規則は独立した強制力を持っていない。以上は単に慣習(habitual)功利主義者の優勢のパタンを要約しただけである。
標準的に、功利主義者はこうした種類の反論に対してふたつの答を持っている。ひとつは、あなたは規則に反したことを行った場合の帰結を知ることはできないというものである。したがって全体として功利主義的正当化をもつようなあらゆる規則を守っているという推定が存在しなければならない。たとえそれが、言論の自由を行使すれば功利主義的によからぬ帰結が生じるような気がしたとしても、そんなことはわかりっこないのだということである。わたしはこれを認識論説(epistemic argument)と呼ぶことにしよう。功利主義者の唱える説のふたつ目は、やはりわたしが信用説(trust argument)と呼んでいるものである。人々に言論の自由を与えるとか、そういう規則は、人々がそうした規則は尊重されるべきだと思って信用している場合にのみ機能するという説である。そうすることが不愉快な(repulsive)ことだと思える場合は、言論の自由を認める規則に従えないなら、その規則に対する信用は弱まるのである。規則に対して功利主義的な信用を重視することには、規則がある特別な場合に反故にされるべきか否かを考慮に入れることが追加されなければならない。
要はどっちも不適切なのである。認識論説に対してはこう答える。認識論的な状況が完全であって、その帰結がどうなるかわかっているような場合を想像してみるだけでよい。そのような場合は、認識論説を法的な認可によって防ぐ(block)ことになる。認識論説の不適切は認識論的な困難がない、つまり認識論的に完璧な知識を持つような場合を想像してみる思考実験によって示される。そのような場合、わたしの言論の自由の権利はとかくのことがあっても影響は受けない。言論の自由ということの要は認識論的なものではないのである。信用説は、これもやはり弱いものである。その主張は、わたしの言論の自由の権利は、わたしがそれを攻撃的に行使する場合、権利を廃することは原則に対する信用を弱めるであろうという事実によって維持されるというものである。しかし、それは権利をある疑わしい経験的な仮説次第のことにしてしまう。その仮説というのは、覆されうる原則はそれを弱めるだろうということである。だがそうならないとしたらどうなのだろう?認識論説の場合のように、法的な認可の場合を考えてみればよい。いずれの説も弱点は同じである。その権利の、まさにその存在が欲望によらない行為理由である場合には破綻してしまうし、それを欲望によらないものにする特徴はまた功利主義や帰結主義と無関係なものにしてしまうということである。手短に言えば、これらの説は権利に対していかなる独立した地位を与えることもできないし、それゆえに権利を権利として認めることもできないのである。
このように、規則功利主義は、功利主義をその明白な弱点から救跋するには不適切な努力である。
(つづく)
8-5 言論の自由の権利
絶対的な消極的権利の最小リストを作ることができると言った。その議論を導くために、基本的な消極的権利、言論・表現の自由ということがあらゆる人権の理論によって一般に合意されているものかどうかを確認してみようと思う。この議論はわたしにとって消極的な権利と積極的な権利の区別を明確にすることを可能にするものでもある。なぜ社会は言論の自由を認める(grant)べきなのか?わたしには、言論の自由についてなされている現実の主張は嫌になるほど弱いものだと思える。ふたつの型の主張がある。ひとつは言論の自由は神様から授かりしものであり、したがって尊いものでなければならないというものである。もうひとつは、言論の自由は功利主義的な基礎のもとで正当化されるというものである。後者の立場からなされた最も有名な文書はミルの「自由論*」である。
| * | Mill, John Stuart, On Liberty and Other Essays, New York: Oxford University Press, 1998. |
ところで、合衆国における権利についての議論で奇妙なのは、それらがしばしば問題の憲法の条文を示すことで端折られてしまいがちだということである。だから多くのアメリカ人にとって言論の自由の正当化ということは憲法修正第一条で保証された権利だという、ただそれだけのことになってしまっている。何が議論か、世も末(end of discussion)である。ドレイ制度の何が間違っているのか、それは修正第十三条に反する、それだけだと言わぬばかりである。もしもこれらの議論の目的が、いずれの場合においても問題の権利についての適切な正当化は存在しないということなのだとしたら、と仮定してみる。それは合衆国における権利の議論を端折ることができて政治的に有用だということなのかもしれない。だがそれは哲学を満たすものではない。神の権威に訴えることについても同じことが言える。権利が授かった地位機能の形態ならば、それらは合理的な基礎のもとに正当化されなければならない。今からわたしは言論の自由についてその正当化を確認してみる。
権利の功利主義的な正当化は嫌になるほど不適切なものである。特に言論の自由の場合は、これ以上ひどいものはないくらいである。もしわたしの言論の自由の権利が、わたしが言論の自由を行使することが最大多数の最大幸福を導く(conduce)という事実から導かれるものだとしたら、その権利の存在と行使はまったく最大多数の最大幸福という特定の事実に依存することになる。その場合、わたしが言論の自由を行使することによって最大多数の最大幸福をもたらさないなら──たとえばそれが、わたしの属する共同体の成員にとって胸糞の悪い、乱暴な言い草であるような場合、わたしは言論の自由を失う[左様ナ事ヲ言ッテハナラヌ]ということになる。それはバカ気た結論であり、そういうことになってしまう理論は何かが間違っているのでなければならない。
| ※ | 他人が真面目に書いた文章の上でこうした主張を読むのは、いったいいつ以来のことだろう。涙が出そうだ。いやマジで。 |
さらに、規則功利主義(rule utilitarianism)に訴えたとしてもその理論を救跋することはできない。功利主義的な正当化の標準的な規則の場合を考えてみればわかる。わたしが一般的な功利主義者ないし帰結主義(consequentialist)の立場に立って一日に2回歯を磨くという規則に従っているとする。つまりわたしは日に2回歯を磨く方がましだ(better off)と思っているということである。しかし何らかの特別な理由で、わたしの歯にカタストロフィックな帰結が生じたとしたら(たとえばわたしの歯が突然放射能を帯びて、歯を磨いたら街ごと吹っ飛んでしまうとか)、歯を磨くべしの規則を求める独立した強制力は何もないことになる。守るべきはわたしの歯なのか、この街なのか、功利主義的な究極の選択になってしまう。規則は独立した強制力を持っていない。以上は単に慣習(habitual)功利主義者の優勢のパタンを要約しただけである。
標準的に、功利主義者はこうした種類の反論に対してふたつの答を持っている。ひとつは、あなたは規則に反したことを行った場合の帰結を知ることはできないというものである。したがって全体として功利主義的正当化をもつようなあらゆる規則を守っているという推定が存在しなければならない。たとえそれが、言論の自由を行使すれば功利主義的によからぬ帰結が生じるような気がしたとしても、そんなことはわかりっこないのだということである。わたしはこれを認識論説(epistemic argument)と呼ぶことにしよう。功利主義者の唱える説のふたつ目は、やはりわたしが信用説(trust argument)と呼んでいるものである。人々に言論の自由を与えるとか、そういう規則は、人々がそうした規則は尊重されるべきだと思って信用している場合にのみ機能するという説である。そうすることが不愉快な(repulsive)ことだと思える場合は、言論の自由を認める規則に従えないなら、その規則に対する信用は弱まるのである。規則に対して功利主義的な信用を重視することには、規則がある特別な場合に反故にされるべきか否かを考慮に入れることが追加されなければならない。
要はどっちも不適切なのである。認識論説に対してはこう答える。認識論的な状況が完全であって、その帰結がどうなるかわかっているような場合を想像してみるだけでよい。そのような場合は、認識論説を法的な認可によって防ぐ(block)ことになる。認識論説の不適切は認識論的な困難がない、つまり認識論的に完璧な知識を持つような場合を想像してみる思考実験によって示される。そのような場合、わたしの言論の自由の権利はとかくのことがあっても影響は受けない。言論の自由ということの要は認識論的なものではないのである。信用説は、これもやはり弱いものである。その主張は、わたしの言論の自由の権利は、わたしがそれを攻撃的に行使する場合、権利を廃することは原則に対する信用を弱めるであろうという事実によって維持されるというものである。しかし、それは権利をある疑わしい経験的な仮説次第のことにしてしまう。その仮説というのは、覆されうる原則はそれを弱めるだろうということである。だがそうならないとしたらどうなのだろう?認識論説の場合のように、法的な認可の場合を考えてみればよい。いずれの説も弱点は同じである。その権利の、まさにその存在が欲望によらない行為理由である場合には破綻してしまうし、それを欲望によらないものにする特徴はまた功利主義や帰結主義と無関係なものにしてしまうということである。手短に言えば、これらの説は権利に対していかなる独立した地位を与えることもできないし、それゆえに権利を権利として認めることもできないのである。
このように、規則功利主義は、功利主義をその明白な弱点から救跋するには不適切な努力である。
| ※ | 前半はよかったが後半の議論は功利主義の議論についてそれなりの素養がないと(現にわたしにはないのだが)何言ってんだかよくわからん。どうでもいい重箱の隅を突いているようにも見えるわけだが、哲学の厄介なところは、自分のよく知らない議論は何でもそう見えてしまうということである。風邪で熱がある時には一番読まない方がいいところを読む羽目になってしまったのかもしれない。 |
(つづく)