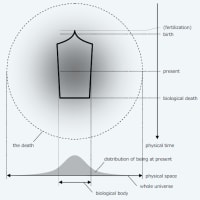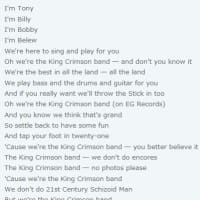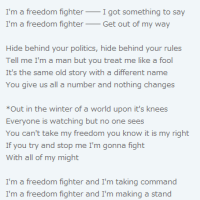いつの時代もワカモノの中の人は大変だということでは同じだが、大変さの具体性は世代によってずいぶん違うものである。
何のハナシかというと「便所飯」のことである。大学に入ったのはいいが食堂でメシが食えない、あろうことか学内のトイレで食べている学生さんがいる、という話を、ここ数年ときどき耳にするようになった。この連休中はこれについて、あるいはそこから連想されるようなことをアトランダムに考察してみることにする。
ひとりで食えばいいだろうと思うわけだが、そうできない理由が彼らにはあるのだ。要は「友達のいない人だという目で見られるのが嫌だ」ということらしい。そういう目で見られずに済むためならトイレで飯を食うことも辞さないというのだから、よっぽど嫌なのだろう。
ふたつのことが不思議である。ひとつはもちろん「友達のいない人だという目で見られるのが嫌だ」ということそれ自体である。もうひとつは、ひとりでいる誰かを「友達のいない人だという目で見る」、つまり人がそのような状態でいることが何か途方もなく異常なことだと感じる感覚が不思議である。そして仮に、後者のような感覚が今のワカモノの間ではそれ相応に広く共有されている(この場合の「共有」は相互的な信念ということを必ずしも意味していない。単に統計的に高い割合でという意味である)のだとしたら、前者が生じるのは単に当然のことで、おかしなことでも何でもないということになる。逆にそんな視線の共有ということが事実としてはないのだとしたら、前者はほぼ個人の妄想と見なしてさしつかえないものだということになる。
某大学の調査では400人中9人がトイレで飯を食っているという結果が出たという。この数字はあまりアテにはならない。だいたいこの9人が(あるいは残り391人が)正直に答えたと考えていい根拠がない。人間は少なくともアンケートには嘘を書く生き物である。実際、アンケートの回答に嘘が多いというのは統計的な調査結果に占めるノイズの比率が増大するということである。アンケートの結果が社会的な操作の根拠として利用されることが想像される限り、ノイズを増やすことはそうした操作の有効性を、その意図を拒否するという意味で無効化することにつながりうる。だから、他人や世間から鼻面取って引き回されたくない、そのような目に会わされるのを拒否したいという人は──たいてい拒否するものだと思うが──できるだけサイコロを振ってランダムに回答することが、結局はその人の利益にかなうことになる。
何のハナシかというと「便所飯」のことである。大学に入ったのはいいが食堂でメシが食えない、あろうことか学内のトイレで食べている学生さんがいる、という話を、ここ数年ときどき耳にするようになった。この連休中はこれについて、あるいはそこから連想されるようなことをアトランダムに考察してみることにする。
ひとりで食えばいいだろうと思うわけだが、そうできない理由が彼らにはあるのだ。要は「友達のいない人だという目で見られるのが嫌だ」ということらしい。そういう目で見られずに済むためならトイレで飯を食うことも辞さないというのだから、よっぽど嫌なのだろう。
ふたつのことが不思議である。ひとつはもちろん「友達のいない人だという目で見られるのが嫌だ」ということそれ自体である。もうひとつは、ひとりでいる誰かを「友達のいない人だという目で見る」、つまり人がそのような状態でいることが何か途方もなく異常なことだと感じる感覚が不思議である。そして仮に、後者のような感覚が今のワカモノの間ではそれ相応に広く共有されている(この場合の「共有」は相互的な信念ということを必ずしも意味していない。単に統計的に高い割合でという意味である)のだとしたら、前者が生じるのは単に当然のことで、おかしなことでも何でもないということになる。逆にそんな視線の共有ということが事実としてはないのだとしたら、前者はほぼ個人の妄想と見なしてさしつかえないものだということになる。
某大学の調査では400人中9人がトイレで飯を食っているという結果が出たという。この数字はあまりアテにはならない。だいたいこの9人が(あるいは残り391人が)正直に答えたと考えていい根拠がない。人間は少なくともアンケートには嘘を書く生き物である。実際、アンケートの回答に嘘が多いというのは統計的な調査結果に占めるノイズの比率が増大するということである。アンケートの結果が社会的な操作の根拠として利用されることが想像される限り、ノイズを増やすことはそうした操作の有効性を、その意図を拒否するという意味で無効化することにつながりうる。だから、他人や世間から鼻面取って引き回されたくない、そのような目に会わされるのを拒否したいという人は──たいてい拒否するものだと思うが──できるだけサイコロを振ってランダムに回答することが、結局はその人の利益にかなうことになる。