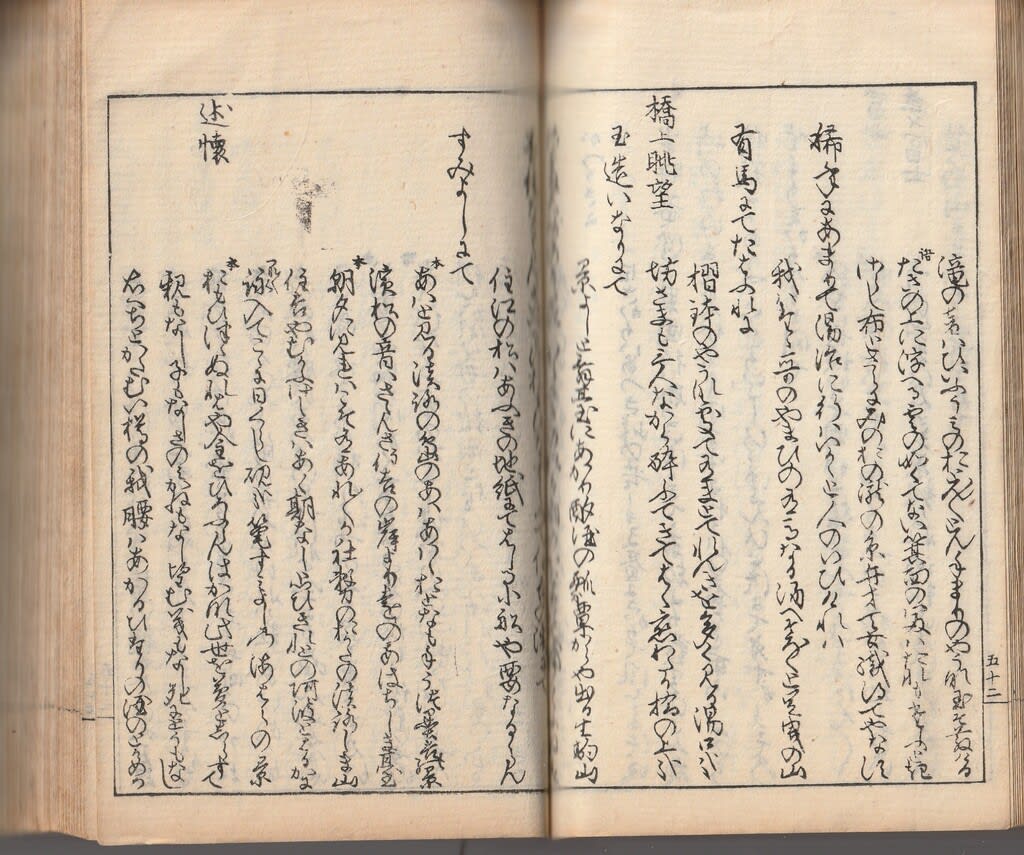柳縁斎貞卯と関係があった大阪の都鳥社で検索したところ出てきたのがタイトルの狂歌仕入帳。これは蟹廼屋(野崎左文)の編になるもので、前半は追悼の歌合などが載っていて、後半の詠草の部分は、途中に「左文翁自画賛」とあり蟹廼屋の詠と思われる。狂歌は東京、大阪、奈良の地名が入った歌が多く、大阪都島社で発表した歌も多数入っている。大正四年頃からの日付が入っていて、ウイキペディアの野崎左文の経歴と照らし合わせると隠居後の詠のようだが、新聞記者の経歴もあることから世相を詠んだ歌が目を引く。いくつか引用してみよう。
庭前露
電燈の色にもにはの白露は夜ごと光つてイルミネーシヨン
電燈で露が光ってイルミネーションと詠んでいる。この時代イルミネーションと言ったらどんな光景を思い浮かべたのだろうか。
御即位式
かしこしな国威をにぎる御手をもて民をなでんの御即位乃式
よろこびも此上はなし一天のみくらゐをつぐ万乗の君
大正天皇の即位の礼は大正四年にずれこんだ。すでに御病気がちだったようだ。一首目の「なでん」の横に朱字で「南殿」と書きこみがある。
寄国祝
めでたしな年をまたいで新領土ふみひろげたるあし原の国
一次大戦中のことであるが、大正四年から五年へ「年をまたいで新領土」はどこのことだろうか、私の歴史の知識ではよくわからない。
展望車富嶽
展望車不二のながめも一等とめづるは雪の白切符客
人穴にはひる心地ぞ展望車富士を見るころくゞる隧道
一等車の切符が白切符だったようだ。どんな展望車だったのか、今度は鉄道の知識がなくてよくわからない。
電車値上げ
土手に生ふる松の外にも値上りのけふから目立つ外濠電車
賃金をませし電車を唱歌にもこわねを上げて唄ふ子供等
つむじより曲る電車のわかれ道横に車を押す値上げ論
値上げ論は横車を押すものだと詠んでいる。よくある話かもしれない。
海の博覧会
海博を見て行くも目の薬なり真珠の玉はよう買はずとも
大正五年の海事水産博覧会(東京・上野公園) のことのようだ。
大正琴
はりがねの音色は遠くつたはりぬ電信機にも似たる琴とて
大正琴は当時新しい楽器だったようだ。
煽風器
煽風器そばで私が起すのじやないと張子の虎は首ふる
煽風器かけて寝らるゝ御隠居は左り団扇にまさる老楽
扇風機は明治からあったが量産されたのは大正に入ってからだという。
天気豫報
うみ路からいたくも風のふき出物あすの天気ははれとこそ見め
疑ひの雲さへ出て晴といふ豫報もあてにならぬ秋の日
間違ひのなきぞめでたき君が代の五風十雨の天気豫報に
天気予報を新聞、ラジオで知ることができるようになったのは大正末期のことで、この歌が詠まれた頃、天気予報は交番に張り出されていたそうだ。五風十雨をネットで引くと「世の中が平穏無事であるたとえ。気候が穏やかで順調なことで、豊作の兆しとされる。五日ごとに風が吹き、十日ごとに雨が降る意から。 」とある。最近あまり使わない言葉だろうか。
理髪師運動
運動にボートは漕がで理髪師が乗るは鋏の音のちよき舟
理髪師がはさみ仕事の運動にいづる庭球(テニス)の芝も五分刈
理髪師が議員選挙の運動に仲間の手までかり込んで来る
大正六年の歌。翌大正七年から理髪師の資格試験が始まっていて、それを求める運動があったようだ。しかし三首目には議員運動とあって、これは選挙運動のようにも思える。ちょき(猪牙)舟とは、舳先が細長く尖った屋根なしの小さい舟のことで江戸の川船として使われたとある。
同盟罷業
鋸も大工はとらで資本家のきをひいてみる同盟罷業
長いものにいつか捲かれて罷業さへよりの戻りし製鋼会社
大正八年の歌。この年のストライキは497件と空前の件数となったが、このあと恐慌がきて減少に転じたとある。
飛行郵便
雁がねの翅はからで郵便の文字も空ゆく世とはなりにき
先着をきそへる中に郵便のふくろをしよつて帰る水田氏
大鵬のはがきも持つか数百里四時間にゆく飛行郵便
大正八年十月に東京大阪間で郵便飛行のテスト飛行が始まって、3機のうち水田中尉の飛行機は往路で不時着となってしまった。二首目はそれを詠んでいるようだ。あとの2機は往復飛行に成功とある。しかしこの歌のせいで失敗の水田さんだけ覚えてしまった。三首目の大鵬、相撲取りの大鵬は昭和の横綱だけのようで、ここは中国に伝わる伝説の巨鳥のことのようだ。
簡易食堂
君が代の昌平橋に市人の腹つゞみうつ簡易食堂
薯(イモ)ばかり出すとて簡易食堂に客よぶうぶう不平鳴らすな
君が代の昌平橋に市人の腹つゞみうつ簡易食堂
薯(イモ)ばかり出すとて簡易食堂に客よぶうぶう不平鳴らすな
大正九年の歌。昌平橋の簡易食堂は公設で、大正七年の米騒動の後、地方からの労働者や学生のために作られたとある。
国勢調査
宣伝のビラを富士ほど積上げて一夜に出来る国勢調査
大正九年に行われた日本最初の国勢調査を詠んだ歌。このビラについては、最近、遅生様のブログに画像が出ていた。
こうして見てみると、この時代の狂歌も中々面白い。他の人の詠も読んでみたいものだ。