今日の城山湖では28MHz電圧給電アンテナの製作のお手伝いをしました。
私の完成品を見本に同じものを作ります。
ズバリ! いかに忠実に作るかが鍵でした。
コイルの密度、コイルとエレメント、給電線の配線、同軸ケーブルを使ったコンデンサーの接続と、簡単な構造ながらどっちがどうだっけというポイントがたくさんあります。
調整です。エレメントは完成品と全く同じ長さでスタート。
コンデンサの値を小さくしていくと同調点が徐々に上がっていきます。
と共に、SWRもどんどんとよくなっていく・・・はずでしたが・・・
徐々に悪くなり、カーブもブロードになっていきます。SWR3以上。
エレメントの折り返しをかなりやっても同調点があまり変わらない・・・
(´ε`;)ウーン…おかしい。
途中でSWRがドカーンと跳ね上がったり。そんな時は配線が外れたか、コイルが隣の輪に触れていたり。
それは単純な原因、それを除いてもおかしい。なぜだ。
エレメントをつける位置が違っていました。
それを直すと本来の、狭帯域のストンと落ちる電圧給電アンテナが出来上がりました。
アンテナ作りは楽しい!
春のDXシーズンで大活躍してくれるかなぁ。
そして、先日モービルホイップを黒く塗って調子に乗って、みなさんのアンテナも塗ろう!とアンテナを並べてもらったのですが・・・塗料が途中で切れて「あらあら」状態に。
幸い黒なのでまた塗り足せばきれいになるのですが、何とも半端な状態が城山スペック。?
大変申し訳ございませんでした~。










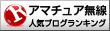
















昨日はアンテナ製作お手伝いありがとうございました。
忠実に作らなくてと思っても不器用さがたたってお手数をおかけしました。
繋ぎ間違えは致命的でしたが、ほんのわずかな所で全然違ってしまうというのが良くわかりました。完成品のアンテナで何気に電波を出してると気付きませんが、絶妙なんですね。
勉強になりました。
水平系の方とグランドウェーブで話す時は斜めに倒すと良いこともあります。
あのアンテナ、あと1mm同軸ケーブルコンデンサーを切って、エレメントを数センチ伸ばすとSWR1.0にベタ落ちになります。
初めて作った時はもっと長いエレメントの状態でスタート。全然低い周波数にディップポイントがあって、そのうちそれが消えて、別のところに現れたディップが本物で、コンデンサー、エレメントを切りつつ、一旦バンドの下でSWR最下点を出して、そこから最下点を維持するように徐々に交互に切り詰めてバンド内に収めたんです。
今回はエレメント調整を略して給電部のコンデンサーのみの調整という方法を取りました。
同じ長さでローディングコイルを入れて21MHzの電圧給電を作りたいですね。