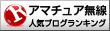FTX-1でFT8をやる時、WSJT-Xというソフトを使用しています。
新しいリグなので最初はリグの選択が見つからないのですが、リグライブラリを更新するとFTX-1が指定できるようになります。
ところが、当初は送信中に落ちるし、Fake Split はおかしいはで、全然駄目でした。
日々改良が進んで新しいリグライブラリが更新されていくのですが、送信中に落ちる、はなかなか解消しませんでした。
暫くは送信中に落ちることのないFT991を選んで使用していました。
でもこれだとFake Split が使えません、というか、リグの周波数は読み取れるのですが、リグの周波数を動かすことが出来ません。なので7MHzの2つの周波数の行き来はリグのダイヤルを回すしか方法がありませんでした。
バンドチェンジも手動です。
暫く放っておけばきっとちゃんとしたバージョンが出るだろう、と思って放置していました。
Fake Split が使えないので、選択する周波数は1500~2000Hzを選んでいました。(なぜそうするかは後述)
本日久々にリグライブラリの更新を行ってみました。
再起動して、リグを選択。実際に交信してみたところ、送信が落ちることは無くなりました。
Fake Split をやってみました。
ちゃんと動きます。
これでやっと普通の動作になりました。
Fake Split (疑似スプリット)を使いたい理由は、万が一でも歪んだ電波による、お二階、三階を出さないため、なんです。
ひずみ成分は倍音を含みますから、400Hzの信号が歪むと、800Hz、1200Hz、1600Hz、2000Hz、2400Hz、2800Hz、3200Hz、3600Hz、4000Hzと倍の関係の信号が発生してしまう可能性があります。
そのうち3000Hz を超える信号は、無線機のフィルターがカットしてくれるから良いのですが、それ以下は無線機はカットしませんから、電波に乗って飛んでいってしまいます。
最近はあまり見かけませんが、以前は子や孫を連れた電波を出す人が多く居ました。歪みが原因です。
歪みを発生させるのは、パソコンの中の音声処理、リグの入力などでどこか適正なボリュームで動させていないと起こります。エレキギターはわざと歪ませてあの音を出しています。歪ませないとフォークギターのようなきれいな音色になってしまいます。汚い音にしないとエレキギターの魅力が出ませんね。FT8でそれをやってしまうとみんなに迷惑かけるし電波型式を逸脱しますから駄目なんです。
で、1500Hz以上の周波数を使う理由は、倍音ですら無線機のフィルターが効くから、歪んでも迷惑をかけにくい、というわけです。
7.041MHzで1500Hzの音を出すと、7.042500MHzの電波が出る。
同様に 500Hz の音を出すと、7.041500MHzの電波が出る(リスクあり)。
同様に 2500Hz の音を出すと、7.043500MHzの電波が出ます(損失の可能性あり)。
2500Hzはフィルターのスカートにかかるかな、という音なのでパワーが乗らない可能性がありますから、300Hzより下、2700Hzより上とかはあまり使わないほうが良いでしょうし、パソコンや無線機の得意な音域というのもあるので端のほうは出力の差も大きくなる可能性があります。
では、7.041MHzで受信している局に、500Hzの音を届けたいとしたら、
パソコンで500Hzの音を作って流せばよいのですが、先程説明した通り、500Hzの信号は、倍、倍の倍、などの歪みを送信してしまうリスクがあります。
そこで、ソフト側は素晴らしい対策をしてくれました。
どの周波数で送るにしてもパソコン側は1500Hzから2000Hzの音しか出さないようにして、
その代わり、その分無線機の送信周波数をずらす、
という工夫です。
500Hzの音を届けたいとしたら、7.041500MHzの電波を出せばよい。
パソコンは1500Hzの音を作り、無線機は7.040MHzで送信すれば、はい、7.041500MHzになりますね。
同様に2800Hzの音を届けたいとしたら、7.043800MHzの電波を出したいわけで、
パソコンは1800Hzの音を作り、無線機は7.042MHzで送信すれば良い。
どちらもパソコンが作る音は1500~2000Hzで収まっています。
それがFake Split (疑似スプリット)機能です。
そういう機能を常に使っていたいから、それが実現する日を待っていたわけです。
FT8をやっている方は、皆さん、Fake Split 使ってくださいね。
あ、まだ少し変だなぁ。送信が遅く始まる・・・。もう少し良くなるのを待とう。