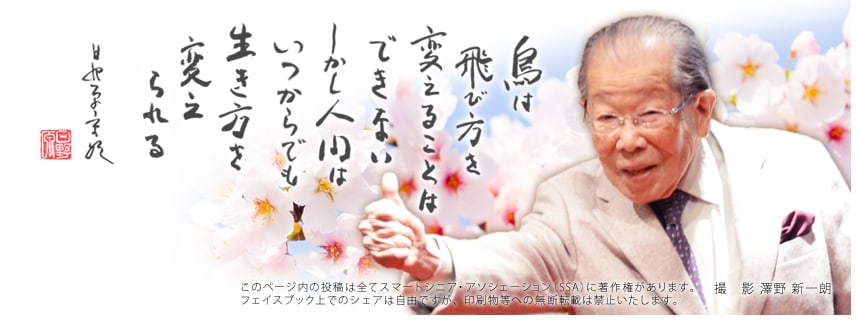日記によると当時は、単身赴任で名古屋鶴舞線塩釜口のワンルームマンションで生活し、今のマンションを探した。引っ越しのゴタゴタと当時の様子が、駅は無人駅(下欄参照)でした。懐かしい思い出、残念ながら駅の写真は撮っていなかった。
1991年12月25日、三好ヶ丘ヒルズへ引越し
21日、横浜へ行き引越し準備。22,23と多忙。23日午後に名古屋へ戻る。
24日、9時から八事NTTへ行き電話の権利売り渡し手続きをする。
7万円で買ったものがなんと4.8万にしかならなかった。地下鉄電車の定期券を購入した。期間は今日から半年間で114,270円、栄から伏見経由で三好ヶ丘まで。それから息子のクリスマスプレゼント「ビッグロゴ」を買い塩釜口のワンルームマンションで引越し準備開始。
25日、塩釜口から2トン車で三好ヶ丘へ引越し。
少しして横浜から大型の10トン車の引越し車がきた。転居完了。
26日、月曜から今日まで三日間転居休暇。
一段落したので午後会社に行き机上の整理を定時に帰る。
27日、今年最後の出勤。
納会は各フロア―毎に実施。納会の途中から社長のところへ挨拶に行った。転居も無事終わった事を報告。私が行った時は丁度合間だったのか誰もいなかったので少しゆっくり話しをしてくれた。
28日から31日の暮れまで整理で大変でした。
正月はとりあえず寝る所を確保しただけといった状況である。
31日に三好町の東海銀行へ住所変更等の手続きに行って来た。
1992年、1日、素晴らしい天候で引越し後のよき新年のスタートとなった。
家の中の整理整頓と久し振りに布団を干す等落ち着いた1日であった。
2日、3日と息子と小学校に行きドッチボールをしたりマンションの周りを散策したりして過ごした。自然に満ち溢れた町である。買い物や病院等不便な所もあるが緑が多く子供にはよい環境と言える。
マンション選びの時に最優先としたのが子供優先の環境選びであった。
4日、三好町役場に行き住民異動届等の手続きをした。
三好町まで歩いて約1時間。家族でブラブラと散歩がてらに出かけた。三好町ではバッターを買ってやった。帰りはバスで赤池に出て電車で三好ヶ丘へ。
こちらは車社会の町トヨタと言われるように車がないとやっていけない。近くのトヨタ車を扱う中古販売所に行きコロナを購入。1800CC 、トータルで84万円。
5日、今日息子が早速野球がしたいというので直ぐとなりの小学校に行き二人で野球をした。少しボールに当るようになった。少しずつではあるが成長しているなと感じた。
4日に三好町役場で転入手続き済み。学校では早速友達が出来楽しそうであった。
8日、今日から三好ヶ丘小学校一年生に転入。
9日の日には友達のところへ行きテレビゲームをしてきたとか。
10日の日には友達3人で遊び大いに楽しんだ様子。しかも3人の中ではボスになっているとか(母の話し)。多少心配していた事であったため直ぐに溶け込んで大変よかった。