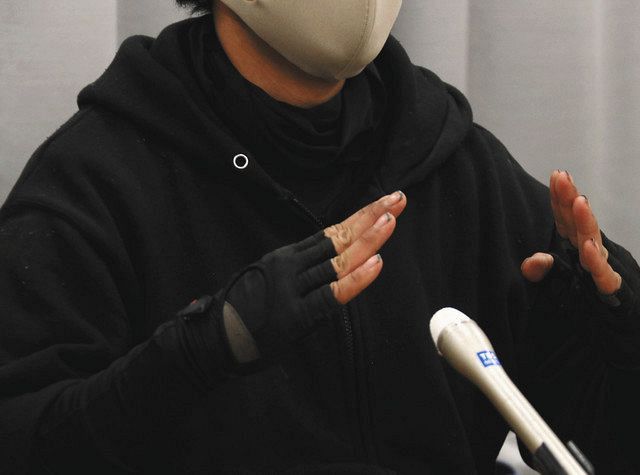【社説①】:いじめ自殺認定 コロナ禍の考慮も重要
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:いじめ自殺認定 コロナ禍の考慮も重要
登別市内で昨年6月、中学1年の男子生徒が転落死したことについて、市教委が設けた第三者委員会は、部活動でのいじめとコロナ禍による不安など複合的な要因で自殺に至った、と認定した。
未来ある13歳はなぜ自ら命を絶たなければならなかったのか。教師をはじめ周囲の大人はどこかで手を差し伸べられなかったか。くみ取るべき教訓は多い。
臨床心理士や弁護士らでつくる第三者委は関係者への聴取など調査を重ねた。概要とはいえ報告書を公表した点は評価できよう。
いじめはどこでも起きる可能性がある。しかもコロナ禍による負担は全ての子供に重くのし掛かっている。教育関係者を含め大人はその前提に立ち、再発を防ぐ手だてを急がなければならない。
第三者委などによると、生徒は中学入学後、コロナ禍で長期休校に入った。不安から長時間、ゲームや会員制交流サイト(SNS)に接し、成績や体力が落ちた。
休校明けの6月から始めた部活動では、体形や技量をからかわれていた。第三者委はこうしたいじめなどの外面的要因と、コロナ禍や将来への不安などの内面的要因を自殺の理由に挙げている。
学校側の問題や再発防止策に触れていないが、部活動の顧問が生徒へのからかいを認識していたほか、生徒は自殺直前に校内で悩みを見せていた。その兆候をつかみ切れなかったことは悔やまれる。
教職員は校内の消毒などコロナ対策に忙殺されていた。だとしても最優先するべきは生徒の命だと意識することが重要だったろう。
外出自粛などによる家庭での虐待リスクの高まりを考えれば、相談窓口の拡充や地域で見守る体制づくりは必要だ。子供が困った時に自らSOSを出せるよう教えることも忘れてはならない。
2013年施行のいじめ防止対策推進法は児童生徒が重大な被害を受けた際、教委や学校が調査組織を設置するよう義務付ける。
だが被害を訴えても調査に至らなかったり、遺族が調査結果に納得しなかったりする例は多い。登別では遺族の要請も踏まえ速やかに対応できた。参考になろう。
今回の報告書概要は「真面目で優しい子ほど追い込まれるが、フォローすべき私たち大人が救えなかった」と記し、当事者の痛みに寄り添った姿勢がにじむ。
生徒の無念や遺族の悲しみを胸に刻み、再発防止につなげるためにも、可能な範囲で報告書全文を公表するよう市教委に求めたい。
元稿:北海道新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2021年03月24日 05:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。