
[※ 「日本だけ賃下げ」(週刊金曜日 1353号、2022年01月21日) ↑] (2022年06月04日[土])
(2022年06月04日[土])
まず、言いたいことがある。
「最終保障供給…小売電気事業者のいずれとも電気の需給契約についての交渉が成立しない場合、契約先が見つかるまで送配電会社が電力を供給する制度」…大手電力会社が再エネをつぶしておいて、電気代が1.5倍ほどにアップ? 核発電回帰!? フザケルのもタイガイにしろ!! 《原発は『プルトニウムをつくる装置』》(故・内橋克人さん)。そんなに自公お維コミを支持して、利権に在り付きたいものかね。《火事場ドロボー》らに唆されて、「原状回復」どころか《原発回帰》。
『●《原発再稼働や増設を唱える連中の頭の中を掻っ捌いて、中身を見て
みたい》(鈴木耕さん)――― なぜ今直ぐ「原状回復」しないの?』
《とくに、原発事故による放射性物質の拡散の影響、それによる
疾病の増大、小児甲状腺癌の発生と検査体制の問題については、
とても数十行の文章では意を尽くせない。それについては稿を
改めようと思う》
『●《【原発耕論…】福島事故で被ばくしたこどもたちに、不安なく過ご
せる未来を!(311子ども甲状腺がん裁判)》(デモクラシータイムス)』
『●子ども甲状腺がん裁判《東電側…弁護団…「原告らは…甲状腺の健康
リスクの上昇には関わりがない」などと因果関係を否定》…血も涙も無し』
軍事費増強、軍事費倍増だそうだ。
『●消費税増税断固反対!!: 約束に無いことのみをやるムダ内閣』
《中途半端という点では、今国会に提出された労働契約法の改正案も
同様だ。有期の契約社員が5年を超えて同じ職場で働く場合、本人が
希望すれば6年目からは無期雇用に転換することを企業に義務づける。
だが、5年を前に契約を打ち切る「雇い止め」が相次ぐのではないか
と懸念されている。更新時に半年あいだを置けば、前の期間は
通算しないですむ「抜け道」も用意された。何より、無期雇用に
転換しても、賃金などの労働条件はそのままでいいという。これでは、
「正社員化への道」は名ばかりになりかねない。》
『●竹中平蔵氏が「解雇特区」構想をぶち上げる!!』
《解雇特区構想は、アベノミクスの成長戦略のひとつとして
「産業競争力会議」が進めているものだ。
「特区構想は“労働基準法”や“労働契約法”の規定を、
特区内に限ってゆるめる内容です。企業と労働者が約束した
条件に沿って解雇できるようにする。…」》
『●「解雇特区」、事実上見送りだそうだが……』
《労働契約法16条には正当で合理的理由がなければ解雇できない
と書かれている。労働者の基本的人権だ。絶対に譲れない一線
なのに、安倍や菅官房長官らはそれを「岩盤規制」と呼んでいる。
人権を規制呼ばわりされたらたまらない》
『●東京新聞【<社説>新しい資本主義 「分配」は掛け声倒れか】
《岸田へ投資を》…「インベスト・イン・キシダ・DEATH」ではねぇ…』
あぁ、「新しい資本主義」…《政治の刷新がない限り、日本は沈みゆくしかない》。軍事費倍増、その5兆円ほどのお金をどこから削り、どこから調達? 消費税分は法人税の穴埋めに使われ…さらに消費税増税でもするのですか?
東京新聞の記事【国公立大や公的機関の研究者 来年3月に約3000人が大量雇い止め危機 岐路の「科学立国」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/179934)によると、《国立大学や公的研究機関に勤める任期付き研究者の大量雇い止めが問題化している。法定の雇用期間の上限規定(10年)が、来年3月末に迫っているからだ。対象の研究者は約3000人。無期雇用への転換も可能なルールだが、経営状況が厳しい大学などが雇い止めを選択する恐れが出ている。科学力低下や海外への頭脳流出も懸念されるのに、文部科学省の動きは鈍い。研究者の大量雇い止め危機の2023年問題。うまく対処する方法はないのか。(特別報道部・宮畑譲、北川成史)》。
『●そもそも、子どもたちのためにこそ
「ドブガネしている」税金を使ったらどうなのか?』
『●「誰のための政治…誰のための税金なのですか。
税金は安倍総理のポケットマネーではありません」!』
『●弱い者イジメ…「『低所得世帯の生活水準が下がった』なら、
『貧困は改善』は嘘で、アベノミクスは失敗」』
『●オトモダチ「利権」塗れ…「この国でもっとも「利権」から遠い
生活保護受給者の暮らしがまた脅かされる」』
『●「FMSは武器取引を通じて、米国が他国を
従属させるシステムでもある。日本の対米追従は強まる一方だ」』
『●アベ様の《国民観、人間観には共通点が多すぎる…
彼の目には私たちが己の財布、兵力、労働力だとしか…》』
『●「どっからどうもってきて出すのか」…軍事費を削り、
弱者救済や災害復旧、防災にこそ血税を使って下さい』
『●対外有償軍事援助FMS…《アメリカからの援助》? アメリカへの
「援助」、狂気な「思いやり」の一種?』
『●「国策の名の下に研究者が軍事研究に加担させられた
歴史を繰り返そうとしている…亡国の施策だ」』
『●《韓国…国防予算の削減…新型コロナウイルス対策に振り向け…極めて
合理的な判断…その合理は日本では通用しない…》(立岩陽一郎氏)』
『●《フィンランド…親の経済力にかかわらずすべての子どもたちが
大学まで行ける…。老後も…》(鈴木穣記者)』
『●同様に、「この28年間の変化は法人税が6兆円…
所得税が6兆円減り、消費税が13兆円増えたことだけなのだ」』
『●前川喜平さん《社会全体が子どもたちを支えられるように、子どもたちに
税金を使う仕組みを作らなければいけない》…逆行するアベ様政権』
『●【NNNドキュメント カネのない宇宙人 信州 閉鎖危機に揺れる
天文台】…《「経済的利益」を重視する国の政策によって…資金》大幅減』
「2005年から運営費交付金を年1%削減し続ける文科省。人件費が
どんどんと削られ、研究者が減らされていく。文系どころか、理系に
対しても未来に投資しない国。一方、巨額の軍事研究費で研究者の
良心を釣る。おカネ儲けのことしか考えていない独裁者・アベ様ら。
この国ニッポンの科学の未来はトンデモなく暗い…。」
『●前川喜平さん《本来は自由で自律的でなければならない分野にまで
政治支配が及ぼうとしている…新聞やテレビ…教育、文化や学問…》』
『●毎日新聞【「軍事研究せぬなら、行政機関から外れるべき」 自民・
下村博文氏、学術会議巡り】…人殺しの研究なんてまっぴら御免だね』
『●「「愛人」だと報じられた女性がいるバーで1回約180万円の
支出を政治活動費で賄っている」財務相』
《「人の税金で大学に」麻生太郎は自分の娘も東大卒だった! 教育への
公的支出を否定する財務相を許していいのか …つまり、教育への
公的支出が少なく家計負担を強いているこの状況が、親の所得格差が
子どもの教育格差につながるという「貧困の連鎖」を
生み出しているのだ》
『●《将来への投資》しないカースーオジサン…児童《手当(公助)を
減らし、自助に頼る。これが菅首相の「自助・共助・公助」の実態だ》』
『●総合科学技術・イノベーション会議(菅義偉議長)…《「稼げる大学」
へ外部の知恵導入 意思決定機関設置、来年法改正》(時事通信)』
『●《さらなる教育の平等…国民総「高スキル人材」の実現だ。社会からの
脱落や孤立化を防ぎ、労働市場でも「誰一人取り残さない」を目指す》』
『●斉加尚代監督『教育と愛国』:《教育への政治支配が続けば、日本の
学校は…政府プロパガンダを信じ込ませる場に堕す》(前川喜平さん)』
『●『教育と愛国』《危うさに気づいた…。監督で毎日放送の斉加尚代さんは、
ゆがむ教育現場のリアルを伝え「教科書は誰のものか」を問う》』
『●《地元テレビはヒレ伏しヨイショの連続》…一方、ある記者は
《「こんな状態でも、ひるんじゃダメよ」――。
橋下市長より大人だ》った』
そんなに違憲に壊憲して、戦争できる国にしたいの? 人の親として、子や孫を戦場に行かせたいものかね、そんなに人殺しに行かせたい?
目取真俊さんのブログ【海鳴りの島から 沖縄・ヤンバルより…目取真俊/戦争で死ぬということ/沖縄戦を戦ったある日本兵の証言より】(https://blog.goo.ne.jp/awamori777/e/a7f54e8f36b295ca99d4bf0431245473)によると、《自らの戦争体験を語れる人がわずかになる一方で、戦争体験をつづった膨大な書籍はどれだけ読まれているのか。戦場で人々はどのように生き、死んでいったのか。そのことを記録した証言集や戦後文学を読むことの意義は大きい。軍隊という組織は外にも内にも暴力がはびこる。上官の暴力に苦しんで自殺した若い兵隊たちが、数多くいた事実も知る必要がある》。
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/179934】
国公立大や公的機関の研究者 来年3月に約3000人が大量雇い止め危機 岐路の「科学立国」
2022年5月28日 06時00分
国立大学や公的研究機関に勤める任期付き研究者の大量雇い止めが問題化している。法定の雇用期間の上限規定(10年)が、来年3月末に迫っているからだ。対象の研究者は約3000人。無期雇用への転換も可能なルールだが、経営状況が厳しい大学などが雇い止めを選択する恐れが出ている。科学力低下や海外への頭脳流出も懸念されるのに、文部科学省の動きは鈍い。研究者の大量雇い止め危機の2023年問題。うまく対処する方法はないのか。(特別報道部・宮畑譲、北川成史)
◆頭脳流出の危機「中国からオファーがあれば考える」
(「10年ルール」撤廃を訴える特任教授の男性
=東京都文京区の東京大学で)
フラスコや顕微鏡、無菌状態にする装置などがところ狭しと並ぶ東京大のバイオ系の研究室。中には1億円以上する機器もある。この研究室は、人件費を含め企業からの寄付金で運営されている。
しかし、来年3月にこの研究室を引き払う可能性がある。研究を仕切る特任教授の任期が切れるからだ。
「この機材を持って別の大学に移れるのならいいが、簡単にポストは見つからない。昨年から10件以上、大学教員の公募に書類を出しているが、全く通らない。同じような境遇の人が殺到しているのだろう」
この研究室の特任教授の男性が切迫した状況をそう訴える。今のポストに就く前は別の大学で無期雇用の教員として勤めていたが、声をかけられ、「よりよい環境で研究したい」と2012年10月に移ってきた。
その半年後に、問題の改正労働契約法が施行された。当時から不安はあったが、「企業から研究費がもらえれば定年まで継続できるだろう、もしくは別の無期雇用のポストに移れるだろう、と高をくくっていた面はある」と振り返る。「こんなことになるなら、前の大学を辞めなかった」と悔やむ。
男性は、自身と日本の研究環境の将来を悲観する。「もちろん今の研究室で続けたいが、背に腹は代えられない。中国からオファーがあれば考える」と吐露。「将来の仕事がないなら、学生も博士課程に進まず就職してしまう。腰を据えた基礎研究はやはり大学が中心。しっかりした基礎研究の土壌がなければ、企業もよい研究・開発はできない」
◆研究機会を与えないのは社会的損失
文科省によると、来年3月末で契約期間が10年に達するのは国立大86校などで3099人。うち契約期間の上限が就業規則などで明示されている1672人は、雇い止めに遭う可能性がさらに高い。中でも東大は346人と最も多い。
(多くの研究者が雇い止めの危機にある東京大学。
中央上は本郷キャンパスの安田講堂=東京都文京区で、
本社ヘリ「あさづる」から)
しかも、有期雇用の研究者が期限を迎えるのは来年3月だけのことではない。以降も続々と発生する。
男性は「本来は期限が来たら無期雇用に移行できるよいルールのはずだが、現実にみんなを無期雇用にするのは無理だ。それなら、このルールを撤廃して、有期雇用を続けてもらったほうがいい」と強調する。
東大広報課は「こちら特報部」の取材に「他のプロジェクトに採用されるなどで、10年を超えて在職することも可能。『一律に雇止め』といった議論とは状況が異なっていると認識している」と回答した。
しかし、有期雇用の教員を支援している東大の無期雇用の教授はこう考えている。「大学は企業などからの研究費が定年の65歳まで出る場合を想定している。プロジェクトが終わってしまえば、人件費が発生することになるから、無期雇用しようということにならない。結局、多くの人が雇い止めに遭うだろう」
その上で、「素晴らしい成果を上げている有期雇用の先生はいる。彼らに研究する環境を与えないのは、大学だけでなく社会的な損失も大きい」と嘆く。
◆文部科学省、雇用判断を大学に丸投げ
有期雇用の研究者の雇い止めの恐れがあるのは他の国立大も同じだ。文科省によると、10年で契約終了が明示されている1672人の内訳は大学別で東京大に続き、東北大(236人)、名古屋大(206人)が多い。
文科省所管の5つの研究機関でも、657人が来年3月末に契約期間が10年に達する。うち契約期限が10年以内と示されているのは317人で、理化学研究所が296人と大半を占める。
そもそも、13年4月施行の改正労働契約法では、同じ勤務先での有期雇用契約の期間が通算5年を超えた場合、労働者が求めれば無期雇用に転換できるルールが定められた。研究者については任期法などで、通算10年という特例が設けられた。文科省人材政策課の担当者は「7、8年という期間の研究事業もあり、5年での業績評価は難しいとの研究者や研究機関の要望を踏まえ、10年に延長された」と説明する。
「10年」を前に広がる雇い止めの不安に文科省の動きは鈍い。法に関するリーフレットを作ったり、大学に説明したりしているというが、対策について大学振興課の担当者は「特別にはない」と素っ気ない。無期雇用への転換促進には「業務の内容がさまざまなので一律に言えない」と話す。
結局、雇用の判断は大学や研究機関に丸投げだ。経済産業省所管の産業技術総合研究所は、対象の研究者ら422人について希望があれば雇用を継続する方針を示している。それを考えれば、何らかの対応ができるようにも見える。
◆有期雇用は人件費の「調整弁」、ハラスメントの温床にも
(研究者の雇い止め問題で動きが鈍い文部科学省)
研究者のキャリア問題に詳しい「科学・政策と社会研究室」代表の榎木英介さんは「文科省はやる気のない問題には『学問の自由』を理由に逃げる。今回がまさにそうだ。研究者の雇用の安定のために導入された制度のはずなのに、雇い止めの口実になっている」と厳しい目を向ける。
榎木さんによると、国から国立大学などへの運営費交付金が減少し財源が減った反動で、研究者の有期雇用が増えた。研究者が人件費の「調整弁」になっている構図が、問題の背景にある。「文科省は問題に踏み込むと、交付金の在り方を追及される。財務省との板挟みになるのが嫌なのではないか」と推し量る。
文科省は、有期雇用は研究者の流動性を高め、切磋琢磨せっさたくまにつながる意義があるとするが、北海道大の光本滋准教授(教育学)は「メリットが現れていない。40代でも落ち着かない研究者がかなりいる。契約を切られたくないため(無期雇用の)教授に物を言えず、ハラスメントの温床になっている」と疑問視する。
◆全般的な国力低下につながりかねない
近年、研究分野で日本の国際的地位が後退しているとされるが、不安定な雇用環境では人材が集まらない。「中国などによる研究者の引き抜きを助長し、全般的な国力の低下につながりかねない」と危惧する。
労働問題に詳しい指宿昭一弁護士は「他の労働者は5年を超えれば、無期雇用への転換を求められるのに、研究者はできない。逆に、長期間、無期への転換を求められないことで安定した雇用の立場を得るハードルを高くしている。この例外自体が変な理屈だった」と指摘する。
指宿さんによると、大学でも事務職員らには「5年」のルールが適用される。そうした職員の雇用をいったん5年で終了し、数カ月後に再び有期で雇い直す大学があった。研究者についても、こうした抜け道を探る動きがあるという。
これについては「いつでも切れる状態にする悪辣なやり方」と強調。「明日の雇用も知れない状況でいい仕事はできない。文科省は対策を考えるべきだ」
◆デスクメモ
昨年3月に閣議決定された科学技術・イノベーション基本計画は研究現場の現状を厳しい環境が継続し、論文の質と量で国際的地位が低下傾向だと分析する。認識は正しいが、政府に改善する気迫が全く見えない。まずは、研究者が能力を存分に発揮できる環境づくりをできないものか。(六)
【関連記事】なぜ少ないの?女性の研究者…当事者に理由を聞いた 「家庭との両立困難」73%、「偏見」64%
=====================================================
=====================================================
【https://blog.goo.ne.jp/awamori777/e/a7f54e8f36b295ca99d4bf0431245473】
海鳴りの島から
沖縄・ヤンバルより…目取真俊
戦争で死ぬということ/沖縄戦を戦ったある日本兵の証言より
2022-05-28 14:15:27
十数年前、沖縄戦を戦った東京都出身の元日本兵に話を聞いた。
その方が負傷と疲労で動けず、沖縄島南部のガマ(洞窟)に横になっていた時のことだ。岩をはさんだ隣のくぼみに重傷の若い兵隊がいた。ある日、轟音とともに手榴弾が破裂し、その兵隊が自決した。岩があったため、証言した人は無事だった。
直後にまわりの兵隊から罵声が飛んだ。
馬鹿野郎、死ぬんなら外に出て死にやがれ。
それまで、自らの死期を悟った兵隊たちは、手榴弾をもって外に出てから自決していたという。
私に話をした元日本兵の方は、その理由を身をもって知った。
自決した遺体はすぐに腐敗し、猛烈な悪臭がガマの中に立ち込めた。
そして、遺体から湧いたウジ虫がまわりに這い出し、その方の体にも這い登ってきた。最初は手で払い落していたが、しだいにその気力もなくなり、ウジ虫が体や顔を這うままに任せていたという。
戦場で死ぬというのはそういうことだ。手足はバラバラになり、顔が押しつぶされ、脳みそが吹き飛び、内臓がはみ出し、泥と汚物にまみれた死体が、77年前、沖縄の戦場のあちこちに転がっていた。
死体は腐敗してガスで膨張し、太ったウジ虫がわき出し、群がる。倒れた母親の乳房にしがみついたまま死んだ乳児の遺体をハエが覆っている。砲爆撃に追われ、時にはそういう死体を踏んで逃げ惑う。それが77年前の沖縄の光景だったのだ。
連日、メディアがウクライナ情勢を伝えている。ロシア軍がどこまで侵攻した、ウクライナ軍がどこまで反撃した、どのような兵器が使われ、どのように戦闘が行われた。大半はそういう情報であり、戦場で死んだ人々の映像もロシアの蛮行を強調するもので、路上に倒れた住民の姿が多い。
それすら日本ではぼかしがかけられる。外国の報道にしても、激しく損傷した遺体を見せるのはメディアでは難しいし、戦意を喪失させるそういう映像は軍や政府に規制されるだろう。
ロシアの戦車や装甲車がミサイルで破壊される様子が、ドローンや地上から撮影した映像で流される。吹き飛ばされる戦闘車両には兵士たちが乗っていて、彼らの死体は元の姿をとどめていないだろう。戦死の知らせを受けた家族や友人らは、悲しみとともに敵への怒りや憎しみを募らせるだろう。
ウクライナ側の視点から報じられる映像や情報にさらされると、戦死していくロシア兵とその家族への想像力がはたらきにくい。戦局や兵器を論じる軍事評論家や研究者の発言ばかりを聞き、高みから情勢を語るだけで、実際に死んでいく住民や兵士の生々しい様子を想像しなければ、勇ましい言葉を吐いて戦争を煽るようになってしまう。
自らの戦争体験を語れる人がわずかになる一方で、戦争体験をつづった膨大な書籍はどれだけ読まれているのか。戦場で人々はどのように生き、死んでいったのか。そのことを記録した証言集や戦後文学を読むことの意義は大きい。軍隊という組織は外にも内にも暴力がはびこる。上官の暴力に苦しんで自殺した若い兵隊たちが、数多くいた事実も知る必要がある。
「南西領土の防衛」と言ったところで、日本政府や自衛隊が守るのは「領土」であり、大半の住民は島から逃げることができず、戦闘に巻き込まれて犠牲になる。戦場になるのは宮古・八重山・与那国を中心とした沖縄で、自分が住んでいるところではない、と考えているヤマトゥンチューは平然と自衛隊の強化を口にする。
宮古・八重山・与那国から、どこに、どうやって住民を避難させるのか。そもそも、公務員や運輸、通信、電力、水道、ガスなど戦争遂行に欠かせない部署の労働者は強制的に勤務させられるし、成人男性の大半は島に残ることを強いられるだろう。
女性や老人、子どもたちにしても、数万人規模をどうやって避難させるのか。船や飛行機をピストン運航してどれだけ対応できるのか。ウクライナのように自分の車で陸路を逃げることはできないのだ。制海・制空権を奪われたらどうするのか。
沖縄戦を見ればわかるように、戦争になれば輸送船も攻撃対象となる。孤立した島で住民はどうやって水や食料、生活必需品を確保するのか。自衛隊が住民を守る、というのは幻想にすぎない。敵の激しい攻撃を受ければ、自衛隊にしても自らを守るだけで精一杯なのだ。
ガマ(洞窟)での体験を語ってくれた元日本兵の方は、私にこうも言っていた。
よく沖縄戦のことを「日米の激戦」と言いますが、「激戦」というのは双方が同じだけの兵力で戦うから「激戦」になるんです。沖縄戦では日米の兵力が比較にならなかった。だから「激戦」ではないんですよ。私たちは一方的にやられてたんです。
沖縄人は自らを守るために必死にならなければ、何度でもヤマトゥに「捨て石」にされる。沖縄戦を生き延びた人たちの証言を、いまこそ数多く読みかえしたい。
=====================================================











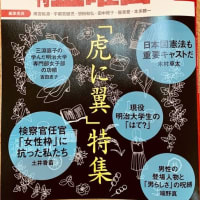











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます