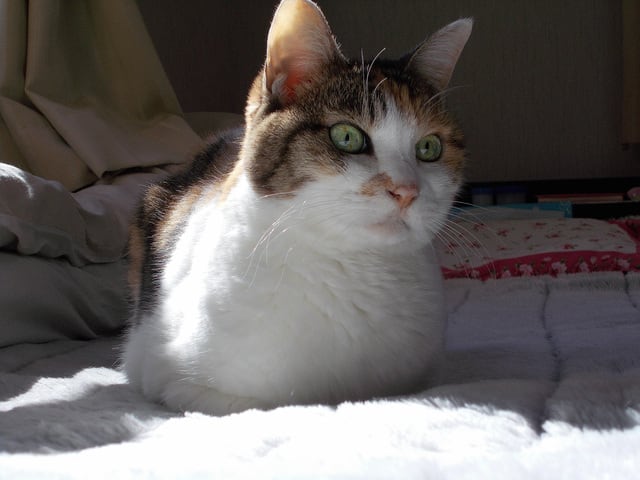大内弘世(おおうちひろよ)は長く南朝方の武将として動いていた。その間、周防(すおう)・長門(ながと)へ軍事侵攻し両国(今の山口県)を制圧、意気揚々と武威を振りかざし偉人を気取っていた。ところがしかし何を思ったのか幕府方へ帰順する。この時期、「太平記」は貞治(じょうじ)三年(一三六四年)と表記しているがそれは誤りで正しくは貞治二年(一三六三年)。「大内介(おおうちのすけ)降参(こうさん)」の条としてまとめられているものの、その文面は政治的指導者のあり方についての論評が半分強を占めている。
「堯(ぎょう)の代に四凶(しきょう)の族(ぞく)あり。魯国(ろこく)に小正茅(しょうせいぼう)あり」(「太平記6・第三十九・一・P.137」岩波文庫 二〇一六年)
漢籍から二箇所引かれている。一つは「堯(ぎょう)の代に四凶(しきょう)の族(ぞく)あり」。次に「魯国(ろこく)に小正茅(しょうせいぼう)あり」。前者は堯の後を継いだ舜によって罰せられた。「四凶(しきょう)の族(ぞく)」は「讙兜(かんとう)・共工(きょうこう)・三苗(さんびょう)・鯀(こん)」の四者。
(1)「讙兜(かんとう)が共工を推薦したとき、堯はそれをしりぞけて工師(土木の長官)にしたが、はたして共工は淫(みだ)らでよこしまで、効果があがらなかった。また、四嶽が鯀(こん)を推薦して洪水を治めさせようとしたとき、堯はやはり、それをしりぞけたが、四嶽が強いて試してみるように言ったので、試したところ、はたして成績が挙らず、百姓が困った。また当時、江淮(こうわい)地方には三苗(さんびょう)がいて、しばしば乱をおこしていたので、舜は巡狩から帰ると帝堯に、共工を幽陵に流して北狄(ほくてき)の風俗を変え、讙兜を崇山(すうざん)に放って南蛮の風俗を変え、三苗を三危(さんき=甘粛の西方にあるといわれる山)にうつして西戎(せいじゅう)の風俗を変え、鯀を羽山に逐うて東夷の風俗を変えるように請うた。この四者が罰せられて天下が、ことごとく服従した」(「五帝本紀・第一」『史記1・本紀・P.18』ちくま学芸文庫 一九九五年)
後者にある「魯国(ろこく)に小正茅(しょうせいぼう)」。孔子によって誅殺され、孔子は魯国の重鎮となる。
(2)「魯の大夫で政治を乱した少政卯(しょうせいぼう)を誅し、自ら国政に参与した」(「孔子世家・第十七」『史記4・世家・下・P.88』ちくま学芸文庫 一九九五年)
さらに繰り返し反復されるフレーズ。
「死をば善道(ぜんどう)に守り」(「太平記6・第三十九・一・P.137」岩波文庫 二〇一六年)
この箇所はもう何度繰り返されたか覚えていないほど。「論語」から「守死善道」の部分のみをそのまま書き下したものだが、なぜか「太平記」はいつもこのセンテンスの他の部分を無視した上で引用するのが特徴的。
「子曰、篤信好学、守死善道、危邦不入、乱邦不居、天下有道則見、無道則隠、邦有道、貧且賤焉恥也、邦無道、富且貴焉恥也
(書き下し)子曰わく、篤(あつ)く信じて学を好み、死にいたるまで守りて道を善(よ)くす。危邦(きほう)には入らず、乱邦(らんぽう)には居らず。天下道あるときは則(すなわ)ち見(あら)われ、道なきときは則ち隠る。邦(くに)に道あるとき、貧しく且(か)つ賤(いや)しきは恥なり。邦に道なきとき、富み且つ貴きは恥なり。
(現代語訳)先生がいわれた。『かたい信念をもって学問を愛し、死にいたるまで守りつづけて道をほめたたえる。危機にのぞんだ国家に入国せず、内乱のある国家には長く滞在しない。天下に道義が行われる太平の世には、表にたって活動するが、道義が失われる乱世には裏に隠れる。道義が行なわれる国家において、貧乏で無名の生活をおくるのは不名誉なことである。道義が行なわれない国家において、財産をもち高位に上るのは不名誉なことである』」(「論語・第四巻・第八・泰伯篇・十三・P.223~224」中公文庫 一九七三年)
次はやや込み入った条件における対応についての是非が焦点。
「百里奚(ひゃくりけい)は虞(ぐ)の君を棄てて、秦(しん)の穆公(ぼくこう)に仕へ、菅夷吾(かんいご)は桓公(かんこう)に下つて、公子(こうし)糾(きゅう)とともに死せざりしはいかに」(「太平記6・第三十九・一・P.138」岩波文庫 二〇一六年)
二つの事例が続けざまに問われる。(1)「百里奚(ひゃくりけい)」のエピソードは「史記・秦本紀」から。(2)「菅夷吾(かんいご)」は「史記・斉太公世家」から。
(1)「繆公は任好(にんこう)の元年、自ら将として茅津(ぼうしん)を伐って勝った。四年、晋から妻を迎えた。晋の太子申生(しんせい)の姉である。その年、斉の桓公が楚を伐ち、邵陵(しょうりょう=河南・許昌の東南方)に行った。五年、晋の献公が虞(ぐ)・虢(かく)を滅ぼし、虞の君と大夫の百里奚(ひゃくりけい)を虜にした。璧(たま)と馬で虞人を買収した結果である。百里奚を虜にすると、秦の繆公の夫人の侍臣にした(百里奚は虞の君の仕えるに足らないのを知り、はやく虞を逃れ虜にならなかったという説がある)。百里奚は秦を逃げ出して、苑(えん=河南・南陽地方)に行ったところ、楚の里人にとらえられた。繆公は百里奚の賢明なのを聞き、重く買いとろうと思ったが、楚人が引き渡さないかもしれないと、人を楚にやって、『貴地にわが侍臣の百里奚がいるが羖羊(めひつじ)の皮五枚でつぐないたい』と言わした。楚人はついに許して百里奚を与えた」(「秦本紀・第五」『史記1・本紀・P.107』ちくま学芸文庫 一九九五年)
(2)「桓公は即位すると、直ちに出兵して魯を攻め、管仲を殺そうと考えていた。すると鮑叔牙(ほうしゅくが)が言った。『わたくしは幸いにもわが君に従うことができ、わが君はついに位にお即(つ)きになりました。しかし、わが君の尊さは、これ以上わたくしらによって増すことはできませぬ。わが君がただ斉一国を統治なさるなら、高傒とわたくしとだけで足りましょうが、もし天下の覇者になろうと思し召すなら、何としても管夷吾(かんいご=管仲、名は夷吾)を手に入れなくてはなりませぬ。夷吾のいる国は、国として重きをなします。彼を失ってはなりませぬ』。桓公はそのことばに従った。そこでいつわって管仲を呼びだし、ぞんぶんに処置するふうをよそおいながら、実は彼を登用しようとした。管仲にはそれがわかっていたので、自らゆくことを願ったのである。鮑叔牙が迎えに行って管仲を引き取った。堂阜(どうふ=斉の国都に近い地)に到着すると手足の桎梏(かせ)をはずし、身を清め祓(はろ)うて桓公に謁見した。桓公は礼を厚くして大夫に取り立て、国政にあずからせた」(「斉太公世家・第二」『史記3・世家・上・P.38~39』ちくま学芸文庫 一九九五年)
さらに孔子の弟子たちにとって百里奚(ひゃくりけい)のケースはさておくとしても、菅夷吾(かんいご)の身の振る舞い方はなかなか納得できるものではなかった。
「菅夷吾は、召忽(しょうこつ)とともに死せざりしを、子路(しろ)、『仁(じん)にあらず』と譏(そし)りしかば、『豈(あ)に匹夫匹婦(ひっぷひっぷ)の諒(まこと)を為(な)して、自ら溝瀆(こうとく)に経(くび)れて知らるること莫(な)きが若(ごと)くならんや』と」(「太平記6・第三十九・一・P.138」岩波文庫 二〇一六年)
「論語」から二箇所引用して語らせるしかない。子路の問いに孔子が答える場面。
(1)「子路曰、桓公殺公子糾、召忽死之、管仲不死、曰未仁乎、子曰、桓公九合諸侯、不以兵車、管仲之力也、如其仁、如其仁
(書き下し)子路曰(い)わく、桓(かん)公、公子(こうし)糾(きゅう)を殺す。召忽(しょうこつ)これに死し、管仲(かんちゅう)は死せず。曰わく、未だ仁ならざるか。子曰わく、桓公、諸侯を九合して、兵車を以てせざるは、管仲の力なり。その仁に如(し)かんや、その仁に如(し)かんや。
(現代語訳)子路がおたずねした。『斉の桓公が競争者の兄公子糾を殺したとき、その付け人であった召忽は君に殉じて死んだが、管仲は生き残って桓公につかえました。これは仁徳に反するといえませんか』。先生がいわれた。『桓公は諸侯を九度集めて会盟を開いたが、武力をもって強制したのではなかった。これはまったく管仲のおかげであった。だれがこの仁徳に及ぶものがあろうか。だれがこの仁徳に及ぶものがあろうか』」(「論語・第七巻・第十四・憲問篇・五・P.399~400」中公文庫 一九七三年)
次に同様の事例について、子貢の問いに孔子が答える場面。
(2)「子貢曰、管仲非仁者与、桓公公子糾、不能死、又相之、子曰、管仲相桓公覇諸侯、一匡天下、民到于今受其賜、微管仲、吾其被髪左衽矣、豈若匹夫匹婦之為諒也、自経於溝瀆而莫之知也
(書き下し)子貢曰(い)わく、管仲は仁者に非(あら)ざるか。桓公、公子糾を殺す。死すること能わず、またこれを相(たす)く、子曰わく、管仲、桓公を相けて諸侯に覇(は)たらしめ、天下を一匡(いっきょう)す。民、今に到(いた)るまでその賜(たまもの)を受く。管仲微(なか)りせば、吾(われ)それ髪(はつ)を被(こうむ)り衽(じん)を左にせん。豈(あに)匹夫匹婦(ひっぷひっぷ)の諒(まこと)を為(な)すや。自(みずか)ら溝瀆(こうとく)に経(くび)れてこれを知るもの莫(な)きが若(ごと)くならんや。
(現代語訳)子貢がおたずねした。『管仲は仁徳のある人ではないのでしょう。桓公が公子糾を殺害したとき、死におくれてしまい、それどころか、桓公の宰相になってこれを助けたのですから』。先生がいわれた。『管仲は桓公を助けて諸侯の覇者とならせ、天下を改革した。人民は現在までそのおかげをこうむっている。管仲が出なかったとしたならば、われわれは今、ざんばら髪に衿(えり)を左前に着ているだろうよ。どうして管仲のような大人物が、一般の男女のように、ちょっとした誠(まこと)を立てるために首つり自殺をして、死骸(しがい)を溝(どぶ)に投げ込まれ、だれにもわからなくなってしまうのと同じようにすべきだと考えられよう』」(「論語・第七巻・第十四・憲問篇・十八・P.401~402」中公文庫 一九七三年)
いつも礼儀を重んじる孔子。とはいえ殉死の風習が常識かつ礼にかなった時代であろうともそれが常に正しいとは限らないと言うわけである。さらに政治的覇者についての評価も孔子にすれば世間の評価と比較して必ずしも一致するとは限らずむしろ一致しない場合が多い。また、孔子は管仲「のような大人物」の言動と一般民衆のそれとを同列に論じることはできないとする。今の言葉で言えば孔子は人材育成に関し、個人的性格や出身階級のばらつきにこだわるタイプではないが、「やればできる。やらなければそれがその人間の限界である」とする精神論の立場を取る。
ところで話は多少脱線するが、たとえ異教徒であっても自陣営に置いておきたい逸材というのはどの時代にもいる。例えば「高僧伝」に出てくる「曇無讖(どんむしん)」のケース。
「曇無讖(どんむしん)はある時、蒙遜(もうそん)に告げた。『幽鬼が集落におし入って来る。きっと疫病が大流行するだろう』。蒙遜は信用せず、自分の目でたしかめたいと思った。曇無讖はさっそく呪術を蒙遜の身に加え、蒙遜は幽鬼を見てちぢみ上がった。曇無讖は『精進潔斎し、神呪でもって追っ払うべきだ』と言い、そこで三日をかけて呪文を誦えたうえ、蒙遜に言った。『幽鬼はもう立ち去った』。その時、国界で幽鬼を見た者がおり、『数百の疫病神があたふたと逃げ去ってゆくのを見た』と言った」(「高僧伝1・巻第二・訳経篇中・曇無讖・P.217」岩波文庫 二〇〇九年)
明らかに仏教徒ではない。ガンジス川流域出身らしいが「涅槃教」に出会い仏教徒へ宗旨替えした謎の「怪僧」。こんなエピソードが見える。
「経典のテキストを失ってはなるまいと枕にして寝ていたところ、何者かがそれを地べたに引きずり下ろそうとする。曇無讖はびっくりして目覚め、盗人だと思った。そんなことが三晩つづき、空中に声が聞こえた。『これは如来の解脱の法蔵である。どうしてそれを枕にするのか』。曇無讖はそこではっと気づいて恥じ入り、特別に高い場所に置いた。夜中にそれを盗もうとした者があり、何度も持ち上げようとするが、まったく持ち上げられない。翌朝、曇無讖が経典を持ち運ぶと、重そうな様子はない。盗もうとした者はそれを見て聖人だと思い、そろってやって来て拝礼してわびた」(「高僧伝1・巻第二・訳経篇中・曇無讖・P.214~215」岩波文庫 二〇〇九年)
だが逆説は、その力の「逸脱=過剰」によって有名になればなるほど周囲が放っておかないことだ。北魏の託跋燾(たくばつとう)が軍事力を振りかざしつつ曇無讖を寄越せと蒙遜(もうそん)に迫ってきた。一度は話し合いですり抜けることができた。しかし二度目はそうはいかない。北魏はさらに本格的な軍事力を誇示して蒙遜を脅迫した。そこで曇無讖は自ら政治闘争の場から離れようとする。立場の変化が本来の目的を有無をいわせず捻じ曲げていくことに耐え難い憂鬱を感じるのだ。こうある。
「北魏の胡虜の託跋燾(たくばつとう)は曇無讖が道術を身に備えていると聞き、使者を遣わして招請するとともに、『もし讖を遣わさなれば、ただちに武力攻撃を加えるぞ』と蒙遜に通告したが、蒙遜は長年にわたって曇無讖に師事していたので、立ち去るのを許すに忍びなかった。その後、北魏はまた偽政権の太常(たいじょう)の高平公李順(りじゅん)を遣わして蒙遜を使持節・侍中・都督涼州西域諸軍事・太傅・驃騎大将軍・涼州牧・涼王に拝命し、九錫(きゅうしゃく)の礼を加えるとともに、さらにまた蒙遜にこう命じた。『聞けばその地には曇摩讖法師がおられ、博学で知識の豊かなことは羅什(らじゅう)の仲間、秘密の呪文の神秘的な効験は澄(ちょう)公の類(たぐい)であるとか。朕は仏道について講義してもらいたく思う。駅馬を馳せて送り届けるがよい』。蒙遜は李順と新楽門の上で宴会し、蒙遜は李順に言った。『西蕃の老臣なる蒙遜、朝廷に仕えたてまつり、不届き千万なことは何ら致さぬのに、しかるに天子様におかれては諂(へつら)いの言葉を信じて受け入れられ、わけもなしにきつく追いつめられる。先日、上表して曇無讖を手元に留めおきたくお頼み申したにもかかわらず、今ここにやって来られて差し出せとの仰せ。このお方はわが一門にとっての老師、一緒に命を落とすのが当然のこと、残された齢(よわい)はまったく惜しくはない。人間生まれては必ず死ぬのがさだめ、いかほどの時間とも思われぬ』。李順は言った。『王の誠実ぶりは以前から際立ち、愛(いと)しの皇子を侍子として入朝させられた。朝廷におかれては王の忠勤を愛(め)でられ、それ故、あきらけくも特別の礼遇を加えられたのである。しかるに王はこの一人の胡僧のために山岳を築くべきほどの偉大な功業を台なしにされ、たった一日の怒りの気持ちを抑えきれず、これまでの美事を損なわれる。そんなことでは朝廷が厚遇されるわけがあろうか。窃(ひそ)かに大王のために賛成しかねる次第だ。主上のこのうえなき虚心坦懐なお気持ちは、弘文(こうぶん)の承知しているところである』。弘文とは蒙遜が北魏に派遣した使者である。蒙遜は言った。『太常どのはまるで蘇秦(そしん)のように口がお上手。恐らく心の中はお言葉とは裏腹なのであろう』。蒙遜は曇無讖を惜しんで遣わさなかったため、再度また北魏から強迫された。蒙遜の義和三年(四二二)三月に至って、曇無讖は西方に旅に出ることを固く請い、あらたに『涅槃教』の後段を探し求めようとした。蒙遜は彼が立ち去ろうとすることに立腹し、そこで密かに曇無讖の殺害を計画した。うわべは取りつくろって食料を支給して出発させ、手厚く財宝を贈り物としたが、出発の日に臨んで、曇無讖はなんと涙を流しながら大衆に告げた。『私には前世の業(ごう)の報いが訪れようとしている。衆聖がたも救うことはできぬ。そもそも心に誓ったことなので、ここに留まるわけにはゆかぬのだ』。出発するに及んで、蒙遜は果して刺客を遣わして道中において殺害させた。享年は四十九。この歳は宋の元嘉十年(四三三)であった。出家も在家も、遠くの者も近くの者もこぞって残念がった。やがて蒙遜のまわりの者は、白昼に鬼神が剣を持って蒙遜に撃ちかかるのを絶えず目にした。四月に至って、蒙遜は病床に臥せって亡くなった」(「高僧伝1・巻第二・訳経篇中・曇無讖・P.221~223」岩波文庫 二〇〇九年)
しかしこのエピソードはただ単に人材登用を巡る政治闘争という凡庸な枠組みでは語りきれない。というのは、曇無讖に対する蒙遜の同性愛的神格化、並びに託跋燾の乱入による三角関係の出現という事態が生じているからである。蒙遜は曇無讖を託跋燾に取られるくらいなら、むしろ曇無讖を殺してしまいたいと欲望しそのとおり殺害した。ところが最愛の同性愛者を失った蒙遜は自分で暗殺を命じておきながら失意のあまり発病。一年後に死去する。このケースで最も傷ついたのは誰か。うすうす自分の将来に暗雲が垂れ込めているのを察し、なおかつ実際に殺された曇無讖ではない。他の誰でもなく暗殺を命じた蒙遜である。さらに述べると、曇無讖に対する至上の同性愛を蒙遜に意識化させたのは託跋燾の国家的圧力の介入による。同じことだが曇無讖に対する蒙遜の同性愛的欲望はその時はじめて因果関係を出現させている点にも注目すべきだろう。
このように貨幣でも軍事力でも解決できないリビドーの流れを解決に導く過程の到来は近代資本主義社会の成立を待たねばならない。貨幣は大事だ。資本主義は貨幣がなければ誰一人として生きていけない世界を樹立させた。今や貨幣は生活していくために必要不可欠な価値物となった。そしてその制度のもとで不要不急の貨幣蓄蔵者とただちに貨幣を必要とする貧困層との格差があまりにも増大した。このような状態を放置して遊んでいたのがかつてのロシアであり中国である。国家は転倒した。その教訓から社会保障制度を取り入れた戦後資本主義は延命する手段を学んだ。資本主義は自分自身を延命させつつ同時に自己目的をも達成するため日夜様々な「公理系」を発明して取り入れ組み込み、もはや諸個人の身体の内部まですっかりデータ化され浸透している。いつどこへどれくらいの貨幣を融通するのがベターか、逆に融通させないのがベターか。貨幣を与えることはとりもなおさず職業もしくは社会保障を与えることである。それができなくては資本は誰の手元へも還流することができない。店頭に並んだ商品が買われなければ資本主義は価値を実現することができず破滅するほかない。破滅を回避したければ資本は労働力を買わなくてはならない。すぐにでも買わなければ自滅する資本の側が今や幾らでもあるからである。
BGM1
BGM2
BGM3
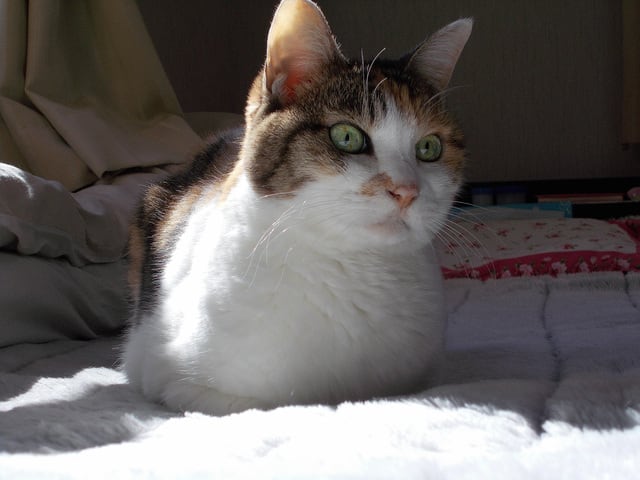
「堯(ぎょう)の代に四凶(しきょう)の族(ぞく)あり。魯国(ろこく)に小正茅(しょうせいぼう)あり」(「太平記6・第三十九・一・P.137」岩波文庫 二〇一六年)
漢籍から二箇所引かれている。一つは「堯(ぎょう)の代に四凶(しきょう)の族(ぞく)あり」。次に「魯国(ろこく)に小正茅(しょうせいぼう)あり」。前者は堯の後を継いだ舜によって罰せられた。「四凶(しきょう)の族(ぞく)」は「讙兜(かんとう)・共工(きょうこう)・三苗(さんびょう)・鯀(こん)」の四者。
(1)「讙兜(かんとう)が共工を推薦したとき、堯はそれをしりぞけて工師(土木の長官)にしたが、はたして共工は淫(みだ)らでよこしまで、効果があがらなかった。また、四嶽が鯀(こん)を推薦して洪水を治めさせようとしたとき、堯はやはり、それをしりぞけたが、四嶽が強いて試してみるように言ったので、試したところ、はたして成績が挙らず、百姓が困った。また当時、江淮(こうわい)地方には三苗(さんびょう)がいて、しばしば乱をおこしていたので、舜は巡狩から帰ると帝堯に、共工を幽陵に流して北狄(ほくてき)の風俗を変え、讙兜を崇山(すうざん)に放って南蛮の風俗を変え、三苗を三危(さんき=甘粛の西方にあるといわれる山)にうつして西戎(せいじゅう)の風俗を変え、鯀を羽山に逐うて東夷の風俗を変えるように請うた。この四者が罰せられて天下が、ことごとく服従した」(「五帝本紀・第一」『史記1・本紀・P.18』ちくま学芸文庫 一九九五年)
後者にある「魯国(ろこく)に小正茅(しょうせいぼう)」。孔子によって誅殺され、孔子は魯国の重鎮となる。
(2)「魯の大夫で政治を乱した少政卯(しょうせいぼう)を誅し、自ら国政に参与した」(「孔子世家・第十七」『史記4・世家・下・P.88』ちくま学芸文庫 一九九五年)
さらに繰り返し反復されるフレーズ。
「死をば善道(ぜんどう)に守り」(「太平記6・第三十九・一・P.137」岩波文庫 二〇一六年)
この箇所はもう何度繰り返されたか覚えていないほど。「論語」から「守死善道」の部分のみをそのまま書き下したものだが、なぜか「太平記」はいつもこのセンテンスの他の部分を無視した上で引用するのが特徴的。
「子曰、篤信好学、守死善道、危邦不入、乱邦不居、天下有道則見、無道則隠、邦有道、貧且賤焉恥也、邦無道、富且貴焉恥也
(書き下し)子曰わく、篤(あつ)く信じて学を好み、死にいたるまで守りて道を善(よ)くす。危邦(きほう)には入らず、乱邦(らんぽう)には居らず。天下道あるときは則(すなわ)ち見(あら)われ、道なきときは則ち隠る。邦(くに)に道あるとき、貧しく且(か)つ賤(いや)しきは恥なり。邦に道なきとき、富み且つ貴きは恥なり。
(現代語訳)先生がいわれた。『かたい信念をもって学問を愛し、死にいたるまで守りつづけて道をほめたたえる。危機にのぞんだ国家に入国せず、内乱のある国家には長く滞在しない。天下に道義が行われる太平の世には、表にたって活動するが、道義が失われる乱世には裏に隠れる。道義が行なわれる国家において、貧乏で無名の生活をおくるのは不名誉なことである。道義が行なわれない国家において、財産をもち高位に上るのは不名誉なことである』」(「論語・第四巻・第八・泰伯篇・十三・P.223~224」中公文庫 一九七三年)
次はやや込み入った条件における対応についての是非が焦点。
「百里奚(ひゃくりけい)は虞(ぐ)の君を棄てて、秦(しん)の穆公(ぼくこう)に仕へ、菅夷吾(かんいご)は桓公(かんこう)に下つて、公子(こうし)糾(きゅう)とともに死せざりしはいかに」(「太平記6・第三十九・一・P.138」岩波文庫 二〇一六年)
二つの事例が続けざまに問われる。(1)「百里奚(ひゃくりけい)」のエピソードは「史記・秦本紀」から。(2)「菅夷吾(かんいご)」は「史記・斉太公世家」から。
(1)「繆公は任好(にんこう)の元年、自ら将として茅津(ぼうしん)を伐って勝った。四年、晋から妻を迎えた。晋の太子申生(しんせい)の姉である。その年、斉の桓公が楚を伐ち、邵陵(しょうりょう=河南・許昌の東南方)に行った。五年、晋の献公が虞(ぐ)・虢(かく)を滅ぼし、虞の君と大夫の百里奚(ひゃくりけい)を虜にした。璧(たま)と馬で虞人を買収した結果である。百里奚を虜にすると、秦の繆公の夫人の侍臣にした(百里奚は虞の君の仕えるに足らないのを知り、はやく虞を逃れ虜にならなかったという説がある)。百里奚は秦を逃げ出して、苑(えん=河南・南陽地方)に行ったところ、楚の里人にとらえられた。繆公は百里奚の賢明なのを聞き、重く買いとろうと思ったが、楚人が引き渡さないかもしれないと、人を楚にやって、『貴地にわが侍臣の百里奚がいるが羖羊(めひつじ)の皮五枚でつぐないたい』と言わした。楚人はついに許して百里奚を与えた」(「秦本紀・第五」『史記1・本紀・P.107』ちくま学芸文庫 一九九五年)
(2)「桓公は即位すると、直ちに出兵して魯を攻め、管仲を殺そうと考えていた。すると鮑叔牙(ほうしゅくが)が言った。『わたくしは幸いにもわが君に従うことができ、わが君はついに位にお即(つ)きになりました。しかし、わが君の尊さは、これ以上わたくしらによって増すことはできませぬ。わが君がただ斉一国を統治なさるなら、高傒とわたくしとだけで足りましょうが、もし天下の覇者になろうと思し召すなら、何としても管夷吾(かんいご=管仲、名は夷吾)を手に入れなくてはなりませぬ。夷吾のいる国は、国として重きをなします。彼を失ってはなりませぬ』。桓公はそのことばに従った。そこでいつわって管仲を呼びだし、ぞんぶんに処置するふうをよそおいながら、実は彼を登用しようとした。管仲にはそれがわかっていたので、自らゆくことを願ったのである。鮑叔牙が迎えに行って管仲を引き取った。堂阜(どうふ=斉の国都に近い地)に到着すると手足の桎梏(かせ)をはずし、身を清め祓(はろ)うて桓公に謁見した。桓公は礼を厚くして大夫に取り立て、国政にあずからせた」(「斉太公世家・第二」『史記3・世家・上・P.38~39』ちくま学芸文庫 一九九五年)
さらに孔子の弟子たちにとって百里奚(ひゃくりけい)のケースはさておくとしても、菅夷吾(かんいご)の身の振る舞い方はなかなか納得できるものではなかった。
「菅夷吾は、召忽(しょうこつ)とともに死せざりしを、子路(しろ)、『仁(じん)にあらず』と譏(そし)りしかば、『豈(あ)に匹夫匹婦(ひっぷひっぷ)の諒(まこと)を為(な)して、自ら溝瀆(こうとく)に経(くび)れて知らるること莫(な)きが若(ごと)くならんや』と」(「太平記6・第三十九・一・P.138」岩波文庫 二〇一六年)
「論語」から二箇所引用して語らせるしかない。子路の問いに孔子が答える場面。
(1)「子路曰、桓公殺公子糾、召忽死之、管仲不死、曰未仁乎、子曰、桓公九合諸侯、不以兵車、管仲之力也、如其仁、如其仁
(書き下し)子路曰(い)わく、桓(かん)公、公子(こうし)糾(きゅう)を殺す。召忽(しょうこつ)これに死し、管仲(かんちゅう)は死せず。曰わく、未だ仁ならざるか。子曰わく、桓公、諸侯を九合して、兵車を以てせざるは、管仲の力なり。その仁に如(し)かんや、その仁に如(し)かんや。
(現代語訳)子路がおたずねした。『斉の桓公が競争者の兄公子糾を殺したとき、その付け人であった召忽は君に殉じて死んだが、管仲は生き残って桓公につかえました。これは仁徳に反するといえませんか』。先生がいわれた。『桓公は諸侯を九度集めて会盟を開いたが、武力をもって強制したのではなかった。これはまったく管仲のおかげであった。だれがこの仁徳に及ぶものがあろうか。だれがこの仁徳に及ぶものがあろうか』」(「論語・第七巻・第十四・憲問篇・五・P.399~400」中公文庫 一九七三年)
次に同様の事例について、子貢の問いに孔子が答える場面。
(2)「子貢曰、管仲非仁者与、桓公公子糾、不能死、又相之、子曰、管仲相桓公覇諸侯、一匡天下、民到于今受其賜、微管仲、吾其被髪左衽矣、豈若匹夫匹婦之為諒也、自経於溝瀆而莫之知也
(書き下し)子貢曰(い)わく、管仲は仁者に非(あら)ざるか。桓公、公子糾を殺す。死すること能わず、またこれを相(たす)く、子曰わく、管仲、桓公を相けて諸侯に覇(は)たらしめ、天下を一匡(いっきょう)す。民、今に到(いた)るまでその賜(たまもの)を受く。管仲微(なか)りせば、吾(われ)それ髪(はつ)を被(こうむ)り衽(じん)を左にせん。豈(あに)匹夫匹婦(ひっぷひっぷ)の諒(まこと)を為(な)すや。自(みずか)ら溝瀆(こうとく)に経(くび)れてこれを知るもの莫(な)きが若(ごと)くならんや。
(現代語訳)子貢がおたずねした。『管仲は仁徳のある人ではないのでしょう。桓公が公子糾を殺害したとき、死におくれてしまい、それどころか、桓公の宰相になってこれを助けたのですから』。先生がいわれた。『管仲は桓公を助けて諸侯の覇者とならせ、天下を改革した。人民は現在までそのおかげをこうむっている。管仲が出なかったとしたならば、われわれは今、ざんばら髪に衿(えり)を左前に着ているだろうよ。どうして管仲のような大人物が、一般の男女のように、ちょっとした誠(まこと)を立てるために首つり自殺をして、死骸(しがい)を溝(どぶ)に投げ込まれ、だれにもわからなくなってしまうのと同じようにすべきだと考えられよう』」(「論語・第七巻・第十四・憲問篇・十八・P.401~402」中公文庫 一九七三年)
いつも礼儀を重んじる孔子。とはいえ殉死の風習が常識かつ礼にかなった時代であろうともそれが常に正しいとは限らないと言うわけである。さらに政治的覇者についての評価も孔子にすれば世間の評価と比較して必ずしも一致するとは限らずむしろ一致しない場合が多い。また、孔子は管仲「のような大人物」の言動と一般民衆のそれとを同列に論じることはできないとする。今の言葉で言えば孔子は人材育成に関し、個人的性格や出身階級のばらつきにこだわるタイプではないが、「やればできる。やらなければそれがその人間の限界である」とする精神論の立場を取る。
ところで話は多少脱線するが、たとえ異教徒であっても自陣営に置いておきたい逸材というのはどの時代にもいる。例えば「高僧伝」に出てくる「曇無讖(どんむしん)」のケース。
「曇無讖(どんむしん)はある時、蒙遜(もうそん)に告げた。『幽鬼が集落におし入って来る。きっと疫病が大流行するだろう』。蒙遜は信用せず、自分の目でたしかめたいと思った。曇無讖はさっそく呪術を蒙遜の身に加え、蒙遜は幽鬼を見てちぢみ上がった。曇無讖は『精進潔斎し、神呪でもって追っ払うべきだ』と言い、そこで三日をかけて呪文を誦えたうえ、蒙遜に言った。『幽鬼はもう立ち去った』。その時、国界で幽鬼を見た者がおり、『数百の疫病神があたふたと逃げ去ってゆくのを見た』と言った」(「高僧伝1・巻第二・訳経篇中・曇無讖・P.217」岩波文庫 二〇〇九年)
明らかに仏教徒ではない。ガンジス川流域出身らしいが「涅槃教」に出会い仏教徒へ宗旨替えした謎の「怪僧」。こんなエピソードが見える。
「経典のテキストを失ってはなるまいと枕にして寝ていたところ、何者かがそれを地べたに引きずり下ろそうとする。曇無讖はびっくりして目覚め、盗人だと思った。そんなことが三晩つづき、空中に声が聞こえた。『これは如来の解脱の法蔵である。どうしてそれを枕にするのか』。曇無讖はそこではっと気づいて恥じ入り、特別に高い場所に置いた。夜中にそれを盗もうとした者があり、何度も持ち上げようとするが、まったく持ち上げられない。翌朝、曇無讖が経典を持ち運ぶと、重そうな様子はない。盗もうとした者はそれを見て聖人だと思い、そろってやって来て拝礼してわびた」(「高僧伝1・巻第二・訳経篇中・曇無讖・P.214~215」岩波文庫 二〇〇九年)
だが逆説は、その力の「逸脱=過剰」によって有名になればなるほど周囲が放っておかないことだ。北魏の託跋燾(たくばつとう)が軍事力を振りかざしつつ曇無讖を寄越せと蒙遜(もうそん)に迫ってきた。一度は話し合いですり抜けることができた。しかし二度目はそうはいかない。北魏はさらに本格的な軍事力を誇示して蒙遜を脅迫した。そこで曇無讖は自ら政治闘争の場から離れようとする。立場の変化が本来の目的を有無をいわせず捻じ曲げていくことに耐え難い憂鬱を感じるのだ。こうある。
「北魏の胡虜の託跋燾(たくばつとう)は曇無讖が道術を身に備えていると聞き、使者を遣わして招請するとともに、『もし讖を遣わさなれば、ただちに武力攻撃を加えるぞ』と蒙遜に通告したが、蒙遜は長年にわたって曇無讖に師事していたので、立ち去るのを許すに忍びなかった。その後、北魏はまた偽政権の太常(たいじょう)の高平公李順(りじゅん)を遣わして蒙遜を使持節・侍中・都督涼州西域諸軍事・太傅・驃騎大将軍・涼州牧・涼王に拝命し、九錫(きゅうしゃく)の礼を加えるとともに、さらにまた蒙遜にこう命じた。『聞けばその地には曇摩讖法師がおられ、博学で知識の豊かなことは羅什(らじゅう)の仲間、秘密の呪文の神秘的な効験は澄(ちょう)公の類(たぐい)であるとか。朕は仏道について講義してもらいたく思う。駅馬を馳せて送り届けるがよい』。蒙遜は李順と新楽門の上で宴会し、蒙遜は李順に言った。『西蕃の老臣なる蒙遜、朝廷に仕えたてまつり、不届き千万なことは何ら致さぬのに、しかるに天子様におかれては諂(へつら)いの言葉を信じて受け入れられ、わけもなしにきつく追いつめられる。先日、上表して曇無讖を手元に留めおきたくお頼み申したにもかかわらず、今ここにやって来られて差し出せとの仰せ。このお方はわが一門にとっての老師、一緒に命を落とすのが当然のこと、残された齢(よわい)はまったく惜しくはない。人間生まれては必ず死ぬのがさだめ、いかほどの時間とも思われぬ』。李順は言った。『王の誠実ぶりは以前から際立ち、愛(いと)しの皇子を侍子として入朝させられた。朝廷におかれては王の忠勤を愛(め)でられ、それ故、あきらけくも特別の礼遇を加えられたのである。しかるに王はこの一人の胡僧のために山岳を築くべきほどの偉大な功業を台なしにされ、たった一日の怒りの気持ちを抑えきれず、これまでの美事を損なわれる。そんなことでは朝廷が厚遇されるわけがあろうか。窃(ひそ)かに大王のために賛成しかねる次第だ。主上のこのうえなき虚心坦懐なお気持ちは、弘文(こうぶん)の承知しているところである』。弘文とは蒙遜が北魏に派遣した使者である。蒙遜は言った。『太常どのはまるで蘇秦(そしん)のように口がお上手。恐らく心の中はお言葉とは裏腹なのであろう』。蒙遜は曇無讖を惜しんで遣わさなかったため、再度また北魏から強迫された。蒙遜の義和三年(四二二)三月に至って、曇無讖は西方に旅に出ることを固く請い、あらたに『涅槃教』の後段を探し求めようとした。蒙遜は彼が立ち去ろうとすることに立腹し、そこで密かに曇無讖の殺害を計画した。うわべは取りつくろって食料を支給して出発させ、手厚く財宝を贈り物としたが、出発の日に臨んで、曇無讖はなんと涙を流しながら大衆に告げた。『私には前世の業(ごう)の報いが訪れようとしている。衆聖がたも救うことはできぬ。そもそも心に誓ったことなので、ここに留まるわけにはゆかぬのだ』。出発するに及んで、蒙遜は果して刺客を遣わして道中において殺害させた。享年は四十九。この歳は宋の元嘉十年(四三三)であった。出家も在家も、遠くの者も近くの者もこぞって残念がった。やがて蒙遜のまわりの者は、白昼に鬼神が剣を持って蒙遜に撃ちかかるのを絶えず目にした。四月に至って、蒙遜は病床に臥せって亡くなった」(「高僧伝1・巻第二・訳経篇中・曇無讖・P.221~223」岩波文庫 二〇〇九年)
しかしこのエピソードはただ単に人材登用を巡る政治闘争という凡庸な枠組みでは語りきれない。というのは、曇無讖に対する蒙遜の同性愛的神格化、並びに託跋燾の乱入による三角関係の出現という事態が生じているからである。蒙遜は曇無讖を託跋燾に取られるくらいなら、むしろ曇無讖を殺してしまいたいと欲望しそのとおり殺害した。ところが最愛の同性愛者を失った蒙遜は自分で暗殺を命じておきながら失意のあまり発病。一年後に死去する。このケースで最も傷ついたのは誰か。うすうす自分の将来に暗雲が垂れ込めているのを察し、なおかつ実際に殺された曇無讖ではない。他の誰でもなく暗殺を命じた蒙遜である。さらに述べると、曇無讖に対する至上の同性愛を蒙遜に意識化させたのは託跋燾の国家的圧力の介入による。同じことだが曇無讖に対する蒙遜の同性愛的欲望はその時はじめて因果関係を出現させている点にも注目すべきだろう。
このように貨幣でも軍事力でも解決できないリビドーの流れを解決に導く過程の到来は近代資本主義社会の成立を待たねばならない。貨幣は大事だ。資本主義は貨幣がなければ誰一人として生きていけない世界を樹立させた。今や貨幣は生活していくために必要不可欠な価値物となった。そしてその制度のもとで不要不急の貨幣蓄蔵者とただちに貨幣を必要とする貧困層との格差があまりにも増大した。このような状態を放置して遊んでいたのがかつてのロシアであり中国である。国家は転倒した。その教訓から社会保障制度を取り入れた戦後資本主義は延命する手段を学んだ。資本主義は自分自身を延命させつつ同時に自己目的をも達成するため日夜様々な「公理系」を発明して取り入れ組み込み、もはや諸個人の身体の内部まですっかりデータ化され浸透している。いつどこへどれくらいの貨幣を融通するのがベターか、逆に融通させないのがベターか。貨幣を与えることはとりもなおさず職業もしくは社会保障を与えることである。それができなくては資本は誰の手元へも還流することができない。店頭に並んだ商品が買われなければ資本主義は価値を実現することができず破滅するほかない。破滅を回避したければ資本は労働力を買わなくてはならない。すぐにでも買わなければ自滅する資本の側が今や幾らでもあるからである。
BGM1
BGM2
BGM3