私はどこかの小学校 にいた。
一度壊れたのちに復旧した校舎に戻ると、一人に一台ずつロッカーが与えられていた。前はこんなもの与えられていなかったのに。なんかへんな感じだなと私は思った。
与えられた灰色のロッカーに大切なものを三ついれた。白い手帳とおそらくはスケッチブックが入っている青いケース、それとあともうひとつ。薄くて長方形で、大きさは白い手帳よりも小さい。何だったのか思い出せないけど、これが一番大切だった気がする。だけどもう思い出せない。ロッカーに鍵はかかるけど、かけていなかった。鍵をかけなくちゃ、大切なものをいれても意味はないのに。
しかしこの三つをロッカーに入れたのは私ではなかった。
私は私の大切なものを子供に託して、その子供がロッカーにいれた。鍵はかけていなかった。たしか男の子だった。
私よりも年若い少年がいる。
夜の学校にいる。
灰色のロッカーが立ち並ぶ暗い廊下に、誰かの気配があった。確かに誰かの動く気配はある。けれどもその存在は確かではなく、気配はあるけど気配しかないような、そんなものがあった。
私と年若い少年は、それぞれの目的で夜の学校に来ていた。私の目的はすでに忘れてしまった。
少年は不安そうな顔つきで私をみて言った。
「ねえ、いま誰かいたよね?」
先ほどの気配を指差し問う少年に、私は「いた」とは答えなかった。
薄暗い廊下にパッと懐中電灯の明かりが広がった。
今度は確かな存在として、白衣を着ている見回りの男がそこにいた。
その見回りの男が何かを言い出す前に、私と少年は走って逃げた。夜の学校はすでに夜の学校ではなく、どこかの街の地下にある研究所に変わっていた。
地上へと伸びる階段の手前に年老いた犬が座っていた。犬はぴくりとも動かなかったが、私たちが通りすぎると「ワン、ワン」とさほど大きくはない声ででも絶え間なく鳴いていた。私と少年はカンカンと音をたてながら螺旋状に続く階段を駆けていった。
地上にでると三人の男の看守が酔っぱらって笑っていた。走ってでてきた私たちをみると、なんでこんな時間にこんな女子供がいるんだというような顔できょとんとしていた。
私と少年が鉄製の出入口からでると、彼らは慌てて私たちを追いかけた。
鉄製の出入口を抜けると、私は男と女の姿に別れ、男の姿の私は引き続き走って逃げた。女の姿の私はただの通行人となった。そこはどこかの駅前だった。
男の私と少年はばらばらにわかれて逃げたが、結局はつかまった。
地面に座り込んでいるつかまった少年に女の私は静かに近寄り、ぽんと頭をたたいて「お疲れさん」と言った。
男の私と少年はパトカーに連行された。
ちょうどそのタイミングで、駅のほうからひとりの女性が現れた。懐かしい顔をした女性だった。
女の私は彼女に言った。
「ほら、いまちょうど連れていかれるところだよ」
女の私も彼女もパトカーに連行される彼らを助けようとはしなかった。
おそらくは助けなくても大丈夫だという確信があった。
ちょうど夜も明けようとしていた。
一度壊れたのちに復旧した校舎に戻ると、一人に一台ずつロッカーが与えられていた。前はこんなもの与えられていなかったのに。なんかへんな感じだなと私は思った。
与えられた灰色のロッカーに大切なものを三ついれた。白い手帳とおそらくはスケッチブックが入っている青いケース、それとあともうひとつ。薄くて長方形で、大きさは白い手帳よりも小さい。何だったのか思い出せないけど、これが一番大切だった気がする。だけどもう思い出せない。ロッカーに鍵はかかるけど、かけていなかった。鍵をかけなくちゃ、大切なものをいれても意味はないのに。
しかしこの三つをロッカーに入れたのは私ではなかった。
私は私の大切なものを子供に託して、その子供がロッカーにいれた。鍵はかけていなかった。たしか男の子だった。
私よりも年若い少年がいる。
夜の学校にいる。
灰色のロッカーが立ち並ぶ暗い廊下に、誰かの気配があった。確かに誰かの動く気配はある。けれどもその存在は確かではなく、気配はあるけど気配しかないような、そんなものがあった。
私と年若い少年は、それぞれの目的で夜の学校に来ていた。私の目的はすでに忘れてしまった。
少年は不安そうな顔つきで私をみて言った。
「ねえ、いま誰かいたよね?」
先ほどの気配を指差し問う少年に、私は「いた」とは答えなかった。
薄暗い廊下にパッと懐中電灯の明かりが広がった。
今度は確かな存在として、白衣を着ている見回りの男がそこにいた。
その見回りの男が何かを言い出す前に、私と少年は走って逃げた。夜の学校はすでに夜の学校ではなく、どこかの街の地下にある研究所に変わっていた。
地上へと伸びる階段の手前に年老いた犬が座っていた。犬はぴくりとも動かなかったが、私たちが通りすぎると「ワン、ワン」とさほど大きくはない声ででも絶え間なく鳴いていた。私と少年はカンカンと音をたてながら螺旋状に続く階段を駆けていった。
地上にでると三人の男の看守が酔っぱらって笑っていた。走ってでてきた私たちをみると、なんでこんな時間にこんな女子供がいるんだというような顔できょとんとしていた。
私と少年が鉄製の出入口からでると、彼らは慌てて私たちを追いかけた。
鉄製の出入口を抜けると、私は男と女の姿に別れ、男の姿の私は引き続き走って逃げた。女の姿の私はただの通行人となった。そこはどこかの駅前だった。
男の私と少年はばらばらにわかれて逃げたが、結局はつかまった。
地面に座り込んでいるつかまった少年に女の私は静かに近寄り、ぽんと頭をたたいて「お疲れさん」と言った。
男の私と少年はパトカーに連行された。
ちょうどそのタイミングで、駅のほうからひとりの女性が現れた。懐かしい顔をした女性だった。
女の私は彼女に言った。
「ほら、いまちょうど連れていかれるところだよ」
女の私も彼女もパトカーに連行される彼らを助けようとはしなかった。
おそらくは助けなくても大丈夫だという確信があった。
ちょうど夜も明けようとしていた。










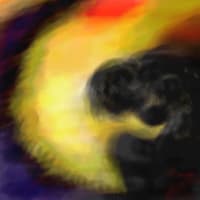

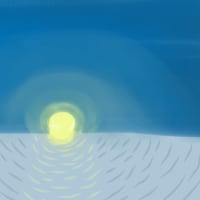
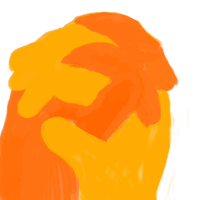




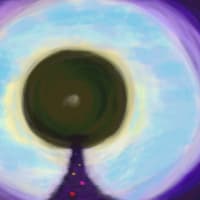
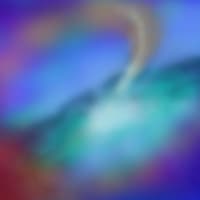
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます