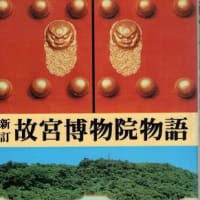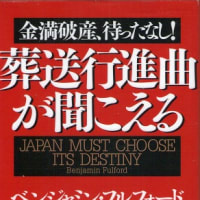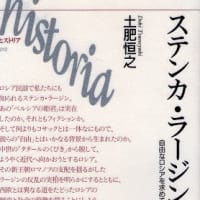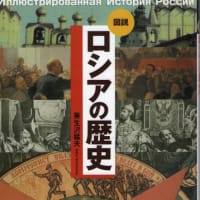例によって図書館から借りてきた本で「周恩来・最後の10年」という本を読んだ。
周恩来の最後の10年を彼の主治医が克明に綴ったもので、十分に読みでがあり、特に文化大革命の記述には手に汗を握る緊張感が漂っていた。
1960年代の中ほどから始まった中国の文化大革命というのは、当時、日本にはあまり克明には伝わってきていなかったと思う。
ところがこれも不思議なもので「造反有理」というスローガンは、巷に氾濫していたわけで、これは一体どういうことなのであろう。
この時代の中国は非常に厳しく情報管理をしていて、中国の現状は我々の側にオープンには伝わっていなかったと記憶するが、それでも文革のスローガンが日本で左翼系学生が唱えていたということは一体どういうことなのであろう。
中国のすることは、我々には理解し難い部分が沢山あるわけで、この本の中でも周恩来の病状を秘密にするということが何のてらいもなく語られているが、これは一体どういうことなのであろう。
国家の首脳が病気になったことなど、秘密にする必要はなさそうに思うが、これが政治の世界ではそうとも言えないらしい。
日本の歴史の中でも、武田信玄は自分の死を秘密するように言ったし、羽柴秀吉も織田信長の死を伏せて毛利と和解をはかったわけで、そういう意味で政治的な首脳者の死を秘密にして、取引を有利に導くことはあるが、中国の首脳ともなればそうそう秘密にするわけにもいかず、それがすぐに漏れることは言うまでもない。
そこで、その後に起きるであろう権力抗争に、その人の死が大きく関与することになるわけで、この部分が極めて中国的である。
私がその点を強調せざるを得ないのは、その部分が極めて土俗的で、民主化と対極の構図を成しているからである。
民主社会ならば、トップの首脳がいくら変わろうとも、事後策が確立しているので、権力構造が乱れるということはありえない。
アメリカの例でも、権力のトップの大統領が撃たれてもただちに副大統領がその職務を代行するわけで、権力の空白期間などというものはありえない。
ところが中国ではそうはならないわけで、トップが倒れるとそのトップの権力を奪還しようと、権力の座の奪い合いが生じるのである。
この本の中でも文化大革命のことが述べられているが、この文化大革命というのは一体何であったのだろう。
毛沢東の第3番目か4番目か知らないが、この紅青という毛沢東夫人とは一体どういう女性なのであろう。
文化大革命を書いた小説「ワイルド・スワン」でも「マオ」でも、極悪人と指摘されているが、人からそういうわれるだけの根拠があるから、そのように糾弾されているのだろうが、紅青がそれだけの悪人だったとしても、その彼女をそういう位置に留め置いたのは、中国の政治局の面々の実績でもあったわけで、それを突き詰めれば毛沢東の責任に帰してしまうではないか。
平たく押し並べて言えば、毛沢東が中国の政治の全責任を負うというのであれば、文化大革命の4人組の揚立そのこと自体が、毛沢東の全責任ということになってしまう。
毛沢東の責任をうんぬんする前に、紅青という女性が政治の場に出てくること自体がおかしなことで、我々の認識ではありえないことである。
そこに中国の政治の後進性が見事に露呈しているともいえるが、中国の政治には有史以来5千年の歴史があるわけで、それは共産主義のわずが20年か30年の歴史とは比較にならない差異であって、その中にあってこういうわけのわからない女性に政治の局面をかきまわされたということは、中国大陸にすむ人々の宿命なのかもしれない。
毛沢東夫人といえば、アメリカならば大統領夫人、日本ならば総理大臣の夫人、イギリスならばやはり総理大臣夫人となり、いわゆるトップ・レデイ―、ファースト・レディーであって、そういう立場の者が政治の場に自らしゃしゃり出ることはしないものである。
国家行事に花を添えるという意味で、トップ夫妻が並んで公に場に顔を出すということはあっても、それが夫人そのものが政治に関与するというのとは訳が違うはずである。
この事は、女性の政治参加を忌諱しているわけではなく、むしろトップの夫人としての身分をわきまえた、民主的な行為であって、いわゆる民主化の本質がよく分かっているということでもある。
民主化ということの本質がよくわかっていないから、トップ・レデイ―やファースト・レディーの立場のものが政治に嘴を差し挟むわけで、それだけ人々の民主化という価値観が浸透していないということを如実に表しているわけである。
紅青本人の政治認識もさることながら、それを容認している毛沢東そのものも、また彼女や彼らを取り巻いている取り巻き連中の政治認識の欠如も、本人以上に稚拙だということである。
紅青本人が政治局局員ということ自体が、毛沢東の女房に対する身贔屓であって、毛沢東自身、聡明な政治感覚があれば、自分の女房を政局員にすること自体おかしな話である。
アメリカ大統領が自ら開く閣議に自分の女房を出席させるであろうか。
日本の総理大臣が閣議の場に自分の女房を出席させるであろうか。
毛沢東はこれと同じことをしていたわけで、こんなバカな話はないと思う。
自分の女房にこんなことをさせる毛沢東もおかしければ、本人そのものの政治感覚も端からおかしいわけで、その毛沢東夫人に取りいって文化大革命を遂行している他の3人の考え方も、徹底的におかしいわけで、我々の感覚からすれば道理の通らないことが2乗にも3乗にも重なって露呈したのが文化大革命であったのではないかと思う。
共産主義革命というのは、既存の旧社会を根底から覆した後で、新秩序を構築する過程で多大な流血が避けられなかった。
これを実行せしめるエネルギーは、基本的にはインテリ―層が無知蒙昧な一般大衆をリードして、旧秩序を破壊し、新に秩序を作らねばならないが、旧秩序を破壊する過程で知識人というものを根絶やしにしてしまったものだから、新しい秩序を築き上げようとする段になると、それにふさわしい人材が不足してしまって、いわゆる無知で野蛮な人材をも渋々ある地位につかせねばならない。
無理もない話で、中国共産党は自分たちだけの力でアジア大陸の共産化に成功したわけではなく、大部分のエリアでは、軍閥や、盗賊や、馬賊や、国民党の各支部や、軍隊が、日和見で寝返った部分もかなり内包しているわけで、そういう連中を党内に抱えている限り、生粋の中国共産党員はいつまでたっても枕を高くして眠れなかったに違いない。
そこに以ってきて、初期の中国共産党の政策は失敗続きであったし、初期の革命を成した人々も、年月の経過とともにマンネリに陥りだしたわけで、安住を求めて冒険を避ける雰囲気が広がったので、そこに純粋な革命第2世代が反発を募らせたものと私は考える。
初期の革命を成した、革命第1世代は世の中が平穏になると安逸な生活を求めるようになり、これが純粋で素朴な思考の革命第2世代には我慢ならないことにうつり、それが革命第1世代を批判する方向に収斂されて行ったものと思う。
問題は、この一連の騒動の中で、中国の人々の間で、仁義も、モラルも、尊敬の念も、儒教思想の長幼の功も、あらゆる既存の価値観を否定したというところにある。
無理もない話で、革命ということは旧秩序の破壊そのものなわけで、それがなされれば人心が乱れるのも自然の摂理に則っている。
彼らの悠久の歴史を、自ら根底から覆したわけで、それを裏で煽っていた毛沢東と4人組の存在というのは、中国の歴史にとっては大きな汚点だったと思う。
毛沢東が死んだとき、彼の功罪は4分6で、善が4分で悪事が6分と評されたものだが、その6分の中にこの文化大革命がおそらく入っているであろう。
周恩来という人は、この毛沢東に影のように付き添ってきたにもかかわらず、中華人民共和国の功績はすべて毛沢東に寄せられるが、それは建国以来、毛沢東と周恩来の二人三脚で来たように見えるが、なぜかその功績は毛沢東のものになってしまう。
周恩来は中国建国以来、毛沢東の女房役のような役回りであったが、その彼をしても紅青の政治的な介入を阻止できなかったということは、どういうことなのであろう。
やはり毛沢東の夫人ということで遠慮があったということなのであろうか。
それに引き換え、紅青の方は、自分の旦那に周恩来の失脚を何度も進言して、その都度毛沢東はその進言を叱責しているわけで、毛沢東にしてみれば、自分の女房の言うことよりも周恩来の言うことに信を置いていたということになる。
当然と言えば当然のことで、中国共産党結党以来の朋友と、女優のなりそこないのような紅青とでは、その言葉の重さが最初から違うわけで、毛沢東にしてみれば、紅青の代わりはいくらもいるが、政治的に適切なアドバイスを得られる最も信頼できる人物としては、周恩来以外にいないわけで、その意味でいくら紅青が周恩来の失脚を願っても、それだけはかなわなかったに違いない。
我々が日本人として中国の文化大革命を見てみると、実に不可解なことが多い。
何故、国家権力でもない民衆が、学校の先生や行政のトップを引き降ろして、直接暴力を加えることが可能なのか不思議でならない。
民衆や学生が大学の先生や行政のトップを暴力で以ってひきづり出して、公衆の面前で殴ったり蹴ったりするということは、その事実だけで中国の人々の民度、知的レベル、倫理観、モラルが低い、ということを指し示しているわけで、別な言い方をすれば政治的に極めて未熟な大衆、民衆ということになる。
そういう人々が、毛沢東語録を掲げさえすれば、そういう卑劣で民意の低い人デナシのする行為が、気高い行為となるわけで、こんなバカな話があるものかと言いたい。
何が造反有理だ!!!!
ただの無頼、やくざ、無法者、愚連隊でしかないではないか。
毛沢東は、こういう連中を煽って、自分の建国当時の革命の同志の失脚を図ったわけで、それもこれも革命が軌道に乗ってくると、よそ事を考える余裕が出てきたので、自分の将来の不安がおぼつかなくなってきたからには他ならない。
「誰かが俺を追い落とすのではないか?」という不安に苛まれて、心安らかでおれなくなったに違いない。
この毛沢東の不安に乗じて紅青夫人を中心に、心の邪な3人が自分たちの政敵を追い落とすことをしたわけで、それは当然権力闘争になり、こういう権力闘争というのはどの政治局面でもあることで不思議ではないが、それを何の権力もない民衆、大衆が根も葉もない虚構を流すことによってまかり通る社会というのはもう人間の社会ではないと思う。
この文化大革命で日本の知識人が案外見落としていることに、この時期中国では都会のインテリ―を田舎に送ってそれを下放と言っていた。
この事実をよくよく見てみると、都会のインテリ―に懲罰を加える意味で地方の田舎に送って、そこで重労働をさせることに懲罰の意味があるわけで、ならば生まれ落ちた時から田舎に住んでいる人たちは一生涯牢屋の中で生きているということになるではないか。
この時期の中国では田舎の人間が都会に来ることを禁止していたが、これなどは田舎で農業に勤しんでいる人間を、人とみなしていないということで、だからこそ都会のインテリ―を田舎に送ることに懲罰としての意味があったわけである
さらにもう少し掘り下げてみると、都会のインテリ―に懲罰を課す主体は一体何なのかという問題である。
大学の学生委員会の長にそういう権限があるのかどうか、行政の中間管理職にそんな権限があるのかどうか、ただなんとなく野次馬の威勢のいい人から、理由もいい加減な罪状を言い渡されて、田舎に送られて農作業させられる人もたまったものではなかろうが、何とも弁解の機会もないわけで、こんなバカな話もない筈であるが、それが10年も続いたというのだから驚く。
10年たった後、その責任を誰かが負ったであろうか?
文化大革命というのは中国人がお互いに中国人を殺しあったわけで、外国に責任の及ぶものではないが、考えてみれば、これが中国5千年の歴史の現実なのであろう。
1949年の中華人民共和国の建国前は、中国の周りには夷狄の存在があって、政治の延長としての戦争は常に行われていたが、それが国家統一をなして夷狄の存在を内側に取り込んでしまったので、中国人同士の無意味な殺傷という形になったものと思う。
こういうことを考えると、我々と中国の人々とは、共通の認識というものが成り立たないわけで、それは物事を判断する基準の相違、いわゆる土俵が違うということで、いくら話しあったところで話が妥協点に導かれるということはあり得ない。
この本の著者は、周恩来の主治医という立場から、本人・周恩来に極めて好意的に描かれているが、中でも周恩来が極めて仕事熱心で、我々の言葉でワーカホリックであることを好意的にとらえているが、いくら政府の要人であろうとも、自分の体を顧みずに仕事に打ち込むということは、善意に解釈しきれない部分があると思う。
ある意味で、政務を私物化しているともとれるわけで、仕事をコントロールするということも要職にあればある程、心がけねばならない事柄だと思う。
しかし、病気、あるいは寿命というのは仕事熱心であろうとなかろうと公平に来るわけで、如何なる要人であろうとも、そういうときにはあっさりとそれを受け入れるべきだと思う。
その前に、要人であればあるほど、適当な時期に引退べきだと思う。
死ぬが死ぬまで権力にしがみつくというのは、私の感覚でいえばみっともない話だ。
その点、西洋人のリーダーは潔く引退して、悠々自適な生活を送るという例があるが、中国人は死ぬが死ぬまで権力にしがみついていないと死んだ時、墓さえ暴かれかねない。
韓国の例など実にすさましいもので、現職を降りたら最後、ただちに監獄に放り込まれてしまい、死刑の判決が下りたと思ったら、いきなり恩赦で無罪などという、まるでジェットコースターのような身の処し方を迫られる。
こういう状況が分かっているからこそ、権力に死ぬまでしがみついていなければならないのであろう。
権力を手放したら最後、ただの人以下になってしまうわけで、それが中国の5千年の歴史の教訓として息づいているのであろう。
死ぬまで権力にしがみつくというのは、不思議なことに、皆、共産主義社会のリーダーであって、自由主義陣営のリーダーは適当な時期に潔く引退しているが、これは共産主義というものの考え方を如実に指し示していると思う。
共産主義というのは基本的に、民主主義の一番遠い対極の位置にいるわけで、それこそ一度権力を手放したら、今度は自分が何時いかなる時に権力の餌食になるかわからないわけで、自分が過去に権力をほしいままにしていた以上、立場が逆転すればそのしっぺ返しは自らの過去に照らして想像できるわけで、ならば当然権力を放り投げるなどということはありえないということになる。
昨今の日本のリーダーを見てみると、安部晋三から福田康夫まで、まるで不甲斐ないリーダーに見えたものだが、中国に比べると、こういう人物が一度は総理の椅子に座って、まさしく自分の勝手で政権を放り出すことのできる世の中というのは、極めて恵まれた社会だということにもなると思う。
毛沢東や周恩来、金日成からスターリンと言うような人は、決してこんないい加減なことで政権を放り出すなどということはしえないわけで、死ぬまで政権を維持しなければ、墓まで暴かれかねなかったわけだ。
それに比べれば日本のリーダーなど極めて能天気な存在だ。
それは国民にも言えるわけで、我々は何処の誰べえとも分からない人間に、いきなり刑務所に入れられるようなバカな話もなく、強制労働などということもないわけで、労働しようにも仕事がないくらいで、その意味で、平和ボケになるのも当然である。
平和ボケと言っておれる間は幸せだと思わなければならない。
周恩来の最後の10年を彼の主治医が克明に綴ったもので、十分に読みでがあり、特に文化大革命の記述には手に汗を握る緊張感が漂っていた。
1960年代の中ほどから始まった中国の文化大革命というのは、当時、日本にはあまり克明には伝わってきていなかったと思う。
ところがこれも不思議なもので「造反有理」というスローガンは、巷に氾濫していたわけで、これは一体どういうことなのであろう。
この時代の中国は非常に厳しく情報管理をしていて、中国の現状は我々の側にオープンには伝わっていなかったと記憶するが、それでも文革のスローガンが日本で左翼系学生が唱えていたということは一体どういうことなのであろう。
中国のすることは、我々には理解し難い部分が沢山あるわけで、この本の中でも周恩来の病状を秘密にするということが何のてらいもなく語られているが、これは一体どういうことなのであろう。
国家の首脳が病気になったことなど、秘密にする必要はなさそうに思うが、これが政治の世界ではそうとも言えないらしい。
日本の歴史の中でも、武田信玄は自分の死を秘密するように言ったし、羽柴秀吉も織田信長の死を伏せて毛利と和解をはかったわけで、そういう意味で政治的な首脳者の死を秘密にして、取引を有利に導くことはあるが、中国の首脳ともなればそうそう秘密にするわけにもいかず、それがすぐに漏れることは言うまでもない。
そこで、その後に起きるであろう権力抗争に、その人の死が大きく関与することになるわけで、この部分が極めて中国的である。
私がその点を強調せざるを得ないのは、その部分が極めて土俗的で、民主化と対極の構図を成しているからである。
民主社会ならば、トップの首脳がいくら変わろうとも、事後策が確立しているので、権力構造が乱れるということはありえない。
アメリカの例でも、権力のトップの大統領が撃たれてもただちに副大統領がその職務を代行するわけで、権力の空白期間などというものはありえない。
ところが中国ではそうはならないわけで、トップが倒れるとそのトップの権力を奪還しようと、権力の座の奪い合いが生じるのである。
この本の中でも文化大革命のことが述べられているが、この文化大革命というのは一体何であったのだろう。
毛沢東の第3番目か4番目か知らないが、この紅青という毛沢東夫人とは一体どういう女性なのであろう。
文化大革命を書いた小説「ワイルド・スワン」でも「マオ」でも、極悪人と指摘されているが、人からそういうわれるだけの根拠があるから、そのように糾弾されているのだろうが、紅青がそれだけの悪人だったとしても、その彼女をそういう位置に留め置いたのは、中国の政治局の面々の実績でもあったわけで、それを突き詰めれば毛沢東の責任に帰してしまうではないか。
平たく押し並べて言えば、毛沢東が中国の政治の全責任を負うというのであれば、文化大革命の4人組の揚立そのこと自体が、毛沢東の全責任ということになってしまう。
毛沢東の責任をうんぬんする前に、紅青という女性が政治の場に出てくること自体がおかしなことで、我々の認識ではありえないことである。
そこに中国の政治の後進性が見事に露呈しているともいえるが、中国の政治には有史以来5千年の歴史があるわけで、それは共産主義のわずが20年か30年の歴史とは比較にならない差異であって、その中にあってこういうわけのわからない女性に政治の局面をかきまわされたということは、中国大陸にすむ人々の宿命なのかもしれない。
毛沢東夫人といえば、アメリカならば大統領夫人、日本ならば総理大臣の夫人、イギリスならばやはり総理大臣夫人となり、いわゆるトップ・レデイ―、ファースト・レディーであって、そういう立場の者が政治の場に自らしゃしゃり出ることはしないものである。
国家行事に花を添えるという意味で、トップ夫妻が並んで公に場に顔を出すということはあっても、それが夫人そのものが政治に関与するというのとは訳が違うはずである。
この事は、女性の政治参加を忌諱しているわけではなく、むしろトップの夫人としての身分をわきまえた、民主的な行為であって、いわゆる民主化の本質がよく分かっているということでもある。
民主化ということの本質がよくわかっていないから、トップ・レデイ―やファースト・レディーの立場のものが政治に嘴を差し挟むわけで、それだけ人々の民主化という価値観が浸透していないということを如実に表しているわけである。
紅青本人の政治認識もさることながら、それを容認している毛沢東そのものも、また彼女や彼らを取り巻いている取り巻き連中の政治認識の欠如も、本人以上に稚拙だということである。
紅青本人が政治局局員ということ自体が、毛沢東の女房に対する身贔屓であって、毛沢東自身、聡明な政治感覚があれば、自分の女房を政局員にすること自体おかしな話である。
アメリカ大統領が自ら開く閣議に自分の女房を出席させるであろうか。
日本の総理大臣が閣議の場に自分の女房を出席させるであろうか。
毛沢東はこれと同じことをしていたわけで、こんなバカな話はないと思う。
自分の女房にこんなことをさせる毛沢東もおかしければ、本人そのものの政治感覚も端からおかしいわけで、その毛沢東夫人に取りいって文化大革命を遂行している他の3人の考え方も、徹底的におかしいわけで、我々の感覚からすれば道理の通らないことが2乗にも3乗にも重なって露呈したのが文化大革命であったのではないかと思う。
共産主義革命というのは、既存の旧社会を根底から覆した後で、新秩序を構築する過程で多大な流血が避けられなかった。
これを実行せしめるエネルギーは、基本的にはインテリ―層が無知蒙昧な一般大衆をリードして、旧秩序を破壊し、新に秩序を作らねばならないが、旧秩序を破壊する過程で知識人というものを根絶やしにしてしまったものだから、新しい秩序を築き上げようとする段になると、それにふさわしい人材が不足してしまって、いわゆる無知で野蛮な人材をも渋々ある地位につかせねばならない。
無理もない話で、中国共産党は自分たちだけの力でアジア大陸の共産化に成功したわけではなく、大部分のエリアでは、軍閥や、盗賊や、馬賊や、国民党の各支部や、軍隊が、日和見で寝返った部分もかなり内包しているわけで、そういう連中を党内に抱えている限り、生粋の中国共産党員はいつまでたっても枕を高くして眠れなかったに違いない。
そこに以ってきて、初期の中国共産党の政策は失敗続きであったし、初期の革命を成した人々も、年月の経過とともにマンネリに陥りだしたわけで、安住を求めて冒険を避ける雰囲気が広がったので、そこに純粋な革命第2世代が反発を募らせたものと私は考える。
初期の革命を成した、革命第1世代は世の中が平穏になると安逸な生活を求めるようになり、これが純粋で素朴な思考の革命第2世代には我慢ならないことにうつり、それが革命第1世代を批判する方向に収斂されて行ったものと思う。
問題は、この一連の騒動の中で、中国の人々の間で、仁義も、モラルも、尊敬の念も、儒教思想の長幼の功も、あらゆる既存の価値観を否定したというところにある。
無理もない話で、革命ということは旧秩序の破壊そのものなわけで、それがなされれば人心が乱れるのも自然の摂理に則っている。
彼らの悠久の歴史を、自ら根底から覆したわけで、それを裏で煽っていた毛沢東と4人組の存在というのは、中国の歴史にとっては大きな汚点だったと思う。
毛沢東が死んだとき、彼の功罪は4分6で、善が4分で悪事が6分と評されたものだが、その6分の中にこの文化大革命がおそらく入っているであろう。
周恩来という人は、この毛沢東に影のように付き添ってきたにもかかわらず、中華人民共和国の功績はすべて毛沢東に寄せられるが、それは建国以来、毛沢東と周恩来の二人三脚で来たように見えるが、なぜかその功績は毛沢東のものになってしまう。
周恩来は中国建国以来、毛沢東の女房役のような役回りであったが、その彼をしても紅青の政治的な介入を阻止できなかったということは、どういうことなのであろう。
やはり毛沢東の夫人ということで遠慮があったということなのであろうか。
それに引き換え、紅青の方は、自分の旦那に周恩来の失脚を何度も進言して、その都度毛沢東はその進言を叱責しているわけで、毛沢東にしてみれば、自分の女房の言うことよりも周恩来の言うことに信を置いていたということになる。
当然と言えば当然のことで、中国共産党結党以来の朋友と、女優のなりそこないのような紅青とでは、その言葉の重さが最初から違うわけで、毛沢東にしてみれば、紅青の代わりはいくらもいるが、政治的に適切なアドバイスを得られる最も信頼できる人物としては、周恩来以外にいないわけで、その意味でいくら紅青が周恩来の失脚を願っても、それだけはかなわなかったに違いない。
我々が日本人として中国の文化大革命を見てみると、実に不可解なことが多い。
何故、国家権力でもない民衆が、学校の先生や行政のトップを引き降ろして、直接暴力を加えることが可能なのか不思議でならない。
民衆や学生が大学の先生や行政のトップを暴力で以ってひきづり出して、公衆の面前で殴ったり蹴ったりするということは、その事実だけで中国の人々の民度、知的レベル、倫理観、モラルが低い、ということを指し示しているわけで、別な言い方をすれば政治的に極めて未熟な大衆、民衆ということになる。
そういう人々が、毛沢東語録を掲げさえすれば、そういう卑劣で民意の低い人デナシのする行為が、気高い行為となるわけで、こんなバカな話があるものかと言いたい。
何が造反有理だ!!!!
ただの無頼、やくざ、無法者、愚連隊でしかないではないか。
毛沢東は、こういう連中を煽って、自分の建国当時の革命の同志の失脚を図ったわけで、それもこれも革命が軌道に乗ってくると、よそ事を考える余裕が出てきたので、自分の将来の不安がおぼつかなくなってきたからには他ならない。
「誰かが俺を追い落とすのではないか?」という不安に苛まれて、心安らかでおれなくなったに違いない。
この毛沢東の不安に乗じて紅青夫人を中心に、心の邪な3人が自分たちの政敵を追い落とすことをしたわけで、それは当然権力闘争になり、こういう権力闘争というのはどの政治局面でもあることで不思議ではないが、それを何の権力もない民衆、大衆が根も葉もない虚構を流すことによってまかり通る社会というのはもう人間の社会ではないと思う。
この文化大革命で日本の知識人が案外見落としていることに、この時期中国では都会のインテリ―を田舎に送ってそれを下放と言っていた。
この事実をよくよく見てみると、都会のインテリ―に懲罰を加える意味で地方の田舎に送って、そこで重労働をさせることに懲罰の意味があるわけで、ならば生まれ落ちた時から田舎に住んでいる人たちは一生涯牢屋の中で生きているということになるではないか。
この時期の中国では田舎の人間が都会に来ることを禁止していたが、これなどは田舎で農業に勤しんでいる人間を、人とみなしていないということで、だからこそ都会のインテリ―を田舎に送ることに懲罰としての意味があったわけである
さらにもう少し掘り下げてみると、都会のインテリ―に懲罰を課す主体は一体何なのかという問題である。
大学の学生委員会の長にそういう権限があるのかどうか、行政の中間管理職にそんな権限があるのかどうか、ただなんとなく野次馬の威勢のいい人から、理由もいい加減な罪状を言い渡されて、田舎に送られて農作業させられる人もたまったものではなかろうが、何とも弁解の機会もないわけで、こんなバカな話もない筈であるが、それが10年も続いたというのだから驚く。
10年たった後、その責任を誰かが負ったであろうか?
文化大革命というのは中国人がお互いに中国人を殺しあったわけで、外国に責任の及ぶものではないが、考えてみれば、これが中国5千年の歴史の現実なのであろう。
1949年の中華人民共和国の建国前は、中国の周りには夷狄の存在があって、政治の延長としての戦争は常に行われていたが、それが国家統一をなして夷狄の存在を内側に取り込んでしまったので、中国人同士の無意味な殺傷という形になったものと思う。
こういうことを考えると、我々と中国の人々とは、共通の認識というものが成り立たないわけで、それは物事を判断する基準の相違、いわゆる土俵が違うということで、いくら話しあったところで話が妥協点に導かれるということはあり得ない。
この本の著者は、周恩来の主治医という立場から、本人・周恩来に極めて好意的に描かれているが、中でも周恩来が極めて仕事熱心で、我々の言葉でワーカホリックであることを好意的にとらえているが、いくら政府の要人であろうとも、自分の体を顧みずに仕事に打ち込むということは、善意に解釈しきれない部分があると思う。
ある意味で、政務を私物化しているともとれるわけで、仕事をコントロールするということも要職にあればある程、心がけねばならない事柄だと思う。
しかし、病気、あるいは寿命というのは仕事熱心であろうとなかろうと公平に来るわけで、如何なる要人であろうとも、そういうときにはあっさりとそれを受け入れるべきだと思う。
その前に、要人であればあるほど、適当な時期に引退べきだと思う。
死ぬが死ぬまで権力にしがみつくというのは、私の感覚でいえばみっともない話だ。
その点、西洋人のリーダーは潔く引退して、悠々自適な生活を送るという例があるが、中国人は死ぬが死ぬまで権力にしがみついていないと死んだ時、墓さえ暴かれかねない。
韓国の例など実にすさましいもので、現職を降りたら最後、ただちに監獄に放り込まれてしまい、死刑の判決が下りたと思ったら、いきなり恩赦で無罪などという、まるでジェットコースターのような身の処し方を迫られる。
こういう状況が分かっているからこそ、権力に死ぬまでしがみついていなければならないのであろう。
権力を手放したら最後、ただの人以下になってしまうわけで、それが中国の5千年の歴史の教訓として息づいているのであろう。
死ぬまで権力にしがみつくというのは、不思議なことに、皆、共産主義社会のリーダーであって、自由主義陣営のリーダーは適当な時期に潔く引退しているが、これは共産主義というものの考え方を如実に指し示していると思う。
共産主義というのは基本的に、民主主義の一番遠い対極の位置にいるわけで、それこそ一度権力を手放したら、今度は自分が何時いかなる時に権力の餌食になるかわからないわけで、自分が過去に権力をほしいままにしていた以上、立場が逆転すればそのしっぺ返しは自らの過去に照らして想像できるわけで、ならば当然権力を放り投げるなどということはありえないということになる。
昨今の日本のリーダーを見てみると、安部晋三から福田康夫まで、まるで不甲斐ないリーダーに見えたものだが、中国に比べると、こういう人物が一度は総理の椅子に座って、まさしく自分の勝手で政権を放り出すことのできる世の中というのは、極めて恵まれた社会だということにもなると思う。
毛沢東や周恩来、金日成からスターリンと言うような人は、決してこんないい加減なことで政権を放り出すなどということはしえないわけで、死ぬまで政権を維持しなければ、墓まで暴かれかねなかったわけだ。
それに比べれば日本のリーダーなど極めて能天気な存在だ。
それは国民にも言えるわけで、我々は何処の誰べえとも分からない人間に、いきなり刑務所に入れられるようなバカな話もなく、強制労働などということもないわけで、労働しようにも仕事がないくらいで、その意味で、平和ボケになるのも当然である。
平和ボケと言っておれる間は幸せだと思わなければならない。