
例によって図書館から借りてきた本で「九十歳の省察」という本を読んだ。
サブタイトルは「哲学的断想」となっているが、著者は沢田允茂という慶応義塾大学の名誉教授ということだ。
私は標題から老人に関する記述かと思って手に取ってみたが、内容は哲学に関する考察で、私の手に負える代物ではなかった。
私のような無学者にとっては、哲学なんてものは何の意味も持たず、まさしく知のセンズリ以外の何ものでもない。
昔、オウム真理教の事件で、その広報を担当していた上裕史浩は、メディアのインタビューの度ごとに、「ああ言えばこう言う、こう言えばああ言う」と禅問答のような対応をしたので、後には「ああ言えば上裕」という風にまで言われたことがある。
私にとっての哲学なるものは、まさしく「ああ言えば上裕」の域を一歩も出るものではない。
この著者も本の中で言っているが、昔のギリシャ、アテネの時代は、普通の市民というのは何も仕事をせずにぶらぶらしている人間のことであって、日々、仕事に追われて汲々している人間は、奴隷クラスの卑しい人間であった、と記されている。。
仕事をするということは卑しいことであって、高貴な人は仕事などせずに、今のカウチ族のように、カウチ・ソファーに身を委ねてポテトチップでもつまみながら、人の噂話に花を咲かせているのがこの時代の普通の市民階層であったそうだ。
選挙権というのは、こういうクラスの人にしかなかったということだ。
つまり、こせこせ労働などせずとも食っていける富裕層の人が、ひとかどの市民であって、労働をするということは、それだけで神の罪科を背負わされた哀れな存在というわけだ。
だから、この時代の立派な青年というのは、一日中仕事もせずにぶらぶらしていて、日向ぼっこをしながら、カウチ・ソファーで、「ああでもないこうでもない」と人の噂話をしつつ、暇つぶしするのが常態であった、ということだ。
その中で「ああ言えばこう言う、こう言えばああ言う」という弁舌の技を磨くことが彼らの教養であった、というわけだ。
道具を使ってモノを作る、武器を持って人と戦う、人の世話をするという行為は、須らく奴隷という身分の者が行う行為であって、市民たるものの行うものではなかった、というわけだ。
古代の民主主義というのは、こういう狭い範囲の民主主義であって、にも拘らず、人間というのはやはり先天的に脳、頭脳を持っているので、モノを考えることが可能であった。
いつの時代でも、自分自身の立場、あるいは在り様を、自分の頭脳で考えるわけで、考えた挙句こうすればもっと合理的になるのではないか、と思考を巡らす。
例えば、飲料水を確保しなければならないという場合、水源の近くに人間の方が寄っていくか、あるいは合理的に水を運んでくる方法がないか、知恵を絞らなければならない。
こういうケースで、現場の人間つまり日々道具を使ってモノを作る作業を行っている人達ならば、過去の経験を上手に生かして、その場に適応した最も合理的な手法を考えだすが、いわゆる市民階層という選良の民は、具体的な経験がないので、口先で「ああでもないこうでもない」と言っている他なく、結果として安易に淘汰されてしまう。
ヨーロッパの古い伝統ある大学というのは、こういう富裕層のサロンであったわけで、ヨーロッパの学問の核となるものは、言うまでもなくこの哲学とか神学にあって、これを私の言葉で述べれば、知のセンズリ以外の何ものでもないということになる。
五体満足な立派な若者が、日がな無為な神学論争に耽っていても、世の中は一向に進化しないわけで、世の中がより良くなるためには、生産の合理性を追及して、奴隷階級に余暇を産み出さないことには、知の底上げには効果がないので、人間の進歩というのはそういう線に沿ってなされてきた。
地球の誕生が46億年前、人類の誕生が約1億年前として、今我々は2012年とその前数百年の歴史しか持っていないわけで、この間に人類の数は60億を越えるかどうかというところに立たされている。
地球が誕生し、人類が誕生し、それが今日まで来る間に、多くのモノが誕生し、それは同時に多くのモノが絶滅していったに違いない。
シダ植物の多くがそうだし、恐竜の多くがそうであるが、人間のみが絶滅することなく数を増やし続けている。
これはある意味で自然界にとって異常な事態ではないかと思う。
地球上に生息した生物は、ある一定の期間繁殖したら、後は絶滅の方向に向かうのが正常な自然なのではなかろうか。
人間だけがその自然の法則というべきか、自然の摂理というべきか正確には知らないが、自然の成り行きに逆らっているのではなかろうか。
何億年というタイム・スパンから、2012年プラス数百年という時間は、確かに一瞬の時間のようにも思える。
我々は有史以来、「人の命は一刻一秒たりとも長らえるべきだ」という思いから脱し切れていないが、これは自然の摂理に反した思考ではなかろうか。
ギリシャのアテネからローマ時代を通じて健全な青年は、日向ぼっこをしながら、日がな「ああでもない、こうでもない」と議論をして、哲学なるものに没頭しても、人の命の価値を正確に評価することが出来ず、人類の根源的願望である長寿願望を否定する論拠を見つけ出せずにいた、ということは一体どういうことなのであろう。
21世紀の今日においても、識者であればある程、人間の長寿願望に正当性を見出して、戦前・戦中の「産めよ増やせよ」をそのまま踏襲した思考に凝り固まっているということは一体どういうことなのであろう。
人類の数は、これから先、級数的に増加するものと考えられる。
昔は、未開の地域では、赤ん坊でも大人でも安易に死んでいって、それを天命だと本人も周囲も、そう思い込んで何の不合理も感じなかった。
ところが昨今では、そういう人々からの突き上げが厳しく、「こういう事態を招いたのは先進国の責任だ、何とかせよ」という欲求が強くなって、救済措置をこうじなければならなくなった。
本来は自分たちの問題であるにもかかわらず、周囲のモノに責任が転嫁されてしまって、先進国の責任にされてしまいがちである。
アテネ、ローマの時代から哲学なるものがあるとすれば、人類はもうそろそろ、人間の長寿願望の空しさを説く時期に来ているのではなかろうか。
今の地球上には、あきらかに文化の格差があるわけで、先進文化圏とそうでない未開の文明圏があり、先進諸国では人の命は一刻一秒たりとも粗末にすべきでないと言っているが、未開地では幼児が十分な栄養が行き渡らないので、幼くして死んでいる。
この状態を「何とかしなければならない」と大騒ぎするのは、先進国の側の知識人であって、それが文明の名で良い事だとされている。
ならば、今後、級数的に増加する人口問題に如何に対応するのかという問題になると、どうのように答えればいいのであろう。
地球にはまだまだ包容力があると言っても、それは何億年というタイム・スパンで量らねばならないわけで、この先1、2年の話ではないと思う。
この本の中には、人々の習慣が皆が皆同じ思考をして、それが普遍化したならば、それが一つのモラルとして確定し、それに反するものを異端者と見做すようになる、述べられている。
ところが、過去の人間は、それこそ皆が皆、長寿願望で一刻一秒たりとも長生きしたいと願っていたので、それが人間の普遍化した思考になってしまっている。
けれども、そこを突き崩すのが哲学者の使命なのではなかろうか。
富裕層の子弟が、五体満足で極めて健康的な青年でありながら、日向ぼっこをしながら日がな知のセンズリに耽って、それでも尚人は長生きを願望して止まないことに異議を差し挟まないというのであれば、彼らの考えは基本的に、古来から連綿と息づいていた奴隷の思考と何ら変わるものではないということになる。
だとすれば、人は高貴な富裕層の出自であろうと、額に汗して働くの出自であろうと、何の変わりも無いということになる。
哲学というものが、富裕層の若者の精神の遊びであるとするならば、それは遅かれ早かれ、精神の退廃に結び付くわけで、それの行きついた先が人間性の回復ということで、自然のままの心の在り様に行きついた、ということではなかろうか。
人間性の回復という言い方は、極めて美しい響きを持っているが、その言葉の裏の一面は、自分の我儘一杯の生活を望むことに繋がっているわけで、自堕落の助長と紙一重である。
自分の欲しいものは手に入れ、嫌いなものを遠ざけることは、人間の欲望の最も自然な在り様である。
ところが知のセンズリをしている連中は、あくまでも富裕層の民であって、暇を持て余した五体満足な毛気盛んな若者なわけで、そういう連中が老獪な大人や無邪気な幼児と同じ価値観で結ばれていては、彼らの估券に関わるわけで、若者ならば若者らしい独特な雰囲気で自己顕示欲を満たしたいだろうと思う。
それで日向ぼっこをしながら「ああでもない、こうでもない」「ああ言えばこう言う、こう言えばああ言う」という無意味な議論を繰り返していたのである。
21世紀の今日、学問というものが就職のためのツールになってしまっているが、この現状には哲学者たるもの大いに発奮し、是正の声を挙げるべきだと思う。
実践的なプラグマチズムに根付いた学問が不要というわけではないが、学問を就職の為のツールにしてしまってはならないと思う。
哲学者足るものは、そういうことを考えているのが真の哲学者ではなかろうか。
現代の進化した社会において、広範な知識は何人にも大いに必要なことは否めないが、大学というモノの本質を今一度根本から見直すべきだと思う。
医学や法律、はたまたテクノロジーを、同じ大学という枠組みで一括りして良いとは思えない。
学問というからには、あくまでも哲学や神学や、自然科学を追求すべきであって、医学や、法律、はたまた工学という分野は、あくまでもテクノロジ-の範疇であって、学問とは別物だと思う。
医学や、法律、工学というのは何処まで行っても就職のための職業課程であって、こういう分野にも学問的領域のあることは素直に認めざるを得ないが、それは就職過程の次に来る問題だと思う。
今、先進国では良い仕事に就くためには良い大学を出ることは必修条件になっているので、猫も杓子も良い大学に行きたがるが、こういう風潮に警鐘を鳴らすべきが哲学者ではなかろうか。
社会人として、知識は無いよりは有った方が良いことは言うまでもないが、教育というのもタダでは出来ないわけで、性根の卑しい若者が、ただたんに出世のための免罪符として大学に蝟集することが許されて良いとは思えない。
こういう風潮は一人や二人の特異な思考でこうなるのではなく、社会全体がそういうムードに浸り切っているからそれが普遍化して、「そうでなければならない」という倫理観、或いはモラルが形成されてしまうのである。
戦後の我々の民主教育では、個性の尊重ということが声高に叫ばれたが、みんなが皆、揃って大学に行くでは、個性を発揮する場を自ら潰しているようなものではないか。
哲学なんてものは、物事の本質を考え抜くことだと思うが、その考え抜いた事を世間に告知しなければ、哲学が死んだ思考のままで終わってしまう。
それではまさしく知のセンズリ、いや猿のセンズリのままでしかない。
サブタイトルは「哲学的断想」となっているが、著者は沢田允茂という慶応義塾大学の名誉教授ということだ。
私は標題から老人に関する記述かと思って手に取ってみたが、内容は哲学に関する考察で、私の手に負える代物ではなかった。
私のような無学者にとっては、哲学なんてものは何の意味も持たず、まさしく知のセンズリ以外の何ものでもない。
昔、オウム真理教の事件で、その広報を担当していた上裕史浩は、メディアのインタビューの度ごとに、「ああ言えばこう言う、こう言えばああ言う」と禅問答のような対応をしたので、後には「ああ言えば上裕」という風にまで言われたことがある。
私にとっての哲学なるものは、まさしく「ああ言えば上裕」の域を一歩も出るものではない。
この著者も本の中で言っているが、昔のギリシャ、アテネの時代は、普通の市民というのは何も仕事をせずにぶらぶらしている人間のことであって、日々、仕事に追われて汲々している人間は、奴隷クラスの卑しい人間であった、と記されている。。
仕事をするということは卑しいことであって、高貴な人は仕事などせずに、今のカウチ族のように、カウチ・ソファーに身を委ねてポテトチップでもつまみながら、人の噂話に花を咲かせているのがこの時代の普通の市民階層であったそうだ。
選挙権というのは、こういうクラスの人にしかなかったということだ。
つまり、こせこせ労働などせずとも食っていける富裕層の人が、ひとかどの市民であって、労働をするということは、それだけで神の罪科を背負わされた哀れな存在というわけだ。
だから、この時代の立派な青年というのは、一日中仕事もせずにぶらぶらしていて、日向ぼっこをしながら、カウチ・ソファーで、「ああでもないこうでもない」と人の噂話をしつつ、暇つぶしするのが常態であった、ということだ。
その中で「ああ言えばこう言う、こう言えばああ言う」という弁舌の技を磨くことが彼らの教養であった、というわけだ。
道具を使ってモノを作る、武器を持って人と戦う、人の世話をするという行為は、須らく奴隷という身分の者が行う行為であって、市民たるものの行うものではなかった、というわけだ。
古代の民主主義というのは、こういう狭い範囲の民主主義であって、にも拘らず、人間というのはやはり先天的に脳、頭脳を持っているので、モノを考えることが可能であった。
いつの時代でも、自分自身の立場、あるいは在り様を、自分の頭脳で考えるわけで、考えた挙句こうすればもっと合理的になるのではないか、と思考を巡らす。
例えば、飲料水を確保しなければならないという場合、水源の近くに人間の方が寄っていくか、あるいは合理的に水を運んでくる方法がないか、知恵を絞らなければならない。
こういうケースで、現場の人間つまり日々道具を使ってモノを作る作業を行っている人達ならば、過去の経験を上手に生かして、その場に適応した最も合理的な手法を考えだすが、いわゆる市民階層という選良の民は、具体的な経験がないので、口先で「ああでもないこうでもない」と言っている他なく、結果として安易に淘汰されてしまう。
ヨーロッパの古い伝統ある大学というのは、こういう富裕層のサロンであったわけで、ヨーロッパの学問の核となるものは、言うまでもなくこの哲学とか神学にあって、これを私の言葉で述べれば、知のセンズリ以外の何ものでもないということになる。
五体満足な立派な若者が、日がな無為な神学論争に耽っていても、世の中は一向に進化しないわけで、世の中がより良くなるためには、生産の合理性を追及して、奴隷階級に余暇を産み出さないことには、知の底上げには効果がないので、人間の進歩というのはそういう線に沿ってなされてきた。
地球の誕生が46億年前、人類の誕生が約1億年前として、今我々は2012年とその前数百年の歴史しか持っていないわけで、この間に人類の数は60億を越えるかどうかというところに立たされている。
地球が誕生し、人類が誕生し、それが今日まで来る間に、多くのモノが誕生し、それは同時に多くのモノが絶滅していったに違いない。
シダ植物の多くがそうだし、恐竜の多くがそうであるが、人間のみが絶滅することなく数を増やし続けている。
これはある意味で自然界にとって異常な事態ではないかと思う。
地球上に生息した生物は、ある一定の期間繁殖したら、後は絶滅の方向に向かうのが正常な自然なのではなかろうか。
人間だけがその自然の法則というべきか、自然の摂理というべきか正確には知らないが、自然の成り行きに逆らっているのではなかろうか。
何億年というタイム・スパンから、2012年プラス数百年という時間は、確かに一瞬の時間のようにも思える。
我々は有史以来、「人の命は一刻一秒たりとも長らえるべきだ」という思いから脱し切れていないが、これは自然の摂理に反した思考ではなかろうか。
ギリシャのアテネからローマ時代を通じて健全な青年は、日向ぼっこをしながら、日がな「ああでもない、こうでもない」と議論をして、哲学なるものに没頭しても、人の命の価値を正確に評価することが出来ず、人類の根源的願望である長寿願望を否定する論拠を見つけ出せずにいた、ということは一体どういうことなのであろう。
21世紀の今日においても、識者であればある程、人間の長寿願望に正当性を見出して、戦前・戦中の「産めよ増やせよ」をそのまま踏襲した思考に凝り固まっているということは一体どういうことなのであろう。
人類の数は、これから先、級数的に増加するものと考えられる。
昔は、未開の地域では、赤ん坊でも大人でも安易に死んでいって、それを天命だと本人も周囲も、そう思い込んで何の不合理も感じなかった。
ところが昨今では、そういう人々からの突き上げが厳しく、「こういう事態を招いたのは先進国の責任だ、何とかせよ」という欲求が強くなって、救済措置をこうじなければならなくなった。
本来は自分たちの問題であるにもかかわらず、周囲のモノに責任が転嫁されてしまって、先進国の責任にされてしまいがちである。
アテネ、ローマの時代から哲学なるものがあるとすれば、人類はもうそろそろ、人間の長寿願望の空しさを説く時期に来ているのではなかろうか。
今の地球上には、あきらかに文化の格差があるわけで、先進文化圏とそうでない未開の文明圏があり、先進諸国では人の命は一刻一秒たりとも粗末にすべきでないと言っているが、未開地では幼児が十分な栄養が行き渡らないので、幼くして死んでいる。
この状態を「何とかしなければならない」と大騒ぎするのは、先進国の側の知識人であって、それが文明の名で良い事だとされている。
ならば、今後、級数的に増加する人口問題に如何に対応するのかという問題になると、どうのように答えればいいのであろう。
地球にはまだまだ包容力があると言っても、それは何億年というタイム・スパンで量らねばならないわけで、この先1、2年の話ではないと思う。
この本の中には、人々の習慣が皆が皆同じ思考をして、それが普遍化したならば、それが一つのモラルとして確定し、それに反するものを異端者と見做すようになる、述べられている。
ところが、過去の人間は、それこそ皆が皆、長寿願望で一刻一秒たりとも長生きしたいと願っていたので、それが人間の普遍化した思考になってしまっている。
けれども、そこを突き崩すのが哲学者の使命なのではなかろうか。
富裕層の子弟が、五体満足で極めて健康的な青年でありながら、日向ぼっこをしながら日がな知のセンズリに耽って、それでも尚人は長生きを願望して止まないことに異議を差し挟まないというのであれば、彼らの考えは基本的に、古来から連綿と息づいていた奴隷の思考と何ら変わるものではないということになる。
だとすれば、人は高貴な富裕層の出自であろうと、額に汗して働くの出自であろうと、何の変わりも無いということになる。
哲学というものが、富裕層の若者の精神の遊びであるとするならば、それは遅かれ早かれ、精神の退廃に結び付くわけで、それの行きついた先が人間性の回復ということで、自然のままの心の在り様に行きついた、ということではなかろうか。
人間性の回復という言い方は、極めて美しい響きを持っているが、その言葉の裏の一面は、自分の我儘一杯の生活を望むことに繋がっているわけで、自堕落の助長と紙一重である。
自分の欲しいものは手に入れ、嫌いなものを遠ざけることは、人間の欲望の最も自然な在り様である。
ところが知のセンズリをしている連中は、あくまでも富裕層の民であって、暇を持て余した五体満足な毛気盛んな若者なわけで、そういう連中が老獪な大人や無邪気な幼児と同じ価値観で結ばれていては、彼らの估券に関わるわけで、若者ならば若者らしい独特な雰囲気で自己顕示欲を満たしたいだろうと思う。
それで日向ぼっこをしながら「ああでもない、こうでもない」「ああ言えばこう言う、こう言えばああ言う」という無意味な議論を繰り返していたのである。
21世紀の今日、学問というものが就職のためのツールになってしまっているが、この現状には哲学者たるもの大いに発奮し、是正の声を挙げるべきだと思う。
実践的なプラグマチズムに根付いた学問が不要というわけではないが、学問を就職の為のツールにしてしまってはならないと思う。
哲学者足るものは、そういうことを考えているのが真の哲学者ではなかろうか。
現代の進化した社会において、広範な知識は何人にも大いに必要なことは否めないが、大学というモノの本質を今一度根本から見直すべきだと思う。
医学や法律、はたまたテクノロジーを、同じ大学という枠組みで一括りして良いとは思えない。
学問というからには、あくまでも哲学や神学や、自然科学を追求すべきであって、医学や、法律、はたまた工学という分野は、あくまでもテクノロジ-の範疇であって、学問とは別物だと思う。
医学や、法律、工学というのは何処まで行っても就職のための職業課程であって、こういう分野にも学問的領域のあることは素直に認めざるを得ないが、それは就職過程の次に来る問題だと思う。
今、先進国では良い仕事に就くためには良い大学を出ることは必修条件になっているので、猫も杓子も良い大学に行きたがるが、こういう風潮に警鐘を鳴らすべきが哲学者ではなかろうか。
社会人として、知識は無いよりは有った方が良いことは言うまでもないが、教育というのもタダでは出来ないわけで、性根の卑しい若者が、ただたんに出世のための免罪符として大学に蝟集することが許されて良いとは思えない。
こういう風潮は一人や二人の特異な思考でこうなるのではなく、社会全体がそういうムードに浸り切っているからそれが普遍化して、「そうでなければならない」という倫理観、或いはモラルが形成されてしまうのである。
戦後の我々の民主教育では、個性の尊重ということが声高に叫ばれたが、みんなが皆、揃って大学に行くでは、個性を発揮する場を自ら潰しているようなものではないか。
哲学なんてものは、物事の本質を考え抜くことだと思うが、その考え抜いた事を世間に告知しなければ、哲学が死んだ思考のままで終わってしまう。
それではまさしく知のセンズリ、いや猿のセンズリのままでしかない。










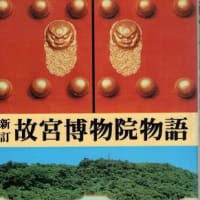




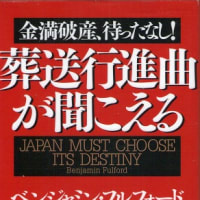

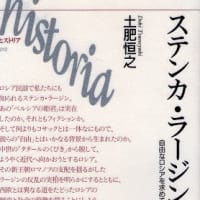
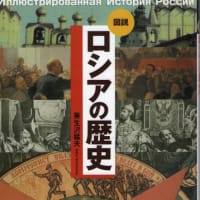

ルイヴィトンバッグ
ロレックス 時計
ミュウミュウ財布
シャネル財布
エルメスバッグ
精巧で美しいファッション!
信用第一、良い品質、 低価格は スタイルが多い 実物写真!
よろしくお願いします
www.gucci33.com