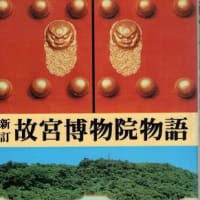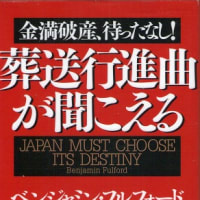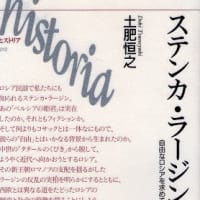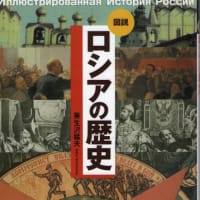例によって図書館から借りてきた本で『マッカアサーへの100通の手紙』という本を読んだ。
サブタイトルには「占領下 北海道民の想い」ということで、北海道新聞の記者が綴った記録なので、取材の対象が北海道の人に限定されているが、占領下において我々の同胞の数多くの人が、当時の最高司令官マッカアサーに手紙を書いたことを記している。
この本のページを最初に開いたのが、きしくも(平成24年)12月8日、日本が71年前に真珠湾攻撃をした日であった。
私は朝起きて最初に新聞を開いたとき、どこかにこの日に関する記事があるか探したが、この日の朝刊にはどこを見てもそれに関する記事は無かった。
夕方、インターネットを見ていたら、ハワイの真珠湾でアメリカ人が追悼式が行った、という読売新聞の記事が目に付いたが、それも淡々と事実を伝えているだけである。
私は昭和15年生まれで、あの戦争の時はまだ小学生にもなっていなかったので、実体験というのはほとんどないが、それでも世代的にそういう話は身近にあった話として受け止めている。
終戦が5歳の時で、小牧飛行場に進駐してきたアメリカ軍のMPが、ジープで小牧の街中の女郎屋や飲み屋を巡回している光景がまぶたに映っている。
その時見たアメリカ人のMPの格好良さ、スマートさ、ジープという軍用車両の合理性に子供ながらにも驚嘆した覚えがある。
あのアメリカ人の体格の良さと、ジープという車の合理性を見て、「これでは我が方が勝てないのも無理ない」と子供心にも思ったものだ。
当時の日本の車、特にトラックは木炭車であって、運転席の後ろにドラム缶を二つ繋いだような窯を持っていて、そこに木炭をくべてもうもうと煙は出すが、一向に力の出ない車であった。
この現実を、洟垂れ小僧の私が指をくわえて眺めながら、どうして大人はこんなアメリカと戦争したのか不思議に思えたものだ。
歴史というものは実に面白いもので、時間が経つにしたがって、古い事実が次々の掘り起こされてくるところがある。
時間の経過とともに、過去の秘密が次々に解除になって、封印されていた事実が明るみに出るということがある。
最近、NHKで放送されたBS歴史館『ミッドウエー海戦』という番組の中で、加藤陽子という大学の先生は、連合艦隊司令長官の山本五十六は当時の日本国民を「衆愚の輩」という認識で見ていたと述べていた。
私の個人的な考え方としては、戦争に負けるような軍人、戦争に勝てないような将軍ならば、戦争のプロフェッショナルとして意味をなさず、国費でそういう人間を養う意味がなかったように思う。
このNHKの番組では、ミッドウエー海戦の敗北は、日本海軍の想定外の事があまりにも重なりあった、と述べているが、想定外のことを想定してはじめて戦争のプロフェッショナルなわけで、事があらかじめ想定された通りに動くのであれば、訓練も準備も最初から不要ということになる。
私の関心は、山本五十六が国民を衆愚とみなしていた点に、彼の慧眼を見る思いがする。
彼は世の中というものをよくよく知っていたに違いないと思うが、惜しむらくは、古典的な古武士の精神構造であったが故に、西洋のプラグマチズムの生贄になったと思えてならない。
というのは情報の軽視、暗号解読の認識の甘さ、が彼の生涯そのものを悪魔の餌食にしてしまったと思えてならない。
彼はある意味で生粋の海軍士官であり、イギリス風のジェントルマンであって、奇襲作戦とか、暗号解読という汚い戦法は、本来ならば忌避したいところであろうが、何が何でも勝つという大命題の前では、そういう綺麗ごとも言っておれず、真珠湾では彼の戦略が功を奏したが、ミッドウエーではそれが裏目に出たということになる。
ただ私が問題にすべきところは、山本五十六が衆愚とみなした日本国民である。
昭和の初期の日本の実情というのは、まさしく山本五十六のような経歴の人間から見れば、衆愚、烏合の衆、有象無象の輩に見えたのも偽らざる心境であったに違いない。
ところが世の中の動きというのは、そういう人々の意向に沿って動くわけで、その結果として戦前の軍国主義の跋扈ということが起きたと考えられる。
「天皇の軍隊」という言葉も、昭和天皇自身が自分の言葉で「帝国軍隊は朕の軍隊である」と言ったわけでもないのに、世間一般にはそうなってしまっていた。
日本陸軍が政府や天皇の意向を無視して中国に進出しても、誰もそれを正規の軌道に乗せるべく、プリンシプルを貫こうとせず、目先の利益に幻惑されて容認してしまったので、抜き差しならなくなってしまった。
その不整合の部分をアメリカは突いてきたのだが、その時点ではすでに既成事実が出来上がってしまっていたので引くに引けなくなってしまったということだ。
戦後に生きたものとして忘れてならないことは、先の戦争の悲劇性の根源を、我々はともすると軍部の責任として糾弾することで自己の責任を昇華した気でいるが、これは根本的に間違った認識だと思う。
軍部や軍隊の立ち居振る舞いの背景には、日本の国民の潜在意識が反映されているわけで、それは貧乏からの脱出という無意識の願望が軍隊を構成している構成員としての農民や百姓の中に息づいていたということである。
戦後になって、あの戦争の責任を軍部や軍人に蔽い被せて「悪いのは彼等だ」という評価を下して、国民大衆は被害者だという論旨で、自己を正当化しているが、彼らの言う悪人に仕立て上げられた軍人や軍部も、元を正せば地方の農民や食うや食わずの水飲み百姓であったわけで、そういう人たちが時の時流に便乗して、無責任にも軍国主義を吹聴して回ったのである。
人が生きるということは、基本的には生存競争を生き抜くということであって、自分が生きんが為には如何に上手に時流を見極め、その時流に便乗するかにかかっているのである。
だから生き馬の目を抜く厳しい現世を生き抜くためには、その時々の、その場の状況にあった時流を見極め、それが軍国主義の時代ならば真っ先にその旗振りをし、それが平和主義の時代になれば反政府、反体制の旗幟をはっきりさせることで、時流に乗っかることが出来るのである。
しかし、終戦直後の我々同胞の政治に対する関心というのは、戦時体制の元では我々は見事に騙され、嘘で塗り固められていた事実を知るにつけ、同胞の政治家および軍人に対する不信感は極限まで高まっていたに違いない。
そういう状況の中に、マッカアサーという新しい統治者が現れると、それに対する全幅の信頼というのも、ある意味で前世期の反動という面も無きにしも非ずであろう。
戦前・戦中・戦後と虐げられてきた日本の国民、庶民にとって、文字通り解放軍であり、救世主であり、慈愛に満ちた為政者として映ったとしても不思議ではない。
この本を読んでみると、占領下においてマッカアサーが絶対的な権力を握った新しい統治者として君臨している状況下において、「良い世の中にする」という口実の元、自分の周囲の人間を密告する気風が感じられる。
そういう事を考える人は、本人自身はそれこそ清廉潔白で、真面目で、正直な人だとは思うが、いかなる社会、いかなる組織でも、必ず腐敗した汚い部分はあるわけで、それは我々の国だけの事ではなく、いかなる国でも同じだと思う。
本人が真面目であるが故に、周囲の汚い部分が気に障り、それを正そうと真面目に考えた結果が、密告という手段になるものと推察する。
人が人を統治している社会で、正しいとか正しくない、善とか悪、正義と不正義という言葉は何の意味も持たないわけで、人は他者との生存競争の中で、適者生存の自然の摂理の中でサバイバルをして生きているのであって、綺麗ごとを言っていた日には自然淘汰されかねないのである。
昭和初期の日本は貧しくて、日本の大部分の人は食うや食わずの農民で、そういう人たちが軍隊に入ってアジアを自分の眼で見てみると、アジアにはまさにフロンティアであって、そこに進出すれば貧乏からの脱出が可能だと思うのも自然の流れである。
アジアの側からすれば、侵略されたという論理であろうが、我々の認識ではサバイバルであったわけで、そうしなければ我々は飢え死にしたかもしれない。
現に終戦直後は日本民族は餓え死にしかかったではないか。
それを救済してくれたのはアメリカの食糧支援であったので、その意味でもマッカアサーは日本国民から慕われるのも当然の成り行きではある。
しかし、我々の隣人が新しい為政者に同胞の悪事を密告するというのも、日本人にあるまじき行為ではあるが、組織の中で職権や権威をかさに着て悪事を働く同胞や同僚の存在も由々しき問題ではある。
しかし、密告と言うのはどうにも汚い行為に見えてならない。
この本の中でも述べられているが、戦前・戦中の軍国主義は案外在郷軍人会という組織の監視が厳しくて、人々は本音を言う事を憚ったのではなかろうか。
要するに、密告されることの恐怖に怯えて、言うべきことも言わずに沈黙してしまったわけで、治安維持法があったからモノが言えなかったのではなく、近隣の同胞や周囲の隣人の密告が恐ろしくて、本音を言う事を抑えていたと思われる。
この本の中には、旧ソビエットの日本人捕虜の扱いに対する救済の手を差し伸べるようにマッカアサーに懇請する手紙もあったが、旧ソ連の日本人捕虜の扱いに関しては、もっともっと積極的に相手の非を糾弾するキャンペーンが必要だと思う。
ポツダム宣言受諾後のソ連側の武力行使と戦争犯罪については、世界の世論にもっともっと積極的にキャンペンを貼るべきだと思う。
ソ連が崩壊したから言うのではなく、ソ連という国、旧ソビエット連邦という国家、共産主義という政治体制の元での不法行為、こういう点を相手に突き付けて、こちらの整合性を積極的にアピールすべきだと思う。
我々は自分がいくらひどい仕打ちを受けても、長い時間が経つとその恨みつらみを綺麗に忘れて、目先の利益に惑わされそうになるが、そうあってはならない。
戦後の日本が戦争放棄を憲法で謳っているのであれば、我々の武器は言論でしかないわけで、口で言い合うだけならば人を殺傷する恐れは全くないのだから、それを有効に使うべきだと思う。
こういう日本の立場を世界に知らしめるには、それ相当の戦略がいるわけで、こういう戦略、政策、施策の遂行ならば、我が同胞の知識人の総意を結集することも可能のように思えるのだが、そこがそうならないところがわが民族のアキレス腱ということが言える。
戦前の天皇陛下を頂点とする軍国主義も、天皇が自ら言ったわけではなく、日本という国家の組織の中のある段階の部分が、天皇および統治者の潜在意識を慮って、「こうしておけばお上はきっと喜ばれるに違いない」という発想が根底にあったものだから、下々の者は結果的に抑圧されることになったのである。
戦後になって天皇の上にマッカアサーが君臨したとなると、それと同じ心情でもって、新しい為政者にすり寄る気持ちが芽生えたに違いない。
本来の自然の人間の感情からすれば、今迄敵とみなして戦ってきた相手であって、その相手に占領されて、敵の親玉にすり寄ること自体不合理であり、その上不遜な態度であるが、それを我々は何の疑念も持たずにやって来たということである。
昭和20年8月15日において、天皇陛下が玉音放送をしても尚徹底抗戦を唱えた一部の軍人がいたが、彼らは戦争の大義、戦争という生存競争の本質に忠実たらんと思っていたに違いなかろうが、そこでの大義や戦争の本質は、当時の戦争遂行のための理念と理想でしかなかった。
明らかに現実とは遊離していたわけで、そのままその理念と理想を貫き通せば、日本民族の絶滅、日本民族の地上からの淘汰という現実が見えていなかったということである。
あの時点でそれが見えていたのは昭和天皇ただ一人で、我々の同胞の誰一人それが見えていなかった
歴史の教訓として我々が考察しなければならないことは、天皇制の元での軍国主義を、政府の機関、軍部の機関、統治システムの機関のどの部門、どの所管が国民に強いたのかという検証である。
小学校や中学校という教育の現場で、天皇の御真影の遥拝などという行為を誰が何処でそういう意味のない事を人々に強制したのか言う事である。
そういう指示命令が出ると、それに従わず自主的な学級運営すると、当局に密告する同胞、隣人がいたわけで、それが恐ろしくて結果的に「人の振り見て我が振り直す」ということになるのである。
この日本民族の特質は、今に始まったことではなく、日本民族が誕生したときから引き継がれていたはずであるが、それが移民族と生死をかけて生存競争を展開し、自然淘汰の摂理に抗う生き方の選択を迫られた時に計らずも露呈したわけで、我々の過去の歴史にはない事例に直面したということだと思う。
我々が戦争の勝者に対して、こういう手紙を出すということは、マッカアサーあるいはGHQというものがまさしく正真正銘の救世主として映ったということだと思う。
戦争が終わるまでの日本、昭和20年8月までの日本には、敵が内側にいたのかもしれない。
当時の普通の国民、市民は、正確な戦況は知らなくとも、日本の旗色が悪いということは薄々感じていたに違いない。
そもそも戦場に行く兵士を、喜んで送り出す家族の存在などというのは、極めて欺瞞に富んでいるわけで、いかなる民族にもそういう深層心理はありえないと思う。
自分の祖国の危機に貢献するという大義は、どこの国にもあるであろうが、その大義と家族愛を計って、どちらを重視するかという選択は個々の人間に課せられているであろう。
だが、喜んで自分の息子を戦場に送りたいと思っている親はいないと思う。
そうであるからこそ、出征兵士を送り出した家を褒め称え、崇め奉って自尊心を下支えする必要があったわけだ。
軍国主義が世相を風靡する事態に対して、それを牽制すべきが本来ならば知識人と、そのツールとしてのメデイアでなければならなかった。
山本五十六は軍人であると同時にハーバード大学に留学した経験もあったわけで、その彼の知見でもってすると、当時の日本国民の有り体は「衆愚」であったわけで、彼がそう思う基底の部分には、当時の世相が軍国主義という時流に翻弄されている現実からであろうと推察する。
問題は、彼のようなインテリ―で、軍人であって、海軍の中でも良識派として知られた影響力の大きい人ならば、国民に向かって「あなた方の目指していることは間違っていますよ」と大きな声で言うべきであった。
それを言うとテロの標的にされるので、身の安全のために海上勤務にした、とまことしやかに言われているが、前線では1銭5厘で集められて兵士がばたばたと死んでいるのに、「命が惜しくて言うべきことも言えなかったのか」ということになる。
基本的に民主主義というのは衆愚政治に限りなく近いわけで、その衆愚を想い通りに誘導するのが民主政治の本領であって、政治家たるものそのための戦略に巧妙にコミットしなければならない。
最大多数の最大幸福というのは、具体的には豊かな生活の補償なわけで、経済が常に右肩上がりであり続ければ、その政権は衆愚としての国民から支持が得られるに違いない。
だけれども、常に右肩上がりの成長というのは自分たちだけで達成されるものではなく、外部要因で常に揺らいでいるので、自分たちの努力だけでは何とも解決し難いモノを内包している。
普通の国民、市民が、為政者にこういう手紙が出せる、という状況は大いに人々の意識を覚醒したに違いない。
サブタイトルには「占領下 北海道民の想い」ということで、北海道新聞の記者が綴った記録なので、取材の対象が北海道の人に限定されているが、占領下において我々の同胞の数多くの人が、当時の最高司令官マッカアサーに手紙を書いたことを記している。
この本のページを最初に開いたのが、きしくも(平成24年)12月8日、日本が71年前に真珠湾攻撃をした日であった。
私は朝起きて最初に新聞を開いたとき、どこかにこの日に関する記事があるか探したが、この日の朝刊にはどこを見てもそれに関する記事は無かった。
夕方、インターネットを見ていたら、ハワイの真珠湾でアメリカ人が追悼式が行った、という読売新聞の記事が目に付いたが、それも淡々と事実を伝えているだけである。
私は昭和15年生まれで、あの戦争の時はまだ小学生にもなっていなかったので、実体験というのはほとんどないが、それでも世代的にそういう話は身近にあった話として受け止めている。
終戦が5歳の時で、小牧飛行場に進駐してきたアメリカ軍のMPが、ジープで小牧の街中の女郎屋や飲み屋を巡回している光景がまぶたに映っている。
その時見たアメリカ人のMPの格好良さ、スマートさ、ジープという軍用車両の合理性に子供ながらにも驚嘆した覚えがある。
あのアメリカ人の体格の良さと、ジープという車の合理性を見て、「これでは我が方が勝てないのも無理ない」と子供心にも思ったものだ。
当時の日本の車、特にトラックは木炭車であって、運転席の後ろにドラム缶を二つ繋いだような窯を持っていて、そこに木炭をくべてもうもうと煙は出すが、一向に力の出ない車であった。
この現実を、洟垂れ小僧の私が指をくわえて眺めながら、どうして大人はこんなアメリカと戦争したのか不思議に思えたものだ。
歴史というものは実に面白いもので、時間が経つにしたがって、古い事実が次々の掘り起こされてくるところがある。
時間の経過とともに、過去の秘密が次々に解除になって、封印されていた事実が明るみに出るということがある。
最近、NHKで放送されたBS歴史館『ミッドウエー海戦』という番組の中で、加藤陽子という大学の先生は、連合艦隊司令長官の山本五十六は当時の日本国民を「衆愚の輩」という認識で見ていたと述べていた。
私の個人的な考え方としては、戦争に負けるような軍人、戦争に勝てないような将軍ならば、戦争のプロフェッショナルとして意味をなさず、国費でそういう人間を養う意味がなかったように思う。
このNHKの番組では、ミッドウエー海戦の敗北は、日本海軍の想定外の事があまりにも重なりあった、と述べているが、想定外のことを想定してはじめて戦争のプロフェッショナルなわけで、事があらかじめ想定された通りに動くのであれば、訓練も準備も最初から不要ということになる。
私の関心は、山本五十六が国民を衆愚とみなしていた点に、彼の慧眼を見る思いがする。
彼は世の中というものをよくよく知っていたに違いないと思うが、惜しむらくは、古典的な古武士の精神構造であったが故に、西洋のプラグマチズムの生贄になったと思えてならない。
というのは情報の軽視、暗号解読の認識の甘さ、が彼の生涯そのものを悪魔の餌食にしてしまったと思えてならない。
彼はある意味で生粋の海軍士官であり、イギリス風のジェントルマンであって、奇襲作戦とか、暗号解読という汚い戦法は、本来ならば忌避したいところであろうが、何が何でも勝つという大命題の前では、そういう綺麗ごとも言っておれず、真珠湾では彼の戦略が功を奏したが、ミッドウエーではそれが裏目に出たということになる。
ただ私が問題にすべきところは、山本五十六が衆愚とみなした日本国民である。
昭和の初期の日本の実情というのは、まさしく山本五十六のような経歴の人間から見れば、衆愚、烏合の衆、有象無象の輩に見えたのも偽らざる心境であったに違いない。
ところが世の中の動きというのは、そういう人々の意向に沿って動くわけで、その結果として戦前の軍国主義の跋扈ということが起きたと考えられる。
「天皇の軍隊」という言葉も、昭和天皇自身が自分の言葉で「帝国軍隊は朕の軍隊である」と言ったわけでもないのに、世間一般にはそうなってしまっていた。
日本陸軍が政府や天皇の意向を無視して中国に進出しても、誰もそれを正規の軌道に乗せるべく、プリンシプルを貫こうとせず、目先の利益に幻惑されて容認してしまったので、抜き差しならなくなってしまった。
その不整合の部分をアメリカは突いてきたのだが、その時点ではすでに既成事実が出来上がってしまっていたので引くに引けなくなってしまったということだ。
戦後に生きたものとして忘れてならないことは、先の戦争の悲劇性の根源を、我々はともすると軍部の責任として糾弾することで自己の責任を昇華した気でいるが、これは根本的に間違った認識だと思う。
軍部や軍隊の立ち居振る舞いの背景には、日本の国民の潜在意識が反映されているわけで、それは貧乏からの脱出という無意識の願望が軍隊を構成している構成員としての農民や百姓の中に息づいていたということである。
戦後になって、あの戦争の責任を軍部や軍人に蔽い被せて「悪いのは彼等だ」という評価を下して、国民大衆は被害者だという論旨で、自己を正当化しているが、彼らの言う悪人に仕立て上げられた軍人や軍部も、元を正せば地方の農民や食うや食わずの水飲み百姓であったわけで、そういう人たちが時の時流に便乗して、無責任にも軍国主義を吹聴して回ったのである。
人が生きるということは、基本的には生存競争を生き抜くということであって、自分が生きんが為には如何に上手に時流を見極め、その時流に便乗するかにかかっているのである。
だから生き馬の目を抜く厳しい現世を生き抜くためには、その時々の、その場の状況にあった時流を見極め、それが軍国主義の時代ならば真っ先にその旗振りをし、それが平和主義の時代になれば反政府、反体制の旗幟をはっきりさせることで、時流に乗っかることが出来るのである。
しかし、終戦直後の我々同胞の政治に対する関心というのは、戦時体制の元では我々は見事に騙され、嘘で塗り固められていた事実を知るにつけ、同胞の政治家および軍人に対する不信感は極限まで高まっていたに違いない。
そういう状況の中に、マッカアサーという新しい統治者が現れると、それに対する全幅の信頼というのも、ある意味で前世期の反動という面も無きにしも非ずであろう。
戦前・戦中・戦後と虐げられてきた日本の国民、庶民にとって、文字通り解放軍であり、救世主であり、慈愛に満ちた為政者として映ったとしても不思議ではない。
この本を読んでみると、占領下においてマッカアサーが絶対的な権力を握った新しい統治者として君臨している状況下において、「良い世の中にする」という口実の元、自分の周囲の人間を密告する気風が感じられる。
そういう事を考える人は、本人自身はそれこそ清廉潔白で、真面目で、正直な人だとは思うが、いかなる社会、いかなる組織でも、必ず腐敗した汚い部分はあるわけで、それは我々の国だけの事ではなく、いかなる国でも同じだと思う。
本人が真面目であるが故に、周囲の汚い部分が気に障り、それを正そうと真面目に考えた結果が、密告という手段になるものと推察する。
人が人を統治している社会で、正しいとか正しくない、善とか悪、正義と不正義という言葉は何の意味も持たないわけで、人は他者との生存競争の中で、適者生存の自然の摂理の中でサバイバルをして生きているのであって、綺麗ごとを言っていた日には自然淘汰されかねないのである。
昭和初期の日本は貧しくて、日本の大部分の人は食うや食わずの農民で、そういう人たちが軍隊に入ってアジアを自分の眼で見てみると、アジアにはまさにフロンティアであって、そこに進出すれば貧乏からの脱出が可能だと思うのも自然の流れである。
アジアの側からすれば、侵略されたという論理であろうが、我々の認識ではサバイバルであったわけで、そうしなければ我々は飢え死にしたかもしれない。
現に終戦直後は日本民族は餓え死にしかかったではないか。
それを救済してくれたのはアメリカの食糧支援であったので、その意味でもマッカアサーは日本国民から慕われるのも当然の成り行きではある。
しかし、我々の隣人が新しい為政者に同胞の悪事を密告するというのも、日本人にあるまじき行為ではあるが、組織の中で職権や権威をかさに着て悪事を働く同胞や同僚の存在も由々しき問題ではある。
しかし、密告と言うのはどうにも汚い行為に見えてならない。
この本の中でも述べられているが、戦前・戦中の軍国主義は案外在郷軍人会という組織の監視が厳しくて、人々は本音を言う事を憚ったのではなかろうか。
要するに、密告されることの恐怖に怯えて、言うべきことも言わずに沈黙してしまったわけで、治安維持法があったからモノが言えなかったのではなく、近隣の同胞や周囲の隣人の密告が恐ろしくて、本音を言う事を抑えていたと思われる。
この本の中には、旧ソビエットの日本人捕虜の扱いに対する救済の手を差し伸べるようにマッカアサーに懇請する手紙もあったが、旧ソ連の日本人捕虜の扱いに関しては、もっともっと積極的に相手の非を糾弾するキャンペーンが必要だと思う。
ポツダム宣言受諾後のソ連側の武力行使と戦争犯罪については、世界の世論にもっともっと積極的にキャンペンを貼るべきだと思う。
ソ連が崩壊したから言うのではなく、ソ連という国、旧ソビエット連邦という国家、共産主義という政治体制の元での不法行為、こういう点を相手に突き付けて、こちらの整合性を積極的にアピールすべきだと思う。
我々は自分がいくらひどい仕打ちを受けても、長い時間が経つとその恨みつらみを綺麗に忘れて、目先の利益に惑わされそうになるが、そうあってはならない。
戦後の日本が戦争放棄を憲法で謳っているのであれば、我々の武器は言論でしかないわけで、口で言い合うだけならば人を殺傷する恐れは全くないのだから、それを有効に使うべきだと思う。
こういう日本の立場を世界に知らしめるには、それ相当の戦略がいるわけで、こういう戦略、政策、施策の遂行ならば、我が同胞の知識人の総意を結集することも可能のように思えるのだが、そこがそうならないところがわが民族のアキレス腱ということが言える。
戦前の天皇陛下を頂点とする軍国主義も、天皇が自ら言ったわけではなく、日本という国家の組織の中のある段階の部分が、天皇および統治者の潜在意識を慮って、「こうしておけばお上はきっと喜ばれるに違いない」という発想が根底にあったものだから、下々の者は結果的に抑圧されることになったのである。
戦後になって天皇の上にマッカアサーが君臨したとなると、それと同じ心情でもって、新しい為政者にすり寄る気持ちが芽生えたに違いない。
本来の自然の人間の感情からすれば、今迄敵とみなして戦ってきた相手であって、その相手に占領されて、敵の親玉にすり寄ること自体不合理であり、その上不遜な態度であるが、それを我々は何の疑念も持たずにやって来たということである。
昭和20年8月15日において、天皇陛下が玉音放送をしても尚徹底抗戦を唱えた一部の軍人がいたが、彼らは戦争の大義、戦争という生存競争の本質に忠実たらんと思っていたに違いなかろうが、そこでの大義や戦争の本質は、当時の戦争遂行のための理念と理想でしかなかった。
明らかに現実とは遊離していたわけで、そのままその理念と理想を貫き通せば、日本民族の絶滅、日本民族の地上からの淘汰という現実が見えていなかったということである。
あの時点でそれが見えていたのは昭和天皇ただ一人で、我々の同胞の誰一人それが見えていなかった
歴史の教訓として我々が考察しなければならないことは、天皇制の元での軍国主義を、政府の機関、軍部の機関、統治システムの機関のどの部門、どの所管が国民に強いたのかという検証である。
小学校や中学校という教育の現場で、天皇の御真影の遥拝などという行為を誰が何処でそういう意味のない事を人々に強制したのか言う事である。
そういう指示命令が出ると、それに従わず自主的な学級運営すると、当局に密告する同胞、隣人がいたわけで、それが恐ろしくて結果的に「人の振り見て我が振り直す」ということになるのである。
この日本民族の特質は、今に始まったことではなく、日本民族が誕生したときから引き継がれていたはずであるが、それが移民族と生死をかけて生存競争を展開し、自然淘汰の摂理に抗う生き方の選択を迫られた時に計らずも露呈したわけで、我々の過去の歴史にはない事例に直面したということだと思う。
我々が戦争の勝者に対して、こういう手紙を出すということは、マッカアサーあるいはGHQというものがまさしく正真正銘の救世主として映ったということだと思う。
戦争が終わるまでの日本、昭和20年8月までの日本には、敵が内側にいたのかもしれない。
当時の普通の国民、市民は、正確な戦況は知らなくとも、日本の旗色が悪いということは薄々感じていたに違いない。
そもそも戦場に行く兵士を、喜んで送り出す家族の存在などというのは、極めて欺瞞に富んでいるわけで、いかなる民族にもそういう深層心理はありえないと思う。
自分の祖国の危機に貢献するという大義は、どこの国にもあるであろうが、その大義と家族愛を計って、どちらを重視するかという選択は個々の人間に課せられているであろう。
だが、喜んで自分の息子を戦場に送りたいと思っている親はいないと思う。
そうであるからこそ、出征兵士を送り出した家を褒め称え、崇め奉って自尊心を下支えする必要があったわけだ。
軍国主義が世相を風靡する事態に対して、それを牽制すべきが本来ならば知識人と、そのツールとしてのメデイアでなければならなかった。
山本五十六は軍人であると同時にハーバード大学に留学した経験もあったわけで、その彼の知見でもってすると、当時の日本国民の有り体は「衆愚」であったわけで、彼がそう思う基底の部分には、当時の世相が軍国主義という時流に翻弄されている現実からであろうと推察する。
問題は、彼のようなインテリ―で、軍人であって、海軍の中でも良識派として知られた影響力の大きい人ならば、国民に向かって「あなた方の目指していることは間違っていますよ」と大きな声で言うべきであった。
それを言うとテロの標的にされるので、身の安全のために海上勤務にした、とまことしやかに言われているが、前線では1銭5厘で集められて兵士がばたばたと死んでいるのに、「命が惜しくて言うべきことも言えなかったのか」ということになる。
基本的に民主主義というのは衆愚政治に限りなく近いわけで、その衆愚を想い通りに誘導するのが民主政治の本領であって、政治家たるものそのための戦略に巧妙にコミットしなければならない。
最大多数の最大幸福というのは、具体的には豊かな生活の補償なわけで、経済が常に右肩上がりであり続ければ、その政権は衆愚としての国民から支持が得られるに違いない。
だけれども、常に右肩上がりの成長というのは自分たちだけで達成されるものではなく、外部要因で常に揺らいでいるので、自分たちの努力だけでは何とも解決し難いモノを内包している。
普通の国民、市民が、為政者にこういう手紙が出せる、という状況は大いに人々の意識を覚醒したに違いない。