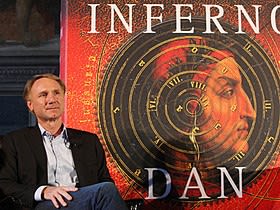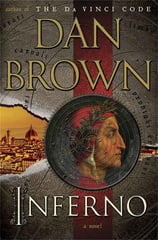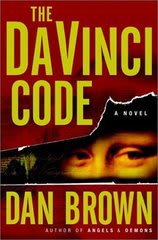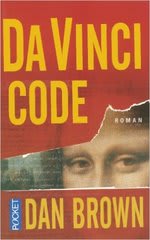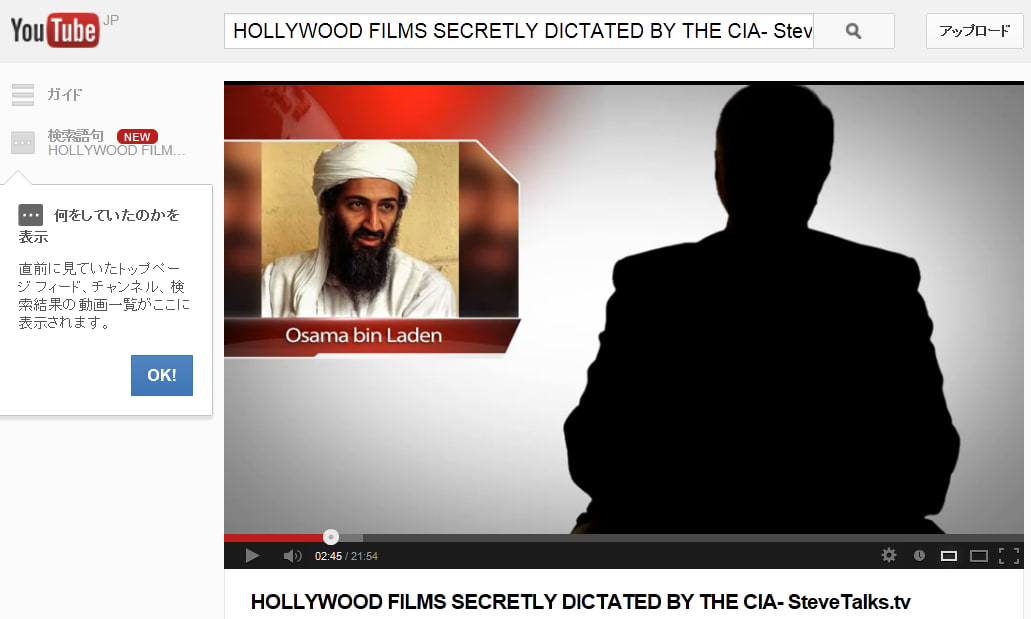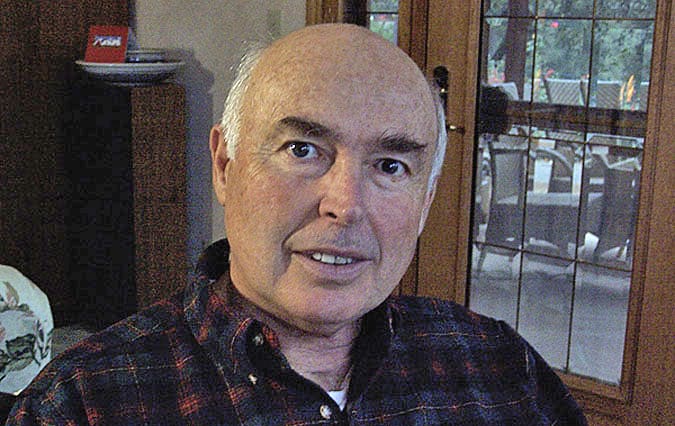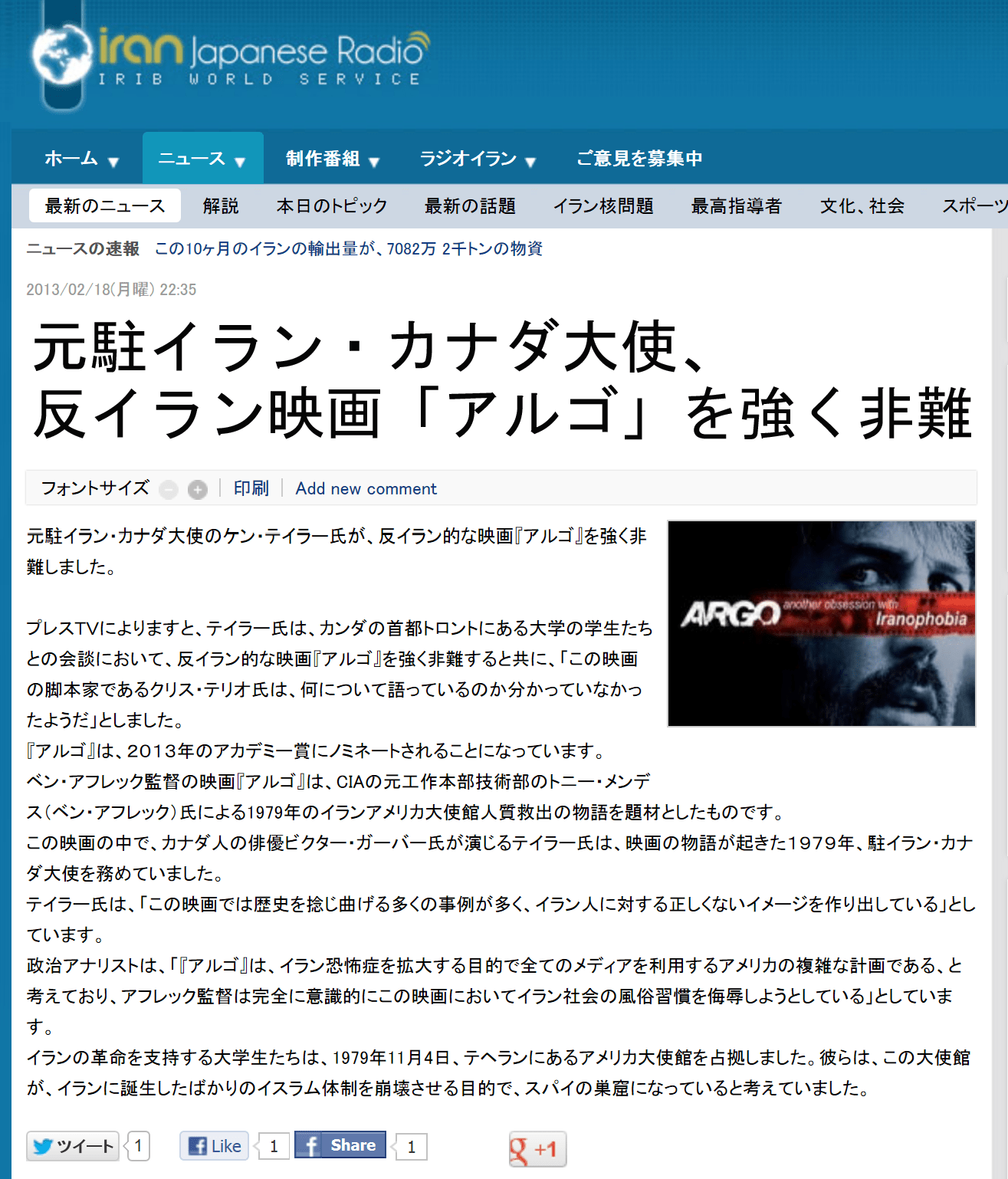映画評 「クリミナル 2人の記憶を持つ男」 “ジェリコ” は 「コンサルタント」 だ!(ネタバレ満載)
映画.com による公式の解説
ケビン・コスナー主演で、CIAエージェントの記憶を脳に移植された囚人がテロリストとの戦いに挑む姿を 描いたスパイアクション。米軍の核ミサイルをも遠隔操作可能なプログラムを開発した謎のハッカー「ダッチマン」の居場所を知る唯一の人物で、CIAのエージェントのビリーが任務中に死亡した。
描いたスパイアクション。米軍の核ミサイルをも遠隔操作可能なプログラムを開発した謎のハッカー「ダッチマン」の居場所を知る唯一の人物で、CIAのエージェントのビリーが任務中に死亡した。
「ダッチマン」の脅威から世界の危機を救う最後の手段として、ビリーの記憶を他人の脳内への移植する手術が検討され、その移植相手として死刑囚ジェリコ・スチュアートが選ばれた。
ジェリコは凶悪犯である自分自身と、脳内に移植されたCIAエージェントのビリーというまったく逆の2つの人格に引き裂かれながら、テロリストとの壮絶な闘いに巻き込まれていく。
主演のコスナーほか、ゲイリー・オールドマン、トミー・リー・ジョーンズ、ライアン・レイノルズ、「ワンダーウーマン」のガル・ガドットら、新旧スターが顔を揃える。監督は「THE ICEMAN 氷の処刑人」のアリエル・ブロメン。

わたしは主なスパイもの映画はほとんど観ているが、この作品はどうやら豪華キャストでもっている印象がある。ストーリー/脚本の水準はあまり高くない。
1) まず、「脳の移植」 というこの物語のカギとなる設定に現実感が無い。SF的な前提でスタートするスパイアクションにどれだけリアリティを与えて観客を引っ張っていけるかに注目したが、成功しているようには思えなかった。
2) また“脳記憶の他人への転写” のもつ倫理的問題についても見過ごすことのできない面がある。
3) アメリカ=正義の味方=CIA の図式から一歩も出ていない前世紀の映画の印象。
星2つである。 ★★☆☆☆ (星2.9のつもりだったが、3つはあげたくないので2つにした)
ケビンコスナー扮する凶悪犯罪者 ジェリコ は、秘密を持ったまま死んだCIA工作員の前頭葉の記憶を移植される。ウィキペデイアによると、前頭葉については、以下のようにある。
「前頭葉の持つ実行機能 (executive function) と呼ばれる能力は、現在の行動によって生じる未来における結果の認知や、より良い行動の選択、許容され難い社会的応答の無効化と抑圧、物事の類似点や相違点の判断に関する能力と関係している。
前頭葉は、課題に基づかない長期記憶の保持における重要な役割も担っている。それらはしばしば大脳辺縁系からの入力に由来する情動と関連付けられた記憶である。前頭葉は社会的に好ましい規範に適合するようにこのような情動を調整する。」
なるほど、ジェリコ は少年時代に父親による暴力的虐待の結果、前頭葉に障害を負い、それが原因で、反社会的かつ暴力的な行動を重ね、凶悪犯として終身刑という設定である。

この伏線部分で、ジェリコ は “悪人” ではなく、 “障害者” であることがわかる。

そして、前頭葉が未発達なまま成人になった稀有な例であったために、記憶転写の受容者として選ばれたというわけなのだが、一般の観客にはわかりにくいようだ。「なんでわざわざ凶悪犯の脳に移植するのか?」 とぼやいているひともけっこういるようだ。

臨床的なリアリティの欠如
つまり受容者の前頭葉の記憶の上に “上書き” するのではなく、未使用部分に他人の記憶データを書き込む、 ということなのだ。たしかに人間の脳は、ハードディスクのように簡単に “上書き” ができるわけはない。元あった記憶がすべて “上書き” で消えて、転写された新しい記憶だけになることはあり得ないだろう。


映画の中でも、「これは “脳移植” ではなくて、“記憶情報を流し込むのだ”」 と言わせている。しかし、前頭葉の未発達な “未使用部分” への “新規の書き込み” じたいが “上書き” よりもずっと現実性があるとはとても思えない。“あり得なさ” は大して変わらないだろう。
あと、「前頭葉」と言っていながら、前頭部はおろか側頭部にも手術痕は見えない。手術痕はなぜか後頭部にあるのだ。手術痕が前頭部にあったら、やはり目立ち過ぎて、たしかに異様なヒーローになってしまうかもしれない。
さらに言わせて頂ければ、脳神経科の外科的手術なら当然、頭髪はすべて剃るはずである。たしかにこのストーリーでは、いわゆる “脳移植” ではなくて、AからBへの脳記憶だけの流し込みであって、何ら外科的な作業が無いとしても、剃るはずである。なぜならば、頭部を覆う電極ネットにあるたくさんの電極は頭部の皮膚に密着していなければならないはずだからである。Aの脳記憶を電気的な信号にしてBの頭蓋骨の下の前頭葉に流し込むのに、それも医学史上初の “手術” なのに、電極を頭髪の上にふわっと載せるだけなわけがないだろう。このあたりはもう臨床的なリアリティがまったくない。
せめて頭髪を全部剃って、スキンヘッドにすべきであった。そして、毛糸の帽子でも被せればよかっただろう。しかし、“毛糸の帽子を被ったスキンヘッド” では、ヒーローのイメージに似つかわしくないと判断されたのかもしれない。
まあ、科学的な突っ込みはこのくらいで勘弁してあげようか。
さて、映画評をいくつか見ると、ケビンコスナーの悪役ぶりへの称賛が非常に目立つ。たしかにハリウッドには、ケビンコスナー、ハリソンフォード、トムハンクス、マットデイモン といった、悪役としてはほとんど使いものにならない “素晴らしい俳優たち” がいるものだ。
しかし、ケビンコスナー扮する作品中の ジェリコ は、“悪人” ではなく、“障害者” ということになるはずだ。家庭内暴力によって重度の障害を負った男であることは、ストーリーからして明らかである。ならば、ケビンコスナーが “悪人” を演じていることにはならない。
つまり、ジェリコ は、ベンアフレック主演の 「コンサルタント」 と同様に 「精神障害者」 なのである。 確かに ジェリコ は刑務所に入っているが、「凶悪犯」 である以前に 「精神障害者」 であるとはっきり言える。


「コンサルタント」 は、自閉症で、特に “高機能自閉症” に属する症例であって、自閉症患者独特の “マイワールド” に生きており、自閉症患者特有の方法で悪人どもを追い詰め、退治するのだ。
そして、ジェリコ の場合は2つの人格が表になったりウラになったりしながら、悪玉を追い詰めるという展開となる。


2) 倫理的問題
さて、「コンサルタント」 も ジェリコ も、ふつうの健常者とは違うさまざまな問題に直面しながら生きているのだが、ジェリコの場合は、障害のある自分の人格に加えてもう一つ別の健常者の人格まで背負いこむことになっているので、幾度となく頭痛と混乱に見舞われる。ここが、“記憶転写” のリアリティを出す山場ということになる。

けっきょく、前頭葉に新しく流し込まれた健常者の記憶情報が本来のジェリコの記憶情報を次第に支配していく。つまり、脳に流し込まれた他人の記憶情報によって、受容側の人格が乗っ取られてしまうのだ。


傍若無人で粗暴だった人格が、“ふつうのひと”っぽくなっていって、めでたしめでたし、という “ヒューマンドラマ” が浮かび上がってくる仕掛けである。罪深かった人間が 「少しずつ人間の心を取り戻していく」 というやつである。
そもそも、流し込まれた記憶情報はCIAの工作員のものである。CIAの工作員をするような男の心がそんなに人間的なものとは、わたしには到底思えないのである。
CIAであれ、誰であれ、これは、一種の “ロボトミー” ではないか。元の粗暴な性格が、治療もしくは学習や経験によって非暴力的になったのではなく、まったく別人の健常者の記憶を強制的に流し込んで “人畜無害” にしたということではないか。それを ジェリコ の本来の人格を消し去ることによって実現している。実質的には “入れ替え” である。違うだろうか?エンジン不具合のあったベンツの、エンジンだけをポルシェのエンジンに替えたようなものだ。これはもうベンツではない。ポルシェでよく走ればいいじゃないか、という問題ではなかろう。
さらに別のたとえで言うならば、先住民の住む大陸に別の文明の担い手たちが移り住んで来るようなものである。先住民たちは駆逐され、やがて大陸は新たな入植者たちの天下になってバンザーイ!というプロセスである。
人畜無害になるのならば、別人の人格の記憶情報を流し込むことも是認されるという隠れたメッセージがここにはあることを見据えておく必要がある。この発想は、“ロボトミー” よりも非人道的であるかもしれない。他人の脳記憶を流し込んで障害が治るならば結構じゃないか、と思うひともいることだろう。しかし、よく考えて頂きたい。いくら障害が治ったって、別人になったんじゃ意味がないだろう。
2つの人格の見事なタッグマッチによって悪玉をさんざんやっつけた ジェリコ は数日後のラストシーンで砂浜にひとり立っている。殺されたCIA工作員の記憶情報が自分の脳に注入された ジェリコ は、今や振舞いも言動もそのCIA工作員っぽくなっている。“真人間” としての新たな人生のスタートを予感させるシーンである。
しかし、そこにいるのはCIA工作員のビリーじゃないのか? ジェリコ、お前はもう死んでいる。
CIA工作員ビリーの美貌の妻と愛くるしい娘とが砂浜にやって来て、ジェリコ を温かく迎えてこの映画は “幕” となる。この “ハッピーエンド” をすんなり受け入れさせようとするこのドラマ構成には危険なものが潜んでいる。
考えても見たまえ、死んだCIA工作員ビリーは ジェリコ の身体に乗って愛する家族のもとに戻ったようなものではないか?
たとえそれがビリー本人の意志ではないとしても、ジェリコ の人格は崩壊し、彼の身体は、工作員ビリーの記憶と心を宿すものとして、つまり “ビリーの入れ物” であるからこそ彼の家族に歓迎されているのである。ジェリコ はもはや “抜け殻” にすぎない。他人の人格の入れ物としての存在価値しかないのだ。
「勘違いするなよ、ジェリコ!お前の人格など、どうでもいいのだ。美しい未亡人と娘にとって、お前はビリーの記憶と心の “入れ物” として機能してくれればいいだけなんだ。ジェリコ としての自分が受け入れられているなんて間違っても思うなよ!」
この映画は生命倫理的に非常に大きな問題を、薄っぺらなハッピーエンドでお茶を濁している。いや、とんでもない結論を観客に受け入れさせようとしている。
3) アメリカ=正義の味方=CIA?
大国の核ミサイルをも遠隔操作可能なプログラムを開発した謎のハッカー「ダッチマン」の居場所を知らせないまま殺されたCIA工作員が超イケメンである。そして、テロリストと戦う彼には美しい妻と可愛い娘がいる、というアメリカの独善的美化、悪意や邪心の不在演出が、そもそも前世紀の遺物で、“リアリティなさ過ぎ” である。
21世に入ってからのスパイ映画では、多少はCIAの悪行を暴いたり、CIAの腐敗を織り込むのが定石になってきているのに、いつまでもこんな時代遅れなシナリオを書いていて、あとは適当に豪華キャストで埋め合わせようとしているように思える。


そのプログラムを開発したのが、オランダ人で、 通称 「ダッチマン」 というのも芸が無さ過ぎではないか。フランス人だったら 「フレンチマン」 か?
ちなみに、この 「ダッチマン」 の風貌が ジュリアン・アサンジュを思い起こさせるのは監督の遠望深慮の結果と考えるべきであろう。単なる偶然と思うのは、映画というものを知らないひとである。

さらに、この 「ダッチマン」 がロンドンからロシア亡命を企てるのだが、このあたりは、スノーデンの実話のエピソードに絡めているのは明白である。
つまり、21世紀の アサンジュ と スノーデン が、この20世紀の遺物のシナリオを少しでも現代化してリアリティを醸し出すように サブリミナル素材 として実に安易に使われているのだ。
そして、ロシアもこの 「ダッチマン」 を確保しようと動き出し、三つ巴(どもえ)の様相を呈してくる。
そのプログラムを狙うアナキスト革命家は狂信的なスペイン人という設定。このカルト的アナキスト集団の教祖 には 献身的で行動的な美貌の愛人 がいて、テロリストとして活躍するのだが、教祖と献身的な美女という設定 は、「インフェルノ」 に出てくる狂信的カルトの教祖ゾブリストとその美貌の愛人との関係のパクリであると思える。
ちなみに、こうしたカルト的狂信集団の教祖は必ずと言っていいほど ヒゲ を生やしていて、美女 を腹心としている。肉体関係を持った女しか信用しないということなのかもしれない。


さて、ロシア政府が送り込んでくる連中がまるでロシアンマフィアそのもののようなゴロツキ連中なのには笑えてくる。これはアメリカ人のもつロシア人のイメージのステレオタイプである。
トミー・リー・ジョーンズ について一言


この俳優は今まで 警察や、軍隊や、CIAといった “権力組織” の人間 をさんざん演じてきていて、今回いきなり脳神経科学の教授である。モルモットにされる ジェリコ にいちばん人間的に接する役回りで、人情味溢れる老練の科学者役ということで実に安易にこの豪華キャストのトミー・リー・ジョーンズを抜擢したようだ。高額のギャラが支払われたはずだ。
この映画では終始困ったような顔をしているのだが、まったくのミスキャストである。柄(ガラ)じゃない。こんな雰囲気の研究者がいたら、いくらでも論文のデータ改ざんをしていそうだ。業績よりもむしろ大学内での出世のための根回しに忙しそうだ。トミー・リー・ジョーンズのそういった “俗っぽさ” が彼のキャラクターの土台をなしている。コマーシャルを通じての日本での人気もここにある。これは脳神経科学の教授のイメージに期待される、世智に疎い研究一筋の老教授のイメージと相容れないのだ。
この俳優は、つい昨年公開の「ジェイソン・ボーン」 では、CIAの腐りきった高官を演じていたばかりなのである。そちらのほうはまさに “はまり役” であった。ちなみにそちらの作品は期待以上の完成度で、わたしは星4つを惜しみなくあげたい。


今度の 「クリミナル」 は “スパイもの” とも “CIAもの” とも呼べるくらいの作品だが、すぐにキレるCIAの高官には ゲイリー・オールドマン が好演している。CIAの官僚的体質と無能ぶりを見事に等身大で表現している。「レオン」以来、アクション映画では、いつも存在感のある名わき役として大事にされているのも納得である。

それにつけても、トミー・リー・ジョーンズの “教授役” ほど間が抜けているものはない。彼のキャラクターには、知的探求や研究一筋の要素は皆無である。

彼のイメージは、“科学的知識のかたまり” というよりも “世間知のかたまり” なのである。ミスキャストでも、観客を釣ることができれば、高いギャラも無駄じゃないということか? そして、観客も、「なんかなあ」と、ミスキャストと感じていても、缶コーヒーの爺さん が拝めれば満足するのか。