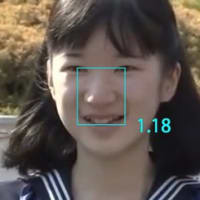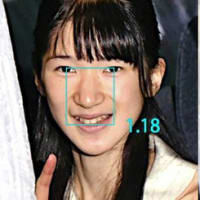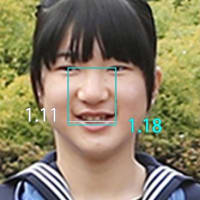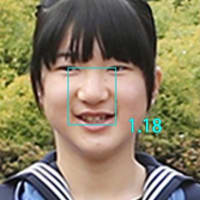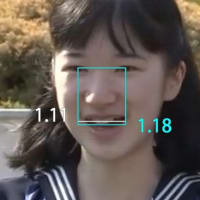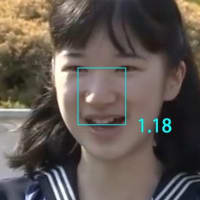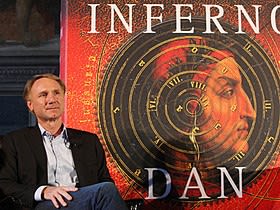
映画評 「インフェルノ」 もう ダン・ブラウン は卒業しませんか?
これは 「ダビンチ・コード」 ファンには、とてもお勧めできない。 ★★★☆☆
人口増加が世界を地球を破滅に導くというカルト思想のカリスマが、致死性のウィルスを世界中にまき散らして人口削減しようとする。しかし、われらが主人公、ラングドン教授がその阻止に大いに貢献するというストーリーである。


おわかりのように、ハルマゲドン思想である。日本のオウム真理教が典型である。観ていて、わたしが嫌な気分になってくるのは日本人としての集団的記憶があるからなのかもしれない。「インフェルノ」のバイオテロに、オウム真理教のサリンガステロがどうしてもかぶってきてしまうのだ。しかし、10代、20代の若者はオウム真理教をあまり知らないので、さほど抵抗はないであろう。



アラブのテロリストがウィルスをまき散らそうとするのを、FBIやCIAのヒーローが阻止する話はもう以前からあるので、バイオテロのアクション映画 としては新鮮味は特にないといえる。「ピースメーカー」 などが代表的かもしれない。


ダン・ブラウンの作品は常にヨーロッパの文化史が下敷きになっていて、主人公のハーバード大のラングドン教授による謎解きによって問題が解決されるというパターンがいつも繰り返される。しかし、失礼ながら、もうダン・ブラウン節にもいい加減飽きてきた。 2003年の 「ダビンチ・コード」 からもう13年も付き合ってきたことになる。

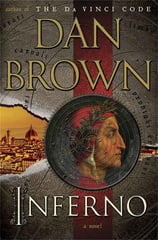

ハリウッドのアクション映画の1つのパターンとして、時限装置とヒーロー達との競争が最後のクライマックスとしてリアルタイムに展開するというのがある。
もっと一般的に言うと、大災害や悲劇を未然に防ぐためにヒーロー達が必死になって奔走するプロセスである。


これほど使い古されたシナリオもないだろう。観ていて、さすがに白けてしまった。単にわたしが歳をとったのだろうか。ハリウッドもこんなシナリオでしか、もうハラハラドキドキの終盤は作れないのだろうか?


ダン・ブラウンの小説では、まず最初に人が死ぬのだ。


そして、主人公ラングドン教授には毎回若い女性が話の序盤に“偶然に”現れる。しかし、それもつかの間、一緒に逃走する羽目になる。


このパターンもダン・ブラウンに限らず、ハリウッド映画では多い気がする。脇役として現れるのはいつも若い女性 と決まっているのもあまりにも定石すぎて、もう勘弁してくれと言いたくなる。
そして、その女性が主人公の謎解きの協力において、驚くべき閃きを見せるというのも繰り返されてきたパターンである。


ただ、私のようなうるさ型のアクション映画ファンも何とか引っ張っていけるのは、ヨーロッパやトルコの古都を目まぐるしく訪れ、ルネッサンス以降の絵画、彫刻、建築を織り込んで観客を飽きさせない工夫が随所になされているからである。


もちろん原作の段階でそうなっているのだ。「ジェームズ・ボンド」や、「ジャック・リーチャー」 や 「ジェイソン・ボーン」 の映画では ボッティチェルリやダンテの「神曲」 が出てくることはない。こういったややハイブロウな、“知的なフレーバー” がダン・ブラウンの真骨頂である と言えるかもしれない。しかし、純粋にアクション映画としては2流以下だろう。
アクション映画の逃走・追跡シーン について今回あらためて気付いたことがある。それは 街をあげてのお祭りとか、デモ行進とか大勢の人間がごった返すイベント を設定する定石があるということだ。


もちろん ただの都会の雑踏 の場合もあるが、今回の場合はさまざまで、コンサートの聴衆を巻き込むシーンも圧巻であった。
言って見れば、“障害物競走” にして混乱状態を現出させるわけである。当然エキストラの大動員である。こういうところに惜しみなく金をかけて、大スペクタクルのリアリティを出すのがハリウッド映画のお家芸である。
さて、彼の独壇場であるはずの、謎解き、歴史的なパースペクティブにおいては、今までの水準をかなり下回っている印象がある。長年のファンには、ダン・ブラウンの手の内がもう透けて見えてしまうということなのかもしれない。


ダン・ブラウンの原作はこの 「インフェルノ」 以前の、「ダビンチ・コード」 から 「ロスト・シンボル」 までは、わたしはすべて原書で読んでから映画を見ている。しかし、今回の 「インフェルノ」 はわたしとしては初めて原作を読まずに観た映画であった。

正直言って、もう小説の原作を読む必要はないと思っている。もうダン・ブラウンは卒業だ。小説の 「インフェルノ」 に 「ダビンチ・コード」 ほどの面白さ、知的興奮がないことは映画だけでも十分にわかってしまう。


逆に言うと、小説 「ダビンチ・コード」 は、けた外れの傑作だったのだ。
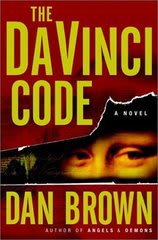


今回の 「インフェルノ」 と比べると、それが特にはっきりすると思う。 「ダビンチ・コード」 は 「インフェルノ」 の10倍のインパクト、深さがあった。それは、「ダビンチ・コード」 が単なるフィクション以上のものを読者に垣間見させたからである。 あの 「ダビンチ・コード」 が例外的な空前のベストセラーだったのだ。当の作者のダン・ブラウン自身、もう自分でも超えられないのではなかろうか。
今でも 「ダビンチ・コード」 は名作だと思う。日本語では読んでいないが、英語で2回読み、その後フランス語の翻訳でも1回読んだ。ちなみにこのフランス語版は、横浜拘置所の獄中で読んだ。最初、外国語の本は内容が検閲できないので差し入れできないと言われて却下された。しかし、英語ですからと言って無理に頼み込んで私の書斎にあった、まだ読んでいなかったのを家内に差し入れさせたのだ。

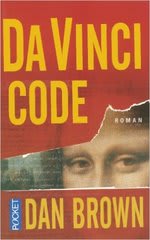 表紙タイトルはほとんど英語版と変らない。
表紙タイトルはほとんど英語版と変らない。
正直にフランス語と言っていたら、まずダメだっただろう。もう8年前のことだ。

わたしは、このダン・ブラウンという作家に敬意を抱いている。それは、彼が面白い小説を思いついたという理由ではない。彼が、ヨーロッパ史、キリスト教史の最新の研究の成果を小説のなかに果敢にも採り込んだからである。
これはかなり勇気のいる行為である。というのは、彼は、ローマカトリック教会の実在のキリスト教組織 Opus Dei を作品中に実名で登場させ、キリスト教の歴史のタブーに踏みこんでいるからである。実際、当時かなり物議をかもしたものだ。


こうした新しいキリスト教観は、もちろん、彼のオリジナルのものではない。彼はある意味で、新しい歴史観の普及者として貢献したと言えよう。彼の作家としての功績は絶大なものがある。

ダン・ブラウンの小説の映画化では一貫して トム・ハンクス が起用されている。たしかに、これは名キャストである。逞しく強いヒーローではなく、文弱でシャイな教授で、ピストルなんか触ったこともないような雰囲気がぴったりである。女たらしでもなく、かといってマイホームパパでもなく、研究三昧の独身の40台の教授というイメージである。
ラングドン教授といえば、トム・ハンクス、ハリー・ポッター といえば、ダニエル・ラドクリフ で決まりなのだ。もう“替え”はきかないだろう。


星3つは、わたしとしては辛いほうだ。星2つにしなかったのは、ヨーロッパの古都を巡るロケの功績を正当に評価してあげたい気持からである。