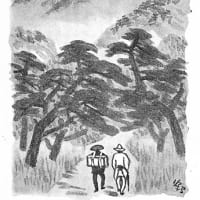日本近代文学の森へ (134) 志賀直哉『暗夜行路』 21 「愛子とのこと」⑴ 「前篇第一 五」その1
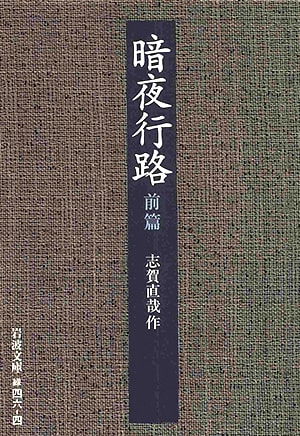
2019.11.10
二度目に登喜子と会う前と後では不思議なほどに謙作の気持は変っていた。彼は今も登喜子を美しく思っている。そして好きだ。しかしその美しく思い方も、好き方も、前の変に重々しく息苦しかった時に較べて、妙に軽快なものになっていた。彼は漸(ようや)く落ち着けた。彼は前の自分を想い、全体何を目がけて、あれほどにも力瘤を入れ、あれほどにも一人先走りしたものか解らない気がした。
勿論、この変化は―つは登喜子の態度で導かれたものである。が、それよりも彼は愛子との事こういう事には変に自信がなくなっていた。そして、この自信なさが、知らず知らずこの落着(おちつき)に彼を満足させようとしているらしかった。
或る彼はもっと突き進みたがっている。しかし他の彼がそれを怖れた。愛子との事で受けた彼の傷手はそれほどにまだ、彼には生々しかった。
「五」になって、初めて愛子とのことがはっきりと描かれることになる。
登喜子のことは好きだが、今のところ深入りしない関係に「落着」ている。「こういう事」に自信のない謙作は、この「妙に軽快」な登喜子との関係が快いというのだ。
なぜ「こういう事」に自信がないかというと、「愛子との事」があったからだ。
この「五」の部分はそのすべてが、愛子とのいきさつを語ることに費やされているが、かいつまんで紹介しておきたい。
愛子の父は水戸の漢方医であった。そしてどういう事情でそうしたかは謙作も知らなかったが、愛子の母は謙作の母方の祖父母を養父母として、其処からその漢方医に嫁入ったのであった。謙作の母と愛子の母とは幼馴染で特に親しかった。彼は母の死後、よく愛子の母から実母の事を聴いた。「いい方でしたよ。涙もろい、本統に親切な方でした」愛子の母はよくこんなにいった。芝居好きで、二人で芝居の真似をして祖母に叱られたというような話もした。
昔は特に養父母というのが多くて、複雑だが、要するに愛子は謙作の血縁のない従姉妹ということになる。謙作の母はすでに亡くなっているので、その母と親しかった愛子の母は、謙作にとっては亡き母のことを聞かせてくれる大事な人だったわけだ。
誰からも本統に愛されているという信念を持てない謙作は、僅(わずか)な記憶をたどって、やはり亡き母を慕っていた。その母も実は彼にそう優しい母ではなかったが、それでも彼はその愛情を疑う事は出来なかった。彼の愛されるという経験では勿論お栄からのそれもなくはない。また兄の信行の兄らしい愛情もなくはない。しかしそれらとは全く度合の異った、本統の愛情は何といっても母より他では経験しなかった。実際母が今でもなお生きていたら、それほど彼にとって有難い母であるかどうか分らなかった。しかしそれが今は亡き人であるだけに彼には益々偶像化されて行くのであった。
謙作の母は、謙作にいつも優しかったわけではなかったけれど、やはり実の母だけが、本当の愛情を注いでくれたのだという謙作の気持ちはよく分かる。「本当の愛情」というのは、言葉では表現できないほど微妙なものであるのだろう。いつも優しい言葉をかけてくれたり、頭をなでてくれたからといってそれが「本当の愛情」を保証するわけではない。
言葉や行動を超えたところにそれはたぶんある。続く部分は、その辺のことを語って見事である。
そして彼は何となく亡き母の面影を愛子の母に見ていた。ある時──多分それは母の十三回忌の時であった。彼はその日本郷の実家に行って、其処で、愛子の母が旧式な大小小紋に黒繻子(くろじゅす)の丸帯を締めて来ているのを見た。その姿が彼の心に不思議な懐しさを起した。彼は何気なくその姿に時々眼をやっていた。すると、何かの機会に偶然並んだ愛子の母がその着物の袖を引いて見せて、
「これも、帯も、今日のお仏様の御遺物(おかたみ)ですよ」といった。彼は妙な気持になった。一種の感じに打たれた。そして彼は黙っていた。少時すると愛子の母は手を袖の中で縮めながら、
「《ゆき》がもう出ないので、腕の方に《あげ》をしてるの」こんな串戯(じょうだん)をいって笑った。
ここで謙作が感じた「妙な気持ち」「一種の感じ」は、なかなか印象的で、当然のように『源氏物語』が頭に浮かぶ。源氏が亡き母の面影を藤壺に見て慕うのも、ひょんなことから耳にした「藤壺は桐壺更衣に似ている」という女房のヒソヒソ話だったはずだ。
「本当の愛情」は、言葉や行動をはるかに超えたところ、「面影」にこそ内在しているのだろうか。
それにしても、こういうところの描き方、志賀直哉はほんとにうまい。
愛子の長兄は慶太郎といって、中学は異っていたが、信行とは同年、謙作よりは二つの年上で、三人は子供の頃からよく遊んだ。しかし信行も謙作も彼とそう親しくはなれなかった。性質に何処(どこ)か合う事の出来ないものがあった。が、その割りには謙作だけは牛込の愛子の家へよく出入りをした。彼は何よりも愛子の母に会いたかったからである。
慶太郎のことを簡潔に紹介している。ここで言及される、慶太郎との「性質の齟齬」は、この後の展開に重要なポイントとなる。大事なことをズバッと書いて、先へ進む。いいテンポだ。
愛子は彼より五つ年下であった。子供の頃は彼は何方かというと愛子を少し五月蠅(うるさ)く感じていた。例えば慶太郎らと何かして遊んでいる時に、何も出来ない癖に仲間入りをしたがったり、またある時は愛子の母と割りに真身(しんみ)り話込んでいるような場合、「もう《ねんね》するの。もう《ねんね》するの」こんな事をいって、母を自分の寝床に連れて行きたがったりする事がよくあったからである。彼はそういう時代から知っているだけに愛子が相当の年になっても妙に異性としては強く来なかった。
次に幼い頃の愛子についても簡潔に描かれる。これだけで、幼い愛子が生き生きと目の前に浮かんでくる。
そして彼が本統に愛子を可憐に思い出したのは彼女が十五、六の時に彼女の父が死んで、その葬式に白無垢を着て、泣いている姿を見た時からであった。
愛子の女学校での英語の試験勉強の手伝などした事もあったが、そういう時には彼は自分の気持を出来るだけ現さないように努めていた。―つは彼の臆病からも来ていたが、同時に彼の感情はそれほど燃えてもいなかった。その上まだ子供気の脱けていない愛子にはそんな事が如何にも遠い事のように感じられたからでもあった。けれども、これは彼の主観の勝った感じ方で、愛子が特別に年よりそういう感情で遅れていたわけではなかった。愛子からすれば、子供からの関係上、謙作にはそういう感情で至極、《あっさり》していられたからでもあったろう。
愛子の母に生母を感じたときが「黒繻子」で、愛子を可憐に思い出したときが「白無垢」という対比も面白い。志賀直哉はそこまで考えていたかどうか分からないが、鮮やかな印象を残す。
愛子が好きになってからも、謙作は「臆病」だった。謙作は、愛子に成熟をみていなかったけれど、それは「彼の主観が勝った感じ方」だとも評されている。