木洩れ日抄 43 あったまきた!
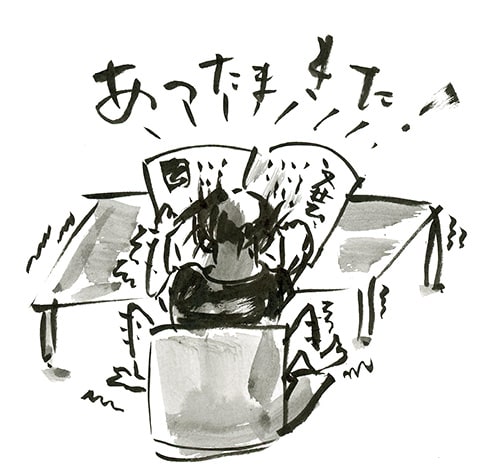
2018.9.1
8月29日の朝日新聞の「文芸時評」で、小説家の磯崎憲一郎が、保坂和志の書評の枕として、こんなことを書いていたのを読んで、久々に頭にきた。
NHKの連続テレビ小説『半分、青い。』を観ていて、どうしても覚えてしまう違和感、という表現では足りない、ほとんど憤りにも近い感情の、一番の理由は、芸術が日常生活を脅かすものとして描かれていることだろう。漫画家を目指すヒロインは、故郷を捨てて上京する、そのヒロインが結婚した夫は、映画監督になる夢を諦め切れずに妻子を捨てる、夫が師事する先輩は、自らの成功のために脚本を横取りしてしまう……漫画や映画、そして恐らく小説の世界も同様に、生き馬の目を抜くような、エゴ剥き出しの競争なのだろうと想像している人も少なくないとは思うが、しかし現実は逆なのだ。故郷や家族、友人、身の回りの日常を大切にできる人間でなければ、芸術家には成れない、よしんばデビューはできたとしても、その仕事を長く続けることはできない。次々に新たな展開を繰り出し、視聴者の興味を繋ぎ止めねばならないのがテレビドラマの宿命なのだとすれば、目くじらを立てる必要もないのかもしれないが、これから芸術に携わる仕事に就きたいと考えている人たちのために、これだけはいって置かねばならない。芸術は自己実現ではない、芸術によって実現し輝くのはあなたではなく、世界、外界の側なのだ。
『半分、青い。』は最初からずっと見ていて、後半からちょっとゴチャゴチャしだして、イマイチだなあと思うところはあるにせよ、この磯崎氏の「違和感」には、とても「違和感」を感じた。「違和感」では足りない、「ほとんど憤りにも近い感情」を持った。いや、それでも足りない。あったまきた!
『半分、青い。』が「芸術が日常生活を脅かすものとして描かれている。」とあるが、完全に間違えている。「芸術が」ではなくて「芸術家志望者が」だというなら、「半分、正しい。」けど。
どこの親だって、子供が「漫画家になりたい」と言い出したら、まずは反対するだろう。つまり、「日常生活を脅かす」と感じるからだ。そんなの、なれるのは一握りだってことを親は知っているからだ。それを、そう感じずに、「そうね、それじゃ、漫画を書いて、世界を輝かせる人になってね。」なんて言う親がいたら、金を払ってでもその顔を見たいものだ。
繰り返すが、『半分、青い。』のどこにも、「芸術」が、「日常生活を脅かすものとして描かれている」ところはない。そんなものは皆無だ。
百歩譲って、磯崎氏の言いたいのは、「芸術を目指すこと」が「日常生活を脅かすものとして描かれている」ということなのだとしよう。しかし、それなら、「芸術を志望する」人間の、「日常」って何だろう。芽が出なくて苦しむのも彼のあるいは彼女の「日常」だろう。ライバルを蹴落とすのも彼のあるいは彼女の「日常」だろう。「日常」っていうのは、朝起きて、パンたべて、行ってきます、って言って家を出るようなことをいうわけじゃない。いろんな「日常」がある。楽しかろうが、苦しかろうが、平凡だろうが、波瀾万丈だろうが、日々の生活が、「日常」である。
言っていけばきりもない。そもそも「ヒロイン」は、「故郷を捨てて」なんかいない。捨てるどころか、鈴愛にとっては故郷は生きるよりどころとしてあり続けている。石川啄木のように、故郷を石もて追われたわけじゃない。鈴愛が「故郷を捨てた」というのなら、東京や大阪の大学に入るために田舎から出てきた者は、みんな「故郷を捨てた」ことになる。馬鹿も休み休み言え、だ。
「ヒロインが結婚した夫は、映画監督になる夢を諦め切れずに妻子を捨てる」とあるが、「捨てた」というより、「別れざるを得なかった」わけだし、「夫が師事する先輩は、自らの成功のために脚本を横取りしてしまう」というのは、表面的な筋だけでいえばそうかもしれないが、「先輩」は、自殺までしかかるほど後悔するのだ。小説家にはあるまじき粗雑な表現である。「横取りする」こと自体が悪いからダメというんじゃ、小説にならないじゃないか。そんなこといったら、「殺人」も「不倫」も、いっさいナシの推理小説を書かなきゃならなくなるじゃないか。
そもそも「夫が師事する先輩」とは何たる書き方であろうか。とても文章表現をナリワイとする人の表現とは思えない。せめて「斎藤工演じるところの映画監督」ぐらいは書いたらどうなのか。なんか、「愛」がないんだよね、この人の文章。対象に対する「愛」がない表現なんて、価値がない。たとえ、けなすにしてもだ。
つまるところ、この人は、このドラマをちゃんと見てないんじゃないのかと思わざるをえない。食事のついでかなんかに、チラ見して、筋だけ知っている程度。もちろん、テレビドラマだから、そういう見方しちゃいけないなんてことはない。どう見たって勝手だけど、新聞に書いて公の目にさらすなら、ちゃんと見ろ、ってことだ。
「漫画や映画、そして恐らく小説の世界も同様に、生き馬の目を抜くような、エゴ剥き出しの競争なのだろうと想像している人も少なくないとは思うが、しかし現実は逆なのだ。」などとヌケヌケ、シャアシャアと言うが、どこにそんな断言する根拠があるのか。「逆なのだ」という「現実」がいったいどこにあるのか。それは、あなただけの「現実」じゃないのか。早稲田出て、三井物産に入って、部長になって、小説書いて、大学教授になっている「あなた」だけの「現実」じゃないのか。(なんだかシットしてるみたいな書き方だなあ。──だとしても、それがぼくの「現実」だ。しょうがないや。)
そもそもあなたは芥川賞をとったから自分は「芸術家」だと思っているのか。もっと言えば、「芸術家」って、「成れる」とか「成れない」とかいったレベルのものなのか。「芸術家」という言葉にあなたはなんの抵抗感も違和感も持たないのか。
かつて、親族に「小説家」がいるなんてことは、誇ることじゃなくて、むしろ隠しておきたいことだった時代もあったってことを、あなたは知っているのか。あなたは小説家になって、ちゃんと「食えている」かもしれないが、「食えていない」小説家がいったいこの世界にどれだけあふれかえっているのか知っているのか。
今さら「破滅型」の小説家のことなんか持ち出してもしょうがないけど、「破滅型」って言われる作家じゃなくても、島崎藤村なんか子供が何人も「餓死」している。(ほんとうは「餓死」というより、栄養失調故の病気)岩野泡鳴は、家族をまったく大事にしなかったけれど(それどころか家族そのものをほとんど否定している。)、それじゃ彼は芸術家とは呼べないのか。詩人とか芸術家と呼ばれる人たちが、故郷でどれほどおとしめられ、侮蔑されたか知っているのか。中原中也は、どれだけ友人から嫌がられたかご存じか。太宰治は、どれだけ周りに迷惑かけた(迷惑なんてレベルじゃなくて、一緒に死んでくれなんていって、女だけ死んじゃったんだからね)か知らないとでもいうのか。
芸術家と呼ばれるような人種は、少なくとも、世俗的な価値観を否定し、場合によっては破壊し、世の中を変えていこうと志すものたちだろうから、生ぬるい「日常生活」を脅かすことこそ、その真骨頂ではなかったのか。
芸術家として生きる人たちが「エゴ剥き出しの競争なのだろう」と想像して何が悪い。漫画家デビュー目指している若者が、小学校の運動会の徒競走みたいに、手をつないでみんなでゴールしようなんて思っているだろうか。いったい漫画家志望の、ピアニスト志望の、画家志望の、役者志望の、その他モロモロの「芸術家志望」の人たちが、どれほど挫折し、呻吟し、諦めていったか、そんなことに想像力を使ったことがあるのか。
「現実は逆なのだ。」というなら、故郷も家族も友人も身の回りの日常もみんな大事にしていれば、それで「芸術家」になれるということか。さすがに、それは無理だろう。そういうものも大事にしつつ、芸術家になるように努力しろってことだろうけど、それができれば苦労はない。あなたにはそれができた、ただそれだけのことじゃないか。それを「これから芸術に携わる仕事に就きたいと考えているい人たち」に向かって押しつけることはない。余計なお節介というものだ。
「芸術は自己実現ではない、芸術によって実現し輝くのはあなたではなく、世界、外界の側なのだ。」なんて、どこかできいたふうなことを、自分で考えたことのように言うな。芸術は、他者の感動によって輝くのだから、単なる「自己実現」だと思って、周りに迷惑かけてワガママを通していればそれでいいわけじゃないことはよくわかる。けれども、そんなことが「分かる」ようになるのは、たぶん、自分が死んでからだ。それまでは、がむしゃらに「自己嫌悪」と懸命に戦いながら、「自己実現」あるいは、「自己表現」をするしかないんだ。
「自己」を無視して、最初から他者の目を気にしているようでは、「芸術」は生まれない。
『半分、青い。』は、何かを作りだそうとする人の、「前向き」な姿勢を描こうとしているが、同時にその「闇」も描いている。その「闇」の描き方は、朝ドラだから、ずいぶんと抑えた描き方をしている。その「抑えた」表現にすら、「どうしても覚えてしまう違和感、という表現では足りない、ほとんど憤りにも近い感情」をもったという「芸術家」磯崎憲一郎とは、いったいいかなる「芸術家」なのであろうか。
保坂和志のそれこそ「日常」を描いた小説を賞賛する書評の枕としてこの文章を書いたということは重々承知だが、枕だからといって、文筆のプロたるもの、甘くみちゃいけない。「次々に新たな展開を繰り出し、視聴者の興味を繋ぎ止めねばならないのがテレビドラマの宿命なのだとすれば、目くじらを立てる必要もないのかもしれない。」などと、「テレビドラマ」に対する冷たい偏見を隠そうともせずに、いや、そういう自分の偏見にまったく気づきもせずに、上から目線で語ることの傲慢さを、少しでも自覚しないかぎり、あなたには「芸術家」を名乗る資格などない、ということだけはいって置かねばならない。


















