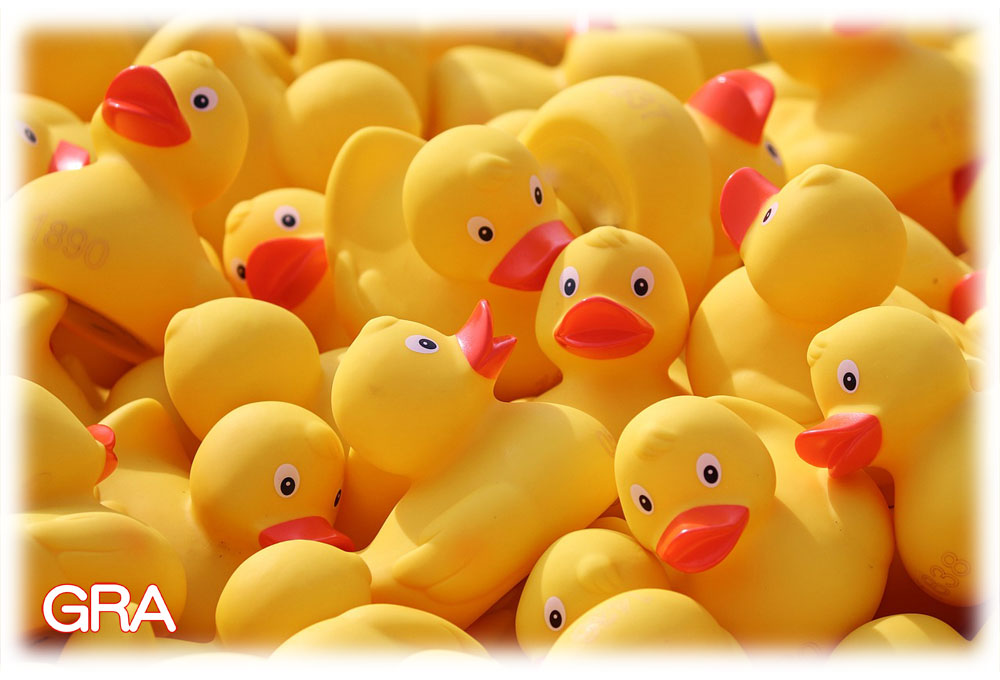今日は、朝の冷え込みも厳しくなく、日中は陽射しもたっぷりで、気温も15℃、
引越しをしてから 4ヶ月が経ち、街の買い物先のレパートリーを増やす為に、自転車で街を散策する事にしました。
『 ワシは昔、内装式に乗っていたんや 』
そして、立ち寄った店の前で、停めた自転車に施錠をしていると、通りすがりの年輩の人に「軽そうなバイクに」と、声を掛けられたのです。「やっぱり、外装式(変速機)の方が軽いだろうな」「ワシは、昔、パナソニックの自転車に乗っていて、お金が無かったから、内装式(内装式変速機の自転車)に乗っていたんや」と、いかにも自転車に興味がある事が分かる話しぶりでした。

その時、“内装式変速機” と聞いて、うかつにも、僕はママチャリ(通称)を頭に浮かべてしまいました。しかし、それは全く違ったのです。「後が内装式変速機の 6段で、前が 3段、合計18段の自転車で、40年前、46歳の時、長距離を走ったんや」「国道29号の志戸坂峠に登って鳥取県の智頭に行って、そこから国道53号で黒尾峠に登って岡山県に入ってから戻る、距離190㎞、13時間の旅で、しかも雨やったんや」と、僕にも馴染みのある峠や地名に聞き入りつつ、40年も前、後が内装式で 6段(速)の自転車が販売されていた事がとても印象に残ったのです。
『 内装式か? 外装式か? 』
そこで、自宅に戻ってから、40年以上も前の、ロードスポーツ タイプではないのに、前3段、後が内装式変速機で 8段の 自転車の画像や資料を検索したのです。それが、10年後の自転車の姿、或いは オートバイのあるべき姿を考えるきっかけにもなったのです。
自転車の変速機と言えば、現在、ロードスポーツタイプの自転車で主流の 変速機(後)は「外装式」です。そして、様々な走行場面での最適な変速比を求めて、その段数は増え続けて、今では 11段(速)が一般的になっています。しかし、装着するフレーム側の寸法は変わらないので、ギアユニット(重なったギア全体)の厚みは変えられず、ギアとチェーンの幅を狭くする為に材質と製作技術の改良が続けられているのです。

僕も、多分に漏れず、そんな 他段数化へ進歩(?)した姿に憧れ、自転車を作った時は、可能な限りギア数の多いユニットを選んだものですし、多くの自転車ライダーにとっても自転車選択の際の注目ポイントでしょう。しかし、内装式(変速機)の凄さを知るにつれて、外装式変速機に未来は無いかも知れないと思うようになったのです。
『 内装式の凄さ 』
そのきっかけになったのが、検索で見つけた、下の内装式変速機のカット図です。

サンギアとピニオンギアなどを組み合わせた「プラネタリーギア」を数セット組み合わせた緻密な構造になっていて、この図の場合、恐らく 4 × 2 で 8段(速)か、もしかすると、14段かと思われますが、とても心が惹かれる構造になっています。
そして、内装式だからこそ、外装式には無い数々の特徴も知ったのです。それは、一つ目は変速が瞬時に出来る事。二つ目は 停車時にも変速が出来る事。三つ目は機械的な伝達ロスが少ない事などです。 外装式の自転車ライダーであれば知っての通り、一般的な外装式の場合には、瞬時の変速は出来ず、停車する前に発車用のギア選択を終えておく必要があり、変速時には音とショックが少なからずあって、大きな段差を通過時にはチェーンが外れる覚悟も必要で、変速した段数によってチェーンは車体内側や外側へと曲げられた状態で使われるなど、外装式変速機には駆動力の伝達損失が多くあるのです。そんな機械的損失の多さに気付かされて、外装式の限界を知り、内装式は決してクラシックでもママチャリ用でもないと知ったのです。
『 電動化の時代へ向けて 』
そして、次のカット図に出会って、未来の自転車やオートバイは「内装式」しかありえないのでは、と思っています。

ドイツの Rohloff(ローロフ)社の、電動モーターが組み込まれている様に見える、内装式変速機のカットモデルで、その段数は 14段となっています。段数の多さもさる事ながら、僕は、このモーターを組み合わせた姿に心が強く揺さぶられたのです。 ご存知の通り、モーターは無回転状態から回転を始める時に一番大きなトルク、つまり一番大きな力を出しますが、それを受け留めるギアの幅は広く、外装式の薄いギアと較べるまでもなく、その力を損失少なく後輪に伝えられる事は明らかです。しかも、その駆動力を瞬時の変速で無駄なく路面に伝えられ、しかも堅牢で密閉された構造で耐久性も高く長寿命だとはっきり示しています。
『 電動化の時代、内装式の時代 』
現在、モーターを装着した電動アシスト自転車の多くは電動モーターをクランク側に装着しています。そして、後輪に「内装式」(多くは3段)の変速機を備えていますが、チェーンやギア(スプロケット)の高くない耐久性を考えれば、モーターの駆動力を制限せざるを得ない筈です。法律上の “電動アシスト” としての制限に守られてから現在の形式が一般的になっていますが、駆動エネルギーの伝達効率や耐久性の低さ、将来の完全電動化などへの発展を考えれば、チェーンを介して後輪を駆動(アシスト)する形式はエコでもなく、サスティナブルでも、スマートにも思えません。
やはり、上記、Rohloff 社 が示している様に、モーターは後輪ハブに組み込む形式こそ未来の姿としか思えません。そして、このモーター組込み型の内装式変速機が一般的になるにつれて、多段化や低コスト化が進み、ロードスポーツ自転車でも モーター無しの内装式変速機が一般的になるでしょう。これは、オートバイや車の場合も同じで、いわゆる【 インホイールモーター 】形式による駆動こそが電動モーター時代の当然の形だと、今回の「内装式」の勉強で改めて確信しました。
自転車で何気なく出掛けるのは、やっぱり、人との近さや出会いがあって、とても面白いですね。だって、今回の様な出会いから、色々な事を知り、未来を考えるきっかけが生まれたのですから。
**********
【 参考資料 】
独・Rohloff 社 公式Webサイト URL
https://www.rohloff.de/de/produkte/speedhub
<上記Webサイトより一部転載> (日本語訳)
「 新しい Rohloff E-14 では、Speedhub が電動自転車に最適なシフト ユニットになります。 ボタンを押すだけで最高レベルのシフトの快適さと同期したシフトを実現します。 電気ドライブの強力なパワーをこれほど効果的に実現できるギアハブはありません。 そして、それらのどれもより速くシフトしません。 わずか 180 ミリ秒で、電子シフト コントロール Rohloff E-14 が Speedhub の新しいギアにシフトします。 ボタンに触れるだけで、1 つまたは複数のギアを一度に簡単にシフトできます。 比類のない長寿命、526% の幅広いギア範囲、およびすべてのギア ハブの中で最高の効率を備えた Speedhub は、すべてのプレミアム e-バイクの基礎を形成します。 」

https://gra-npo.org