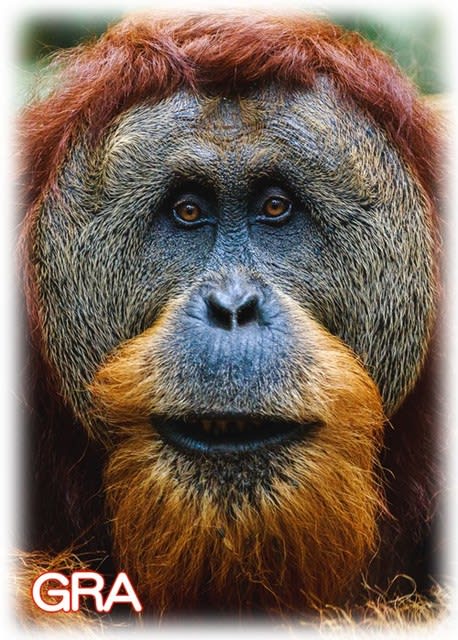以下、私達・NPO法人GRAが主催する各種イベントにおけるポリシーを説明する文章です。
他の開催団体が主催するイベントとは開催ポリシーが異なる特徴がありますので、参加の際には留意願います。
『 お客様は、神様? 』
よく使われる言葉で「 お客様は神様です 」という言葉があります。
以前、国民的人気を誇った男性歌手がステージ上で発してから更に有名になった言葉ですが、日本では生活の様々なところに深く浸透しています。
モノを販売する販売業からサービス業に携わる人は当然の事、芸能から芸術、文学に至るまで、お金を払う人を “神様” と崇め、人気を得るために “神様” の歓心を媚び、その声に耳を傾けようとする一面があります。

一方、おものてなしの国と言われる国でさえ、この “風習” は決して良い事ばかりではない事は明らかです。
対価を支払いさえすれば、何かにつけて「お客さまを何だと思っている!」という言葉を振りかざし、言葉や行動で威圧するのが日常茶飯事になっているのを目にします。
店員への暴言や乗務員への暴力行為、学校へのモンスター行為だけを指しているのではありません。 言動に出ないまでも、この国では大半の人の心に染みついている意識であり言葉なのです。
では、私達・GRAでは 参加者を “神様” として扱うのか? 単刀直入に答えれば、誰であっても “神様” 扱いはしませんし、“仏様” 扱いもしません。
それは、イベント参加費を支払う参加者はもちろん事、参加常連者であっても、運営統括責任者であっても特別扱いはありません。

ただ、私達は、一人ひとりの考えや意見を公平に尊重すると同時に、全員に対してイベント運営趣旨への理解と尊重を求め、一緒に参加責任と運営責任を負う事を求めています。
これは、1991年に GRA発足以降、基本的に変わらぬポリシーです。
『 お客様扱いは、しません 』
“お客様”とは、料金や何かしらの対価を支払えば、それに見合うだけの物品やサービスを享受するのが当然と考え、それを疑おうとしない人達の事です。
しかし、不相応な “お客様” 意識を誇示する場合には、少なくとも相手側が営利行為をしているかどうかを見極めるべきです。

私達・NPO法人GRAは、NPO(特定非営利活動法人)の名称の通り、収益活動を目的にした営利団体ではありません。
それはNPO法人になる以前から、1991年発足以降、代表や理事、社員全員が無給で運営業務を担当しており、それは内閣府等へ報告して公式Webサイトで公開している通りです。

つまり、GRAが主催するイベントに参加した際、一般的な「 いらっしゃいませ! 」という挨拶はしませんし、参加費を支払う際にも「 ありがとうございます 」の言葉は一切ありません。
ここまでの説明で、多くの人は次の様に思うかも知れません。
「 “お客様扱い” をしないのは分かったけど、しても問題ないのでは? 」
「 そんな事では参加者が増えないのでは? 」と。
そんな疑問を感じる人はきっと少なくないでしょう。
『 なぜ、お客様無用なのか ?』
一般的な講習会などイベントでは、全員が一緒に同じ事を習う学校と同じで、受講者毎に不足気味な科目への対応は無く、その講習内容は運転操作の反復練習・丸暗記学習に偏り、まるで小学生への対応と同じです。
もちろん、殆どの人は一般的なその方式で満足しているかも知れませんが、私達の目標は「小学校方式」では達成する事が出来ないと考えています。

GRAの活動目標は【 いつまでも楽しく安全にオートバイに乗り続けられる環境を、ライダー自らが生み出すのを促し、その意識と行動を備えた人を全国各地で増やす 】という内容です。
つまり、単にライディング技術の上達に熱心な “お客様” や “生徒” を求めているのではなく、総合的な世界観と行動力を伴った大人を求めていると言えるでしょう。
オートバイを末永く楽しむための知識や技術、社会での課題などを共有し合い、積極的にそれらの共有を広める可能性のある大人、つまり “ 仲間 ” や “ 同志 ” を求めているのです。
その目的の為に、“お客様扱い” はしませんし、その趣旨に関心や理解が進められる人だけに参加を呼び掛けているのです。

追加説明:『 特別な GRAイベント 』
これらを実現させる為に、先ずGRAでは、開催イベントに次の 4つの特徴を設けています。
1. 少人数制での開催 ・・ より適確な対応と育成のため
2. 自在なカリキュラム対応 ・・ 参加者の要望・意見に合わせて、多様で高度なカリキュラムでの対応
3. 参加しやすい環境作り ・・ 低額の参加費と当日受付制の採用など
4. 見学&聴講フリー制採用
GRAでは、お客様扱いをせずイベントの開催目的の理解を求めますが、一般的な講習イベントでは決して得られない、多くの知識やカリキュラムの提供の用意があります。
〇 オートバイの基本的な構造とその特性から導き出される最適なライディングの講習
〇 求めるライディング技術とレベルに応じた走行練習コースの設定
〇 構成する部品の役割と適切な整備方法の講習
〇 そしてライダー毎にオートバイを調律するセッティング理論と実技講習
ただし、これらの事柄は参加者の積極的な要望があってから個々にその場で応じるもので、何度も言いますが、開催趣旨を理解しようとしない “お客様” や、受け身参加の “生徒” な人には適したイベントとは言えませんし、そういう方々の参加は私達は望んでおりません。
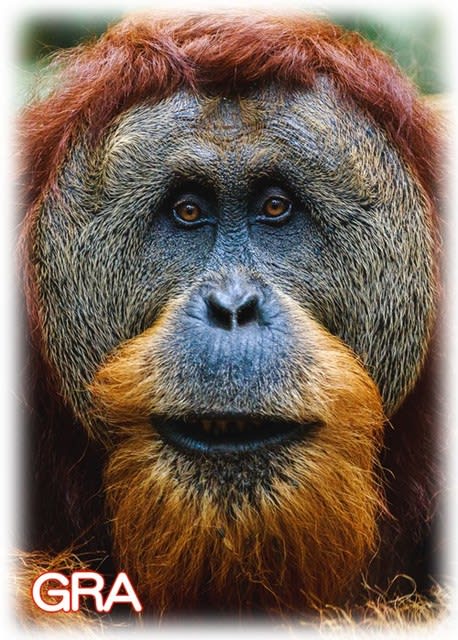
他の開催団体が主催するイベントとは開催ポリシーが異なる特徴がありますので、参加の際には留意願います。
『 お客様は、神様? 』
よく使われる言葉で「 お客様は神様です 」という言葉があります。
以前、国民的人気を誇った男性歌手がステージ上で発してから更に有名になった言葉ですが、日本では生活の様々なところに深く浸透しています。
モノを販売する販売業からサービス業に携わる人は当然の事、芸能から芸術、文学に至るまで、お金を払う人を “神様” と崇め、人気を得るために “神様” の歓心を媚び、その声に耳を傾けようとする一面があります。

一方、おものてなしの国と言われる国でさえ、この “風習” は決して良い事ばかりではない事は明らかです。
対価を支払いさえすれば、何かにつけて「お客さまを何だと思っている!」という言葉を振りかざし、言葉や行動で威圧するのが日常茶飯事になっているのを目にします。
店員への暴言や乗務員への暴力行為、学校へのモンスター行為だけを指しているのではありません。 言動に出ないまでも、この国では大半の人の心に染みついている意識であり言葉なのです。
では、私達・GRAでは 参加者を “神様” として扱うのか? 単刀直入に答えれば、誰であっても “神様” 扱いはしませんし、“仏様” 扱いもしません。
それは、イベント参加費を支払う参加者はもちろん事、参加常連者であっても、運営統括責任者であっても特別扱いはありません。

ただ、私達は、一人ひとりの考えや意見を公平に尊重すると同時に、全員に対してイベント運営趣旨への理解と尊重を求め、一緒に参加責任と運営責任を負う事を求めています。
これは、1991年に GRA発足以降、基本的に変わらぬポリシーです。
『 お客様扱いは、しません 』
“お客様”とは、料金や何かしらの対価を支払えば、それに見合うだけの物品やサービスを享受するのが当然と考え、それを疑おうとしない人達の事です。
しかし、不相応な “お客様” 意識を誇示する場合には、少なくとも相手側が営利行為をしているかどうかを見極めるべきです。

私達・NPO法人GRAは、NPO(特定非営利活動法人)の名称の通り、収益活動を目的にした営利団体ではありません。
それはNPO法人になる以前から、1991年発足以降、代表や理事、社員全員が無給で運営業務を担当しており、それは内閣府等へ報告して公式Webサイトで公開している通りです。

つまり、GRAが主催するイベントに参加した際、一般的な「 いらっしゃいませ! 」という挨拶はしませんし、参加費を支払う際にも「 ありがとうございます 」の言葉は一切ありません。
ここまでの説明で、多くの人は次の様に思うかも知れません。
「 “お客様扱い” をしないのは分かったけど、しても問題ないのでは? 」
「 そんな事では参加者が増えないのでは? 」と。
そんな疑問を感じる人はきっと少なくないでしょう。
『 なぜ、お客様無用なのか ?』
一般的な講習会などイベントでは、全員が一緒に同じ事を習う学校と同じで、受講者毎に不足気味な科目への対応は無く、その講習内容は運転操作の反復練習・丸暗記学習に偏り、まるで小学生への対応と同じです。
もちろん、殆どの人は一般的なその方式で満足しているかも知れませんが、私達の目標は「小学校方式」では達成する事が出来ないと考えています。

GRAの活動目標は【 いつまでも楽しく安全にオートバイに乗り続けられる環境を、ライダー自らが生み出すのを促し、その意識と行動を備えた人を全国各地で増やす 】という内容です。
つまり、単にライディング技術の上達に熱心な “お客様” や “生徒” を求めているのではなく、総合的な世界観と行動力を伴った大人を求めていると言えるでしょう。
オートバイを末永く楽しむための知識や技術、社会での課題などを共有し合い、積極的にそれらの共有を広める可能性のある大人、つまり “ 仲間 ” や “ 同志 ” を求めているのです。
その目的の為に、“お客様扱い” はしませんし、その趣旨に関心や理解が進められる人だけに参加を呼び掛けているのです。

追加説明:『 特別な GRAイベント 』
これらを実現させる為に、先ずGRAでは、開催イベントに次の 4つの特徴を設けています。
1. 少人数制での開催 ・・ より適確な対応と育成のため
2. 自在なカリキュラム対応 ・・ 参加者の要望・意見に合わせて、多様で高度なカリキュラムでの対応
3. 参加しやすい環境作り ・・ 低額の参加費と当日受付制の採用など
4. 見学&聴講フリー制採用
GRAでは、お客様扱いをせずイベントの開催目的の理解を求めますが、一般的な講習イベントでは決して得られない、多くの知識やカリキュラムの提供の用意があります。
〇 オートバイの基本的な構造とその特性から導き出される最適なライディングの講習
〇 求めるライディング技術とレベルに応じた走行練習コースの設定
〇 構成する部品の役割と適切な整備方法の講習
〇 そしてライダー毎にオートバイを調律するセッティング理論と実技講習
ただし、これらの事柄は参加者の積極的な要望があってから個々にその場で応じるもので、何度も言いますが、開催趣旨を理解しようとしない “お客様” や、受け身参加の “生徒” な人には適したイベントとは言えませんし、そういう方々の参加は私達は望んでおりません。