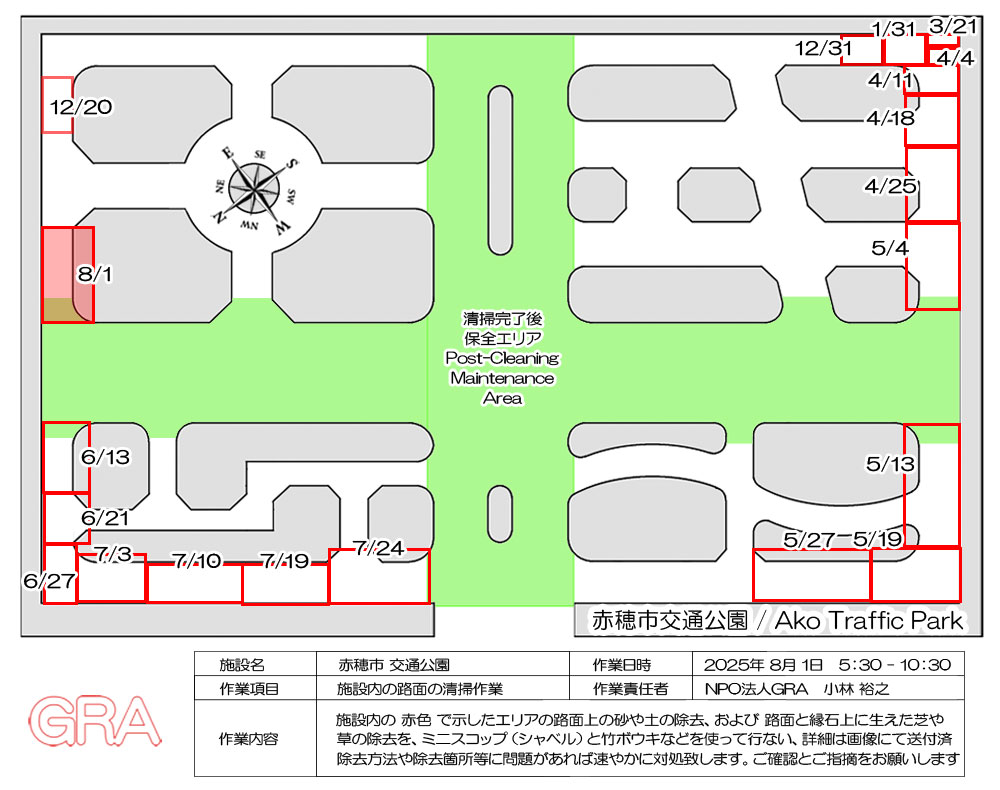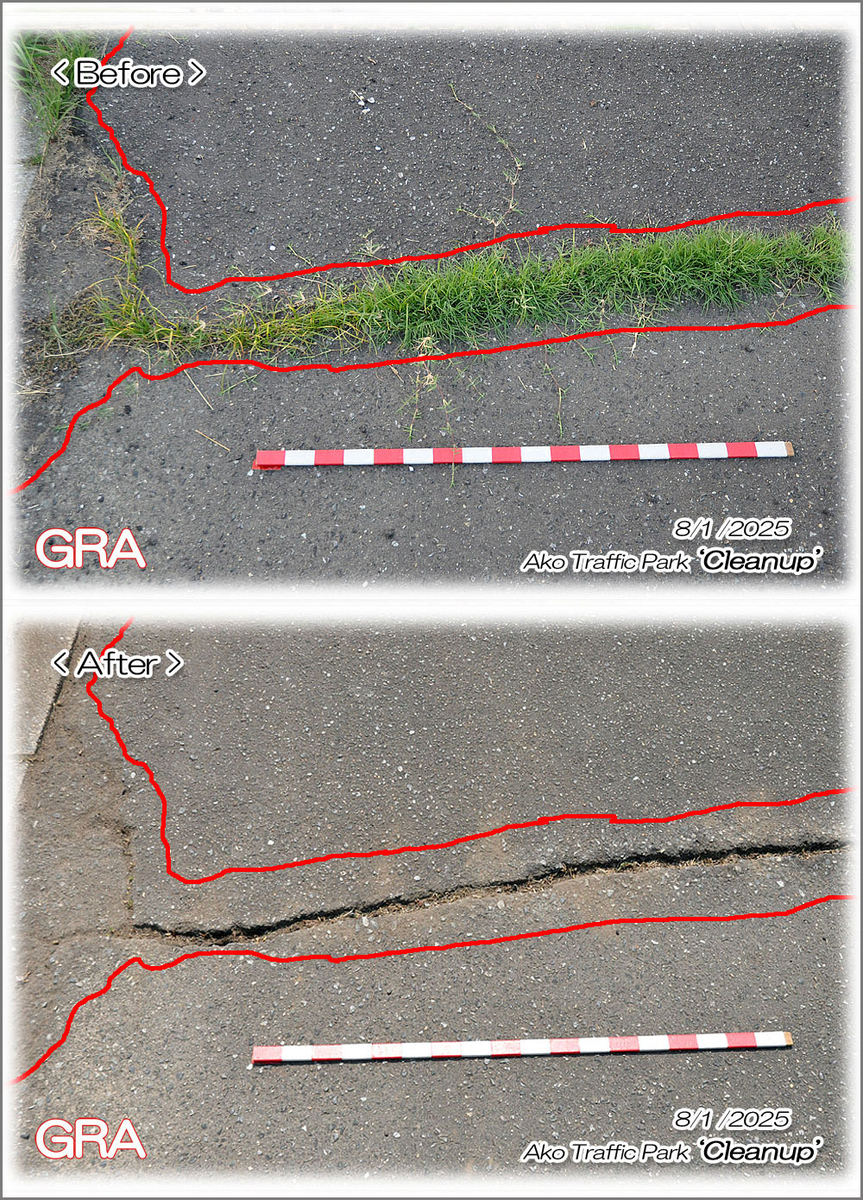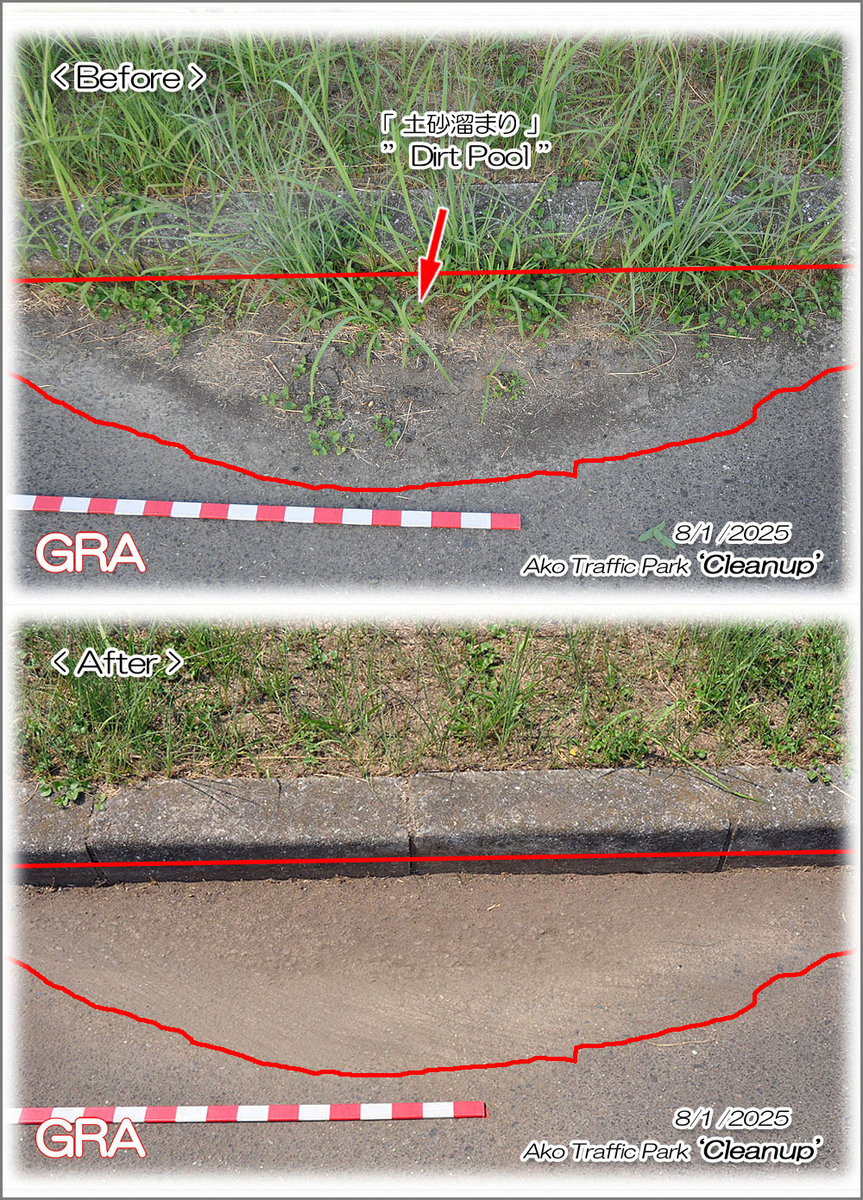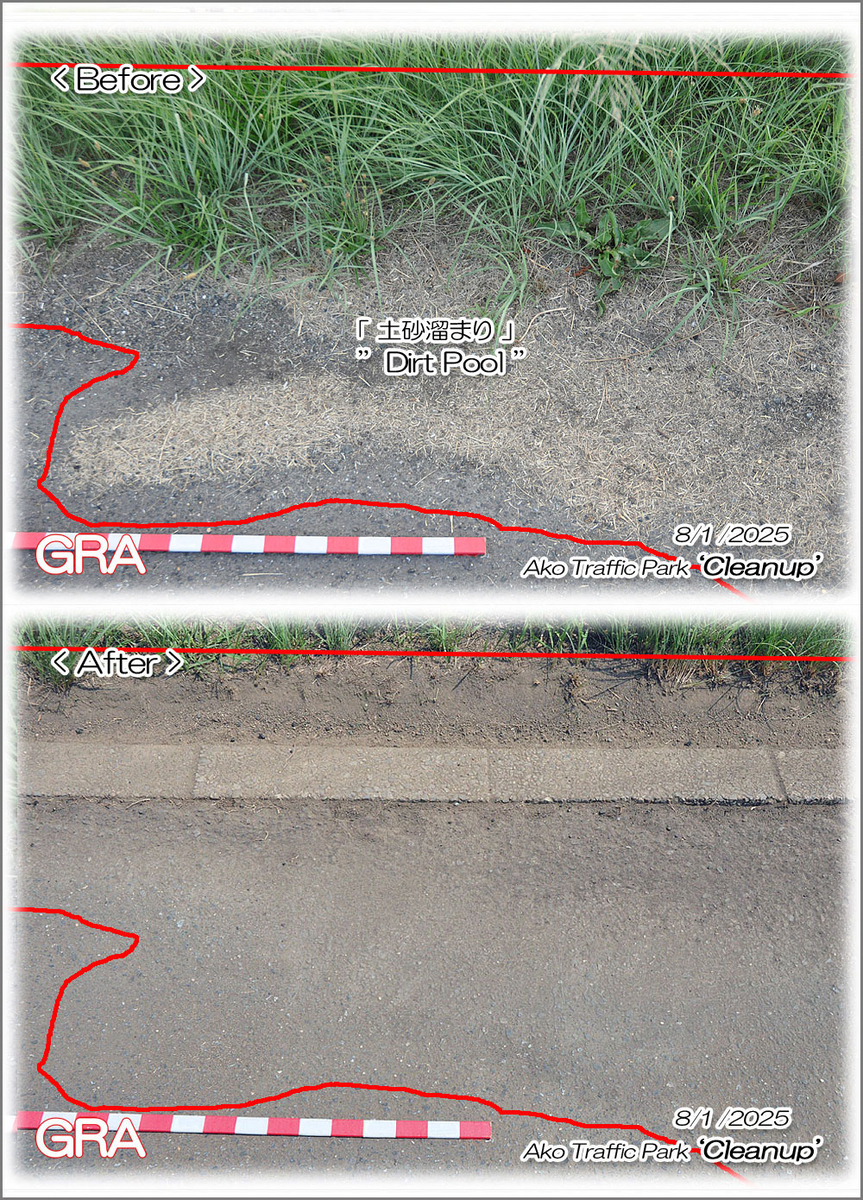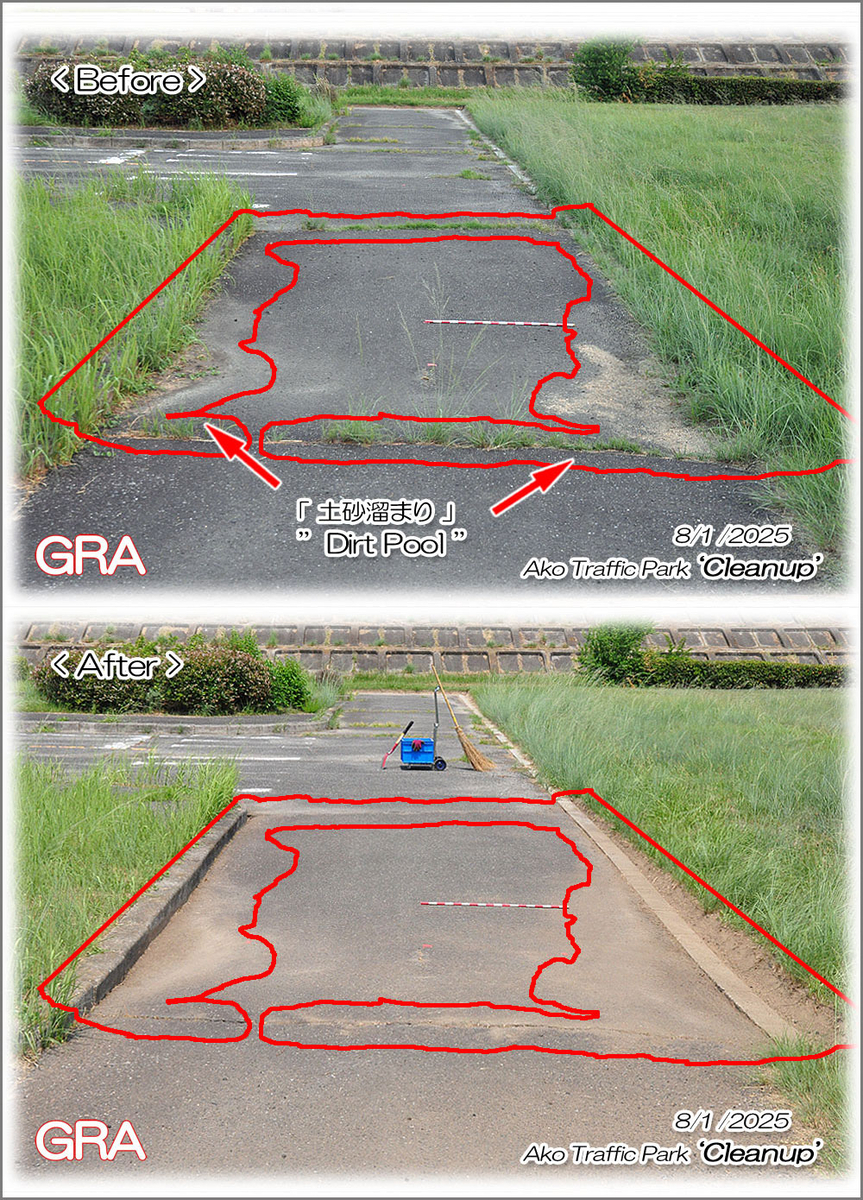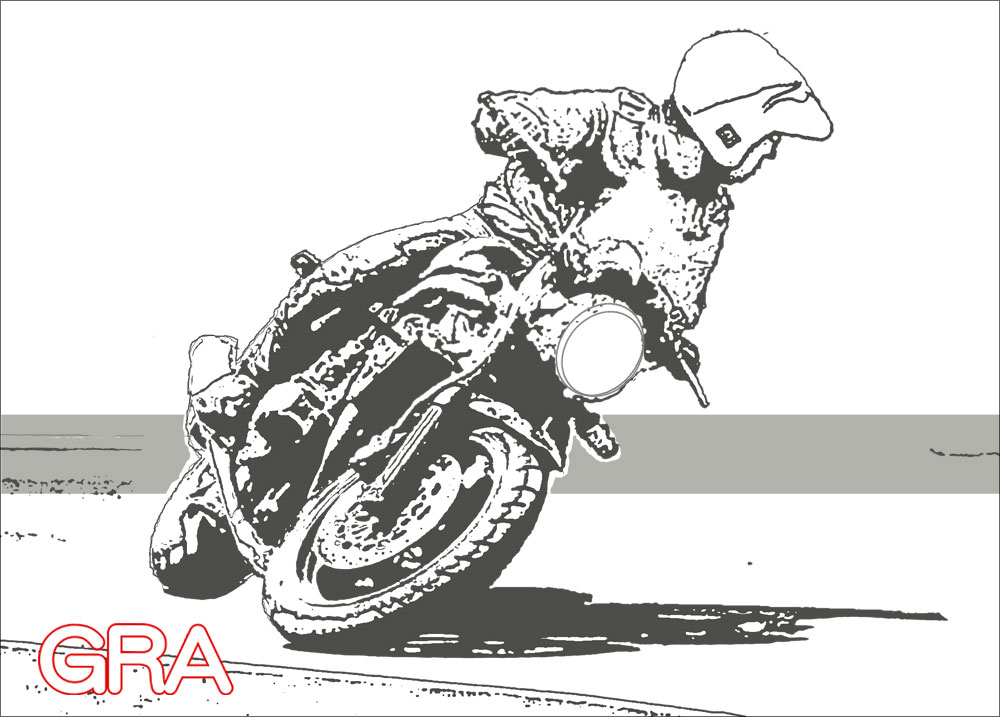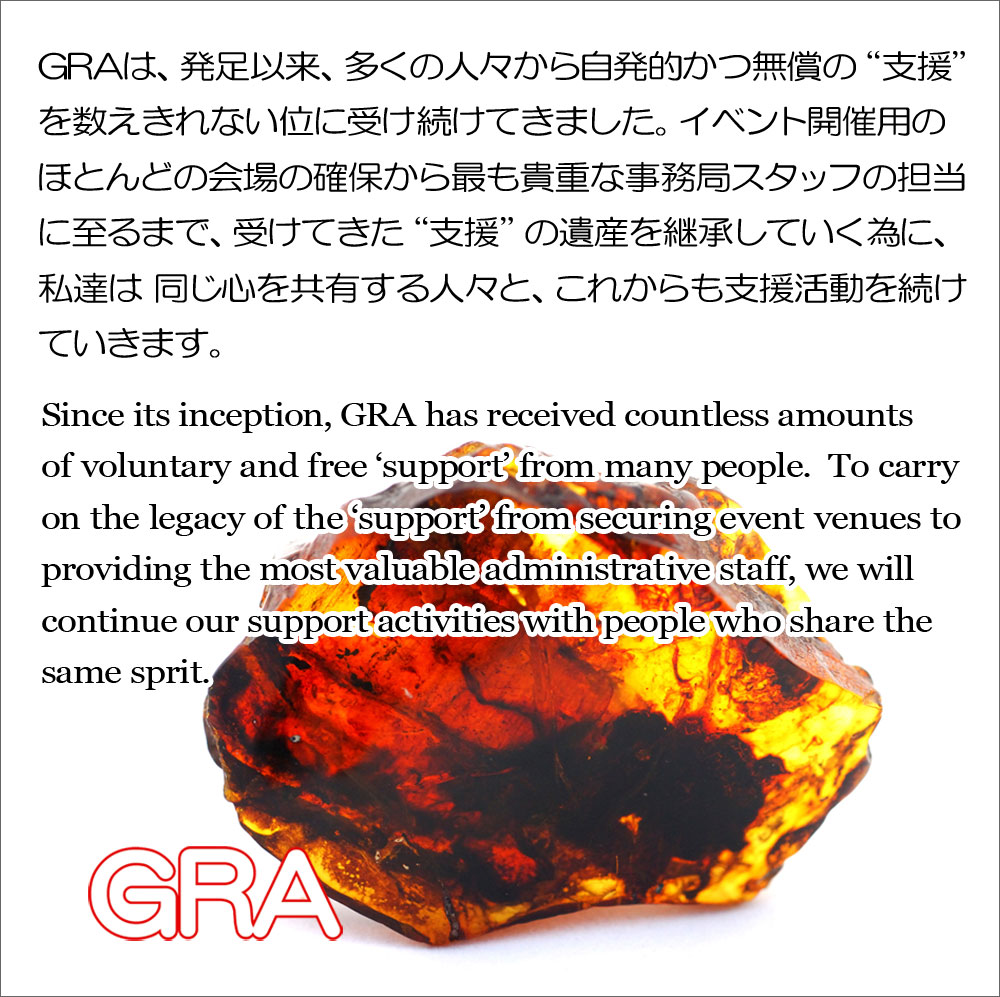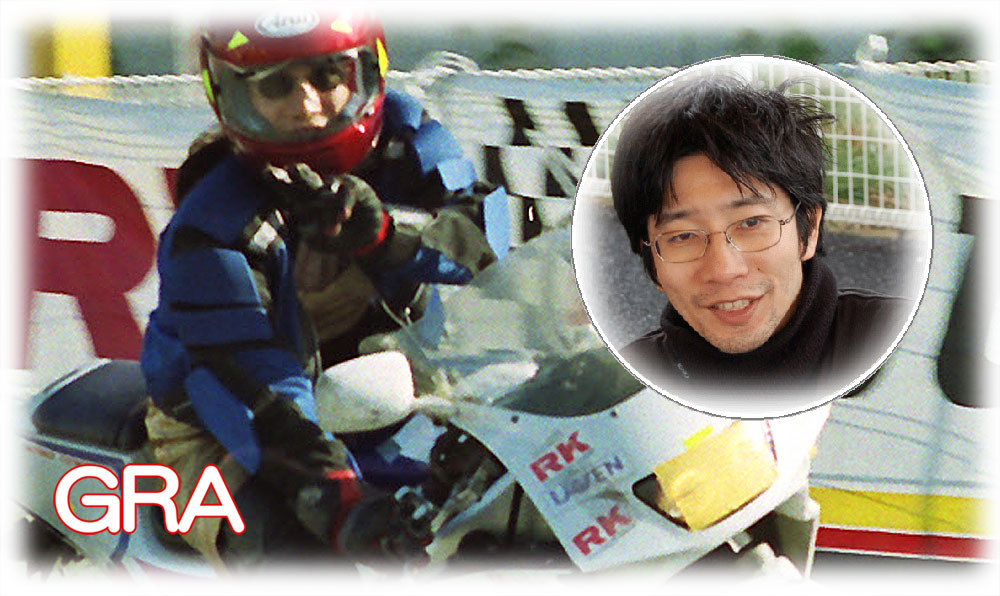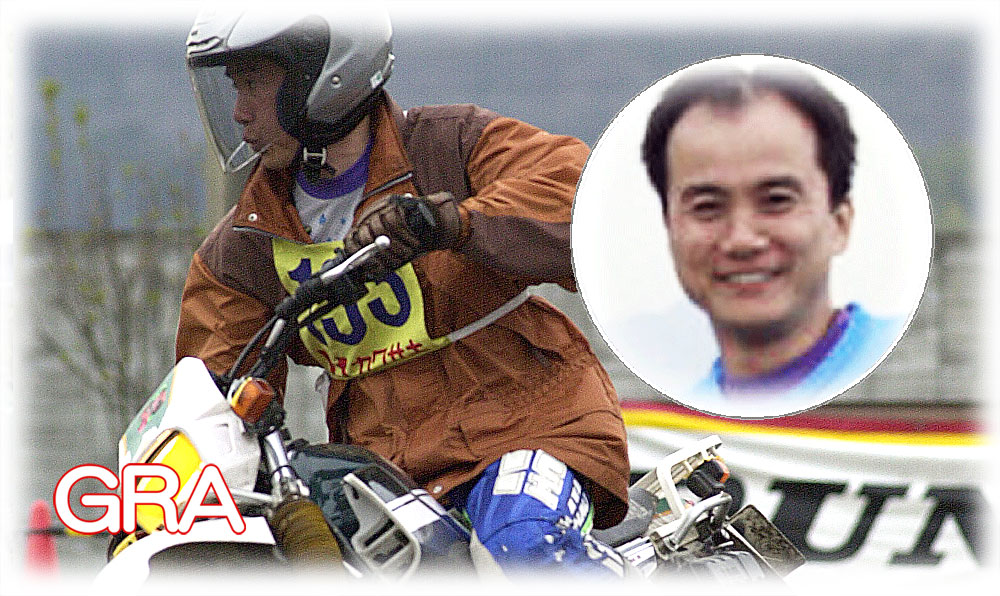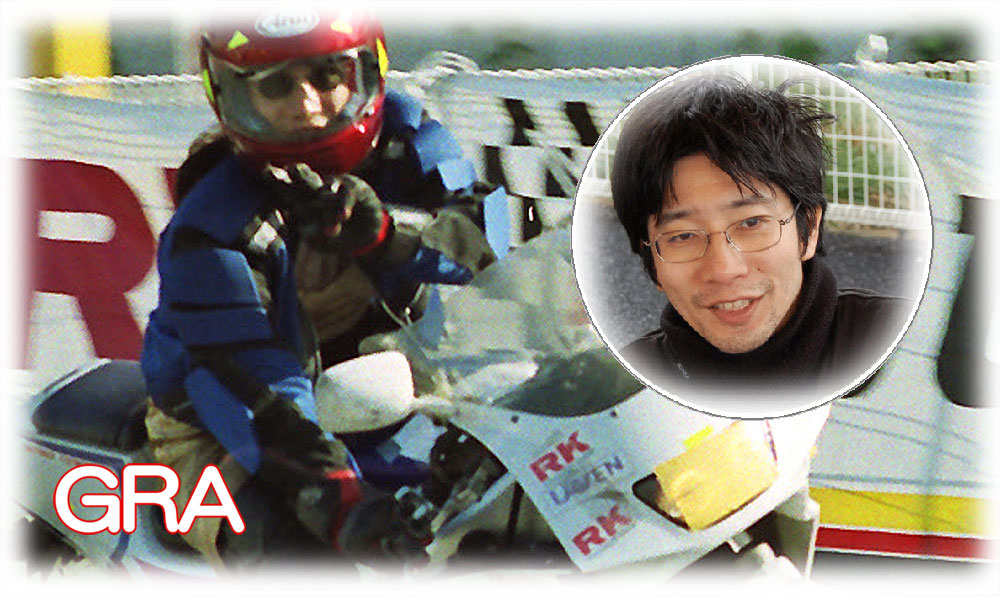「活動を続けるのに必要な事は?」と尋ねられたら、「お金」とか「参加者人数」、「充実した機材」と答える人も少なくないでしょう。しかし、僕は、「人」だと答えます。それも、殆どの場合、目立たない所にいる人です。
If you were to ask, "What do you need to continue your activities?", many people would probably answer "money," "number of participants," or "good equipment." However, I would answer "people."
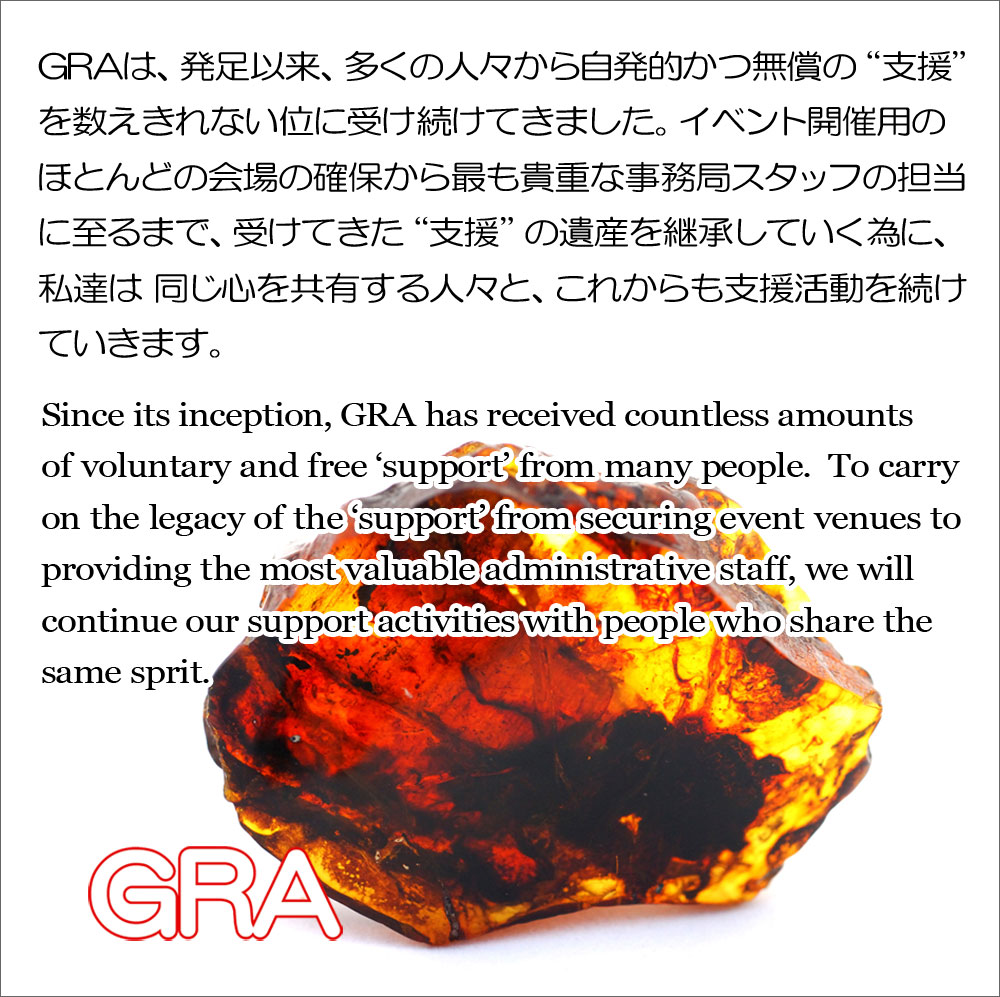
『 経理 / Accounting 』
設立した1991年から「お金」の事は殆ど関心はありませんでした。営利を目的している訳でもなく、収入を転用する事もなく、ただ、銀行の専用口座に預け続けるだけの様な状態が続いていました。しかし、1995年以降、イベント開催数が増えて、年間 30回を超える様になり、きちんとした管理が必要になり、そんな時に「経理しましょうか」と言ってくれたのが 大阪の Sさんと Hさんでした。Sさんは 1998年から2年間、Hさんが 2000年間からの 2年間を担当してくれて、お蔭様で、年間 40回以上のイベントを無事に開催し続ける事が出来ました。ありがとうございました。
Since the company's founding in 1991, I've had little interest in money. We weren't profit-making organizations, nor did we divert our income. We simply deposited our money in a dedicated bank account. However, since 1995, the number of events we held increased, and proper management became necessary. That's when Ms. S and Ms. H from Osaka offered to handle the accounting. Ms. S handled the accounting for two years from 1998, and Ms. H handled the accounting for two years from 2000. Thanks to their help, we've been able to successfully hold over 40 events a year.


そして、2002年から 10年以上に亘って担当して、GRAの形態に合った経理システムを構築してくれたのが、現在はパラグアイに住む Oさんです。彼は、開催するイベント毎に現金の出納が分かり易く、入力作業も楽になる様に、Excelでイベント別、項目別の 経理用ワークシートを構築してくれたのです。ありがとうございました。イベント別にまとめられた詳細なシステムのお蔭で、安心して運営が出来ましたし、次に経理を担当してくれた方にもスムーズに引き継ぐ事が出来ました。
And then, from 2002, Mr. O, who now lives in Paraguay, took over the accounting for over 10 years, building an accounting system tailored to GRA's structure. He created an accounting worksheet in Excel for each event, with each event and item categorized, to make it easier to understand the cash receipts and payments for each event and to input data. This detailed system organized by event allowed us to operate with peace of mind, and it remains an important system for us today.

2016年、そんな経理を引き継いでくれたのが 大阪の O君です。彼は、この経理だけでなく、文才と情熱にも溢れる人で、多方面でGRAの活動を支え続けてくれている方です。お世話になっています。
In 2016, Mr. O from Osaka took over the accounting duties. Not only is he skilled in accounting, but he is also a talented and passionate person who continues to support GRA's activities in many ways.
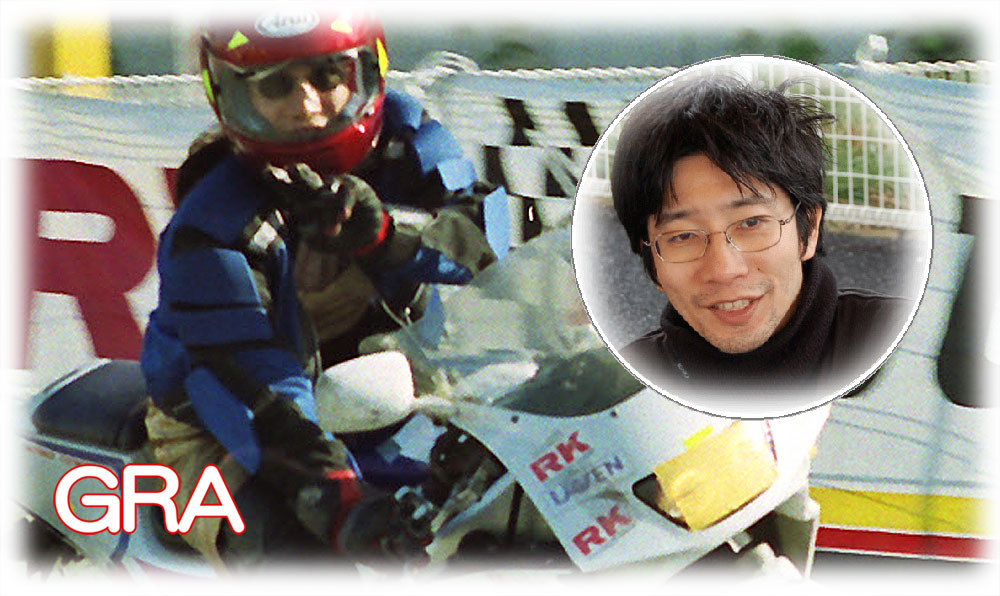
『 Webサイト / Web Site 』
インターネットが徐々に普及し始めていた 1998年、「Webサイトを作りませんか」と言ってくれたのが 兵庫の U君でした。当時は、Webサイトの黎明期で、決して一般的ではなかったのですが、彼はGRA専用のWebサイトを一人で構築してくれたのです。お蔭様で、その後の インターネットの浸透と発展に伴って、Webサイトによる告知活動を広げる基礎になりました。ありがとうございました。
In 1998, when the Internet was gradually becoming popular, Mr. U from Hyogo asked me, "Why don't you make a website?" At the time, websites were still in their infancy, but he built a website for GRA all by himself. Thanks to him, we were able to lay the foundation for expanding our website-based advertising activities.

そんな 生まれたての Webサイトを、イベント告知からイベント開催後の各種リリースページまで備えた立派なサイトへと組み上げてくれたのが 大阪の Kさんでした。彼女は、サイト制作用のソフトを使わず、より緻密なページレイアウトから配色までをアレンジ可能な、俗にに言うタグ打ち呼ばれる、HTML言語による直接入力で、数多くのページを作成してくれた偉大な功労者です。ありがとうございました。彼女のお蔭で、イベント告知から開催リポート、感想文、そして コース図やリザルトまでを備えた 立派な Webサイトになったのです。
It was Ms. K from Osaka who helped us turn this fledgling website into a fully functional site, complete with event announcements and various post-event release pages. She was a great contributor, creating numerous pages directly in HTML, without using website creation software, allowing for more precise page layout and color scheme adjustments. Thanks to her work, we were able to create a fully functional website, complete with event schedules, event reports, course maps, and results.

その Webサイトを、更に詳細な情報発信が可能になった、現在の様式まで再構築してくれたのが 大阪の T君です。2010年から、彼が Webサイト構築に取り組んでくれたお蔭で、現在の 3000ページを超える Webサイトが出来上がりました。本格的に Webサイトを作成した事がある人なら理解できるでしょうが、GRA の多様な内容と圧倒的なページ数の Webサイトへと再構築してくれた彼の労力と功績の大きさは計り知れません。 ありがとうございます。単純に計算しても、再構築に要した時間は 数百時間以上にはなる筈です。本当にお世話様です。
It was Mr. T from Osaka who rebuilt the website into its current format, which allows for even more detailed information to be disseminated. Thanks to his efforts since 2010 to build the website, we have now reached the current size of over 3,000 pages. His contribution to making it possible to provide GRA with diverse content and detailed information is immeasurable. The time he has spent must have amounted to several hundred hours. We are truly grateful for his help.
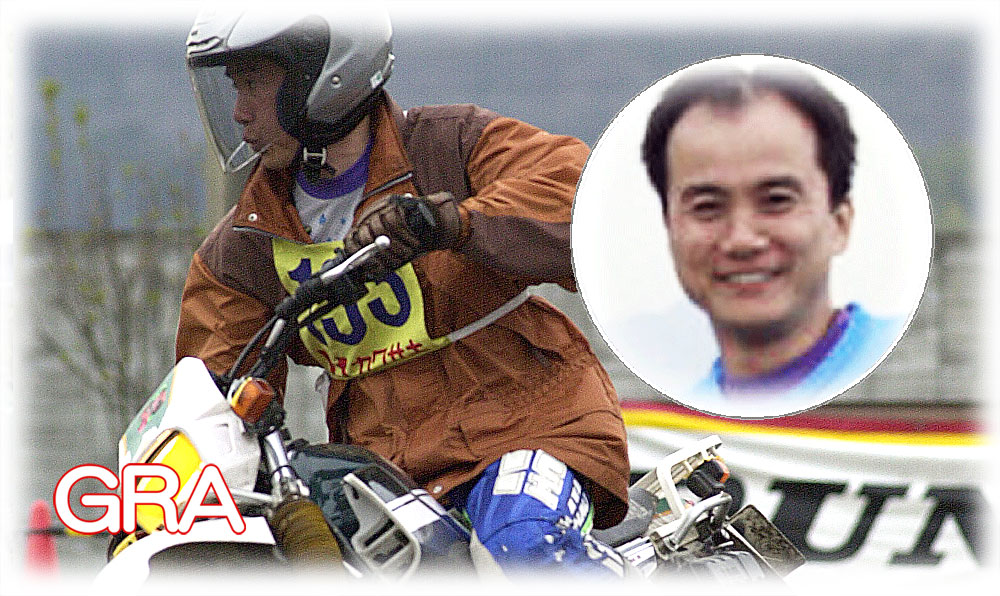
『 NPO法人 / NPO 』
2004年、将来の活動の形態を模索した時期、「NPO法人にしませんか?」と提案してくれたのが 神奈川の M君でした。 その頃、1991年以来掲げていた活動目標である、ライダーの意識向上と社会的認知度の向上を果たすには、社会的な責任の薄い任意団体ではなく、社会的な信頼も得られる法人組織にする事を検討していた頃でしたから、正に救いの一言でした。M君は、遠隔地に住んでいる事もあって、イベントへの参加は 僅か3回と少なかったのですが、きっと、彼なりに何かをしたいと考えてくれていたのでしょう。そして、彼の提案に同意したわずか数か月後、彼から届いた封筒には、NPO法人化に必要な申請書類と申請手続き案内の一式の書類が入っていて、定款の条項などに問題さえ無ければ、あとは押印して提出できる状態でした。ありがとうございました。お蔭様で、無事に今も NPO法人として社会貢献活動を続けられています。
In 2004, Mr. M from Kanagawa suggested we become an NPO. At the time, we were considering changing from a voluntary association with little social responsibility to a corporate organization with a strong social credibility in order to achieve our goals of raising rider awareness and social recognition. His words were a lifesaver. Mr. M only attended three events, but I believe he wanted to support us in his own way. Just a few months after I agreed to his proposal, I received an envelope from him containing the necessary application documents and a set of application procedure guides for becoming an NPO. As long as there were no problems with the information provided, all that was left to do was stamp the documents and submit them. Thanks to him, we are still able to continue our social contribution activities as an NPO.

そんな M君が作ってくれた書類を確認して、僕が経験が無かった法務処理を自ら進めてくれたのが 大阪の K君です。 彼は、GRA開催イベントへの参加回数は少なく、僕にとっては目立たない人だったのですが、何故か、NPO法人化の動きを察知して、自ら経験のある法務処理を申し出てくれて、それ以来、NPOとしての重要な管理を担当してくれています。ありがとうございます。どうぞ、これからも宜しくお願いします。
Mr. K from Osaka was the one who checked the documents prepared by Mr. M and took it upon himself to handle the legal matters, which I had no experience in. He rarely attended GRA events and was not very noticeable to me, but when he noticed the move to incorporate as an NPO, he offered to handle the legal matters, which he used his experience in, and has since been in charge of important management tasks for the NPO.

『 事務局スタッフ / Office Staff 』
「事務局スタッフ」とは、他の多くの 支援者の方とは異なる特別な人達です。他の 業務で支援して下さった方は、自由な裁量で、空き時間に支援して下さったのですが、「事務局スタッフ」は 膨大な事務局活動を担う為に、毎週、活動拠点に来て、数時間、無報酬で活動を支援してくれた方々です。その中でも特別な存在が 大阪の Tさんと O君です。
The "Office Staff" are special people who are different from many other supporters. While other supporters provide support at their own discretion and in their free time, the "Office Staff" come to a designated activity base every week to handle various administrative tasks and work several hours without pay. Among them, Ms. T and Mr. O from Osaka are particularly special.
Tさんは、イベント開催数が増えて、事務処理量が一気に増えた 1998年から、「事務ミーティング」と称して、週に一回以上開催していた事務処理の為の集まりに参加してくれる様になりました。1日あたり 3時間以上、毎週殆ど欠かさずに、約17年間に亘って担当して下さいました。彼女が事務処理に費やしてくれた時間は 軽く 2000時間以上にもなり、他の方々の支援を時間を遥かに超えています。その上、それ以上の貢献は、GRAの目標や理念を信じ続けて、長年に亘って一緒に行動してくれた事です。その彼女の貢献があったからこそ、GRAは活動を継続する事ができましたし、現在の活動に繋がっています。もし、彼女の貢献が無かったら、現在のGRAは存在しなかったのは間違いなく、最も深く感謝をすべき大切な人です。本当にありがとうございました。
In 1998, when the number of events increased and the amount of administrative work grew, Ms. T began attending "administrative meetings," which we held once or twice a week to handle administrative tasks. She spent more than three hours a day, almost every week, for approximately 17 years. She has devoted well over 2,000 hours to administrative tasks. What's even more important is her continued belief in GRA's goals and ideals and her commitment to working with us for so long. It's thanks to her contributions that GRA has been able to continue its activities. Without her contributions, GRA would undoubtedly not exist today, and she is an important person for whom we owe our deepest gratitude. Thank you very much.

O君も、Tさんと同じく1998年から、週1日以上、毎週欠かさず活動拠点に来てくれて、事務処理を行なう支援を 10年以上してくれました。彼も、GRAの掲げている目標を深く理解してくれて、積極的に参加してくれた方で、他にも 広報や経理などの業務も担当してくれるなど、GRAの活動には欠かせない大切な人です。
Since 1998, Mr. O has come to our base at least once a week without fail, helping with administrative tasks, for over 10 years. He also deeply understands and supports GRA's goals, and is an important person who is indispensable to GRA's activities, taking care of public relations, accounting, and other tasks.
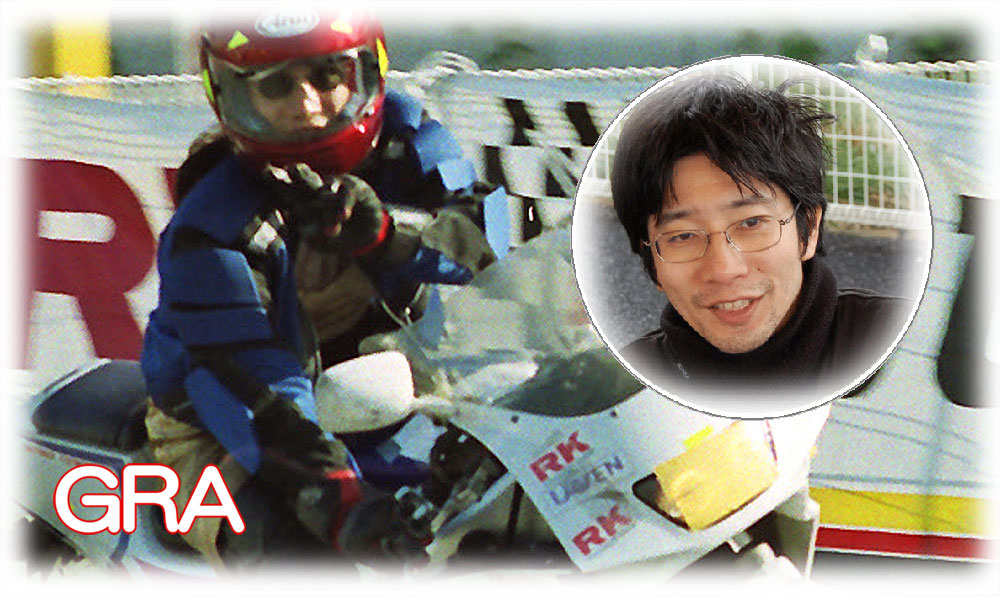
以上で紹介した、TさんとO君の他にも、「事務ミーティング」に参加して、雑多で膨大な処理を行なってくれた方々もいた事も忘れてはいません。時には、終電時刻まで一緒に処理をしてくれた事も少なくありませんでした。改めてお礼を申し上げます。
In addition to Ms. T and Mr. O, introduced above, I will not forget the other people who participated in "administrative meetings" and handled a huge variety of tasks. I would like to express my gratitude once again.

『 最後に / Closing Thoughts 』
僕にとって、活動で最も大切にすべき事は、設立当初の活動目標や理念を貫く事だと考えています。その為、例え、華やかなイベント開催が無くなり、一見、活動形態が大きく変わったと見えたとしても、活動の目的や理念は変更していません。時代に合わせて、活動の形態を変更しているに過ぎないのですが、そんな時でも、同じ目的を見て、長年に亘って一緒に歩み続けてくれた人々こそ 最も貴重な存在であり、GRAが長年に亘り活動を続けられた事の最大の要因です。
過去に「脱皮計画」と称して、何度か活動の形態を変更してきました。時には、イベント開催数を絞ったり、数年に亘って休止した結果、華やかな走行系イベントに憧れて参加をしていた数多くの人々は GRAに失望して関心を失いました。実際、2001年1月、『第一回脱皮計画』の説明会を大阪市内で開催した際、その説明会の冒頭で、「なぜ、事務局は、勝手にイベント開催をやめたのだ!」と、怒りも交えて大きな声を発した人が居ました。彼は、参加したイベント当日だけ担当スタッフ職をこなしていた方ですが、事前に計画の概要主旨は郵送されていたにも関わらず、イベント当日以外の事務局の負担量を尋ねず、「事務局スタッフ」の存在を一切想像せず、その上、「事務局スタッフ」として大きな貢献をしてくれていた Tさんと O君の目の前で、大声で事務局の活動を非難したのです。
事務局の活動に感謝も敬意も示さない、大変に無礼な発言でしたが、その時は、予想していなかった発言だった事もあり、彼に対する指摘や反論はしませんでした。しかし、後になって考えれば、彼の行為によって、『脱皮計画』は行なって当然だったと確信しました。GRAが掲げていた活動目標を軽視しただけでなく、活動を続ける為に多大な支援をしている人達を無視して、イベントに参加して自身が楽しむ事を優先している人の存在があったからこそ『脱皮計画』が必要になったのです。だから、『脱皮計画』を重ねる度に、走行系イベントへの参加者数は減っていきました。しかし、華やかなイベント開催の有無に関わらず、活動理念に共感して、現在も支え続けてくれている人達には恵まれ続けています。そして、変わらぬ理念を突き通す活動を続ける限り、その様な方々は世界中に増えていくと僕は信じています。
以上の通り、GRAは、数多くの支援に恵まれて活動を続けてきました。だからこそ、活動理念に沿って、ライダー意識の向上と社会貢献の為の支援活動を続けていきます。
NPO法人GRA 代表 小林 裕之
For me, the most important thing in our activities is to adhere to the goals and principles we had when we were founded. For that reason, even if there were times when we stopped holding flashy events and our activities seemed to have changed significantly, the people who shared our goals and continued to walk alongside us over the years are our most valuable assets, and they are the biggest reason why GRA has been able to continue its activities for so many years.
In the past, we have changed the format of our activities several times, under the guise of a "de-pick" plan. At times, we stopped holding events for several years, and as a result, many people who had participated in GRA because they admired the flashy running events lost interest in it. In fact, at the beginning of an information session on the "de-pick" plan held in January 2001, someone raised their voice in anger, asking, "Why did the secretariat just stop holding events on their own?" Despite having received a detailed outline of the plan in the mail in advance, he failed to inquire about the administrative workload beyond the event itself. Furthermore, he loudly criticized the administrative office's activities in front of Ms. T and Mr. O, who had made significant contributions as "administrative staff."
At the time, I didn't point out or argue with him because his comments were unexpected, but later I became convinced that his actions made the "Evolving Plan" a necessity. The "Evolving Plan" was necessary precisely because there were people who not only disregarded GRA's stated goals, but also prioritized their own enjoyment by attending events, ignoring the people who provided so much support to continue the organization. Therefore, with each "Evolving Plan," the number of participants in running events decreased. However, we continue to be blessed with people who sympathize with our philosophy and continue to support us to this day. And I believe that as long as we continue our activities with the same philosophy, there will be more people like that around the world.
Hiroyuki Kobayashi, Representative of NPO GRA