去年の12月の始めに友人が車を出してくれ、
郊外へのドライブとして、清の西陵に出かけてきました。
場所は、北京から西南に120㎞ほど行った河北省の易県。

写真: 近郊の村には、そこかしこに八旗の旗が翻っています。
一気にテンション、マックス!(笑)
清代の歴代皇帝の陵墓は、
北京入りする以前の皇帝のものは、東北地方に、
それ以後は、北京の近郊に東西に一ヶ所ずつに分けて埋葬されています。
近郊と言っても、明の歴代皇帝の陵墓である「明の十三陵」が、北京から50㎞しか離れていないのに比べ、
清の東陵も西陵も、ともに100㎞以上離れており、
さすが騎馬民族の皇帝は、距離感覚が違いすぎるわー、と感心します。
史実によると、清の東陵は順治帝が狩りをしている時に気に入った場所、
そしてこの清の西陵は、雍正帝が十三弟の充(ふたをとる)祥に風水師をつけて探させたところという。
場所を探しに行くにしても
行くスケールが広すぎ、っというやつです(笑)。
さて。
この清の西陵に埋葬されている皇帝たちをざっと見て行きましょう。
ついでに東陵の方も。

写真: 雍正帝の陵墓・泰陵。
清の西陵
泰陵 雍正帝
昌陵 嘉慶帝
慕陵 道光帝
崇陵 光緒帝
おまけ: ラストエンペラー溥儀の墓もあり。
清の東陵
孝陵 順治帝
建陵 康熙帝
裕陵 乾隆帝
定陵 咸豊帝
惠陵 同治帝
おまけ・・・でもないけど、目玉の一つ、西太后の菩陀峪定東陵
こうして見てくると、西陵は東陵と違って、「華がない」、「スターがいない」のである。
派手で目立つイベントをしまくったイケイケドンドンの康熙帝や乾隆帝、それに西太后は皆、東。
クレイジーでやぶれかぶれな人生、人格だった分だけ、ドラマチックなエピソード満載のトンデもない皇帝たち、
--順治帝、咸豊帝、同治帝も皆、東。
--それに対して、西の皇帝は、
雍正帝は他人に厳しく、自分にはもっと厳しく、
修行僧のように昼夜を問わず働き続け、あっという間に過労死してしまったり、
嘉慶帝や道光帝は、60年以上にわたって、贅沢の限りを尽くした乾隆帝の尻拭いとでも言おうか、
倹約財政であまり派手なこともようせず、慎ましく、おとなしく、
ご先祖さまの遺産をなるべく食いつぶさぬことだけを心掛けて[事なかれ主義」を貫いたような地味地味な皇帝。
光緒帝は、西太后に脊髄の神経まで抜き取られてたんとちゃうんか、というくらい
生涯、かごの中の鳥のように過ごして、影がうすうすの皇帝。
---そんな西と東の大きな差のために、
どうやら観光客は、圧倒的に東陵に行きたがるらしい。
それに比べて、西陵は比較的、観光客も多くなく、
特に私たちが訪れたのは、極寒の12月だったため、
ますますひゅうひゅうと北風ばかりが頬を殴りつけるような、
情緒あふれる環境でした。
そんな比較的「手垢の跡が薄い」、
世の無常をよろしく感じることのできる西陵は、
独特の雰囲気がありました。
清の西陵を最初に開いたのは、雍正帝である。
順治帝が東陵に愛新覚羅家の陵墓を決めてから、
清朝の末代まで、東陵に歴代の皇帝が埋葬されるはずだった。
伝統的な中国王朝の決まりに則れば、そうなる。
だから「明の十三陵」は、一ヶ所に皆、固まっている。
(永楽帝以後)

写真: 雍正帝の泰陵へ続く遊歩道。
遥か昔の古い中国の書≪周礼≫に則り、「昭穆之制」に従うはずだった。
つまりは始祖の廟墓を中央にして、親子代々、「昭」の字と「穆」の字を継承し、
「昭」は左に、「穆」は右に、と順番に陵墓を配置していく、というものである。
雍正帝も当初は、祖父・順治帝と父・康熙帝の陵墓のある東陵の近くで候補地を探していた。
その結果、雍正7年、二人の眠る孝陵と景陵からも遠くない九鳳朝陽山に「よき地」を選び出した。
しかしその後、大臣らが
「九鳳朝陽山は、風水の条件に不備がある上、土壌に砂が多く、陵墓に適していない」
と言い出し、新たな候補地探しが始まった、とされる。
ぽちっと、押していただけると、
励みになります!

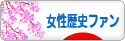
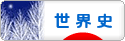
郊外へのドライブとして、清の西陵に出かけてきました。
場所は、北京から西南に120㎞ほど行った河北省の易県。

写真: 近郊の村には、そこかしこに八旗の旗が翻っています。
一気にテンション、マックス!(笑)
清代の歴代皇帝の陵墓は、
北京入りする以前の皇帝のものは、東北地方に、
それ以後は、北京の近郊に東西に一ヶ所ずつに分けて埋葬されています。
近郊と言っても、明の歴代皇帝の陵墓である「明の十三陵」が、北京から50㎞しか離れていないのに比べ、
清の東陵も西陵も、ともに100㎞以上離れており、
さすが騎馬民族の皇帝は、距離感覚が違いすぎるわー、と感心します。
史実によると、清の東陵は順治帝が狩りをしている時に気に入った場所、
そしてこの清の西陵は、雍正帝が十三弟の充(ふたをとる)祥に風水師をつけて探させたところという。
場所を探しに行くにしても
行くスケールが広すぎ、っというやつです(笑)。
さて。
この清の西陵に埋葬されている皇帝たちをざっと見て行きましょう。
ついでに東陵の方も。

写真: 雍正帝の陵墓・泰陵。
清の西陵
泰陵 雍正帝
昌陵 嘉慶帝
慕陵 道光帝
崇陵 光緒帝
おまけ: ラストエンペラー溥儀の墓もあり。
清の東陵
孝陵 順治帝
建陵 康熙帝
裕陵 乾隆帝
定陵 咸豊帝
惠陵 同治帝
おまけ・・・でもないけど、目玉の一つ、西太后の菩陀峪定東陵
こうして見てくると、西陵は東陵と違って、「華がない」、「スターがいない」のである。
派手で目立つイベントをしまくったイケイケドンドンの康熙帝や乾隆帝、それに西太后は皆、東。
クレイジーでやぶれかぶれな人生、人格だった分だけ、ドラマチックなエピソード満載のトンデもない皇帝たち、
--順治帝、咸豊帝、同治帝も皆、東。
--それに対して、西の皇帝は、
雍正帝は他人に厳しく、自分にはもっと厳しく、
修行僧のように昼夜を問わず働き続け、あっという間に過労死してしまったり、
嘉慶帝や道光帝は、60年以上にわたって、贅沢の限りを尽くした乾隆帝の尻拭いとでも言おうか、
倹約財政であまり派手なこともようせず、慎ましく、おとなしく、
ご先祖さまの遺産をなるべく食いつぶさぬことだけを心掛けて[事なかれ主義」を貫いたような地味地味な皇帝。
光緒帝は、西太后に脊髄の神経まで抜き取られてたんとちゃうんか、というくらい
生涯、かごの中の鳥のように過ごして、影がうすうすの皇帝。
---そんな西と東の大きな差のために、
どうやら観光客は、圧倒的に東陵に行きたがるらしい。
それに比べて、西陵は比較的、観光客も多くなく、
特に私たちが訪れたのは、極寒の12月だったため、
ますますひゅうひゅうと北風ばかりが頬を殴りつけるような、
情緒あふれる環境でした。
そんな比較的「手垢の跡が薄い」、
世の無常をよろしく感じることのできる西陵は、
独特の雰囲気がありました。
清の西陵を最初に開いたのは、雍正帝である。
順治帝が東陵に愛新覚羅家の陵墓を決めてから、
清朝の末代まで、東陵に歴代の皇帝が埋葬されるはずだった。
伝統的な中国王朝の決まりに則れば、そうなる。
だから「明の十三陵」は、一ヶ所に皆、固まっている。
(永楽帝以後)

写真: 雍正帝の泰陵へ続く遊歩道。
遥か昔の古い中国の書≪周礼≫に則り、「昭穆之制」に従うはずだった。
つまりは始祖の廟墓を中央にして、親子代々、「昭」の字と「穆」の字を継承し、
「昭」は左に、「穆」は右に、と順番に陵墓を配置していく、というものである。
雍正帝も当初は、祖父・順治帝と父・康熙帝の陵墓のある東陵の近くで候補地を探していた。
その結果、雍正7年、二人の眠る孝陵と景陵からも遠くない九鳳朝陽山に「よき地」を選び出した。
しかしその後、大臣らが
「九鳳朝陽山は、風水の条件に不備がある上、土壌に砂が多く、陵墓に適していない」
と言い出し、新たな候補地探しが始まった、とされる。
ぽちっと、押していただけると、
励みになります!



















清の皇帝の陵墓ですか・・・・
日本で言えば天皇陵みたいなものか、
実際の形が見てみたいです。
騎馬民族と言えど100キロはしんどそう。
いつもありがとうです。(^_-)-☆ぽち!
陵墓の形は。。。。
後から一部写真が出てくると思うのですが、
でかいわ、周りに建造物つきだわ、で
あまり全体像がよく見えません。
基本的には、ビルの三階建てくらいの巨大な土饅頭になっていて、
その前方、南側に宮殿のような建物があり、
地下に行くと、土饅頭の下まで道がつながっていて、
棺の安置場所まで行くことができます。
上は階段を上っていくと、南側には、天安門のように
墓の前にある広場を見渡せるようなテラスになっています。
北側は、土饅頭の上の縁を囲むようにぐるりと
周遊できるような城壁の上のような構造になっています。
これは明の十三陵も同じ構造なので、
伝統的な風水の考えに則った作りなのだと思います。
blue.ap.teacup.com/applet/salsa2001/4301/trackback
blue.ap.teacup.com/applet/salsa2001/4266/trackback
blue.ap.teacup.com/applet/salsa2001/123/trackback
科学的な分析をありがとうございます。
おそらく「ちょっとそこまで」という概念自体が
定住民族とは、まったく違うのでしょうね。