
既存の配線を含めて、どれが流用できてどれが新たに入手が必要なのか?その辺の見通しを経て、本体側の段取り(収納&接続)はお陰様で無事に終えた。引き続き、セパレートパネルの取り付け関連に進みたいと思う。
まず、取り付け位置は助手席アッパーボックスの扉?蓋?の右端だ。ここはTM-D710Gのセパレートパネルを付けていた場所で、基本的には入れ替えだ。
ここでのセパレートパネル実績だが、単に超強力両面テープで貼り付けていたTM-D710Gでさえ、1度剥がれて落下した事案がある。そこで、セパレートパネルの寸法と重量を測定してみることにした。
まず、ノギスで筐体を測定。結果、幅157、高さ65、厚さ63(mm単位に切り上げ)であった。これ、正直大きいね。高さはFT-900ほど(注:記憶イメージ比)ありそうだし、厚さはFT-891Mの2倍近くある気がする。
次に、重量を家庭キッチン用の上皿ばかりで測定した結果、360gであった。セパレートパネルの重量は今まで量ったことが無かったけど、ぶっちゃけ手に持った感じは重い。これ、奥行方向の長さもあるし、いつもの超強力両面テープで貼り付けるだけでは夏場の強い陽射しで絶対に落下する!と思えてならない。
一応オプションに“MMB-103”とか言うダッシュマウントブラケットがあるけど、今回の場所では重量(落下防止)に対応する仕様ではない。また、パネル両端付近を操作した時に指の力でフラフラして、安定感がイマイチに思えるし。そこで、ホームセンターで“曲板”というt1.2×40×150の、その気になれば素手でも力を加えれば曲がってくれるものを見つけ、2枚購入。これを整形して落下を防ぐブラケットを製作することにした。
形状の根拠とするために助手席アッパーボックスの扉?蓋?の寸法を簡易的に確認し、取り付け時の上側は引っかける形状、途中は曲面に沿うように狙って多角形的な鈍角曲げなどを5~6か所、下側はセパレートパネルを受けるための面となるよう、板金加工を行った。
曲げ加工には、ちゃんとした金型を使っているわけではないので、2個のバラツキが極力小さくなるように、並べて比較しながら実施。併せて、取り付け曲面に合うよう形状をキープしながら、素手で微調整した。
実際に取り付け場所にぶら下げてみたところ、セパレートパネルの座り面が先端に向かって下向きになっていたので、現物(セパレートパネル、扉?蓋?とも)に当てて確認しながら、素手で微調整して少し上向きに。これで、この角度をチャラにするくらいの上り坂で真夏の日中に長時間駐車しない限り、落下する事案は発生しないだろう。
あとは双方の貼り付け面を脱脂後に超強力両面テープで貼り付け、流用を決めたLANケーブルを接続した状態で再ぶら下げ。LANコネクタジャックをブラケットで塞ぐわけにも行かないので、ブラケット位置は左に寄せることに。
それと、2個のブラケット形状が完全に揃っていないからだと思うけど、アッパーボックスの扉?蓋?の縁と平行になりきらず僅かに傾いているようだ。まぁ、普段は運転席からしか見ないと思うので無視したらしただけど、気になるようなら詰め物などを検討しよう。
-・・・-
最後に出来栄えの確認。液晶パネル面からの嫌らしい反射も無く、視認性は大丈夫っぽい。それと、お休み(4/28、4/29@GW前半)なこともあって、運用中の方も久々に多く発見できたので、イメージどおりの受信確認が行えた。その際に、機能や設定が必要なことが幾つか見つかったので、これからボチボチやっていきたいと思う。

























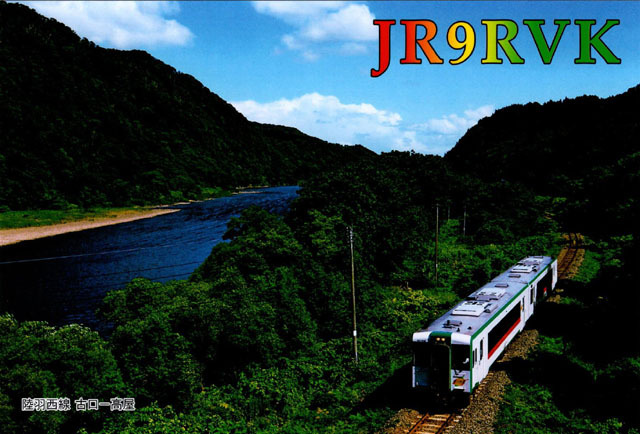
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます