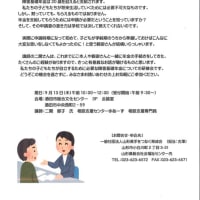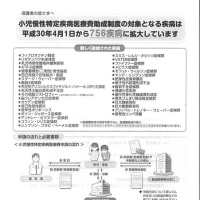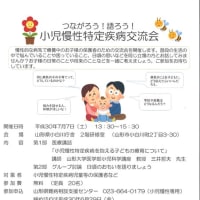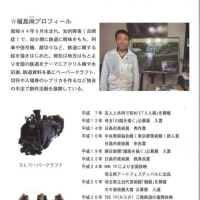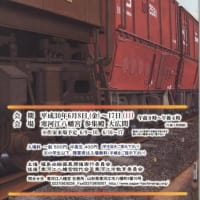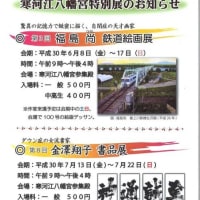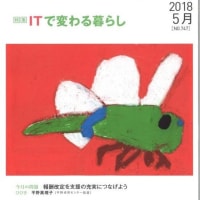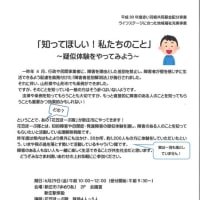知的障害者の「意思決定支援」の考え方や課題について整理した、いい論文を見つけた。
その論文は、柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)である。
その論稿を、分割してずっと紹介している。
その第24回目。
本人の意思にそった個別支援計画作成に関する留意点が、次に述べられている。
*************************************************
【引用始め】
柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)
「発達障害研究」第34巻3号掲載予定http://homepage2.nifty.com/hiroya/isiketteisien.html より
Ⅳ.意思決定支援についての課題
6.意思決定支援についての諸課題
◯ 相談支援におけるサービス利用計画、
障害福祉サービス事業所とのサービス利用契約、
個別支援計画などについて、
可能な限り本人が理解できるように、
わかりやすい表現や説明を行い、
時には映像や見学、
体験などの工夫をすること、
本人についての記録を本人が閲覧できるようにすることなど、
支援をする側に様々な努力が求められる。
◯ 個別支援計画の作成に当たっては、
本人の意思・希望にできる限り沿うように、
事業所の創意工夫が求められる。
特に就労継続支援事業B型については、
事業所に「労働指揮命令権」があるように誤解されているが、
最低賃金を保障しておらず「労働」ではないことに留意する必要がある。
◯ 相談支援の体系を、
① 相談支援専門員によるサービス利用計画作成、
② その下でのサービス管理責任者による個別支援計画の作成、
③ その下での支援職員による直接支援、
という様なピラミッド構造とする誤解がある。
知的障害者等の意思決定を支援するのならば、
どの段階においても、
本人と共に、
本人が信頼し日常的に本人をよく知っている直接支援職員や
家族・後見人等を交えた会議をもって進めることが重要である。
また個別支援計画の作成については、
直接に意思決定支援を担う支援職員が携わる仕組みとすべきである。
【引用終わり】
*****************************************************
本人にとって意義のある個別支援計画の作成が望まれる。
計画は本人中心の支援が実現するためのワンステップにしか過ぎない。
計画だけが一人歩きして、それが目的化してしまったらなんのための計画かわからない。
立派な計画をペーパーとして保管しても、それがそのとおりであるかは疑わしい。
計画に対する見直しがあってこそ、より良い支援となる。
実際の支援がどうなされているか正確な評価も重要だ。
(ケー)
その論文は、柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)である。
その論稿を、分割してずっと紹介している。
その第24回目。
本人の意思にそった個別支援計画作成に関する留意点が、次に述べられている。
*************************************************
【引用始め】
柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)
「発達障害研究」第34巻3号掲載予定http://homepage2.nifty.com/hiroya/isiketteisien.html より
Ⅳ.意思決定支援についての課題
6.意思決定支援についての諸課題
◯ 相談支援におけるサービス利用計画、
障害福祉サービス事業所とのサービス利用契約、
個別支援計画などについて、
可能な限り本人が理解できるように、
わかりやすい表現や説明を行い、
時には映像や見学、
体験などの工夫をすること、
本人についての記録を本人が閲覧できるようにすることなど、
支援をする側に様々な努力が求められる。
◯ 個別支援計画の作成に当たっては、
本人の意思・希望にできる限り沿うように、
事業所の創意工夫が求められる。
特に就労継続支援事業B型については、
事業所に「労働指揮命令権」があるように誤解されているが、
最低賃金を保障しておらず「労働」ではないことに留意する必要がある。
◯ 相談支援の体系を、
① 相談支援専門員によるサービス利用計画作成、
② その下でのサービス管理責任者による個別支援計画の作成、
③ その下での支援職員による直接支援、
という様なピラミッド構造とする誤解がある。
知的障害者等の意思決定を支援するのならば、
どの段階においても、
本人と共に、
本人が信頼し日常的に本人をよく知っている直接支援職員や
家族・後見人等を交えた会議をもって進めることが重要である。
また個別支援計画の作成については、
直接に意思決定支援を担う支援職員が携わる仕組みとすべきである。
【引用終わり】
*****************************************************
本人にとって意義のある個別支援計画の作成が望まれる。
計画は本人中心の支援が実現するためのワンステップにしか過ぎない。
計画だけが一人歩きして、それが目的化してしまったらなんのための計画かわからない。
立派な計画をペーパーとして保管しても、それがそのとおりであるかは疑わしい。
計画に対する見直しがあってこそ、より良い支援となる。
実際の支援がどうなされているか正確な評価も重要だ。
(ケー)