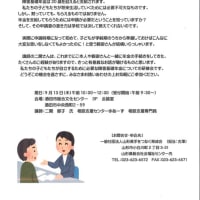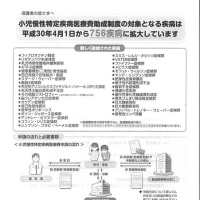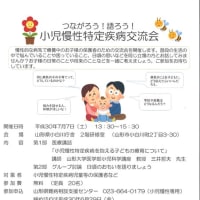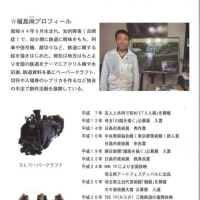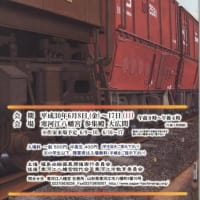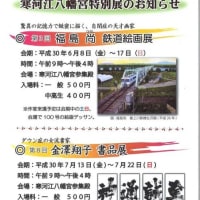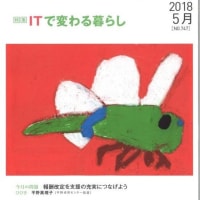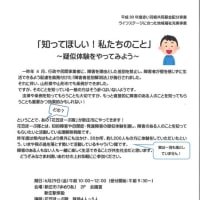知的障害者の「意思決定支援」の考え方や課題について整理したいい論文を見つけた。
柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)の論稿を、分割してずっと紹介している。
その第13回目。
以下は、重度の知的障がい者のかすかな動きに、支援者が敏感に応答し、おしめなしの排尿ができるようになった事例である。
*************************************************
【引用始め】
柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)
「発達障害研究」第34巻3号掲載予定http://homepage2.nifty.com/hiroya/isiketteisien.html より
Ⅲ.意思決定支援の考え方
1.重度の知的障害者にも意思がある…意思表現(意思疎通)支援
A氏は学校卒業後、重症心身障害者通所施設に通うこととなった。
手足がマヒしていて発語もなく、おむつをしていた。
ある日、「Aさんが腰を少し動かした時にトイレに連れて行って便器に座らせたら排尿する」と若い職員が言い出した。
そこで他の職員も気をつけて観察すると、やはりトイレで排尿した。
それを繰り返す内に、A氏ははっきりと腰を動かすようになり、やがておむつは不要になった。
また自分の関心があることを、身を乗り出すようにして示すようになった。
このように、どんなに重い知的障害者でも意思があり、わずかに表現された意思を支援者が読み取り応えることによって、ますますはっきりと表現するようになる。
【引用終わり】
*****************************************************
重度の知的障がい者が支援を受けるだけの人という思い込みで接することは、大いに問題がある。
微細な本人からのサインを支援者側がいかに読み取れるか。
支援者は敏感なアンテナをはって、本人の発するサインに的確な応答が求められる。
例えば、排泄時直前のお尻の動きをよく観察する。排泄を知らせるなんらかの動きがないか探る。
可能性のあるターゲットをしぼって、支援者は本人と密接にかかわる。
そして、特徴的な動きがないかを探り出す。
支援者のより良いかかわりによって、本人側も協力的なかかわりが出てくる。
こうしたことにより、意思疎通が良好な関係を生み出すと言える。
意思決定支援の一環でもある。
(ケー)
柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)の論稿を、分割してずっと紹介している。
その第13回目。
以下は、重度の知的障がい者のかすかな動きに、支援者が敏感に応答し、おしめなしの排尿ができるようになった事例である。
*************************************************
【引用始め】
柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)
「発達障害研究」第34巻3号掲載予定http://homepage2.nifty.com/hiroya/isiketteisien.html より
Ⅲ.意思決定支援の考え方
1.重度の知的障害者にも意思がある…意思表現(意思疎通)支援
A氏は学校卒業後、重症心身障害者通所施設に通うこととなった。
手足がマヒしていて発語もなく、おむつをしていた。
ある日、「Aさんが腰を少し動かした時にトイレに連れて行って便器に座らせたら排尿する」と若い職員が言い出した。
そこで他の職員も気をつけて観察すると、やはりトイレで排尿した。
それを繰り返す内に、A氏ははっきりと腰を動かすようになり、やがておむつは不要になった。
また自分の関心があることを、身を乗り出すようにして示すようになった。
このように、どんなに重い知的障害者でも意思があり、わずかに表現された意思を支援者が読み取り応えることによって、ますますはっきりと表現するようになる。
【引用終わり】
*****************************************************
重度の知的障がい者が支援を受けるだけの人という思い込みで接することは、大いに問題がある。
微細な本人からのサインを支援者側がいかに読み取れるか。
支援者は敏感なアンテナをはって、本人の発するサインに的確な応答が求められる。
例えば、排泄時直前のお尻の動きをよく観察する。排泄を知らせるなんらかの動きがないか探る。
可能性のあるターゲットをしぼって、支援者は本人と密接にかかわる。
そして、特徴的な動きがないかを探り出す。
支援者のより良いかかわりによって、本人側も協力的なかかわりが出てくる。
こうしたことにより、意思疎通が良好な関係を生み出すと言える。
意思決定支援の一環でもある。
(ケー)