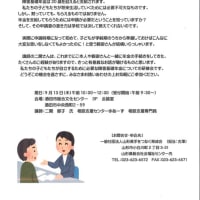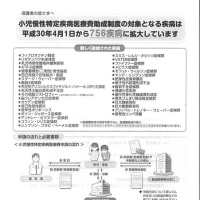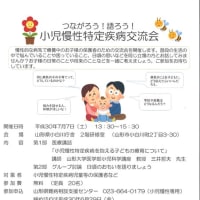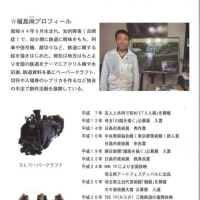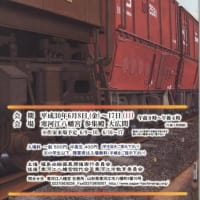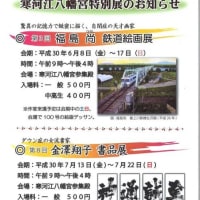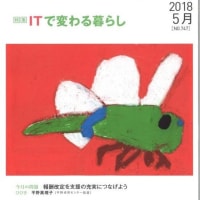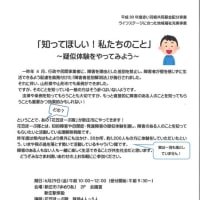知的障害者の「意思決定支援」の考え方や課題について整理した、いい論文を見つけた。
その論文は、柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)である。
その論稿を、分割してずっと紹介している。
その第16回目。
次は、両親を亡くした知的障がい者が在宅しながら、暮らせるようにさまざまな福祉サービスを提供した事例である。
本人のニーズに即したきめ細かな支援がなされている。
これはまさしく、意思決定支援と言って良い。
*************************************************
【引用始め】
柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)
「発達障害研究」第34巻3号掲載予定http://homepage2.nifty.com/hiroya/isiketteisien.html より
Ⅲ.意思決定支援の考え方
4.この町で暮らしたい…意思実現支援
通所施設に通うC氏(男性、30歳代)は、
母親を亡くした翌日に父親も亡くなり、
単身となった。
「僕は小学校の時からずっとここにいた。
(他県の)おじさんの家にも行きたくない。
遠くの(入所)施設にも入りたくない。
家にずっと居たい」と職員に必死に訴えた。
そこで施設と市は、そのまま公営アパートに一人で暮らせるよう、支援体制を整えた。
朝夕は自炊だが、
施設での料理学習が役立った。
昼は施設の給食で栄養を補う。
当時(1989年)は知的障害者ヘルパー派遣制度がなかったが、
市と社会福祉協議会は身体障害者用と高齢者用のヘルパーを、
室内整理や買い物のためそれぞれ週1日派遣した。
生活保護が適用されたが、
1ヶ月間の金銭自己管理ができないので、
市は1週間毎に生活費を渡し、
施設が使い方の助言をした。
C氏は公民館の障害者青年学級に参加し、
今も地域の中で充実した生活を続けている。
今後、このような支援は相談支援事業が担うこととなろう。
【引用終わり】
*****************************************************
以上の事例は、市の福祉担当職員、施設職員、社協、ヘルパー、公民館がうまく連携することができた。
当然、市営アパートの人々による支援もあったはずである。
本人も地域で暮らすための努力もしたからこそ、現在もこの暮らしを続けることができるのである。
20年以上一人暮らしを実現してきた。
地域にある福祉にかかわる最大限の資源をうまく活用した。
本人にかかわる誰かがそんなこと無理といって、協力しなかったら、C氏本人は施設に入所せざるを得なかったに違いない。
当時(1989年)としては奇跡に近い対応だった。
今では、相談支援事業所をうまく使うことによって、本人中心の意思決定支援ができる。
こうしてできあがったシステムを使いこなすことが求められる。
(ケー)
その論文は、柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)である。
その論稿を、分割してずっと紹介している。
その第16回目。
次は、両親を亡くした知的障がい者が在宅しながら、暮らせるようにさまざまな福祉サービスを提供した事例である。
本人のニーズに即したきめ細かな支援がなされている。
これはまさしく、意思決定支援と言って良い。
*************************************************
【引用始め】
柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)
「発達障害研究」第34巻3号掲載予定http://homepage2.nifty.com/hiroya/isiketteisien.html より
Ⅲ.意思決定支援の考え方
4.この町で暮らしたい…意思実現支援
通所施設に通うC氏(男性、30歳代)は、
母親を亡くした翌日に父親も亡くなり、
単身となった。
「僕は小学校の時からずっとここにいた。
(他県の)おじさんの家にも行きたくない。
遠くの(入所)施設にも入りたくない。
家にずっと居たい」と職員に必死に訴えた。
そこで施設と市は、そのまま公営アパートに一人で暮らせるよう、支援体制を整えた。
朝夕は自炊だが、
施設での料理学習が役立った。
昼は施設の給食で栄養を補う。
当時(1989年)は知的障害者ヘルパー派遣制度がなかったが、
市と社会福祉協議会は身体障害者用と高齢者用のヘルパーを、
室内整理や買い物のためそれぞれ週1日派遣した。
生活保護が適用されたが、
1ヶ月間の金銭自己管理ができないので、
市は1週間毎に生活費を渡し、
施設が使い方の助言をした。
C氏は公民館の障害者青年学級に参加し、
今も地域の中で充実した生活を続けている。
今後、このような支援は相談支援事業が担うこととなろう。
【引用終わり】
*****************************************************
以上の事例は、市の福祉担当職員、施設職員、社協、ヘルパー、公民館がうまく連携することができた。
当然、市営アパートの人々による支援もあったはずである。
本人も地域で暮らすための努力もしたからこそ、現在もこの暮らしを続けることができるのである。
20年以上一人暮らしを実現してきた。
地域にある福祉にかかわる最大限の資源をうまく活用した。
本人にかかわる誰かがそんなこと無理といって、協力しなかったら、C氏本人は施設に入所せざるを得なかったに違いない。
当時(1989年)としては奇跡に近い対応だった。
今では、相談支援事業所をうまく使うことによって、本人中心の意思決定支援ができる。
こうしてできあがったシステムを使いこなすことが求められる。
(ケー)