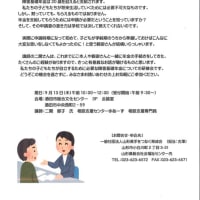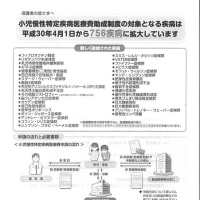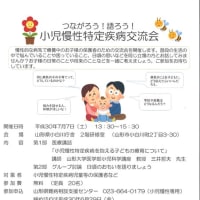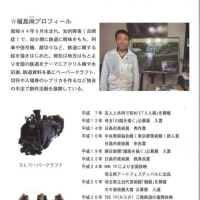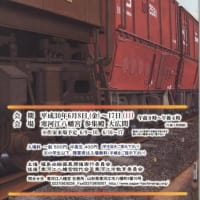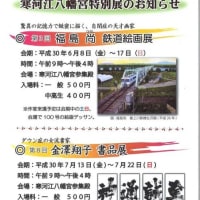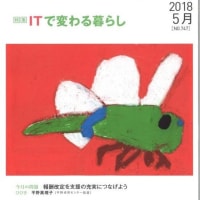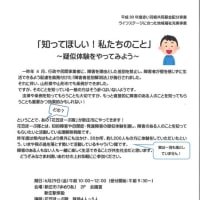知的障害者の「意思決定支援」の考え方や課題について整理した、いい論文を見つけた。
その論文は、柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)である。
その論稿を、分割してずっと紹介している。
その第23回目。
知的障がい者等に「意思決定支援」の概念を導入することは画期的なことである。
そして、支援の担い手の普及・拡大が成功のカギを握る。
その支援者のあり方が次に記されている。
*************************************************
【引用始め】
柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)
「発達障害研究」第34巻3号掲載予定http://homepage2.nifty.com/hiroya/isiketteisien.html より
Ⅳ.意思決定支援についての課題
6.意思決定支援についての諸課題
◯ 知的障害者等への「意思決定支援」の概念の導入は、
保護の客体から権利の主体への価値観の根本的な変革であり、
種々にわたる広範囲の課題がある。
◯ 知的障害者等への意思決定の担い手は多様である。
① 最も身近な家族、
② 訪問系事業・グループホーム・日中活動支援・就労支援・施設入所支援等の日常生活における直接支援職員、
③ 相談支援職員や権利擁護職員・成年後見人等、
④ その他様々な支援者があるが、特に
⑤ ピアサポートと
⑥ 市民サポートは今後強化する必要のある担い手である。
◯ ピアサポートとは、
同じ障害のある人相互による支援であり、
障害者権利条約26条でもリハビリテーションでの活用が特記されている。
知的障害者に必要なのは青年期のハビリテーション(自己確立支援)であるが、
同様にピアサポートの活用が重要である。
また知的障害者の当事者活動(本人活動)を支援すること、
育成会組織等への参加を進めることも重要である。
◯ 市民サポートとは、
知的障害者等に1対1でボランティア的に関わる市民の活動であり、
友人として話し相手をしたり、
時には一緒に遊びに行く。
スウェーデンではコンタクトパーソンという。
日本でも横浜市が「後見的支援制度」として「安心サポーター」を推進している。
ビフレンダー(to be a friendからの造語)など類似の取組が徐々に増えているが、
積極的・組織的な推進が望まれる。
【引用終わり】
*****************************************************
知的障がい者等に対する「意思決定支援」の担い手は、直接関係する支援者(家族・事業所職員)だけでなく、地域住民を含んだサポート体制を整備することが重要である。
それには育成会の役割が大きい。
ピアサポート、市民サポートを今後いかに取り入れるか。
それを推進していく方策をどうしていくか。
全日本育成会組織としての取り組みが始まっている。
ただ、会員一人一人のそれに関する理解向上こそ重要な要素となる。
(ケー)
その論文は、柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)である。
その論稿を、分割してずっと紹介している。
その第23回目。
知的障がい者等に「意思決定支援」の概念を導入することは画期的なことである。
そして、支援の担い手の普及・拡大が成功のカギを握る。
その支援者のあり方が次に記されている。
*************************************************
【引用始め】
柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)
「発達障害研究」第34巻3号掲載予定http://homepage2.nifty.com/hiroya/isiketteisien.html より
Ⅳ.意思決定支援についての課題
6.意思決定支援についての諸課題
◯ 知的障害者等への「意思決定支援」の概念の導入は、
保護の客体から権利の主体への価値観の根本的な変革であり、
種々にわたる広範囲の課題がある。
◯ 知的障害者等への意思決定の担い手は多様である。
① 最も身近な家族、
② 訪問系事業・グループホーム・日中活動支援・就労支援・施設入所支援等の日常生活における直接支援職員、
③ 相談支援職員や権利擁護職員・成年後見人等、
④ その他様々な支援者があるが、特に
⑤ ピアサポートと
⑥ 市民サポートは今後強化する必要のある担い手である。
◯ ピアサポートとは、
同じ障害のある人相互による支援であり、
障害者権利条約26条でもリハビリテーションでの活用が特記されている。
知的障害者に必要なのは青年期のハビリテーション(自己確立支援)であるが、
同様にピアサポートの活用が重要である。
また知的障害者の当事者活動(本人活動)を支援すること、
育成会組織等への参加を進めることも重要である。
◯ 市民サポートとは、
知的障害者等に1対1でボランティア的に関わる市民の活動であり、
友人として話し相手をしたり、
時には一緒に遊びに行く。
スウェーデンではコンタクトパーソンという。
日本でも横浜市が「後見的支援制度」として「安心サポーター」を推進している。
ビフレンダー(to be a friendからの造語)など類似の取組が徐々に増えているが、
積極的・組織的な推進が望まれる。
【引用終わり】
*****************************************************
知的障がい者等に対する「意思決定支援」の担い手は、直接関係する支援者(家族・事業所職員)だけでなく、地域住民を含んだサポート体制を整備することが重要である。
それには育成会の役割が大きい。
ピアサポート、市民サポートを今後いかに取り入れるか。
それを推進していく方策をどうしていくか。
全日本育成会組織としての取り組みが始まっている。
ただ、会員一人一人のそれに関する理解向上こそ重要な要素となる。
(ケー)