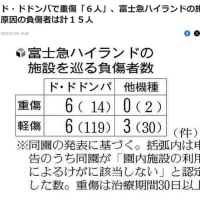日頃からヨットだとか帆船にさほどの感心はなかったのだが、今年9月のロシアでの帆船レースで沼津を母港とするAmi号がクラス2位に入賞したと報道で知り、ちょっと感心を持ち、静浦漁港の堤防内にて遠望してきました。
全長16mちょっとの黒い船体で、2本のマストを持つ船体で、この様な2本以上のマストを持つ船をスクーナーと呼ぶことを知りました。マストを除けば船高は低く構え、帆走中は風向きによるでしょうけど、それなりに大きくロールしても、安定度は高いという設計なのでしょう。以前にちょっと知り合いの又聞き話しで聞いたことで真偽の程は明確ではありませんが、この船の造船は、静浦からもほど近い重寺の工房で造船されたと聞きます。それが、1990年の完成であったということらしいです。
しかし、かつての伊豆国君沢群戸田村は今や沼津市の南端の地ですが、この戸田が日本の外洋帆船の生誕の地、もっと云えば外洋船のルーツとなる地点であることを意識する方は少ないのかもしれません。時は江戸時代、ある程度整備されてきた東海道でさえ、道は険しく山坂多くと、とても大量輸送はできず、もっぱら大量輸送は海運に頼っていたらしいことはものの本からも明らかでしょう。そこで使用された船は、廻船と呼ばれる木造船で、1本マスト帆が1枚という単純な作りで、陸から僅かに沖に出るのが精一杯で、陸伝いに全国各地を港から港へと搬送していたそうです。風向きが追い風なら、まあまあの速力を得たのでしょうけど、風向きが悪くなると、速やかに近くの港に入って、風が変わるのを待つことを繰り返しながら、帆走を続けていたそうです。例えば伊豆半島の西側だけの港を地図を見ながら想像してみましょう。沼津から下田まで、その間には、戸田、土肥、宇久須、安良里、田子、堂ヶ島、仁科、松崎、岩地、雲見、妻良、入間、中木、石廊崎、手石辺りと、風待ち港があったのだろうと想像します。この内、件の戸田には、往時は5つの廻船問屋があり栄えたと文献で知ります。恐らく、現在より人口も多かったことでしょう。
そんな時代に、ロシア軍艦ディアナ号が安政の大地震による津波で破損し、その修理先を戸田に定めて回航したが、折からの台風で富士沖で沈没してしまったことは皆が知るところでしょう。しかし、当時の田子の浦漁民の救助もあり、生存した艦長プチャーチン以下乗組員は徒歩で、戸田を目指し、ここで小型の洋式帆船(スクーナー)を、日本人船大工を指揮して造艦し、ロシアへ帰ったとの話しです。想像するに、この新造船(ヘダ号)は、今目にしたAmiに近い大きさだったのではないかと想像ができます。と、云う訳で、今までの単純1枚帆から、様々な風に対応して航行できる洋式帆船から、その後蒸気機関だとか動力を得て、鉄を始めとする重工業の発展もあって、世界トップクラスの造船大国に至った、一つの起点がここにあったと意識します。



全長16mちょっとの黒い船体で、2本のマストを持つ船体で、この様な2本以上のマストを持つ船をスクーナーと呼ぶことを知りました。マストを除けば船高は低く構え、帆走中は風向きによるでしょうけど、それなりに大きくロールしても、安定度は高いという設計なのでしょう。以前にちょっと知り合いの又聞き話しで聞いたことで真偽の程は明確ではありませんが、この船の造船は、静浦からもほど近い重寺の工房で造船されたと聞きます。それが、1990年の完成であったということらしいです。
しかし、かつての伊豆国君沢群戸田村は今や沼津市の南端の地ですが、この戸田が日本の外洋帆船の生誕の地、もっと云えば外洋船のルーツとなる地点であることを意識する方は少ないのかもしれません。時は江戸時代、ある程度整備されてきた東海道でさえ、道は険しく山坂多くと、とても大量輸送はできず、もっぱら大量輸送は海運に頼っていたらしいことはものの本からも明らかでしょう。そこで使用された船は、廻船と呼ばれる木造船で、1本マスト帆が1枚という単純な作りで、陸から僅かに沖に出るのが精一杯で、陸伝いに全国各地を港から港へと搬送していたそうです。風向きが追い風なら、まあまあの速力を得たのでしょうけど、風向きが悪くなると、速やかに近くの港に入って、風が変わるのを待つことを繰り返しながら、帆走を続けていたそうです。例えば伊豆半島の西側だけの港を地図を見ながら想像してみましょう。沼津から下田まで、その間には、戸田、土肥、宇久須、安良里、田子、堂ヶ島、仁科、松崎、岩地、雲見、妻良、入間、中木、石廊崎、手石辺りと、風待ち港があったのだろうと想像します。この内、件の戸田には、往時は5つの廻船問屋があり栄えたと文献で知ります。恐らく、現在より人口も多かったことでしょう。
そんな時代に、ロシア軍艦ディアナ号が安政の大地震による津波で破損し、その修理先を戸田に定めて回航したが、折からの台風で富士沖で沈没してしまったことは皆が知るところでしょう。しかし、当時の田子の浦漁民の救助もあり、生存した艦長プチャーチン以下乗組員は徒歩で、戸田を目指し、ここで小型の洋式帆船(スクーナー)を、日本人船大工を指揮して造艦し、ロシアへ帰ったとの話しです。想像するに、この新造船(ヘダ号)は、今目にしたAmiに近い大きさだったのではないかと想像ができます。と、云う訳で、今までの単純1枚帆から、様々な風に対応して航行できる洋式帆船から、その後蒸気機関だとか動力を得て、鉄を始めとする重工業の発展もあって、世界トップクラスの造船大国に至った、一つの起点がここにあったと意識します。