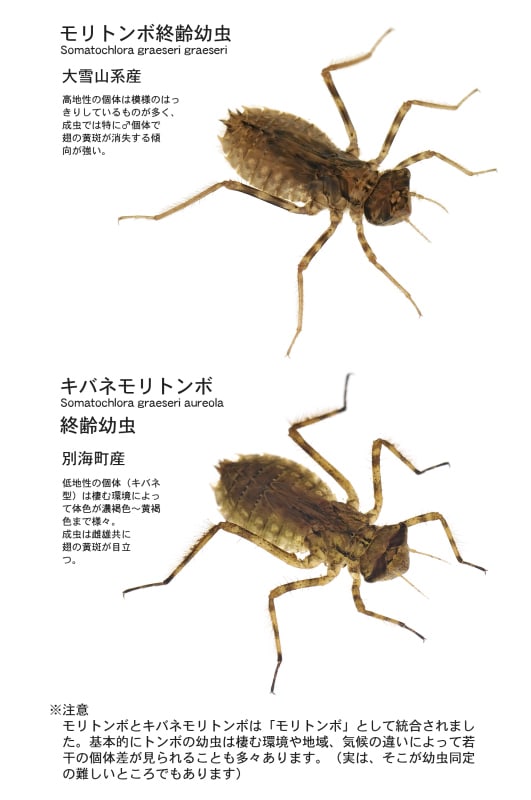北海道でもあと3週間もすればオオルリボシヤンマが羽化してきます。そこで、写真によるルリボシヤンマ属の終齢幼虫比較を行ってみました。マダラヤンマ以外であれば、まだ植生の少ない今が採集時でもあります。道内で「ヤゴ屋」をやられている方は少ないとは思いますが、同定の参考にして頂けたらと思います。
1.オオルリボシヤンマ
全国的に見ても最も一般的なルリボシ属のトンボなので、本種を基準に同定を行うのが良いと思います。成虫も含めルリボシヤンマと良く似ており同定が難しいと言われていますが、第6腹節にはっきりとした側棘と頭部側面に淡い側線(矢印)があるので、慣れてしまえば簡単に見分けることができます。
2.ルリボシヤンマ
全体的にコントラストのない体色をしており、オオルリボシには手足に明確なマダラ模様がありますが、本種は不明瞭です。また、腹部背面に一直線状の褐色状があり、第6腹節の側棘は非常に小さく目立ちません(個体によっては痕跡程度しかないものもいる)。
3.イイジマルリボシヤンマ
ルリボシ幼虫と非常に良く似ていますが、終齢幼虫の比較では明らかに小さく細身なことと、体表がより艶っぽいこと、第6腹節の側棘が無い或いは痕跡程度しかないことで見分けられます。しかし、ルリボシ幼虫にも同じような特徴が見られるので、同定には注意が必要です。
4.マダラヤンマ
体表、手足のマダラ模様が明瞭な個体が多く、体形的に見ても同属3種との違いは明らかです。終齢幼虫では同属中最も小さく、第6腹節にははっきりとした側棘があります。幼虫期間が3ヶ月程度とアカネ並に短く、道内では8月上旬頃から羽化が始まります。