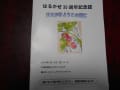わたしはこの春、「高齢者講習」を受講、認知・実車検査を受け運転免許証の更新ができた。
81歳であるから次の更新時には84歳となる。
高齢者の運転に危惧の目が注がれ、「免許証返納」を勧める世の中である。これからの3年間、乗り続けるのが憚れる事態であるのは承知している。
だが、「個人差があるだろう」というのが、わたしの立場だ。
昨年8月まで6年間、「送迎」を中心に都内のディサービスに勤務、車の行きかう都内の主要道路・脇道・路地を縦横無尽に走り回ってきた。
職場だけでなく、居住地においても自動二輪車・軽自動車を毎日のように駆り、無事故・無違反「ゴールド免許」保持者なのだ。
だから人にはとやかく言ってもらいたくない。
しかしそんな強気な気持ちがぐらつく事態がきた。
免許を更新して3ケ月が経った7月、2009年5月から11年間おせわになった「ダイハツ・ムーブ」が突然へたり込み、レッカー移動。
走行距離は14万キロを超えていたが、「エンジンの調子はよい」と修理工場のおじさんは太鼓判を押していた。.
だが修理のたんびに、「年式が古く部品がなかなかみつからない」とこぼしてもいた。
それもそのはずこの軽自動車は、友人の娘さんが10年近く乗り、走行距離95000㌔、「廃車にする」というのを貰い受けたものだ。
娘さんとわたしに仕えて、あわせて20年以上働いたことになる。
「修理すれば費用は莫大なものになる」と、通告され廃車にすることを決めた。
これからは「車なしの生活にしよう」とふと思う。
近年、足腰の不調が強まった妻の通院などをどうするか。これはタクシーなどを使うしかないだろう。
修理屋にすすめられる「中古車」を買い、購入費・車検・保険料・修理代などを考えれば、月に数回のタクシー代のほうが安上がりにちがいない。
なにしろ次の免許更新まで3年しかなく、それ以降は「免許証返納」しかないな、と思っていたのだから、それを早めてしまおうか。
だが動力源がないと、不便なこともある。
週に数回、ボランティアに等しい「新聞配達」がある。
息子の朗が田を耕し収穫した「阿智米」のファンが多く、月に何回も10㌔・20㌔と運ぶのには、自転車では遠すぎる。
そうだ運転免許証はバイクだけを残して返納しよう。警察のホームページをみるとそういう方法もあるようだ。
気持ちは「中古バイク」購入に固まる。
それでインターネットで調べはじめた。バイクといっても移動用だけではない。荷物も運ばなければならない。
そういう機種に的を絞って調べる。
新車だと40万ほどする。中古はどうかと見ると安くなってはいるが、べらぼうに安くはなっていない。
これだったら新車にした方がよかろう。
20年来世話になっている修理屋に連絡する。「バイクのカタログをもってお伺いする」と即答、「バイクだと奥さんを乗せて通院することもできない。いっそのこと軽の中古車を探した方がよいのでは……」とわが家の事情を知るおじさんが云う。
それもそうだ、同程度で軽自動車が入るなら、それに越したことはない。
バイクはやめにして、軽の中古の出物を待つことにした。
何回か引き合いがあったが、落札値が合わず日にちが経つ。
とうとう「ムーブ」がエンコして2ヶ月を迎えようする8月29日、「スズキ・ワゴンアール」を迎え入れた。
14年前の車だそうだが「走行距離」13500㌔余り、車体も傷はなくきれいだ。
車には「シルバーマーク」が貼られていたというから、お年寄りが大事に乗っていたにちがいない。
この車がいま庭に鎮座している。
眺めやりながら「免許証返納」は遠のいた。
3年経ったら「高齢者講習」を受けて、免許証更新に挑まねばと密かに思っているところである。