
(牡丹灯籠より・07年初演 お露を演じる加藤木朗)
このスペースにときどき顔を出す
和力広報担当の加藤木雅義が寄稿してくれました。以下、全文を掲載いたします。(加藤木照公)
大阪G20サミット前の「持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」が、令和元年6月15日と16日に行われました。
会場となる軽井沢プリンスホテルでの歓迎レセプション(14日)に和力が呼ばれたことは、加藤木の親族に驚きをもって伝達されました。もちろんそれは、
「和力も世間に認められて主要国の代表にその芸を披露することが出来るまでになったのか」
という思いでした。その一方で、和力が出演する会場にも注目されたのが今回の特徴でした。
加藤木朗の従兄弟が経営する(株)中條がそうだったのです。中條とは東京の食肉商社で、ホテル、レストランにお肉を卸している会社です。
今回のレセプション招待の報に接した中條社長(57歳)は
「それはすごい。(軽井沢プリンスホテルは)お得意先なので先方に従兄弟がお世話になることを連絡しておきます。和力の出演を誇りに思います」
というメールをわたしに返してきた。
田楽座の前は?
ここで、わたしが加藤木朗ファンのみなさまにお伝えしたいのは、(株)中條と加藤木朗の関わり、そして中條の会社としての成長の軌跡なのです。
わたしの兄・加藤木照公が中條さんのことをここのブログで何度か記述していますが、朗との関わりがないのでファンのみなさまには縁の遠い話だったのではないかと思われます。
加藤木朗は、田楽座で10年修行し、それから和力を結成して現在に至っているのは、コアなファンでしたらご存知だと思います。しかし、その田楽座の前に朗が何をしていたのかは、あまり知られていません。ここが本日のブログの見どころとなります。
結論から申しあげますが、生まれ育った秋田県を出た朗は上京し、この(株)中條に就職して初めて社会に出たのです。17歳の時でした。それから20歳の年に田楽座に行ったのがことのあらましとなります。

(中條直営レストラン JR三河島駅そば)
「どうやら中條さんは今や東京で1、2位を争うほどの規模を持つお肉屋さんになっているようですよ」と朗の口から聞いたのは、わたしが朗の住む阿智村に遊びに行った4年前(2015年)のことでした。最初は3人で出発した中條さんは、すでに70人従業員を抱える大きな企業になっていたのです。HPを調べると、取引先として都内の有名ホテルグループ、全国の調理師学校、各国の大使館があがっています。すでに小売りはやめてしまっていたようです。
中條さんとは
中條さんの出発はJR三河島駅(荒川区)から歩いて10分ほどのさびれた商店街の一角に構えた10坪ほどの精肉店でした。たぶんつぶれたお店の跡地を買ったものだったと思います。開店はチンドン屋さんをくり出す賑やかなものでしたが「今度、いつつぶれるのかしら」という声がご近所でもれたほどの、前途多難な出発だったのです。
少し、歴史をふり返りますので、わたしの兄姉構成を申しあげます。
わたし(雅義)は5人兄姉の末っ子として生まれました。まるで江戸落語に出てくるような遊郭に隣接した長屋でわたしたち兄姉は育ったのです。
長兄→朗の父
長姉→中條の創業者夫婦
次姉
末姉
わたし(雅義)
戦後の集団就職で上京した義兄がこつこつと蓄財して、三河島にお店を持てるようになったのは、昭和39年(1964年)の東京オリンピックの年でした。現社長はその時1歳。
親族内に産業が興ったのですから、わたしの兄姉は学校を出るともれなく中條さんに就職して社会に出るのが習わしになっていました。長兄も秋田県にある劇団に就職が決まっていたのですが、開店後、半年はお店を手伝い、それから秋田に旅立っていったのです。朗はまだこの世にいません。
次姉、末姉につづき、わたしも学校を出るとすぐに中條さんのお世話になります。大阪万博(1970年)の年でした。そのころ秋田で朗が生まれて1年がたっています。
わたしが勤め始めた時、中條さんの従業員はまだ6名ほどでした。小売りに2名、卸しに4名の布陣。
社長の義兄には外商の才能があり、小売りは人に任せて、卸しのお客さまを次々に開拓していました。しかしそこは新参者の肉屋です。町の小さなレストランや中華そば屋さんが主な得意先でしかありません。
義兄が「これからは有名なホテルやレストランと取り引きしないと、社会の信用ができない」という大きな夢を新入社員のわたしに語ったことがあります。しかしそれには高い壁があったのです。有名どころには戦前からの肉屋が取り引きしていて、新参者がいくら値引きをしても跳ね返されてしまう。
値段や肉の品質なのではなく、信用がなければ有名なところに食い込めないのが現実だったようです。
なぜ 奇跡がおこった
しかし、そこに奇跡がおこった。
わたしが勤めるころになると赤坂プリンスホテルと取り引きするようになっていたのです。
時は高度成長の真っ最中でした。プリンスグループといえばリゾート開発をかかげて破竹の勢いで成長していた企業だったのです。そこになぜ新参者の中條が入ることができたのか? それは誰もが思う疑問です。
これにお応えするためには、少し寄り道をしなくてはいけません。
それは、料理人というある意味、特殊な世界について知っていただきたいのです。
わたしが中條さんに就職してお肉を配達するようになって、一番、最初に驚かされたのは、調理人=コックさんの権力の強さでした。どんな大きなレストラン、ホテルでも支配人と同じくらいにコックさんの発言力があったのです。
学校で公式なことしか学んでこなかったわたしには、これが大きなカルチャーショックでした。普通、現場の人間よりネクタイを締めた事務方が上だと思いがちですが、調理の世界では現場が圧倒的に力を持っていたのです。
後年、わたしが勝手に解釈したのは、
「いくら立派なホテルやレストランでもただの箱ではないか。その胃袋をつかんでいるのはわれわれだ」
というのが調理人さんたちの自負だったということでした。そういうふうに考えれば、いくら立派なホテルを造っても料理が美味しくなければお客さんは来てくれません。
ここでもうひとつ知っておいていただきたいのは、出入り業者はその建物(ホテル)に付いているお肉屋さんと、それとは別にコックさんが連れてくるお肉屋さんの2種類があるということです。コックさんは権力が強いので、「この業者でないと俺の味は出せない」と言えば、そういうことも通ってしまったのかもしれません。
後年、秋田から上京した朗は、中條さんで数年間お世話になりますが、やはり同じ思いをしたらしい。
「力を持っているのはコックさんだとわかったので、その方と仲良くなるようにしました。そうしたら注文が増えてくるのです」と朗はわたしに語っています。彼の方はわたしと違って賢いので、すぐに対応ができたのでしょう。
生涯、親友のちぎり ――見えないピラミッドーー
そうやって現場で権勢を誇っているコックさんですが、頭の上がらない存在もあるのです。それは調理というのは徒弟制度、技術伝承の世界ですから、教えてくれる師匠、先輩には逆らえない。なので、われわれには見えないピラミッドがコックさんの世界にはあるようなのです。
それが帝国ホテルグループ、プリンスホテルグループといろいろあるのでしょうが、外部の者にはなかなか見えない世界なのです。
ただこのグループの絆は強く、上下関係は厳しいと、聞いたことがあります。
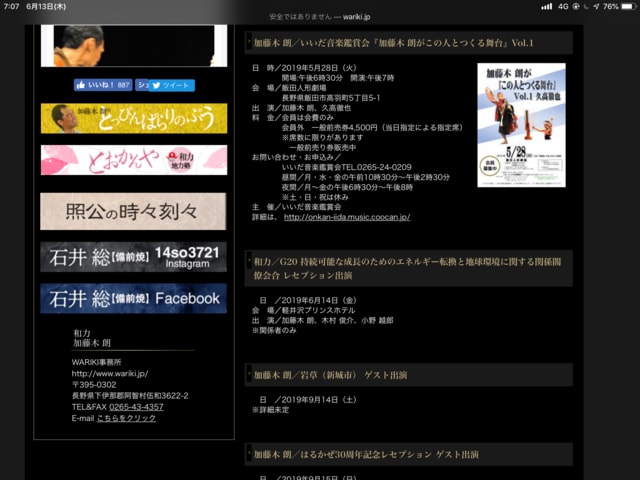
(和力HP スケジュール欄より レセプションの告知)
そして中條さんに話を戻していきます。
義兄は外商の才能があると前に申しあげました。それは誰からも好かれる気性と誠実な生き方があったからだと、身近に接したわたしは推測するのです。
その義兄が駆け出しのとき、配達先のコックさんと意気投合してしまった。調理場の片隅でふたりは
「俺とおまえは一生、親友だぞ」
と誓い合ったのだと言います。まるでドラマのワンシーンのようです。
堅いちぎりをしたその相手のコックさんが、後年になって、あれよあれよと出世して赤坂プリンスホテルの総コック長になってしまった。
赤坂プリンスといえば、数あるプリンスホテルグループの総本山です。
つまり、義兄の親友はプリンスホテルグループの総大将になっていたのでした。
先ほど、取引業者にはコックさんが連れてくる肉屋さんがいると申しましたが、プリンスくらいの大きなところでは、いくら親友といえどもすぐに取り引きできるものではありません。ただ、総料理長としては「こういう料理をしたいのにどこの肉屋にも置いてない」という食材を中條さんに相談して、それを持ってきてもらったことはあったらしい。
最初は小さな取り扱いだったのですが、徐々に信用を得て赤坂での取引量が増えてくる。
やがて、「プリンスと取り引きしているなら、うちにも」と声がかかるようになり、次々と商機が広がっていったのだと思われます。
「思われます」と他人事のように書いていますが、その頃、わたしは中條さんを退職して職場を替えていたのです。
1983年東京ディズニーランドが開園する時にも中條さんが園内のレストランと契約したと、風の便りで聞いていました。中條さんが開店して19年目。このとき朗、14歳。まだ田沢湖町神代中学の生徒です。
朗も上京
兄夫婦が秋田の劇団を辞める決心をして東京へ出て来たのは、朗が16歳の時でした。まだ高校1年生在学中を気遣って、「卒業するまでは秋田で」と朗を残しての上京でした。
40歳過ぎの兄夫婦の就職を正社員として受け入れたのは社業が拡大する中條さんだったから出来たのかもしれません。その1年後に朗も秋田を出て東京へ。朗は中條さんで仕事をしながら、残りの勉学を修めるに至りました。
※ここで朗ファンにエピソード1
朗が田楽座から独立して和力を結成したころ、わたしは、その時はもう現役を退いていた秋田の劇団幹部だった人にお話をうかがったことがあります。
元幹部氏は「あの時(朗の上京時)、どうして劇団は朗を手放してしまったのか」という後悔をわたしに語ったのです。
注釈すれば、そのとき朗はまだ学生で舞台に立ったことはありません。
「栴檀は双葉より芳(かんば)し」という言葉があります。これは銘木というのは大きくなって急に銘木になるのではなく、芽が出たときからすでに銘木の片鱗をうかがわせているーーというような意味だと思われます。わたしはこの言葉を知るにつけて、幼いときの朗に思いをはせるのです。
朗は年少のころより、芳しい香りを周囲に漂わせていたと聞きます。わたしにとっては歳の離れた甥っ子であり、そして東京と秋田という遠隔地でもあって朗と接する機会はめったにありませんでした。そうであるにかかわらず、小さな朗のエピソードの数々はわたしの耳にも入ってきたのです。
幼い朗の立ち居振る舞いをみて、「将来、この劇団を背負って立つのはこの子だろう」と周囲の大人は見ていた節があった。それが朗の舞台人としての素養を見出してのものなのか、人を率いるリーダーの才覚を感じ取ったのか、わたしにはわかりません。
その多くの証言をわたしは知っていますが、ここでのテーマではないので今回はふれません。
冒頭に登場する中條の2代目がいます。彼は朗より7歳上の従兄弟なのですが、この男も年少より大物ぶりを発揮してた逸材だったのです。「将来、この子は荒川(居住地)一番の大親分になるのではないか」と小学生のころより噂されていました。こちらがあまりに強烈だったので、遠く朗の噂を聞いても、「そうなんだ」くらいにしか思えなかったのは事実です。
しかし、幼いころのことを知っている秋田の劇団関係者には朗の退団はショックだったのではないかと想像はできます。
そういういきさつの中で、この元幹部氏が「どうして朗を手放したのか」と嘆いたのは、それは彼が劇団員の気持ちを代表して吐露したものではないかとわたしには受けとめられたのです。
あの時、元幹部氏は「(朗が)劇団に残っていれば、今ごろは劇団のトップになっていた」とわたしに断言したのです。
ちなみに、彼がそう確信したのは、和力の名作「牡丹燈籠」をご覧になった後のことでした。幽霊に取り憑かれてやせ細る店子を心配した大家が、新三郎を訪ねる道行きのシーン。
「あの大家扮する朗の立ち姿、面構えが良い」と、あれはスターになる顔だ、とおっしゃっていたのが、この方のわたしへの遺言となったのです。(その3年後にご逝去されました)
しかし、あの時、仮に秋田に残ったとすれば、朗は中條さんとも田楽座とも出会うことなく、今もなかったことにもなります。人生の選択というのは不思議というしかありません。
※エピソード2
中條に就職した朗は新米(しんまい)ですから、仕事の合間にまかないに使う食材の買い出しを命ぜられたといいます。
その頃になると中條さんでは従業員が増えて、その人たちの食べるものを用意しなくてはならなくなっていたのでしょう。
ある時、いつも朗とコンビを組んで買い物に行く新人が、「朗と一緒に行くのはイヤだ!」と急に言い出した。
朗ファンとしては聞き捨てならない言葉ですね。
「どうして朗サンと一緒だとイヤなのさ」という声が聞こえてきそうです。
驚いた周囲が、朗と何があったのかその新人クンに聞き出したところ・・・
買い物を終えて支払いを済ますと、朗が目の前にある物をひょいと手に取って、「これ、おまけに良いですか」と言うのだそうだ。
その取り方のあまりに自然なことと、そのときの朗の愛らしいにっこり顔に負けて、お店の人は「え? い、いいですよ」と折れてしまう。それが店は違っても毎回、やるのだというのです。
新人クンは、そのときの朗はとても良い笑顔なんだと証言する。「だったら良いではないか」と思いますよね。でも相棒は違った。
「だから、それがイヤだ」というのです
何だかイヤがり方が複雑ですね。
わたしも東京人ですからこの新人クンの気持ちはとてもわかるような気がします。東京の人は自分から「おまけして」というのを本能的に恥ずかしいと思ってしまう傾向があるのです。彼はそばにいて恥ずかしかったのですね。
しかし、朗はいったいどんな極上な表情で「これ、いい?」とお店の人におねだりしたのでしょう。

(中條の社屋)
中條さんがかつては跳ね返された戦前からの肉屋さんはどうなったのか?
「どうやら、昔からのお肉屋さんはバブルの時に土地取引に手を出して失敗し、あらかた店を畳んでしまったようです」
中條さんは新興勢力ですから転がす土地もなかったし、投機するにもそれにあてる財力もなかったはずです。それがかえって幸いしたのかもしれません。
「結果、本業重視の中條さんが生き残って、気がつくと業界の上の方に押し出されてしまったらしい」
と、4年前の阿智村での立ち話。
身内のこととはいえ、10坪のお店から現在の中條さんまでになるのは昭和のサクセスストーリーに類することだと思われます。
さて、みなさんに注目していただきたいのは、中條さんの今があるのはプリンスホテルグループが出発点だということなのです。
中條さんにとってプリンスは恩義のある会社なのだということを頭に置いていただきたい。
もちろん今、現在は、全国各地のプリンスホテルと取り引きがあります。取り引きがあるということは、ただ品物を送って済ましているのではなく社長がすべてに訪問してご挨拶しているのです。それが恩義のあるグループへの礼だとは思うのです。
現社長は、かつて人としての魅力で事業を拡大してきた義兄の、その血をわけた子でもあります。しかも彼は噂通り荒川一の大親分になっていますから、お得意様のことはただ知っているだけの間柄ではなく、もっと色濃くお付き合いをしているにちがいありません。
そうなると、冒頭に持ち出した
「(軽井沢プリンスホテルは)お得意先なので連絡しておきます」
という中條社長の言葉は、あらためて重みを持ってわれわれに迫ってくるのです。
さて、ようやく本題に戻って来ることができました。
軽井沢プリンスは国際会議を開催するほどの著名なホテルです。したがって調理場の取引業者も中條1社ということはあり得ません。複数の業者さんが入っているはずです。でも、赤坂プリンスから50年以上のお付き合いしていることを考えれば、中條が主取り引きの業者である可能性は大いにあることです。
6月14日(金)、G20の閣僚級のレセプションで朗が舞い、
その後の晩餐会で供されるメインデッシュが中條さんのお肉だとしたら、こんな素敵な巡り合わせはないと思うのです。
(令和元年6月16日)加藤木 雅義
中條さんの直営レストランのご案内
http://vingt-neuf-29.com/
(株)中條HP
http://www.nakajyo-meat.co.jp/

























