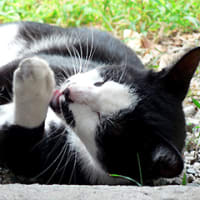私が商工会議所の手伝いをしてた頃だが、 年度末を控えて、そうそうたる人達が、雁首を揃えて陳情に見えられる。 卒業が近いのに、就職の決まってない学生の採用を、経済界に促すのが目的。 こんな定例的パフォーマンスが、何の役にも立たないことを、互いは承知している。 そして新聞テレビなどのマスコミは、この光景をニュースで一斉に伝える。
今年の就職率も良くないようだが、決して買い手市場ではなく、売り手市場のままだ。 企業側にとって、大変な求人難なのが実情。 企業が必死で追い求めるのは、「2、6、2」の法則 (2割は欲しい学生、6割はどうでもいい学生、2割はいらない学生) で上位2割の学生。 多くの企業が奪い合い、学生はそれを見透かして、厳しく企業を選別する。 この現象は、いつの時代も変わらない。
上位2割の話になるが、企業は学業成績に必ずしも拘っていない。 最近重視されるのは、面接や作文で、学生の本質を見抜くため、意地の悪い質問を連発して、即妙なコメントを求める。 但し残念ながら、日本の学生のコメント力は、かなり低いらしい。また文章を書かせて、考え方や性格、さらには考察力のレベルなどを読み取る意図が、企業側にある。 しかるに付け焼刃の知識や、模範解答集などの軽装備は通用しない。 一方学生側は、会社の企業文化や、経営理念まで踏み込んだ質問をしてくるので、会社側にも、しっかりとした理論武装が必要。 かくして激しい攻防の末、互いの納得を経て採用が決められる。
大手企業の役員から聞いた話だが、厳しい選別で採用した学生ほど、3年ぐらいで辞め易く、気が抜けないと言う。 辞める権利と、辞めさせる権利を互いが保留して、いかに魅力ある存在であり続けか、この緊張感が、企業と人材を活性化するのかもしれない。 それは、もてる男と女の関係にも似ている。
さて中小、中堅クラスの企業では、中位の6割から、マシなのを選ぶのは難しい。 そこで将来を託す人材だけは、大手企業でしっかりした基礎教育を受け、かつ起業を志望する、若手をスカウトするのも、ひとつの選択。 アメリカではこのケースでの後継者選びが、広く普及しており、日本でもこれから増えると思われる。
「ゼロからのスタートより、ある程度基礎のできた会社でトップを目指す方が、リスクが低く、時間の節約になるのでは?」 これがスカウトの相手に伝えるメッセージ。 提示条件は株の譲渡、まず3割程度を銀行からの借金で買わせ、保証人になってやる。 仮に、見込み違いだったときは、株を買い戻して、新たな候補者を探せばいい。 但しこうした後継者選びをする場合、オーナーには「株式公開に準じた」ルールの厳守と、心構えが不可欠。 ハッピーリタイアは、オーナーにとって、最後の大仕事。 アドヴァイスに応じます。