第1章 総則(1条~6条)
特段、問題点は見あたらない。
なお、第4条規定の「第1号法廷受託事務」とは「法律又はこれに基づく政令により、都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの」(地方自治法2条9項1号)
第2章 国民投票の投票権(7条)
満20歳以上のものに限定している点、また憲法改正国民投票運動に関する違反以外の罪で禁固以上の刑に処せられた者などを除外している点は、問題だと考える。
将来の日本のあり方を決めるという意味では、義務教育卒業年齢者には、投票権を与えるべきではないか。
また、服役中の者を除外する合理的理由はない。
第3章 国民投票に関する区域(8,9条)
特段、問題点は見あたらない。
なお、与党協議会実務者会議(以下「協議会」という)において、国政選挙との同時開催は禁止されることとなったため、条文が変更される予定。
第4章 投票人名簿(10条~18条)
協議会によって、公職選挙法に規定する選挙人名簿を使用することとされた。
よって、大幅削除の予定。
実質的には、特段、問題点は見あたらない(年齢の点は除く)。
ただし、閲覧にあたっては、プライバシーの侵害に留意するべきである。
第5章 在外投票人名簿(19条~30条)
協議会によって、公職選挙法に規定する在外選挙人名簿を使用することとされた。
よって、大幅削除の予定。
公職選挙法30条の4において、一定の国などに「引き続き3ヶ月以上」住所を有する者と規定されている点が問題である。
憲法改正の発議から投票まで30日(協議会で30日に短縮された)以後90日以内とされているため、海外で投票しようと考えた長期旅行者などが投票の機会を失う。発議から投票までの最短期日を下回るよう規定すべきではないか。
第6章 国民投票の期日等(31、32条)
31条の憲法改正発議から投票まで「60日以後90日以内」は、協議会で30日以後90日以内と修正された。
30日は短すぎないか。発議段階で十分な情報が国民に伝わっているのが通常だろうが、手続法においては、通常ではない場合をも、考慮に入れるべきである。すなわち、憲法改悪をひそかに発議して国民に負担を押しつけようとしているような場合、十分な国民的議論を行う必要がある。
最短は60日あるいは90日でもよいのではないか 。
なお、協議会において、国政選挙との同時開催は禁止されることとなったため、条文が変更される予定。この点は、改善されたといえよう。
32条の告示も「20日」では短か過ぎよう。
第7章 投票及び開票(33条~46条)
協議会によって、投票用紙の様式(36条)、投票の方式(37条)、投票の効力(43条)そのほか国民投票に関し、必要な事項は、憲法改正の発議の際に、別に定める法律の規定によるものとされた。
したがって、複数項目にわたり改正案が示された場合(例えば、9条変更と環境権の新設)、一括で賛否の意思を示すのか、各項目ごとに示すことができるのか、不明確。この点は、各項目ごとに示すことを明記すべきである。
日弁連の意見書参照http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/data/2005_14.pdf
第8章 国民投票分会及び国民投票会(47条~53条)
特段、問題点は見あたらない。
第9章 国民投票の効果(54条)
「有効投票の総数の2分の1」というのは考えられる最低の基準であり甘すぎる。
「有効投票総数の2分の1かつ有権者数の3分の1」にするとか、「有効投票総数の3分の2」にするとか、最低投票率を定めるなどの基準を設けるべきである。
日弁連の意見書参照http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/data/2005_14.pdf
第10章 訴訟(55条~60条)
協議会によって、下記のとおり修正された。
自民党提示案では、一の「国民投票無効の訴訟」と二の「国民投票の結果の無効の訴訟」を一つの訴訟として規定していたが、公職選挙法の「選挙無効訴訟」、「当選無効の訴訟」の区分にならって区別して規定した。
一 国民投票無効の訴訟 ※「選挙無効の訴訟」に相当する訴訟
1 国民投票の効力に関し意義があるときは、投票人は、中央選挙管理会を被告として、国民投票の結果の告示の日から起算して30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができるものとすること。
2 1による訴訟の提起があった場合において、国民投票に関する規定に違反することがあるときは、国民投票の結果(憲法改正に対する賛成投票の数が有効投票総数の二分の一を超えること又は超えないことをいう。)に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、裁判所は、その国民投票の全部又は一部の無効の判決をしなければならないものとする。
二 国民投票の結果の無効の訴訟 ※「当選無効の訴訟」に相当する訴訟
国民投票の結果の効力に関し異議があるときは、投票人は、中央選挙管理会を被告として、国民投票の結果の告示の日から起算して30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができるものとすること。
三 訴訟の処理に係る原則
一又は二による訴訟については、裁判所は、他の一切の訴訟に優先して、速やかにその裁判をしなければならないものとすること。
四 訴訟の提起が投票の効果に与える影響
一又は二による訴訟が提起されても、その無効判決が確定するまでは、国民投票の効果に影響を及ぼさないものとすること。
以上については、意思申立期間が短い、東京高裁に限定している、などの問題がある。
日弁連の意見書参照http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/data/2005_14.pdf
第11章 再投票及び更正決定(61条)
第10章の変更に伴う変更あり。
第10章との関連で問題となるか。
第12章 国民投票に関する周知(62条)
協議会によって、投票所内に憲法改正案が掲示されることとなった。
特に問題点は見あたらない。










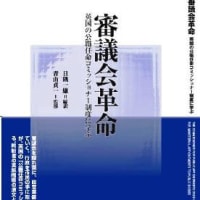
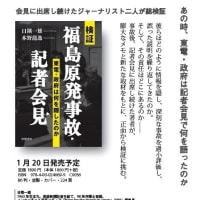
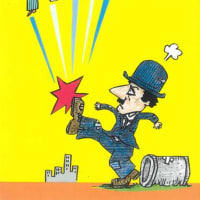
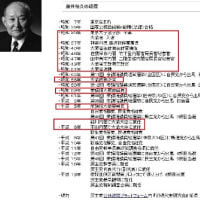
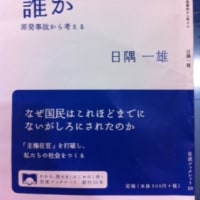
http://mehonkokunoyukue.seesaa.net/article/8847107.html
第2章の国民投票の投票権について(cf.拙案Ⅰ)
・高校三年生に対する教師の影響
・高校三年は大学受験期であり、就職活動期
・身体的肉体的安定の為にも、第二次性徴後が妥当
・公民権停止者は法を犯したから停止者だ
忙しいから投票できないというのも本当に受験生が忙しいでしょうか。世の会社員は受験期よりもよほど真剣に仕事に取り組んでいるのではないでしょうか?いま仕事に取り組んでいるくらい,高校時代に勉強していたら,俺だって私だって東大に行けた,という人は多いでしょう。
第2次性徴うんぬんは19歳とあまり関係ないのでは?
公民権停止に関しては,法を犯した者は憲法を犯した者という考え方には賛同しかねるし,現憲法に大人しく従う人だけにしか投票させないという考え方にも賛同しかねます。
第二次性徴は義務教育終了後ではダメだというためのものです。誤解を与えるような書き方でした、すみません。
すべての法規範は憲法の理念を具現化したものだという認識でいます。一般国民の法律違反をすなわち憲法違反だとすることはおっしゃるとおり法的には違うのかもしれません。
しかし現憲法の枠内の法律は守らなくてよいということに違和を私は感じます。憲法に従うのは日本人として当たり前のことで、憲法違反を容認するような発言は、どうかと思います。
現憲法を守れない者に、現憲法に規定された改正への国民投票に参加させることは心情的に適当ではないと思います。護憲派の方ならなおさらそうだろうと思ったのです。
もう少しお聞きしてみたいことがございます。よければご協力お願いします。
憲法改正や選挙の投票は成年者が行うべきだと思うのですが、それについてはどういう感想でしょうか。私は社会的責任のある成人だからこその参政権だと思っています。
また、最低限18歳から投票させるべきだという明確な理由はございますか。
韓国の選挙権年齢が19歳だった記憶があります。その他の法整備も19歳に合わせていくようです。成人年齢はどうでしたか…記憶が曖昧ですみません。なぜ韓国が欧米などで主流の18歳ではなく19歳に下げたのかを知りたいと思っているのですが、資料を見つけることができません。徴兵が関係しているのかなと勝手に想像しますがURLなどご存知でしたらぜひお教えください。