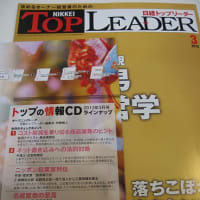昨日、大阪産業創造館にて決算書セミナーを実施した。
テーマは「貸借対照表」であった。
損益計算書は、いくら儲かって、いくら損したのかを示している。
従って、商人の頭の中をそのまま数字に落とし込む形になるので、社長にとって
とっつきやすいところはある。
ただ貸借対照表は、損益計算書と比較すると、とっつきにくい面がある。
社長の中には、損益計算書は読めても貸借対照表は読めないという方が多いのも
うなずける。
しかし、お金を残す経営を目指すうえでは、貸借対照表はすごく大切である。
寝ているお金をいかにたたき起こし、究極の資産「現金キャッシュ」を手元に
増やしていくか。
我々税理士が頭を痛める現象の一つに「勘定合って銭足らず」がある。
つまり、帳簿上は利益がたくさん出て、それ相応の税金がかかるのに、帳簿上の
利益に見合った現金キャッシュがない状況である。
中小企業にとって理想的なのは「勘定ほどほど銭たくさん」だと私は考えている。
ただこういう状況にするには、日本の税制構造上、無手勝流では不可能である。
生きた税法の知恵も求められる。
今日を皮切りに来月までに10本のセミナー講師を務める予定になっている。
新会社法施行により、従来の社長のお金の常識が崩壊した今、税理士の使命として
どんどん私の考えを世に情報発信していきたいと思いますので、よろしくお願い
します!
テーマは「貸借対照表」であった。
損益計算書は、いくら儲かって、いくら損したのかを示している。
従って、商人の頭の中をそのまま数字に落とし込む形になるので、社長にとって
とっつきやすいところはある。
ただ貸借対照表は、損益計算書と比較すると、とっつきにくい面がある。
社長の中には、損益計算書は読めても貸借対照表は読めないという方が多いのも
うなずける。
しかし、お金を残す経営を目指すうえでは、貸借対照表はすごく大切である。
寝ているお金をいかにたたき起こし、究極の資産「現金キャッシュ」を手元に
増やしていくか。
我々税理士が頭を痛める現象の一つに「勘定合って銭足らず」がある。
つまり、帳簿上は利益がたくさん出て、それ相応の税金がかかるのに、帳簿上の
利益に見合った現金キャッシュがない状況である。
中小企業にとって理想的なのは「勘定ほどほど銭たくさん」だと私は考えている。
ただこういう状況にするには、日本の税制構造上、無手勝流では不可能である。
生きた税法の知恵も求められる。
今日を皮切りに来月までに10本のセミナー講師を務める予定になっている。
新会社法施行により、従来の社長のお金の常識が崩壊した今、税理士の使命として
どんどん私の考えを世に情報発信していきたいと思いますので、よろしくお願い
します!