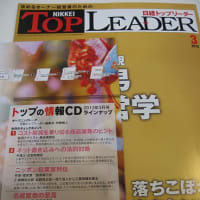「好事魔多し」という格言があります。
良いことが続く時にはとかくアクシデントが起きやすい。
だから、気をつけるようにという戒めですね。

ただなぜ「とかく」起きやすいのか?
それは、気が緩んで脇が甘くなるということがあると
思います。
歴史をひも解き、「本能寺の変」がなぜ起きたのか
を考えると、そのヒントが浮かび上がります。

なぜ信長は少人数の小姓のみを引き連れて本能寺に
泊まったのか?
乱世の収まっていないこの時代、主君が寝首を取られる
ことのないようにするのは、大名の最低限のリスク管理
だったはず。
しかし光秀の襲来時、肝心の信長の周囲には森蘭丸らの
近習しかいませんでした。

この背景に武田家を滅亡に追いやったことが挙げられて
います。
信長は、信玄や勝頼が率いる武田軍に対し、長年にわたり
脅威を感じていました。
そんな中、武田氏に内部崩壊の動きがあるのを見て、
信長が武田領に本格侵攻したのは、長篠の戦いの実に
7年後のこと。
本能寺の変のわずか1ヶ月半前。
信長は本能寺への道中、安土城から持参した天下の名物
茶器を並べ、公家衆や大商人に見せびらかすなど、およそ
戦場に赴く途中とは思えない様相だったそうです。
あの信長でさえ、武田軍のプレッシャーからの解放感の前
では、リスク感覚が吹き飛んでしまった可能性が高い。
そう分析する見解もあります。
▼勝って兜の尾を締めよ
という格言もあります。
ちょっとうまくいったからといっていい気になっていたら、すぐに
痛い目に遭う。
「危機の時代」の今、経営の舵取りがほんとに難しいですね。
でも古今東西、戦国時代も現代も同じ失敗が繰り返されています。
お互いしっかり肝に銘じたいですね。

良いことが続く時にはとかくアクシデントが起きやすい。
だから、気をつけるようにという戒めですね。

ただなぜ「とかく」起きやすいのか?
それは、気が緩んで脇が甘くなるということがあると
思います。
歴史をひも解き、「本能寺の変」がなぜ起きたのか
を考えると、そのヒントが浮かび上がります。

なぜ信長は少人数の小姓のみを引き連れて本能寺に
泊まったのか?
乱世の収まっていないこの時代、主君が寝首を取られる
ことのないようにするのは、大名の最低限のリスク管理
だったはず。
しかし光秀の襲来時、肝心の信長の周囲には森蘭丸らの
近習しかいませんでした。

この背景に武田家を滅亡に追いやったことが挙げられて
います。
信長は、信玄や勝頼が率いる武田軍に対し、長年にわたり
脅威を感じていました。
そんな中、武田氏に内部崩壊の動きがあるのを見て、
信長が武田領に本格侵攻したのは、長篠の戦いの実に
7年後のこと。
本能寺の変のわずか1ヶ月半前。
信長は本能寺への道中、安土城から持参した天下の名物
茶器を並べ、公家衆や大商人に見せびらかすなど、およそ
戦場に赴く途中とは思えない様相だったそうです。
あの信長でさえ、武田軍のプレッシャーからの解放感の前
では、リスク感覚が吹き飛んでしまった可能性が高い。
そう分析する見解もあります。
▼勝って兜の尾を締めよ
という格言もあります。
ちょっとうまくいったからといっていい気になっていたら、すぐに
痛い目に遭う。
「危機の時代」の今、経営の舵取りがほんとに難しいですね。
でも古今東西、戦国時代も現代も同じ失敗が繰り返されています。
お互いしっかり肝に銘じたいですね。