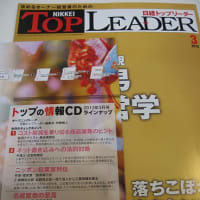先日、岐阜県の飛騨高山に遠征しました。
日本生命・岐阜支社主催の生前贈与対策のセミナー講師を
務めるためです。
飛騨高山といえば、江戸時代以来の城下町・商家町の姿が
保全され、日本の原風景を残す街として知られる。
フランスのミシェランの実用旅行ガイドでは、
★必見の観光地として3つ星マーク

関西や東京とは別世界の雪化粧。

そんな地域だからこそ、相続では【家督】の考え方が
根強い。
【家督相続】とは、
民法旧規定で戸主が死亡したとき、一人の相続人が戸主の
身分・財産を相続することで、それに伴うすべての権利と
義務を含む
という考え方で、江戸時代にできた。
その後、太平洋戦争後の民法改正で廃止になり、
現民法では【均分相続】
がうたわれている。
これが昨今、
▼相続が“争族”に変わる
一つの要因となっている。

「本家 vs 分家」
の構図になり、長男中心か、兄弟皆平等か、
遺産分割の方針の対立が生じるのは世の常である。
本家は、権利の承継だけでなく、
お墓を守る、家督を守るといった義務の承継も考慮せよと主張。
一方、分家は現民法の「均分相続」の考え方を主張。
実務上では、昔の家督相続に根差した【本家中心の相続】
が過半数を占めるが、遺産分割協議の争点になる。
争族の予防策は、
▼生前の親子間のコミュニケーション
が命。
分家の子供たちに盆や正月に顔を合わせたときの【配慮】
をしながらも、
家を守るという本家の大変さを親が【はっきり】伝えること。
ここでも星野仙一氏の名言、
「誰に対しても、配慮はしても遠慮はするな」
が大切になる。

江戸時代の名残を感じる「飛騨高山」で家督相続について
深く考えることができました。
高城剛氏の言葉「アイデアと移動距離は比例する」はその通り。
飛騨高山の皆様、ありがとうございました。

日本生命・岐阜支社主催の生前贈与対策のセミナー講師を
務めるためです。
飛騨高山といえば、江戸時代以来の城下町・商家町の姿が
保全され、日本の原風景を残す街として知られる。
フランスのミシェランの実用旅行ガイドでは、
★必見の観光地として3つ星マーク

関西や東京とは別世界の雪化粧。

そんな地域だからこそ、相続では【家督】の考え方が
根強い。
【家督相続】とは、
民法旧規定で戸主が死亡したとき、一人の相続人が戸主の
身分・財産を相続することで、それに伴うすべての権利と
義務を含む
という考え方で、江戸時代にできた。
その後、太平洋戦争後の民法改正で廃止になり、
現民法では【均分相続】
がうたわれている。
これが昨今、
▼相続が“争族”に変わる
一つの要因となっている。

「本家 vs 分家」
の構図になり、長男中心か、兄弟皆平等か、
遺産分割の方針の対立が生じるのは世の常である。
本家は、権利の承継だけでなく、
お墓を守る、家督を守るといった義務の承継も考慮せよと主張。
一方、分家は現民法の「均分相続」の考え方を主張。
実務上では、昔の家督相続に根差した【本家中心の相続】
が過半数を占めるが、遺産分割協議の争点になる。
争族の予防策は、
▼生前の親子間のコミュニケーション
が命。
分家の子供たちに盆や正月に顔を合わせたときの【配慮】
をしながらも、
家を守るという本家の大変さを親が【はっきり】伝えること。
ここでも星野仙一氏の名言、
「誰に対しても、配慮はしても遠慮はするな」
が大切になる。

江戸時代の名残を感じる「飛騨高山」で家督相続について
深く考えることができました。
高城剛氏の言葉「アイデアと移動距離は比例する」はその通り。
飛騨高山の皆様、ありがとうございました。