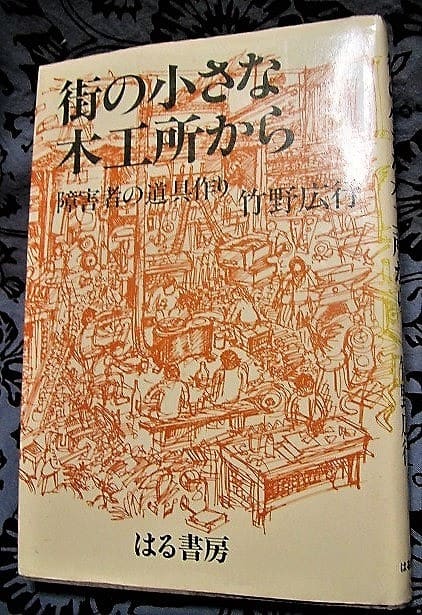
身障者たちの生活用具のオーダーメイドのパイオニア、「でく工房」の力まない生き方が素敵だ。
竹野広行『街の小さな木工所から』(はる書房、1985.2)の仕事に対する情熱とゆとりとが仲間を呼ぶ。
物故した竹野さんだが彼が育てつながったネットワークは全国に広がっている。
救われた身障者、救われた木工アーティストの存在は、竹野さんらの温かいまなざしが注がれている。

読みながら、出版社の良心的な取り組みが儲け本位の大手出版社と違うのをひしひしと感じ入る。
赤貧の暮しをしながらの著者たちの格闘と同じ目線を編集者たちからも感じる。
売れなかったであろう本書だが、竹野さんらが切り拓いた世界は燦然と記憶され、雇用を生み出している。
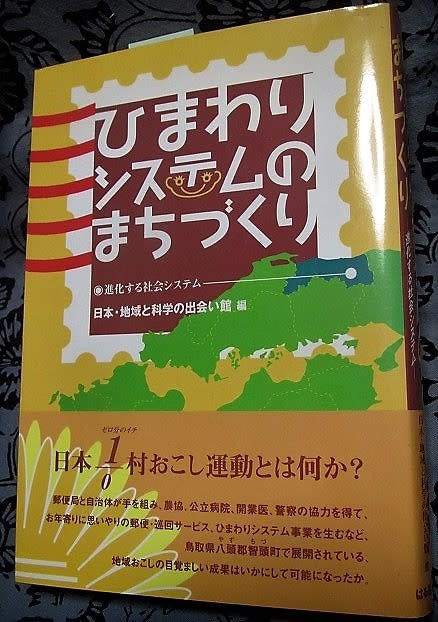
たまたま読もうとした本、日本・地域と科学の出会い館編『ひまわりシステムのまちづくり』(はる書房、1997.6)もなんと同じ「はる書房」だった。
郵便局と福祉とが見事に提携したシステム構築のムラおこしだ。
とくに、厳しい一人暮らし老人への声掛けや薬・日用品買物代行を郵便局員が担うとは画期的だ。
当時の郵政省にも影響を与えたようだが現状は広がっているとは言えない。
とはいえ、間違いなくセンセーショナルな中身であることは確かだ。

残念なのは、執筆が饒舌な研究者らに頼っていることだ。
そのため、現場のディティールやリアリティーが伝わらない。
研究者やプランナーが中山間地に果たした役割は大きいものの、どうも一般読者にはわかりにくい。
住民に密着したルポルタージュがあればもっと説得力ある感動が伝わると思うのだが。
つまり、研究者・プランナー・行政マン・郵便局長らに続く市民リーダーが育たなかったのだろうか。
その溝を埋めていく作業はどこの地域でもぶつかる壁なのかもしれない。
とはいえ、郵便局の果たす役割の深さ、「ひまわり=日回り」の発想の転換になったことは間違いない。
そこまで実現するにあたっての苦闘、住民間の軋轢などは伝わってくる。
竹野広行『街の小さな木工所から』(はる書房、1985.2)の仕事に対する情熱とゆとりとが仲間を呼ぶ。
物故した竹野さんだが彼が育てつながったネットワークは全国に広がっている。
救われた身障者、救われた木工アーティストの存在は、竹野さんらの温かいまなざしが注がれている。

読みながら、出版社の良心的な取り組みが儲け本位の大手出版社と違うのをひしひしと感じ入る。
赤貧の暮しをしながらの著者たちの格闘と同じ目線を編集者たちからも感じる。
売れなかったであろう本書だが、竹野さんらが切り拓いた世界は燦然と記憶され、雇用を生み出している。
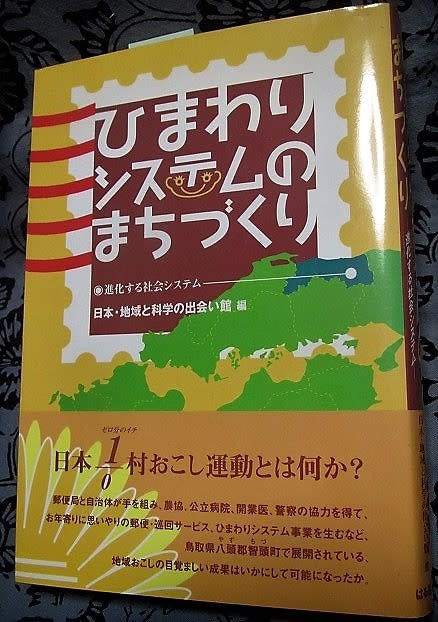
たまたま読もうとした本、日本・地域と科学の出会い館編『ひまわりシステムのまちづくり』(はる書房、1997.6)もなんと同じ「はる書房」だった。
郵便局と福祉とが見事に提携したシステム構築のムラおこしだ。
とくに、厳しい一人暮らし老人への声掛けや薬・日用品買物代行を郵便局員が担うとは画期的だ。
当時の郵政省にも影響を与えたようだが現状は広がっているとは言えない。
とはいえ、間違いなくセンセーショナルな中身であることは確かだ。

残念なのは、執筆が饒舌な研究者らに頼っていることだ。
そのため、現場のディティールやリアリティーが伝わらない。
研究者やプランナーが中山間地に果たした役割は大きいものの、どうも一般読者にはわかりにくい。
住民に密着したルポルタージュがあればもっと説得力ある感動が伝わると思うのだが。
つまり、研究者・プランナー・行政マン・郵便局長らに続く市民リーダーが育たなかったのだろうか。
その溝を埋めていく作業はどこの地域でもぶつかる壁なのかもしれない。
とはいえ、郵便局の果たす役割の深さ、「ひまわり=日回り」の発想の転換になったことは間違いない。
そこまで実現するにあたっての苦闘、住民間の軋轢などは伝わってくる。















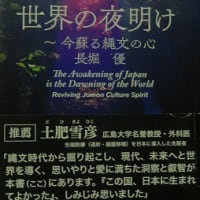












そのおかげかそうでないのか、先週は体調崩して絶不調だったんですが、今はなんとか回復しました。
世捨て村に近々山葵を植える予定です。
この2体の出番がやっと来たと急遽載せたわけでございます。
許可なくご本尊を載せてしまったことを深くお詫びいたします。
世捨て村の自然はきわめて豊かであることをいつも思い出しております。ムラのいい空気を吸ってVXではなく山葵で解毒されるよう祈願します。