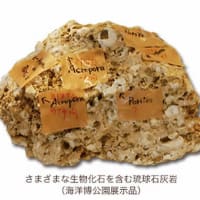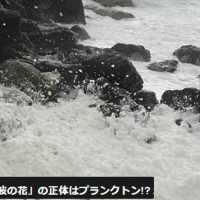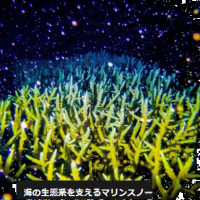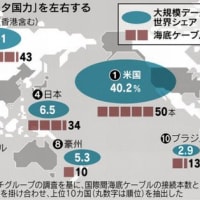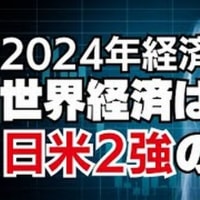🌸世界の古典 必読の200作品、はじめに(佐藤優氏)
⛳不確実な社会を生き抜くとき、「古典」は力強い道標となる
⛳不確実な社会を生き抜くとき、「古典」は力強い道標となる
☆私たちが直面している諸問題
*人類の歴史で、繰り返し問われてきたものばかりだ
☆筆者はかつて国家の内側にいた
☆筆者は、三井物産の落札で、偽計業務妨害の容疑をかけられた
*その案件は、条約局が決裁しいた
*筆者の個人の背任罪など成立するはずもないと思っていた
*そうした主張は通らなかった
☆筆者は、国家の暴力性に向き合い、その怖さを知った
*メディアは、基本的に国家に同調する恐怖も肌で感じた
☆その時に気づいたこと
☆その時に気づいたこと
*数人でも友人がいれば、人は自分の理性を維持して耐えていける
*数人の友人の存在によつて、私は自分を見失わずにすんだ
*友人とは、必ずしもリアルな人間関係である必要はない
*友人とは、必ずしもリアルな人間関係である必要はない
☆私たちは「古典」を通じて死者を味方につけることができる
*神学者は、イエス・キリストに相談するために『聖書』を読む
☆死んでしまった人、遠くにいる会ったこともない人
☆死んでしまった人、遠くにいる会ったこともない人
*テキストを通じて友人関係になっていくことが可能
☆「古典」を通じて、無数の死者
*今を生きる私たちの味方になってくれる
⛳古典は「構造」を描き出すので、アナロジカルな力を持つ
☆古典の特徴は、「閉じている」ことにある
*物語として閉じられているので、構造が見える
⛳古典は「構造」を描き出すので、アナロジカルな力を持つ
☆古典の特徴は、「閉じている」ことにある
*物語として閉じられているので、構造が見える
*その構造は、いかなる時代にも通用可能である
☆一見似ていないもの
☆一見似ていないもの
*ある種の違った物語を適用して考えていく力が古典にある
⛳人間は何度も同じ過ちを犯す
☆元連合赤軍幹部の坂口弘氏が執筆した『あさま山荘1972』
⛳人間は何度も同じ過ちを犯す
☆元連合赤軍幹部の坂口弘氏が執筆した『あさま山荘1972』
*立派な古典といえるだろう
*大勢の同志を″粛清″する結果に至った連合赤軍事件の内情
*人間が社会の中でいかに失敗していくか
*大勢の同志を″粛清″する結果に至った連合赤軍事件の内情
*人間が社会の中でいかに失敗していくか
*古典から学ぶべき大切なテーマだ
☆人間は誰しも間違えることがある
☆人間は誰しも間違えることがある
*その時、人間は似たような間違いを犯す
☆古典は「正しさ」だけではない
☆古典は「正しさ」だけではない
*「失敗の歴史」として読むことも必要
☆私たちはポストモダン以降の時代を生きている
☆私たちはポストモダン以降の時代を生きている
*絶対的に正しいものなどない、との考えが前提になっている
*しかし、「私にとって絶対に正しい」とのことはありうる
*それを追究していくことは非常に重要だろう
*それは当然、別の人にとっては別の「絶対に正しい」ものがある
*正しいものが複数並存している、といつことと同義である
☆自分が絶対に正しいものを追究しているつもりでも
*「正しさ」が本来のあるべき姿からずれている
*おかしな方向へと向かっていく可能性がある
*おかしな方向へと向かっていく可能性がある
*そのような感覚を持つことは大切だ
☆それを、古典の中から拾っていくことが重要だ
⛳古典の評価は時代とともに変化する
☆古典の読み方そのものが、時代とともに変わってくる
⛳古典の評価は時代とともに変化する
☆古典の読み方そのものが、時代とともに変わってくる
☆そのようなことを意識しておくことも大切だ
☆戦前における『太平記』の読み方
☆戦前における『太平記』の読み方
*後醍醐天皇に忠義を尽くして自害した楠木正成を称揚
*忠君愛国の本として読まれていた
*忠君愛国の本として読まれていた
*今は、『太平記』は、鎮魂のための書である
*南朝の後醍醐天皇に対する批判も含め
*北朝サイドの本ではないかとの読みが一般的である
⛳古典を読むことは
☆「今」を俯激して考える力をつけることに他ならない
☆現在、さも真実のように声高にいわれている主張
☆その思想体系を知り、相対化して考えることができる力が得られる
☆自分自身にとっての正しさを追究し続ける知的体力も得られる
☆自分自身にとっての正しさを追究し続ける知的体力も得られる
☆他者の正しさも複数並存しているとの認識する力も得る
☆これらこそ「古典」が持つ底力である
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
⛳出典、『世界の古典』
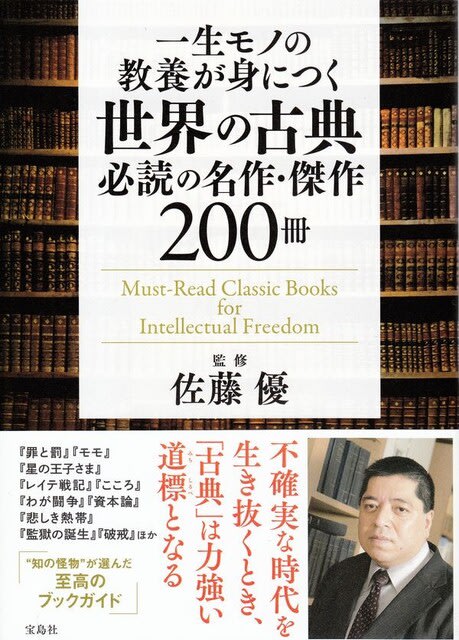
世界の古典 必読の200作品、はじめに(佐藤優氏)
(『世界の古典』記事より画像引用)