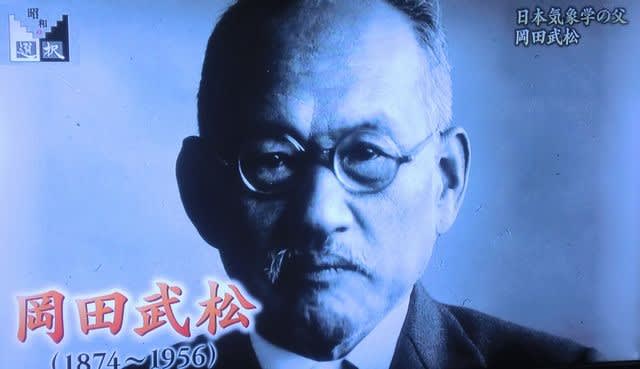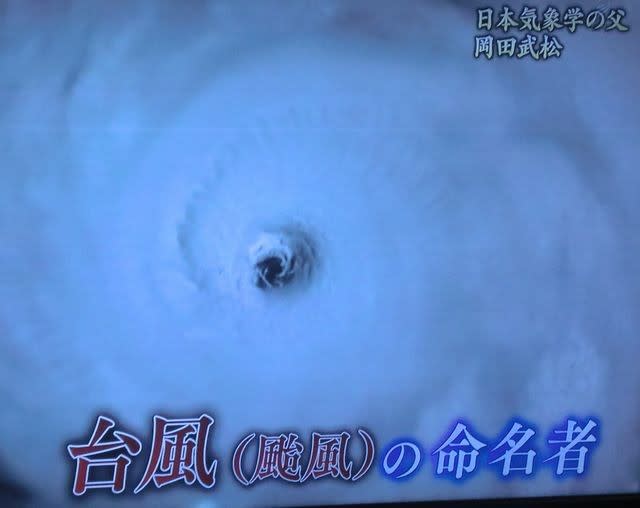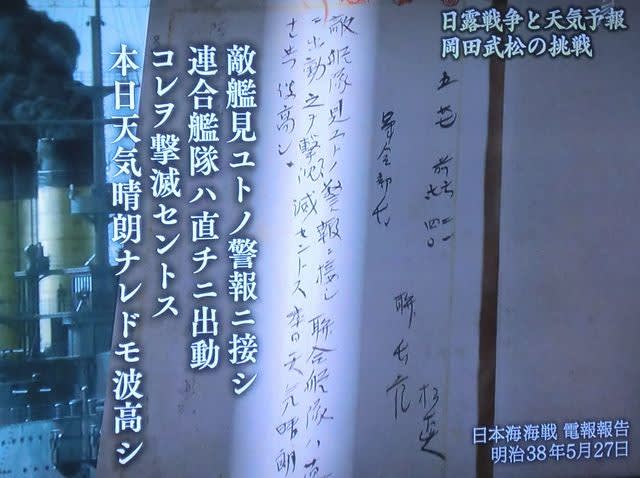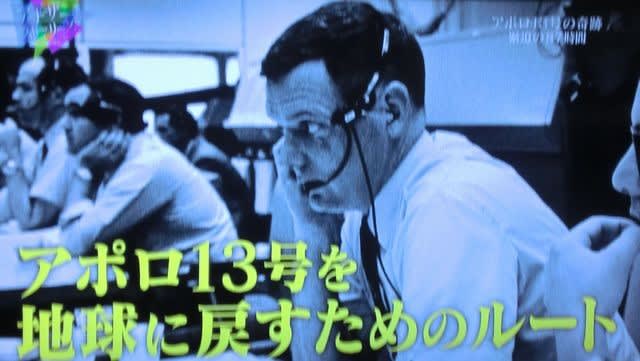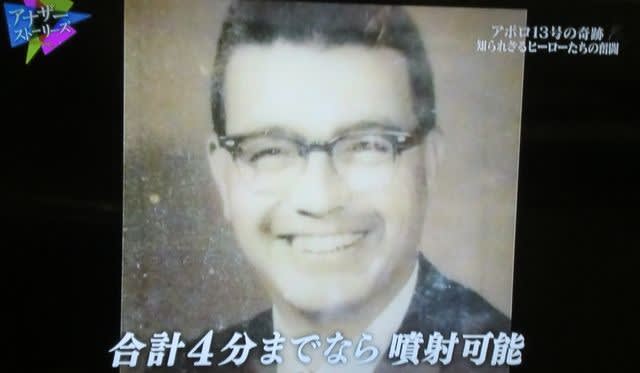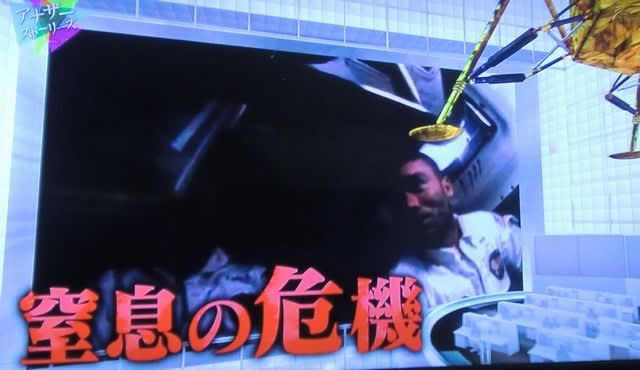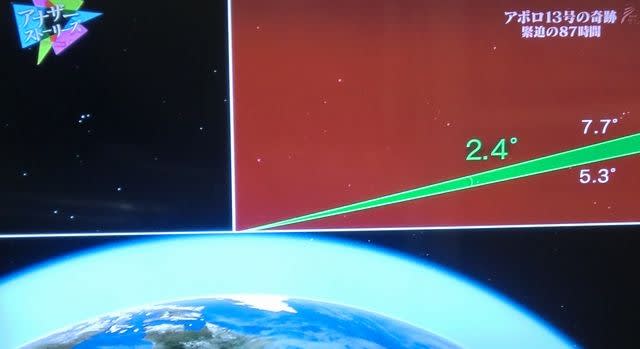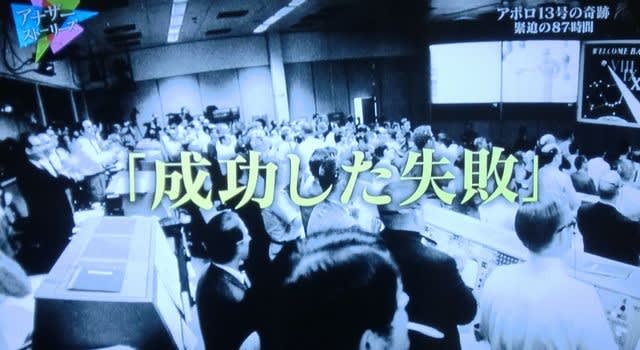巨大地震が、首都圏&東海地方を襲う
巨大地震が、首都圏&東海地方を襲う☆首都機能崩壊の可能性も―命を守るために最低限の準備を急ぐとき
☆「超地震大国」に見合う防災システムが必要
☆政府が極度の東京一極集中の問題を解決出来ない
*結果として、首都直下地震や南海トラフ地震は脅威であり続ける
☆巨大地震がいつ起こっても不思議ではない現在の状況
 6月は半月で73回の有感地震
6月は半月で73回の有感地震☆関東エリアでは、「緊急地震速報」が続いた
☆6月に入って15日間
*全国各地で、最大震度4を含めて73回の有感地震が起きた
☆地震が連続して起きている要因
*東日本大震災の影響で、プレートのゆがみで生じている
*ゆがみの補正で地震発生している
☆阪神・淡路大震災以降
*政府の地震調査委員会毎年、地震発生確率等を検討している
*30年以内に首都直下地震(M7クラス)70%の確率で発生すると
*南海トラフ地震は70%以上と高い数字を示す
 大停電・断水・交通マヒが続く
大停電・断水・交通マヒが続く☆首都直下地震や南海トラフ地震での東京予測被害
*地震で6万棟の建物が倒壊、火災によって焼失
*死者は約2万3千人
*固定電話、携帯電話とも、通話には使えない状態
*メールもすぐには届かない
*都区部の約50%断水し、下水道も約10%が使用できない
*鉄道は、地下鉄で1週間、私鉄・在来線で1か月程度は動かない
*経済被害は国の年間予算に匹敵する約95兆円
☆東海地方等の広域被害が想定される南海トラフ地震
*東日本大震災のときより短時間で巨大な津波が押し寄せる
*死者は32万人、経済被害は220兆円を超え
 1週間を目途に食料など備蓄を
1週間を目途に食料など備蓄を☆大地震に対する備えで最も重要なこと
*命を落とさない事
*支援が来なくても大丈夫なように備蓄しておくこと
*1週間以上の備蓄はほしい
☆武漢コロナが、大都市の弱点を露にした
*首都圏を巨大地震が襲ったら、影響はコロナの比でない
*首都圏には約4千万人が住む
*政治経済などのほとんどの拠点が集まている
☆東京一極集中に突き進んできた日本
☆防災・減災にはあまりにも無策だった
(敬称略)
 知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載 出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました
出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
 私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います 詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください 出典、『THEMIS7月号』
出典、『THEMIS7月号』
北海道から沖縄まで中規模地震続発中
(『THEMIS7月号』記事より画像引用)