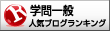ヴィンセント・ヴァン・ゴッホは、1886年3月、事前の連絡もしないでいきなりパリにやって来て、弟テオの部屋に転がり込んだ。88年2月までの期間をパリで過ごし、約200点の油彩を制作している。ロートレックやピサロ、ゴーガン、ベルナールらと知りあい、すでにアントワープで知った浮世絵と新印象主義の影響のもとに、あるいはパリ生活の雰囲気によって、ピサロやスーラから影響を受け、色彩は一変して明るくなり、新印象主義風の点描となっていた。しかし、結局パリでの生活は心身を疲労させるばかりだった。彼はモデルを雇う金がないため、この期間に27点もの自画像を制作している。疲労と困窮のなかにある35歳のゴッホに、生活費の安いフランス南部アルルで療養することを勧めたのは、南仏出身の友人ロートレックだった。アルルの町はローヌ川沿いには田園地帯が広がり、太陽が輝き、色彩に溢れていた。
こうし経緯があって、89年5月までつづくアルル時代は、結果的にゴッホの制作が飛躍的な展開をとげ、その画作の頂点となる作品が制作された時期である。
アルル駅の近くのラマルティーヌ広場にあるジョゼフ・ジヌーが経営する「カフェ・ド・ラ・ガール」に下宿していた彼は、制作のかたわら、この土地に芸術家たちの共同体をつくって共同生活をするという考えに夢中になった。
パリの画家仲間十数人に手紙を送るなどして、5月、3軒隣の家を借り受け、少しずつ手を入れ、9月から移り住んだ。ヴィンセント自らがその外壁を黄色く塗ったのは、黄色が神の光明のしるしだと信じていたからだった。そして10月、テオに借金があったゴーガンがその返済のかわりに、この「黄色い家」にやって来た。
ゴーガンはタヒチヘ行く前の短期間を過ごすつもりだったようだが、ヴィンセントはそれよりも長い期間の共同生活を望んでいたようである。しかし結局、強烈な個性は互いに相いれず、12月になるとゴーガンは、ヴィンセントとの共同生活に限界を感じ、パリに帰ることを考えるようになった。彼はある晩、カフェでアブサンを飲んでいたが、突然グラスごとゴーガンの顔めがけて投げつけたという。その直後にヴィンセントは、テオからの手紙で弟が婚約したことを知らされる。ゴーガンの回想録によると、共同生活9週目の12月23日の夜、夕食の後で散歩に出ると、まもなく背後に聞き慣れた小刻みな足取り近づいて来たので振り向くと、刃を立てた剃刀を手にしたヴィンセントが飛びかかってきた。ゴーガンが睨みつけると、彼は立ち竦み、首を項垂れて走り去ったという。「黄色い家」に戻ったヴィンセントは、左耳の下部――耳たぶを切り取ると、止血をしてからベレー帽をかぶって、それを馴染みの娼婦ラシェルに贈った。その後彼は家に戻り、窓の鎧戸を下ろしてベッドにもぐり込んだ。この「耳切り事件」はゴーガンを同情させて引き止めるためともいわれ、またゴーガンから自画像の耳の形がおかしいと指摘されたことに激怒した結果ともいわれている。
翌朝ヴィンセントは癲癇発作を起こして意識不明の状態でいるところを警察に発見されて病院に運ばれた。ゴーガンは荷物をまとめてアルルを去った。テオはゴーガンの電報を受けて、クリスマス・イブに夜行列車でアルルに急いだ。
2週間後の1月7日にゴッホは退院して「黄色い家」に戻った。平静を取り戻すと、「親愛なる友」ゴーガンに手紙を書き、レー医師の肖像や、耳に包帯をした自画像2点を描き、またルーラン夫人をモデルに《子守女》(《ゆりかごを揺らす女》)を描いた。だがやがてふたたび癲癇発作が起こった。2月7日に入院、10日後に仮退院したものの、周囲の住民たちに「耳切り事件」は知れ渡っていて、彼は危険人物と見做され、この「赤毛の狂人」を病院へ収容する嘆願書が警察に提出され、2月26日になって彼はまたもや病院に収容され、3月23日まで独房に閉じ込められていたが、やがて日中だけ付添人と外出することを許されると、絵の制作を再開した。地元の少年たちは彼を「狂人」と揶揄して「黄色い家」にまで追いかれて来て石を投げつけた。
4月17日にテオがヨハンナ・ボンゲル(通称ヨー)と結婚。同月下旬、サル牧師から聞いたサン=レミの精神病院(サン=ポール・ド・モソル)に移る気持ちになり、テオに転院の手続をとってほしいと手紙で頼んだ。5月8日になって、そのサル牧師に伴われ、アルルから25キロほど北東にあるサン=レミの精神病院に入院。1年間の入院生活がはじまる。
広いとはいえない病室にはベッドがひとつ、窓には当然、鉄格子が嵌っていた。担当医が絵の制作を許可したので、テオは兄のアトリエとして庭が見える部屋を借り、2部屋分を支払った。入院翌月の7月5日、ヴィンセントはヨーが妊娠したことを知らされ、その翌日に野外制作中に激しい発作を起こして意識を失った。7月の間じゅう錯乱状態がつづいた。8月になるとひどく衰弱し、毒性の絵具を口にしたり、ランプの油を飲むなどしたため、当面アトリエに入ることが禁止された。翌月には絵筆を手にすることができたが、ヨーの出産が近づいた12月、またしても錯乱して絵具を喰らおうしたので、医者は絵具を没収し、スケッチだけを認めた。
10月に彼はブリュッセルの〈第8回20人展〉に出品の招待を受け、翌年1月18日に開催された同展に出品した6点のうち《赤いぶどう畑》(88年制作)1点が400ベルギーフランで売れた。生前に売れたのはこの1点のみだった。
結局、サン=レミの病院では4回にわたって発作と脱力状態にみまわれているものの、創作意欲は失われず、発作の合間を縫っていくつかの代表作が制作された。この時期には彼の内面の不安が形態や筆致、テーマなどによって激しく先鋭化し、その情念が大地や糸杉や夜空などに象徴化されている。――ヨーロッパでは糸杉は死の象徴と結びついているが、ヴィンセントは意に介さなかった。《星月夜》(89年6月)《糸杉》(89年6月)《星月夜の糸杉のある道》(90年5月)などを含む300点以上の油彩と素描が、このサン=レミ時代に制作されている。
入院中、彼は繰り返し癲癇発作と精神的危機に見舞われ、その間には悲鳴をあげ、絶叫もしたが、意識が戻ると、その記憶はまったく残っていなかった。しかし彼は院内での様子を見て、他の精神病息者たちから悪影響を受けて、自分もやがて同じような死に方をするのではないかという不安が強まり、またサン=ポール・ド・モソルでの治療では回復の見込みがもてないと考え、90年5月、医師ポール・ガシェの滞在するオーベル・シュル・オワーズに移った。当初ヴィンセントはガシェ博士の家に近いオテル・サントーバンに宿泊していたが、やがてラ・メール広場のカフェ・ラヴーの2階の1室に移り住んだ。最初のうち、ヴィンセントはガシェ博士と気が合って、しばしば招かれて制作もした。7月6日、ヴィンセントはパリに出てロートレックやベルナール、評論家オーリエらとの再会を果たした。この直後、ガシェの娘マルグリットに求愛して拒否されたという説があり、ガシェ博士との仲も冷え切っていた。この時期の作品《麦畑のうえの烏》あるいは《荒れ模様の空と畑》などには、不気味な死の影が色濃くただよっている。彼の精神状態に動揺を与えていたことのひとつには、終生彼を援助した弟テオの、画商としての経営の行き詰まりがあったようである。7月27日の夕方、彼は麦畑の中でピストル自殺を遂行、胸部(腹部とも)を貫いた弾丸はわずかに急所をそれ、重傷ながらヴィンセントは自力で下宿のアトリエに戻った。ガシュの知らせでテオが翌朝パリから駆け付けた。28日にはヴィンセントの容態は落ち着きを取り戻したかに見えた。彼はパイプをくゆらせ、「精神まったく明晰で」テオと穏やかに語り合ってもいた。しかし夜半になって急変し、29日午前1時半、静かに息をひきとった。――「悲しみはいつまでも続く……」という最後の言葉を残して。
死の前に彼はゴーガンに次のように書き送っている。
「あなたという人を知り、あなたにいらざる苦痛を与えた僕であるから、面目ない状態で生きのびるより明晰な精神状態のまま死を迎えるほうが人間らしい品位を保てるというものだ」
37年の短い生涯のうちの、約10年ほどの画歴のなかで850点以上の油彩作品を制作したゴッホの病歴については、従来から癲癇性発作や精神病などがいわれてきたが、その他にも数多くの仮説があり、それらを排除して医学的診断および精神医学的診断を確定するにはいたっていない。
サン=レミ療養所の医師ペイロンは、89年5月9日付けの文書で「散発的に見舞われるてんかん性発作」という所見を述べている。これはアルル時代にヴィンセントを看護したレー医師の診断を支持するものだった。
《ゴッホがてんかん患者であったとする診断は、フランスを除いては定着していなかった。ドイツでは、ゴッホの苦悩の生涯の縦糸をたどって、てんかんの典型的発作が認められないとして、ゴッホてんかん説はまともに取り上げられなかった。この点ドイツでやっと一歩を進めたのがクライストで、彼はゴッホの生涯にエピソードとして語られる朦朧状態に言及して説をうちたてた。ヤスパース、それにプリンツホルンも、自由な考え方によって在来の説の轍を脱するにしてはいわばあまりに固定観念にとらわれていた。哲学をライフ・ワークとしたヤスパースは、それから二、三〇年後の時点で、ゴッホの精神分裂症説をてんかん説に転轍する余裕がなく、プリンツホルンも、一九二二年にオスロにエヴァンゼンを訪ねた際、そのことを指摘されながらも自説を撤回しなかった次第については、一九二六年のクレペリン祝賀記念論文集にはっきり記されている。
ゴッホが精神的な朦朧状態と突発的な狂騒状態に陥ることがあった事実をみて、フランスの医師たちが早い時点でてんかんの症候であると診断を下せたのはなぜだろうか? おそらくひとつには一九世紀半ばのフランスの精神科医たちが名声噴々であったこともあるが、また実際に精神病理学的知見に関して他のヨーロッパ諸国の医師たちに彼らが立ちまさっていたことにも求められよう。当時すでに、フランスの精神医学者の泰斗たちが、痙攣症、てんかんおよびてんかん類似の病状に関心を寄せていた。一八三八年にはエスキロールが、痙攣状態に立ち入らずにではあるが、てんかん症候群の記述に手をつけていたし、一八六〇年にはモレルが、「てんかんでないてんかん」として記述している。
この一八六〇年にはファルレも、「精神的小発作」を病理学的に他の病気と境界を画して命名している。彼がこう名づけたものは、患者がもの静かに暮しながらも時に陥る精神の錯乱状態で、今日ではいわば正気を失わないせん妄状態と称されているものである。ファルレにいわせれば、この症状に見舞われた者が後になって生活のエピソードとして思い出す一状態とは次のようなものである。患者は多少とも持続して頭の働きが鈍くなりふさぎこんで、観念連合が不活発になって知覚の統合がままならず、不安感を抱き、離人症体験に苦しめられる。彼によれば、潜伏性の経過は以上のような現われによって特徴づけられる。臨床的に観察された患者は、一種の麻酔状態と朦朧状態との意識の幅のあいだのさまざまな様相を呈し、操り人形的挙動と仮性躁病的なはしゃぎ状態を伴っていた。
この「精神的小発作」とならんでファルレは二つ目の精神錯乱状態を区別したが、こちらの特徴は、今までのもの静かさの堰が切れて、錯乱と由々しい狂騒におびただしい幻覚症状が伴うものである。つまり、「精神的大発作」である。この場合は、端緒をなすのが精神運動性の危機で、つづいて躁病的な猛々しいまでの錯乱状態を現出することがあって、通常、これによって最終的には疲労困憊と終末睡眠に陥る。また症候学的に見れば、健忘を伴うような程度の錯乱状態となる。場合によってはなはだしい狂騒状態のつづく数日後、患者はずっと疲労衰弱状態に落ち込む。激越な危機的状態については、彼らのうちには何の記憶も残らない。しかしこれにつづく完全な疲弊状態のときの記憶は残りつづける。潜行性の具体的な印象や、幻視的性格を帯びた幻覚過程ははっきり記憶に留まっていて、その記述が可能である。》(マンフレート・イン・デア・ベーク『真実のゴッホ ある精神科医の考察』/徳田良仁訳)
ゴッホの生前、まず検討されるのが常だった進行麻痺は、現在では明らかに否定されている。また当時さかんに議論された神経病的兆候は、臨床的には認められていない。精神病理学的にも、ゴッホが歩んだ生涯の概要は、さまざまな症状を伴った進行麻痺という伝染病を立証するものではない。精神分裂病に関しては、彼の残した38枚の自画像を並べて見ても、どこにも均衡を失った要素はなく、精神分裂病と断定できるフォルムも見出されないという。
85年末から翌年初頭にかけて、ゴッホはベルギーのアントワープに滞在していたが、この時期に彼は梅毒と診断されて治療を受けていることから、W・ランゲ=アイヒバウムは「急性梅毒性分裂・てんかん様障害」と診断している。またこの頃からつづくパリ時代にかけて、彼はアブサンを多量に摂取するようになった。アブサンの原料であるニガヨモギに含まれるツジョンという有毒成分は、振戦譫妄、癲癇性痙攣、幻聴などのアルコール中毒を引き起こすことが知られている。サン=レミの精神病院で彼が絵具のチューブの中身を飲み込んだりしたのは、溶剤のテレビン油をがツジョンと似ているせいだという指摘もある。
1979年、安田宏一博士は、ゴッホと弟テオとの間で取り交わされた数百通の手紙を分析した結果、今まで精神病とされてきたゴッホの病気が「メニエール病」だったという新説を発表し、欧米にも紹介された。ゴッホの手紙には回転性のめまい、吐き気、左の耳鳴り、難聴など、メニエール病特有の症状が書かれているが、このメニエール病説の実例として上げられているのが《星月夜》で、この絵の特徴のうねるように渦を巻く夜空が、水平・回旋混合性の眩暈――眼振をあらわし、メニエール病などの内耳疾患にみられる眩暈に特徴的なものであるという。
ゴッホは日頃から、何の前ぶれもなくやってくる激しい回転性の眩暈、強い吐き気、耳鳴り、難聴などの発作に悩まされていた。ゴーガンとの共同生活に入った頃には病気もかなり進行し、左耳にはつねに気が変になるかと思うほどの耳鳴り、あるいは難聴があったと思われる。耳切り事件のときも、ゴッホは発作に襲われていたのかもしれない。――傍らにいたゴーガンは、ゴッホが眩暈と吐き気、嘔吐に苦しむのを見て、薄気味悪くなり、彼を見捨てて行ってしまう。残されたゴッホは、寂しさのなかで、自分を理解してくれる酒場の娼婦に、耳鳴りのする左の耳たぶを削ぎ落として捧げた。――経験者でなければ理解できない眩暈の苦しみは、ときに突然襲いかかり、突然去ってゆく。その様子を目にする他人たちには、精神病の発作と見まがうばかりの不気味な印象があるのかもしれない。
メニエール病は、病原因不明の内リンパ水腫に起因する眩暈、耳鳴り、耳閉塞感、難聴などを主症状としている。メニエール病の名は、1861年にフランスの医師メニエール(1799~1862)が、発作性の眩暈に耳鳴りと難聴をともなう患者を解剖し、発表して以来、眩暈を訴える内耳疾患の患者に対して、メニエール症候群とかメニエール病という診断が下されるようになった。だがその後、疾患に種々の多様性があることが判明し、メニエール症候群という名称はしだいに使用されなくなり、内耳の中に存在する内リンパ液の圧が高くなる内リンパ水腫に起因する疾患のみを、メニエール病というようになった。
厳密に区別されるべきメニエール病は、度重なる眩暈の発作に、必ず耳鳴りと難聴をともなう内耳の病気であり、脳の疾患から生ずる神経の症状がまったくないことが条件となる。内リンパ水腫の原因については、体内の電解質調節障害、水分代謝障害、ホルモンの異常、塩分貯留説、アレルギー説、交感神経の過敏による血管収縮説などが云々されるが、まだ確定されてはいない。
典型的なメニエール病では、特別の誘因もなく突然、耳鳴りや難聴が生じると、激しい眩暈が起こる。これに耳閉感がともなうこともある。眩暈の発作中、気分が悪く、冷や汗をかいたり、吐き気や嘔吐をともなう。眩暈には、外界や自分の体が回転しているような感じのものが多いが、意識障害はなく、数分から数時間ほどつづくと、激しい眩暈はなくなる。頭や体を動かすと、短時間の軽い眩暈感は数日間残る。耳鳴りと難聴は回復することもあるが、残存するか進行することが多く、眩暈発作が反復する特徴がある。そのため、難聴は眩暈発作のたびに増悪し、高度になっていく。
メニエール病における難聴は、内耳性の感音難聴である。その他の随伴症状として、心悸亢進、頭重感、頭痛、肩こり、また精神の不安状態に陥ることもある。眩暈発作などがない時期を間欠期、休止期などというが、患者は休止期が終わって眩暈発作がまた突然起こるのではないかと、精神的に不安な状態にみまわれるのである。
メニエール病に似た症状を示す疾患には、多くのバリエーションがある。一回だけの発作で高度な難聴となり、激しいめまいを起こす突発性難聴、耳鳴りや難聴などは伴わないが、激しい眩暈発作を一回だけ起こす前庭神経炎、眩暈とともに物体が二重に見える複視、言語障害、ある種の意識障害や失認などが、メニエール病の症状と重なるものを共有している。
――またこのメニエール病説との関連で、彼が度重なる激しい発作の合間に、極めて冷静に制作していたことから、そのアウラ体験が注目される。
ゴッホのアウラ体験を考える前に、文学的な一例を挙げよう。
ドストエフスキーはアウラ体験を有する癲癇患者でありながら、その緊迫した体験を作品の中に克明に再現していることが知られている。
《ある数秒間があるのだ、――それは一度に五秒か、六秒しか続かないが、そのとき忽然として、完全に獲得されたる永久調和の存在を、直感するのだ。これはもはや地上のものではない。といって、何も天上のものだというわけじゃない。つまり、現在のままの人間には、とうていもちきれないという意味なんだ。どうしても生理的に変化するか、それとも死んでしまうか、二つに一つだ。それは論駁の余地のないほど明白な心持ちなんだ。まるで、とつぜん全宇宙を直感して、『しかり、そは正し』といったような心持ちなんだ。……何よりも恐ろしいのは、それが素敵にはっきりしていて、なんともいえないよろこびが溢れていることなんだ。もし十秒以上つづいたら、魂はもう持ち切れなくて、消滅してしまわなければならない。ぼくはこの五秒間に一つの生を生きるのだ。そのためには、一生を投げ出しても惜しくない。それだけの価値があるんだからね!(ドストエフスキイ『悪霊』米川正夫訳)》
木村敏氏は『時間と自己』の中で、このキリーロフの言葉を引用しながら、次のように書いている。「これは死の直前の、生から死への参入の体験というよりは、むしろ死の世界ヘ一歩足を踏み入れた人が、死の側から生を見ている体験だといってもよいだろう。アウラ体験もそれと同じく、すでに開始された発作によって否応なく永遠の非日常性の世界へ拉致されようとしている人が、非日常性の側から日常性の世界を見ている光景である。つまりそこでは、日常の生の世界とはまったく別種の、それとは絶対に比量しえない『時間』が支配していて、この別種の『時間』の相のもとに生が照らし出された姿が、アウラ体験なのである。」
永遠が日常性との関係で意識されるとき、それは必ず「永遠の瞬間」あるいは「永遠の現在」として現前する。
永遠がその圧倒的なリアリティをもって襲いかかってくるのは、このような「永遠の瞬間」としての「いま」以外には考えられない。
先にも引用したマンフレートは『真実のゴッホ ある精神科医の考察』所収の『視覚的アウラ(前兆)、ゴツホの場合も妥当するだろうか?』という小文の中で、モーリス・レミーという脳波の専門家が出会った三七歳の女性患者C嬢の症例を紹介している。 C嬢の一家に癲癇病者は皆無で、彼女の両親は二人とも実生活に疎いインテリだった。本を読むことに没頭して、子供たちの教育をなおざりにし、子供たちの世話を召使いたちに委ねていたという。
C嬢は3歳のとき中耳炎を患い、さらに髄膜炎に苦しんだ。6歳で頭蓋骨骨折で意識を失ったことがあり、16歳のときに百日咳にかかったあと脳炎を患った。この頃はじめて局在徴候なしの典型的癲癇発作が起こったという。発作と発作とのあいだ、彼女は衝動的でいらつきがちだった。やがて彼女の情緒的反応が全般的に鈍くなり、記憶障害が起こり、気持ちの集中すらできなくなった。両親が死ぬと、汚い下宿に移って犬猫を飼い、まともな食事も摂らず自堕落な生活を送っていた。その後マルゼンスの州立治療療育院に収容されねと、彼女は過敏で風変わり、同時に粘着質の過度な正義感と自己中心的傾向を示した。目にしたものをペンや絵具で描く才能に周囲が興味を示すと、彼女は個々のアウラについて言葉で表現するようになった。
――最初、頭が割れるような気持ちがして、人間には耐え切れないと思われるほどの猛烈な苦痛に襲われる。それは何の前触れもなくやって来て、その瞬間に彼女は自身の最良と思われる絵を破り、お気に入りのものも含めてレコード盤などを叩き壊してしまう。「頭痛がはじまると同時に幻覚に見舞われるが、それは心躍らせる多彩な幻視のかたちをとる。すると限りなく幸福な思いがして、まったく思いもかけず至高かつ至福の状態へと拉し去られたように感ずる。彼女はそれを天国的な瞬間と感じ、この世ならぬ快楽を享受している気持ちになる。するともう二度と再び、ふだんの生活にはもどりたくないと思う。」この状態はあまりにもこの世ならぬ素晴らしさなので、とても言葉では表わせない。「色鮮やかな壮麗さと美とにうちのめされる」のである。
これらの幻視体験を、彼女は絵に描いてみようとしたが、結局それは幻視に及びもつかない退屈なものだった。アウラに見舞われているときの彼女は両目を見開いているが、幻視以外に何も目に入らない。彼女が見るのはたくさんの星、極楽鳥、微妙に色合いを変化させたバラの花環、色鮮やかな紋様などである。紋様はアーチ状に勤いている。そして風景と星、極楽鳥と色彩、そのすべてが回転木馬に乗っているように彼女をめぐって回転する。この瞬間の至福感のためならば、一切を何を投げうってもいいと彼女は思う。心を不安にさせるものを何も感じず、あるときは望遠鏡のようなもので何千光年もの時空を透視している気がして、死ぬしかないとさえ思ったという。
そして、このような幻視体験を得るためには、高い代価を支払わねばならない、と彼女は言う。ひとたび至福の絶頂に達すると、内部で旋回の度を早める渦動が起こりはじめ、頭に湿った布を巻かれたような感じがする。そして世界の終わりを迎えるかのような不安に襲われる。凍え死ぬかのような感じで、頭に一撃を受けて気を失うかのようである。この状態から覚めるすこし前からだろうか、何か音楽のようなものが聞こえていて、それもしかし曖昧で、記憶が数時間にわたって混迷しているため、前後不覚の状態である。
《彼女の絵は稀蔵本となって、束の関に過ぎゆくアウラ体験をとらえて諭じているモーリス・レミーの著書中に収録されている。それらを目にすると、彼女の絵をかたちづくっているありようが何とファン・ゴッホの絵と類を同じくすることかと、奇異の念に襲われる。彼女にフィンセントのような造形力と芸術的表現力が欠如するのは確かだが、私たちはおのずから次のように自問自答せざるを得ない。ファン・ゴッホはどの程度まで自らの内的幻視を絵に表現しおおせたのだろうか、そして、あの糸杉も、アウラの火焔が翻案されたものだったのだろうか?
》(マンフレート・イン・デア・ベーク『真実のゴッホ ある精神科医の考察』)
《星月夜》はサン=レミ時代の代表作であるばかりでなく、ゴッホの作品中屈指の名作であるが、たんなる風景画ではなく、感情の起伏がそのまま絵筆のタッチと化したかのような特異さのため、ゴッホの心理状態を象徴する絵として、さまざまな読み解きがなされている。
療養所から見た風景がもとになっているというが、写実そのものではない。糸杉はオリーヴとともに彼が好んだ樹木だが、焔の如く夜空を斬り裂いて、その向こうに渦巻く星と月は、恐ろしいエネルギーをたたえながら、その旋回するダイナミズムによって全風景を席巻している。まるで宇宙の秘められた力が激しく流動しているかのようでありながら、同時にふしぎと静謐な印象もある。タッチは素早く、ためらう様子が感じられない。
この作品の「現前」によって表現されているのは、幻視家ゴッホが天空の無限を眺望している「いま」の様相である。星々は粗野なまでに拡大されながらも、有機的な存在感を示して、寄り添ってくるかのようである。その様態には万物流転の秘匿された深奥の秩序さえ感じられる。《 この絵の雰囲気は宿命をはらんでいる。星形をなし、環をなし、迷路をなす形とうねりとが、天空に跳梁する雲から遠ざかろうとしているのか、それに近づこうとしているのかは決めがたく、絵に見入る者の意識の緊張状態で遠ざかるようにも近づくようにも見える。》(同右)
いずれにしても、この絵は、見る者に自己との位置関係を強く意識させるのである。一般的にアウラ体験者が積極的にその体験を表現することは稀で、アウラ体験者自身によってすら、その重要性が認識されることはない。仮に彼らが自らの体験を言葉によって伝えようとしても、適切な言葉を見つけるのが困難な場合が多い。先に引用したドストエフスキーの記述は、稀な体験報告といえる。そしてゴッホの《星月夜》にも、そのような希有な体験の「いま」が表現されているのである。
ゴッホ ―― メニエール病とアウラ体験____1

ゴッホ ―― メニエール病とアウラ体験____2

ゴッホ ―― メニエール病とアウラ体験____3

ゴッホ ―― メニエール病とアウラ体験____4

ゴッホ ―― メニエール病とアウラ体験____5

ゴッホ ―― メニエール病とアウラ体験____6

ゴッホ ―― メニエール病とアウラ体験____7

こうし経緯があって、89年5月までつづくアルル時代は、結果的にゴッホの制作が飛躍的な展開をとげ、その画作の頂点となる作品が制作された時期である。
アルル駅の近くのラマルティーヌ広場にあるジョゼフ・ジヌーが経営する「カフェ・ド・ラ・ガール」に下宿していた彼は、制作のかたわら、この土地に芸術家たちの共同体をつくって共同生活をするという考えに夢中になった。
パリの画家仲間十数人に手紙を送るなどして、5月、3軒隣の家を借り受け、少しずつ手を入れ、9月から移り住んだ。ヴィンセント自らがその外壁を黄色く塗ったのは、黄色が神の光明のしるしだと信じていたからだった。そして10月、テオに借金があったゴーガンがその返済のかわりに、この「黄色い家」にやって来た。
ゴーガンはタヒチヘ行く前の短期間を過ごすつもりだったようだが、ヴィンセントはそれよりも長い期間の共同生活を望んでいたようである。しかし結局、強烈な個性は互いに相いれず、12月になるとゴーガンは、ヴィンセントとの共同生活に限界を感じ、パリに帰ることを考えるようになった。彼はある晩、カフェでアブサンを飲んでいたが、突然グラスごとゴーガンの顔めがけて投げつけたという。その直後にヴィンセントは、テオからの手紙で弟が婚約したことを知らされる。ゴーガンの回想録によると、共同生活9週目の12月23日の夜、夕食の後で散歩に出ると、まもなく背後に聞き慣れた小刻みな足取り近づいて来たので振り向くと、刃を立てた剃刀を手にしたヴィンセントが飛びかかってきた。ゴーガンが睨みつけると、彼は立ち竦み、首を項垂れて走り去ったという。「黄色い家」に戻ったヴィンセントは、左耳の下部――耳たぶを切り取ると、止血をしてからベレー帽をかぶって、それを馴染みの娼婦ラシェルに贈った。その後彼は家に戻り、窓の鎧戸を下ろしてベッドにもぐり込んだ。この「耳切り事件」はゴーガンを同情させて引き止めるためともいわれ、またゴーガンから自画像の耳の形がおかしいと指摘されたことに激怒した結果ともいわれている。
翌朝ヴィンセントは癲癇発作を起こして意識不明の状態でいるところを警察に発見されて病院に運ばれた。ゴーガンは荷物をまとめてアルルを去った。テオはゴーガンの電報を受けて、クリスマス・イブに夜行列車でアルルに急いだ。
2週間後の1月7日にゴッホは退院して「黄色い家」に戻った。平静を取り戻すと、「親愛なる友」ゴーガンに手紙を書き、レー医師の肖像や、耳に包帯をした自画像2点を描き、またルーラン夫人をモデルに《子守女》(《ゆりかごを揺らす女》)を描いた。だがやがてふたたび癲癇発作が起こった。2月7日に入院、10日後に仮退院したものの、周囲の住民たちに「耳切り事件」は知れ渡っていて、彼は危険人物と見做され、この「赤毛の狂人」を病院へ収容する嘆願書が警察に提出され、2月26日になって彼はまたもや病院に収容され、3月23日まで独房に閉じ込められていたが、やがて日中だけ付添人と外出することを許されると、絵の制作を再開した。地元の少年たちは彼を「狂人」と揶揄して「黄色い家」にまで追いかれて来て石を投げつけた。
4月17日にテオがヨハンナ・ボンゲル(通称ヨー)と結婚。同月下旬、サル牧師から聞いたサン=レミの精神病院(サン=ポール・ド・モソル)に移る気持ちになり、テオに転院の手続をとってほしいと手紙で頼んだ。5月8日になって、そのサル牧師に伴われ、アルルから25キロほど北東にあるサン=レミの精神病院に入院。1年間の入院生活がはじまる。
広いとはいえない病室にはベッドがひとつ、窓には当然、鉄格子が嵌っていた。担当医が絵の制作を許可したので、テオは兄のアトリエとして庭が見える部屋を借り、2部屋分を支払った。入院翌月の7月5日、ヴィンセントはヨーが妊娠したことを知らされ、その翌日に野外制作中に激しい発作を起こして意識を失った。7月の間じゅう錯乱状態がつづいた。8月になるとひどく衰弱し、毒性の絵具を口にしたり、ランプの油を飲むなどしたため、当面アトリエに入ることが禁止された。翌月には絵筆を手にすることができたが、ヨーの出産が近づいた12月、またしても錯乱して絵具を喰らおうしたので、医者は絵具を没収し、スケッチだけを認めた。
10月に彼はブリュッセルの〈第8回20人展〉に出品の招待を受け、翌年1月18日に開催された同展に出品した6点のうち《赤いぶどう畑》(88年制作)1点が400ベルギーフランで売れた。生前に売れたのはこの1点のみだった。
結局、サン=レミの病院では4回にわたって発作と脱力状態にみまわれているものの、創作意欲は失われず、発作の合間を縫っていくつかの代表作が制作された。この時期には彼の内面の不安が形態や筆致、テーマなどによって激しく先鋭化し、その情念が大地や糸杉や夜空などに象徴化されている。――ヨーロッパでは糸杉は死の象徴と結びついているが、ヴィンセントは意に介さなかった。《星月夜》(89年6月)《糸杉》(89年6月)《星月夜の糸杉のある道》(90年5月)などを含む300点以上の油彩と素描が、このサン=レミ時代に制作されている。
入院中、彼は繰り返し癲癇発作と精神的危機に見舞われ、その間には悲鳴をあげ、絶叫もしたが、意識が戻ると、その記憶はまったく残っていなかった。しかし彼は院内での様子を見て、他の精神病息者たちから悪影響を受けて、自分もやがて同じような死に方をするのではないかという不安が強まり、またサン=ポール・ド・モソルでの治療では回復の見込みがもてないと考え、90年5月、医師ポール・ガシェの滞在するオーベル・シュル・オワーズに移った。当初ヴィンセントはガシェ博士の家に近いオテル・サントーバンに宿泊していたが、やがてラ・メール広場のカフェ・ラヴーの2階の1室に移り住んだ。最初のうち、ヴィンセントはガシェ博士と気が合って、しばしば招かれて制作もした。7月6日、ヴィンセントはパリに出てロートレックやベルナール、評論家オーリエらとの再会を果たした。この直後、ガシェの娘マルグリットに求愛して拒否されたという説があり、ガシェ博士との仲も冷え切っていた。この時期の作品《麦畑のうえの烏》あるいは《荒れ模様の空と畑》などには、不気味な死の影が色濃くただよっている。彼の精神状態に動揺を与えていたことのひとつには、終生彼を援助した弟テオの、画商としての経営の行き詰まりがあったようである。7月27日の夕方、彼は麦畑の中でピストル自殺を遂行、胸部(腹部とも)を貫いた弾丸はわずかに急所をそれ、重傷ながらヴィンセントは自力で下宿のアトリエに戻った。ガシュの知らせでテオが翌朝パリから駆け付けた。28日にはヴィンセントの容態は落ち着きを取り戻したかに見えた。彼はパイプをくゆらせ、「精神まったく明晰で」テオと穏やかに語り合ってもいた。しかし夜半になって急変し、29日午前1時半、静かに息をひきとった。――「悲しみはいつまでも続く……」という最後の言葉を残して。
死の前に彼はゴーガンに次のように書き送っている。
「あなたという人を知り、あなたにいらざる苦痛を与えた僕であるから、面目ない状態で生きのびるより明晰な精神状態のまま死を迎えるほうが人間らしい品位を保てるというものだ」
37年の短い生涯のうちの、約10年ほどの画歴のなかで850点以上の油彩作品を制作したゴッホの病歴については、従来から癲癇性発作や精神病などがいわれてきたが、その他にも数多くの仮説があり、それらを排除して医学的診断および精神医学的診断を確定するにはいたっていない。
サン=レミ療養所の医師ペイロンは、89年5月9日付けの文書で「散発的に見舞われるてんかん性発作」という所見を述べている。これはアルル時代にヴィンセントを看護したレー医師の診断を支持するものだった。
《ゴッホがてんかん患者であったとする診断は、フランスを除いては定着していなかった。ドイツでは、ゴッホの苦悩の生涯の縦糸をたどって、てんかんの典型的発作が認められないとして、ゴッホてんかん説はまともに取り上げられなかった。この点ドイツでやっと一歩を進めたのがクライストで、彼はゴッホの生涯にエピソードとして語られる朦朧状態に言及して説をうちたてた。ヤスパース、それにプリンツホルンも、自由な考え方によって在来の説の轍を脱するにしてはいわばあまりに固定観念にとらわれていた。哲学をライフ・ワークとしたヤスパースは、それから二、三〇年後の時点で、ゴッホの精神分裂症説をてんかん説に転轍する余裕がなく、プリンツホルンも、一九二二年にオスロにエヴァンゼンを訪ねた際、そのことを指摘されながらも自説を撤回しなかった次第については、一九二六年のクレペリン祝賀記念論文集にはっきり記されている。
ゴッホが精神的な朦朧状態と突発的な狂騒状態に陥ることがあった事実をみて、フランスの医師たちが早い時点でてんかんの症候であると診断を下せたのはなぜだろうか? おそらくひとつには一九世紀半ばのフランスの精神科医たちが名声噴々であったこともあるが、また実際に精神病理学的知見に関して他のヨーロッパ諸国の医師たちに彼らが立ちまさっていたことにも求められよう。当時すでに、フランスの精神医学者の泰斗たちが、痙攣症、てんかんおよびてんかん類似の病状に関心を寄せていた。一八三八年にはエスキロールが、痙攣状態に立ち入らずにではあるが、てんかん症候群の記述に手をつけていたし、一八六〇年にはモレルが、「てんかんでないてんかん」として記述している。
この一八六〇年にはファルレも、「精神的小発作」を病理学的に他の病気と境界を画して命名している。彼がこう名づけたものは、患者がもの静かに暮しながらも時に陥る精神の錯乱状態で、今日ではいわば正気を失わないせん妄状態と称されているものである。ファルレにいわせれば、この症状に見舞われた者が後になって生活のエピソードとして思い出す一状態とは次のようなものである。患者は多少とも持続して頭の働きが鈍くなりふさぎこんで、観念連合が不活発になって知覚の統合がままならず、不安感を抱き、離人症体験に苦しめられる。彼によれば、潜伏性の経過は以上のような現われによって特徴づけられる。臨床的に観察された患者は、一種の麻酔状態と朦朧状態との意識の幅のあいだのさまざまな様相を呈し、操り人形的挙動と仮性躁病的なはしゃぎ状態を伴っていた。
この「精神的小発作」とならんでファルレは二つ目の精神錯乱状態を区別したが、こちらの特徴は、今までのもの静かさの堰が切れて、錯乱と由々しい狂騒におびただしい幻覚症状が伴うものである。つまり、「精神的大発作」である。この場合は、端緒をなすのが精神運動性の危機で、つづいて躁病的な猛々しいまでの錯乱状態を現出することがあって、通常、これによって最終的には疲労困憊と終末睡眠に陥る。また症候学的に見れば、健忘を伴うような程度の錯乱状態となる。場合によってはなはだしい狂騒状態のつづく数日後、患者はずっと疲労衰弱状態に落ち込む。激越な危機的状態については、彼らのうちには何の記憶も残らない。しかしこれにつづく完全な疲弊状態のときの記憶は残りつづける。潜行性の具体的な印象や、幻視的性格を帯びた幻覚過程ははっきり記憶に留まっていて、その記述が可能である。》(マンフレート・イン・デア・ベーク『真実のゴッホ ある精神科医の考察』/徳田良仁訳)
ゴッホの生前、まず検討されるのが常だった進行麻痺は、現在では明らかに否定されている。また当時さかんに議論された神経病的兆候は、臨床的には認められていない。精神病理学的にも、ゴッホが歩んだ生涯の概要は、さまざまな症状を伴った進行麻痺という伝染病を立証するものではない。精神分裂病に関しては、彼の残した38枚の自画像を並べて見ても、どこにも均衡を失った要素はなく、精神分裂病と断定できるフォルムも見出されないという。
85年末から翌年初頭にかけて、ゴッホはベルギーのアントワープに滞在していたが、この時期に彼は梅毒と診断されて治療を受けていることから、W・ランゲ=アイヒバウムは「急性梅毒性分裂・てんかん様障害」と診断している。またこの頃からつづくパリ時代にかけて、彼はアブサンを多量に摂取するようになった。アブサンの原料であるニガヨモギに含まれるツジョンという有毒成分は、振戦譫妄、癲癇性痙攣、幻聴などのアルコール中毒を引き起こすことが知られている。サン=レミの精神病院で彼が絵具のチューブの中身を飲み込んだりしたのは、溶剤のテレビン油をがツジョンと似ているせいだという指摘もある。
1979年、安田宏一博士は、ゴッホと弟テオとの間で取り交わされた数百通の手紙を分析した結果、今まで精神病とされてきたゴッホの病気が「メニエール病」だったという新説を発表し、欧米にも紹介された。ゴッホの手紙には回転性のめまい、吐き気、左の耳鳴り、難聴など、メニエール病特有の症状が書かれているが、このメニエール病説の実例として上げられているのが《星月夜》で、この絵の特徴のうねるように渦を巻く夜空が、水平・回旋混合性の眩暈――眼振をあらわし、メニエール病などの内耳疾患にみられる眩暈に特徴的なものであるという。
ゴッホは日頃から、何の前ぶれもなくやってくる激しい回転性の眩暈、強い吐き気、耳鳴り、難聴などの発作に悩まされていた。ゴーガンとの共同生活に入った頃には病気もかなり進行し、左耳にはつねに気が変になるかと思うほどの耳鳴り、あるいは難聴があったと思われる。耳切り事件のときも、ゴッホは発作に襲われていたのかもしれない。――傍らにいたゴーガンは、ゴッホが眩暈と吐き気、嘔吐に苦しむのを見て、薄気味悪くなり、彼を見捨てて行ってしまう。残されたゴッホは、寂しさのなかで、自分を理解してくれる酒場の娼婦に、耳鳴りのする左の耳たぶを削ぎ落として捧げた。――経験者でなければ理解できない眩暈の苦しみは、ときに突然襲いかかり、突然去ってゆく。その様子を目にする他人たちには、精神病の発作と見まがうばかりの不気味な印象があるのかもしれない。
メニエール病は、病原因不明の内リンパ水腫に起因する眩暈、耳鳴り、耳閉塞感、難聴などを主症状としている。メニエール病の名は、1861年にフランスの医師メニエール(1799~1862)が、発作性の眩暈に耳鳴りと難聴をともなう患者を解剖し、発表して以来、眩暈を訴える内耳疾患の患者に対して、メニエール症候群とかメニエール病という診断が下されるようになった。だがその後、疾患に種々の多様性があることが判明し、メニエール症候群という名称はしだいに使用されなくなり、内耳の中に存在する内リンパ液の圧が高くなる内リンパ水腫に起因する疾患のみを、メニエール病というようになった。
厳密に区別されるべきメニエール病は、度重なる眩暈の発作に、必ず耳鳴りと難聴をともなう内耳の病気であり、脳の疾患から生ずる神経の症状がまったくないことが条件となる。内リンパ水腫の原因については、体内の電解質調節障害、水分代謝障害、ホルモンの異常、塩分貯留説、アレルギー説、交感神経の過敏による血管収縮説などが云々されるが、まだ確定されてはいない。
典型的なメニエール病では、特別の誘因もなく突然、耳鳴りや難聴が生じると、激しい眩暈が起こる。これに耳閉感がともなうこともある。眩暈の発作中、気分が悪く、冷や汗をかいたり、吐き気や嘔吐をともなう。眩暈には、外界や自分の体が回転しているような感じのものが多いが、意識障害はなく、数分から数時間ほどつづくと、激しい眩暈はなくなる。頭や体を動かすと、短時間の軽い眩暈感は数日間残る。耳鳴りと難聴は回復することもあるが、残存するか進行することが多く、眩暈発作が反復する特徴がある。そのため、難聴は眩暈発作のたびに増悪し、高度になっていく。
メニエール病における難聴は、内耳性の感音難聴である。その他の随伴症状として、心悸亢進、頭重感、頭痛、肩こり、また精神の不安状態に陥ることもある。眩暈発作などがない時期を間欠期、休止期などというが、患者は休止期が終わって眩暈発作がまた突然起こるのではないかと、精神的に不安な状態にみまわれるのである。
メニエール病に似た症状を示す疾患には、多くのバリエーションがある。一回だけの発作で高度な難聴となり、激しいめまいを起こす突発性難聴、耳鳴りや難聴などは伴わないが、激しい眩暈発作を一回だけ起こす前庭神経炎、眩暈とともに物体が二重に見える複視、言語障害、ある種の意識障害や失認などが、メニエール病の症状と重なるものを共有している。
――またこのメニエール病説との関連で、彼が度重なる激しい発作の合間に、極めて冷静に制作していたことから、そのアウラ体験が注目される。
ゴッホのアウラ体験を考える前に、文学的な一例を挙げよう。
ドストエフスキーはアウラ体験を有する癲癇患者でありながら、その緊迫した体験を作品の中に克明に再現していることが知られている。
《ある数秒間があるのだ、――それは一度に五秒か、六秒しか続かないが、そのとき忽然として、完全に獲得されたる永久調和の存在を、直感するのだ。これはもはや地上のものではない。といって、何も天上のものだというわけじゃない。つまり、現在のままの人間には、とうていもちきれないという意味なんだ。どうしても生理的に変化するか、それとも死んでしまうか、二つに一つだ。それは論駁の余地のないほど明白な心持ちなんだ。まるで、とつぜん全宇宙を直感して、『しかり、そは正し』といったような心持ちなんだ。……何よりも恐ろしいのは、それが素敵にはっきりしていて、なんともいえないよろこびが溢れていることなんだ。もし十秒以上つづいたら、魂はもう持ち切れなくて、消滅してしまわなければならない。ぼくはこの五秒間に一つの生を生きるのだ。そのためには、一生を投げ出しても惜しくない。それだけの価値があるんだからね!(ドストエフスキイ『悪霊』米川正夫訳)》
木村敏氏は『時間と自己』の中で、このキリーロフの言葉を引用しながら、次のように書いている。「これは死の直前の、生から死への参入の体験というよりは、むしろ死の世界ヘ一歩足を踏み入れた人が、死の側から生を見ている体験だといってもよいだろう。アウラ体験もそれと同じく、すでに開始された発作によって否応なく永遠の非日常性の世界へ拉致されようとしている人が、非日常性の側から日常性の世界を見ている光景である。つまりそこでは、日常の生の世界とはまったく別種の、それとは絶対に比量しえない『時間』が支配していて、この別種の『時間』の相のもとに生が照らし出された姿が、アウラ体験なのである。」
永遠が日常性との関係で意識されるとき、それは必ず「永遠の瞬間」あるいは「永遠の現在」として現前する。
永遠がその圧倒的なリアリティをもって襲いかかってくるのは、このような「永遠の瞬間」としての「いま」以外には考えられない。
先にも引用したマンフレートは『真実のゴッホ ある精神科医の考察』所収の『視覚的アウラ(前兆)、ゴツホの場合も妥当するだろうか?』という小文の中で、モーリス・レミーという脳波の専門家が出会った三七歳の女性患者C嬢の症例を紹介している。 C嬢の一家に癲癇病者は皆無で、彼女の両親は二人とも実生活に疎いインテリだった。本を読むことに没頭して、子供たちの教育をなおざりにし、子供たちの世話を召使いたちに委ねていたという。
C嬢は3歳のとき中耳炎を患い、さらに髄膜炎に苦しんだ。6歳で頭蓋骨骨折で意識を失ったことがあり、16歳のときに百日咳にかかったあと脳炎を患った。この頃はじめて局在徴候なしの典型的癲癇発作が起こったという。発作と発作とのあいだ、彼女は衝動的でいらつきがちだった。やがて彼女の情緒的反応が全般的に鈍くなり、記憶障害が起こり、気持ちの集中すらできなくなった。両親が死ぬと、汚い下宿に移って犬猫を飼い、まともな食事も摂らず自堕落な生活を送っていた。その後マルゼンスの州立治療療育院に収容されねと、彼女は過敏で風変わり、同時に粘着質の過度な正義感と自己中心的傾向を示した。目にしたものをペンや絵具で描く才能に周囲が興味を示すと、彼女は個々のアウラについて言葉で表現するようになった。
――最初、頭が割れるような気持ちがして、人間には耐え切れないと思われるほどの猛烈な苦痛に襲われる。それは何の前触れもなくやって来て、その瞬間に彼女は自身の最良と思われる絵を破り、お気に入りのものも含めてレコード盤などを叩き壊してしまう。「頭痛がはじまると同時に幻覚に見舞われるが、それは心躍らせる多彩な幻視のかたちをとる。すると限りなく幸福な思いがして、まったく思いもかけず至高かつ至福の状態へと拉し去られたように感ずる。彼女はそれを天国的な瞬間と感じ、この世ならぬ快楽を享受している気持ちになる。するともう二度と再び、ふだんの生活にはもどりたくないと思う。」この状態はあまりにもこの世ならぬ素晴らしさなので、とても言葉では表わせない。「色鮮やかな壮麗さと美とにうちのめされる」のである。
これらの幻視体験を、彼女は絵に描いてみようとしたが、結局それは幻視に及びもつかない退屈なものだった。アウラに見舞われているときの彼女は両目を見開いているが、幻視以外に何も目に入らない。彼女が見るのはたくさんの星、極楽鳥、微妙に色合いを変化させたバラの花環、色鮮やかな紋様などである。紋様はアーチ状に勤いている。そして風景と星、極楽鳥と色彩、そのすべてが回転木馬に乗っているように彼女をめぐって回転する。この瞬間の至福感のためならば、一切を何を投げうってもいいと彼女は思う。心を不安にさせるものを何も感じず、あるときは望遠鏡のようなもので何千光年もの時空を透視している気がして、死ぬしかないとさえ思ったという。
そして、このような幻視体験を得るためには、高い代価を支払わねばならない、と彼女は言う。ひとたび至福の絶頂に達すると、内部で旋回の度を早める渦動が起こりはじめ、頭に湿った布を巻かれたような感じがする。そして世界の終わりを迎えるかのような不安に襲われる。凍え死ぬかのような感じで、頭に一撃を受けて気を失うかのようである。この状態から覚めるすこし前からだろうか、何か音楽のようなものが聞こえていて、それもしかし曖昧で、記憶が数時間にわたって混迷しているため、前後不覚の状態である。
《彼女の絵は稀蔵本となって、束の関に過ぎゆくアウラ体験をとらえて諭じているモーリス・レミーの著書中に収録されている。それらを目にすると、彼女の絵をかたちづくっているありようが何とファン・ゴッホの絵と類を同じくすることかと、奇異の念に襲われる。彼女にフィンセントのような造形力と芸術的表現力が欠如するのは確かだが、私たちはおのずから次のように自問自答せざるを得ない。ファン・ゴッホはどの程度まで自らの内的幻視を絵に表現しおおせたのだろうか、そして、あの糸杉も、アウラの火焔が翻案されたものだったのだろうか?
》(マンフレート・イン・デア・ベーク『真実のゴッホ ある精神科医の考察』)
《星月夜》はサン=レミ時代の代表作であるばかりでなく、ゴッホの作品中屈指の名作であるが、たんなる風景画ではなく、感情の起伏がそのまま絵筆のタッチと化したかのような特異さのため、ゴッホの心理状態を象徴する絵として、さまざまな読み解きがなされている。
療養所から見た風景がもとになっているというが、写実そのものではない。糸杉はオリーヴとともに彼が好んだ樹木だが、焔の如く夜空を斬り裂いて、その向こうに渦巻く星と月は、恐ろしいエネルギーをたたえながら、その旋回するダイナミズムによって全風景を席巻している。まるで宇宙の秘められた力が激しく流動しているかのようでありながら、同時にふしぎと静謐な印象もある。タッチは素早く、ためらう様子が感じられない。
この作品の「現前」によって表現されているのは、幻視家ゴッホが天空の無限を眺望している「いま」の様相である。星々は粗野なまでに拡大されながらも、有機的な存在感を示して、寄り添ってくるかのようである。その様態には万物流転の秘匿された深奥の秩序さえ感じられる。《 この絵の雰囲気は宿命をはらんでいる。星形をなし、環をなし、迷路をなす形とうねりとが、天空に跳梁する雲から遠ざかろうとしているのか、それに近づこうとしているのかは決めがたく、絵に見入る者の意識の緊張状態で遠ざかるようにも近づくようにも見える。》(同右)
いずれにしても、この絵は、見る者に自己との位置関係を強く意識させるのである。一般的にアウラ体験者が積極的にその体験を表現することは稀で、アウラ体験者自身によってすら、その重要性が認識されることはない。仮に彼らが自らの体験を言葉によって伝えようとしても、適切な言葉を見つけるのが困難な場合が多い。先に引用したドストエフスキーの記述は、稀な体験報告といえる。そしてゴッホの《星月夜》にも、そのような希有な体験の「いま」が表現されているのである。
ゴッホ ―― メニエール病とアウラ体験____1

ゴッホ ―― メニエール病とアウラ体験____2

ゴッホ ―― メニエール病とアウラ体験____3

ゴッホ ―― メニエール病とアウラ体験____4

ゴッホ ―― メニエール病とアウラ体験____5

ゴッホ ―― メニエール病とアウラ体験____6

ゴッホ ―― メニエール病とアウラ体験____7