1976年刊行の吉村昭のドキュメンタリー小説。
江戸時代(1780年代)に時化で遭難し、
太平洋の無人島に流れ着いた漂流者の実話に基づいた話。
1785年の1月30日、土佐の船乗り長平の乗った船は
救援物資の米を届けた帰りに時化に遭い難破し、
嵐の中、乗組員4人は漂流の末にある島に流れ着いた。
岩石に覆われた島は無人島で樹木は少なかった。
島を探索し大きな鳥が生息している一帯を見つけ、
その鳥を食料として生き延びる。
この辺りで、鳥島だと思った。
鳥島は伊豆諸島にあり東京の沖合い約580Km、
八丈島から約300Km南にあり、
難破した船が流れ着いた事がたびたびあった事は、
長平たちが島内を探索して白骨や漂流物を発見した事から解る。
長平が乗った船が嵐に巻き込まれ難破するところも壮絶だが、
鳥島に流れ着いてからの方がさらに壮絶であった。
漂流と言うタイトルは単に海を漂っているのではなく、
島に流れ着いてからも生きて行くために漂いながら努力している事をも指す。
長平が鳥島に辿り着いた後、1年以内に3人が栄養失調で死に、
1人生き残った長平は絶望して死ぬことも考えたが、
生きることを選び、知恵を働かせて生き延びる。
登場する鳥はアホウドリで渡り鳥であるために、
旅立つまでに干し肉を蓄える。鶏肉だけでは栄養が偏るので、
海で貝や蟹、魚や海藻なども取り、卵の殻で雨水を溜めて、
体力が落ちないように歩き、羽毛で着物を作り寒さをしのいだ。
3年後の1月に備前の船が難破し11人が漂着、
さらに2年後に日向線の6人が漂着した。
長平はサバイバル術を伝授し、漂着した人たちの所有物から、
生きるためには船を造る事を考える。
中には知恵や経験のある人もおり、
手先が器用な人もいたため、流れつく難破船の一部を利用し、
5年後に生存者14人が乗れる船が完成する。
天候を見極めて島を後にした14人は、
途中で青ヶ島へ辿り着き、そこに生活していた2人を乗せ、
70km先の八丈島へ渡る。
遭難から12年4か月経ち長平は36歳になっていたが、
1798年1月、故郷に帰った。その後、結婚し子供も生まれ、
無人島での経験を語り60歳で生涯を終えた。
私もインド生活はサバイバルだったと思ってたけど、
世の中にはもっともっと凄い人がいたものだ。
この本の冒頭で、グアム島の横井正一さん、
ルバング等の小野田寛郎さんの事にも触れられていたので、
ちょっとググってみたのだが、私の記憶や認識が間違っていた事が判った。
グアム島で28年の横井さんは陸軍の軍曹(下士官)であり、
穴を掘って隠れていた(逃げていた)のだった。
ルバング島で29年の小野田さんは少尉(将校=指揮官)であり、
相当数の武器を持ってジャングルに定住せず潜んで戦っていた。
時折、村を襲って物品を略奪する山賊のような生活をしていた。
生きるためにと言えばそれまでであるが。
警官隊や村人と撃ち合いになった事も数回あり、
戦争が終わった事を知らず戦っていた・・・と言う事だし・・・
戦争が生んだ悲劇と片づける事もできるが。






















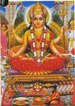





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます