あなおそロシア…3
スターリン信奉者プーチンの登場(1)
ロシア人は非常にプライドが高く、インテリでさえ自分達は他の民族よりも優れて居り、ロシアは特別な国であると信じている節がある。この為帝政ロシア時代も、社会主義ソ連の時代も、そして凋落した今のロシアでさえ、大国である、或いは大国として存在したいという厄介な国・傍迷惑な国、それががロシアであり、誰よりも大国意識が強いのがプーチンなのである。ロシアはあたかもアメリカと対峙する「大国」のように振る舞っており、国際世論の非難の嵐を受けながらも、国際原則を平気で無視する行動をとり続けるのは、ロシアは大国だから誰に遠慮する必要も無い、名実共に大国であることを確固たるものにする為の必要不可欠な行為なのであると、強く信じ切っているからである。その信念は幼少期からの経験に基づく所が大きい。プーチンの青少年期1960~70年代のソ連は絶好調で、『ガガーリンによる世界初の有人宇宙飛行』を成功させ宇宙技術は世界トップ、73年と79年にはオイルショックによる原油価格の高騰により、ソ連経済は順調に成長を重ねていた。同時期アメリカはベトナム戦争にも完敗し、疲弊して活気を失っていたこともありロシア人の多くは「まもなく米国を追い越せる」と信じ切っていた時期でもある。
1922年に成立し1991年に崩壊したソ連は、アジアとヨーロッパにまたがる世界最大の多民族国家で、その面積2240万2200平方キロメートルは地球の全陸地面積の6分の1弱を占め、アメリカ合衆国の約2.4倍、日本の約60倍に相当した。100以上の民族が住み、人口は2億9010万(1991)で、中国、インドに次いで世界第3位であった。ロシア連邦になってからは領土は米国の2倍近く、日本の45倍もあるが、人口は1億4400万人強で、日本より2000万人ほど多いに過ぎず、それも年々減少傾向にある。主な産業は、広大な国土から産出される豊かな資源で、原油の生産は世界3位、天然ガスの輸出量は世界一、穀物大国で小麦、大麦、トウモロコシの輸出は世界有数である。宇宙開発においてはトップ級の技術を持ち、日本人宇宙飛行士の多くを国際宇宙ステーション(ISS)に運んだのはロシアのロケットである。ただし、核兵器や宇宙産業のような国策産業以外の技術力では日本や他の先進国より大きく劣って居り、其の為、経済規模を表す国内総生産(GDP)は170兆円ほどで、米国の10分の1以下、日本の3分の1以下、G7(主要7カ国)各国だけでなく韓国をも下回る11位に過ぎない。兵力でも、ソ連崩壊時140万人だったロシア陸軍は28万人(陸上自衛隊の2倍)に減り、別組織の空挺(くうてい)軍と海軍歩兵を加えて地上戦兵力は36万人で、装備も旧式の時代遅れのものが多いと言われている。 そんなロシアが、世界トップとして誇っているのが殺人兵器・核兵器の数である。核弾頭保有数は米国を上回り、プーチンは核兵器の使用を脅迫の道具に使うなど、ロシアにとっては核兵器が「力の源泉」と言えるだろう。この様に見てくると今やロシアが世界に誇れるのは、領土、核兵器、化石燃料、穀物、宇宙開発技術程度で、経済体制、産業構造、技術開発力などの経済力を決定づける基本的な要因から見て『大国』と言える材料は極めて乏しいと言わざるを得ない。
プーチンはロシアがこのような状態に陥ったのは1991年のソ連崩壊に有ると見ており、ソ連崩壊を「20世紀最大の地政学的悲劇」、「歴史的過ち」であると広言し、ソ連邦の復元、ロシア帝国の栄光を取り戻すことが名実ともに『大国』へ復帰する為に不可欠であり、今回のウクライナ侵攻も『失地回復』であると戦争を正当化しているのである。
この様な背景もあって、プーチンが世界で最も尊敬する人物はロシアの近代化と大国化を推進した「ピヨートル1世(大帝)」であると広言している。(大国化はエカテリーナ2世にも引き継がれ、プーチンはこの女帝も褒め称えて居る)
17世紀はじめ(1613年)に成立したロシア・ロマノフ朝は、スウェーデン王国、ポーランド王国に圧迫され、東ヨーロッパでは弱小勢力にすぎなかった。国内では農奴制の上に有力貴族が存在し、産業も未熟で、近代的な軍隊の創設が急がれていた。ロマノフ朝の君主は自国の後進性に気づき、制度・産業の西欧化を進める必要性を痛感し、特にピョートル1世(大帝)は西ヨーロッパ諸国に習った国家の創出をめざし、自ら大視察団の一員に加わって、産業・軍事・税制・官僚制などで特にプロイセンを手本とした改革が行われた。日本・明治維新の岩倉欧米視察団もプロイセンの官僚制を手本として改革を行って居り、服装も和服を改め、ちょん髷を断髪にするなど洋風化を進めたが、ピョートルも外遊から帰国すると、その服装も西欧風に改めた。其の上挨拶にきた貴族を捕まえては、そばに控えた召使に羊毛用のハサミを持たせ、あごひげをちょん切ってしまった。ロシアの貴族は昔からあごひげを蓄える習慣があったが、ピョートルは「新しいロシア」にはそぐわないと、貴族たちのあごひげを切ってしまったのである。
ピヨートルの大国化は目覚しいものがあった。南下政策ではオスマン帝国が支配する黒海沿岸に進出し黒海に繋がるアゾフ海に面したアゾフを奪取して一帯を支配する拠点を構築した。北方政策ではバルト海の覇権をめぐってスウェーデンとの20年の長期に亙る北方戦争を戦い、緒戦に敗れたが、それを機に軍備を整え、バルト海沿岸に面して新都のペテルブルクを建設して長期戦に備え1709年に勝利し1721年講和約を締結してバルト海の制海権を得た。1712年にはサンプト・ペテルブルクを建設して遷都し、西欧への窓口とした。これによって、バルトの覇者としての地歩を確保した。軍備では特に海軍の育成に努め、バルト海沿岸に要塞・基地を建設、これを拠点とするバルチック艦隊を創設した。
日露戦争の際東郷(平八郎)が打ち破ったロシア艦隊は、はるばるこの基地から派遣され、途中物資補給の為の寄港をフランス、英国等が拒否した為、強力艦隊が疲弊し敗戦に繋がったと言われている。
東方進出に付いては、シベリア進出を推し進め、1689年清国の康煕帝との間で国境を画定する条約を締結した。また1697~99年、コサックの隊長にカムチャツカ探検を命じ、日本との通商路を探っている。
プーチンが崇拝するエカテリーナ2世も領土拡大に大きな力を発揮した。オスマン帝国との2度にわたる露土戦争(1768年-1774年、1787年-1791年)に勝利してウクライナの大部分やクリミア・ハン国を併合しバルカン半島進出の基礎(ヤッシーの講和)を築くこととなった。
6月9日、ピョートル大帝の生誕350年記念イベントに出席したプーチンは若手起業家たちとの会合で、こう述べた。 「ピョートル大帝が、新しい首都サンクトペテルブルクを建設した時、ヨーロッパのどの国もロシアの領土と認めなかった。誰もがスウェーデンだと認識していた。しかし、スラブ系の人々がずっと住んでいて、その領土はロシアの支配下にあった。ピョートル大帝は何をしたのか。スエーデンを打ち破り領土を取り返し、国を強化したのだ。それが、彼の行ったことだ。そして、我々も領土を取り返し、国を強化する番だ」。ピョートル大帝は領土を奪ったのではなく「取り戻した」のだと主張し、「自分自身を守るために、戦わなければならないのは明らかだ。350年前とほとんど何も変わっていない」とピョートル大帝と自らを重ね合わせ、ウクライナ侵攻を暗に正当化したのである。プーチンの行動原理は此処に全て集約されて居り、周辺諸国がロシアを恐れる理由もここにある。
スターリン信奉者プーチンの登場(2)…プーチンの目指すもの
スターリン信奉者プーチンの登場(1)
ロシア人は非常にプライドが高く、インテリでさえ自分達は他の民族よりも優れて居り、ロシアは特別な国であると信じている節がある。この為帝政ロシア時代も、社会主義ソ連の時代も、そして凋落した今のロシアでさえ、大国である、或いは大国として存在したいという厄介な国・傍迷惑な国、それががロシアであり、誰よりも大国意識が強いのがプーチンなのである。ロシアはあたかもアメリカと対峙する「大国」のように振る舞っており、国際世論の非難の嵐を受けながらも、国際原則を平気で無視する行動をとり続けるのは、ロシアは大国だから誰に遠慮する必要も無い、名実共に大国であることを確固たるものにする為の必要不可欠な行為なのであると、強く信じ切っているからである。その信念は幼少期からの経験に基づく所が大きい。プーチンの青少年期1960~70年代のソ連は絶好調で、『ガガーリンによる世界初の有人宇宙飛行』を成功させ宇宙技術は世界トップ、73年と79年にはオイルショックによる原油価格の高騰により、ソ連経済は順調に成長を重ねていた。同時期アメリカはベトナム戦争にも完敗し、疲弊して活気を失っていたこともありロシア人の多くは「まもなく米国を追い越せる」と信じ切っていた時期でもある。
1922年に成立し1991年に崩壊したソ連は、アジアとヨーロッパにまたがる世界最大の多民族国家で、その面積2240万2200平方キロメートルは地球の全陸地面積の6分の1弱を占め、アメリカ合衆国の約2.4倍、日本の約60倍に相当した。100以上の民族が住み、人口は2億9010万(1991)で、中国、インドに次いで世界第3位であった。ロシア連邦になってからは領土は米国の2倍近く、日本の45倍もあるが、人口は1億4400万人強で、日本より2000万人ほど多いに過ぎず、それも年々減少傾向にある。主な産業は、広大な国土から産出される豊かな資源で、原油の生産は世界3位、天然ガスの輸出量は世界一、穀物大国で小麦、大麦、トウモロコシの輸出は世界有数である。宇宙開発においてはトップ級の技術を持ち、日本人宇宙飛行士の多くを国際宇宙ステーション(ISS)に運んだのはロシアのロケットである。ただし、核兵器や宇宙産業のような国策産業以外の技術力では日本や他の先進国より大きく劣って居り、其の為、経済規模を表す国内総生産(GDP)は170兆円ほどで、米国の10分の1以下、日本の3分の1以下、G7(主要7カ国)各国だけでなく韓国をも下回る11位に過ぎない。兵力でも、ソ連崩壊時140万人だったロシア陸軍は28万人(陸上自衛隊の2倍)に減り、別組織の空挺(くうてい)軍と海軍歩兵を加えて地上戦兵力は36万人で、装備も旧式の時代遅れのものが多いと言われている。 そんなロシアが、世界トップとして誇っているのが殺人兵器・核兵器の数である。核弾頭保有数は米国を上回り、プーチンは核兵器の使用を脅迫の道具に使うなど、ロシアにとっては核兵器が「力の源泉」と言えるだろう。この様に見てくると今やロシアが世界に誇れるのは、領土、核兵器、化石燃料、穀物、宇宙開発技術程度で、経済体制、産業構造、技術開発力などの経済力を決定づける基本的な要因から見て『大国』と言える材料は極めて乏しいと言わざるを得ない。
プーチンはロシアがこのような状態に陥ったのは1991年のソ連崩壊に有ると見ており、ソ連崩壊を「20世紀最大の地政学的悲劇」、「歴史的過ち」であると広言し、ソ連邦の復元、ロシア帝国の栄光を取り戻すことが名実ともに『大国』へ復帰する為に不可欠であり、今回のウクライナ侵攻も『失地回復』であると戦争を正当化しているのである。
この様な背景もあって、プーチンが世界で最も尊敬する人物はロシアの近代化と大国化を推進した「ピヨートル1世(大帝)」であると広言している。(大国化はエカテリーナ2世にも引き継がれ、プーチンはこの女帝も褒め称えて居る)
17世紀はじめ(1613年)に成立したロシア・ロマノフ朝は、スウェーデン王国、ポーランド王国に圧迫され、東ヨーロッパでは弱小勢力にすぎなかった。国内では農奴制の上に有力貴族が存在し、産業も未熟で、近代的な軍隊の創設が急がれていた。ロマノフ朝の君主は自国の後進性に気づき、制度・産業の西欧化を進める必要性を痛感し、特にピョートル1世(大帝)は西ヨーロッパ諸国に習った国家の創出をめざし、自ら大視察団の一員に加わって、産業・軍事・税制・官僚制などで特にプロイセンを手本とした改革が行われた。日本・明治維新の岩倉欧米視察団もプロイセンの官僚制を手本として改革を行って居り、服装も和服を改め、ちょん髷を断髪にするなど洋風化を進めたが、ピョートルも外遊から帰国すると、その服装も西欧風に改めた。其の上挨拶にきた貴族を捕まえては、そばに控えた召使に羊毛用のハサミを持たせ、あごひげをちょん切ってしまった。ロシアの貴族は昔からあごひげを蓄える習慣があったが、ピョートルは「新しいロシア」にはそぐわないと、貴族たちのあごひげを切ってしまったのである。
ピヨートルの大国化は目覚しいものがあった。南下政策ではオスマン帝国が支配する黒海沿岸に進出し黒海に繋がるアゾフ海に面したアゾフを奪取して一帯を支配する拠点を構築した。北方政策ではバルト海の覇権をめぐってスウェーデンとの20年の長期に亙る北方戦争を戦い、緒戦に敗れたが、それを機に軍備を整え、バルト海沿岸に面して新都のペテルブルクを建設して長期戦に備え1709年に勝利し1721年講和約を締結してバルト海の制海権を得た。1712年にはサンプト・ペテルブルクを建設して遷都し、西欧への窓口とした。これによって、バルトの覇者としての地歩を確保した。軍備では特に海軍の育成に努め、バルト海沿岸に要塞・基地を建設、これを拠点とするバルチック艦隊を創設した。
日露戦争の際東郷(平八郎)が打ち破ったロシア艦隊は、はるばるこの基地から派遣され、途中物資補給の為の寄港をフランス、英国等が拒否した為、強力艦隊が疲弊し敗戦に繋がったと言われている。
東方進出に付いては、シベリア進出を推し進め、1689年清国の康煕帝との間で国境を画定する条約を締結した。また1697~99年、コサックの隊長にカムチャツカ探検を命じ、日本との通商路を探っている。
プーチンが崇拝するエカテリーナ2世も領土拡大に大きな力を発揮した。オスマン帝国との2度にわたる露土戦争(1768年-1774年、1787年-1791年)に勝利してウクライナの大部分やクリミア・ハン国を併合しバルカン半島進出の基礎(ヤッシーの講和)を築くこととなった。
6月9日、ピョートル大帝の生誕350年記念イベントに出席したプーチンは若手起業家たちとの会合で、こう述べた。 「ピョートル大帝が、新しい首都サンクトペテルブルクを建設した時、ヨーロッパのどの国もロシアの領土と認めなかった。誰もがスウェーデンだと認識していた。しかし、スラブ系の人々がずっと住んでいて、その領土はロシアの支配下にあった。ピョートル大帝は何をしたのか。スエーデンを打ち破り領土を取り返し、国を強化したのだ。それが、彼の行ったことだ。そして、我々も領土を取り返し、国を強化する番だ」。ピョートル大帝は領土を奪ったのではなく「取り戻した」のだと主張し、「自分自身を守るために、戦わなければならないのは明らかだ。350年前とほとんど何も変わっていない」とピョートル大帝と自らを重ね合わせ、ウクライナ侵攻を暗に正当化したのである。プーチンの行動原理は此処に全て集約されて居り、周辺諸国がロシアを恐れる理由もここにある。
スターリン信奉者プーチンの登場(2)…プーチンの目指すもの














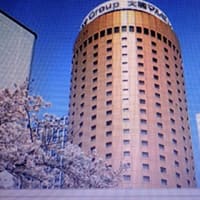





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます