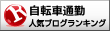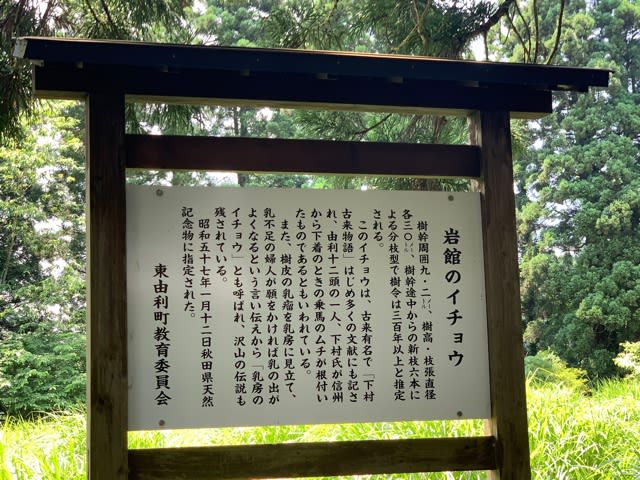本荘郷土資料館では2月11日から公開の本荘ひな街道の展示準備が完了しました。
 天神様も飾ります。秋田市に明治期より伝わる八橋人形が収蔵されているので、受験期でもあるので展示します。
天神様も飾ります。秋田市に明治期より伝わる八橋人形が収蔵されているので、受験期でもあるので展示します。天神様といえば「学問の神さま」として名高いです。
天神様の本当の名前は菅原道真といいます。
もともと天皇の側近で、平安時代の秀才と呼ばれていた人でした。
あまりの秀才ぶりから、異例の速さで右大臣までに出世してしまったほどのエリートです。今だと官房長官かな!
字がとても上手で、空海、道風と並んで、「日本の三筆」なんて言われています。
そんな訳で、天神様は「学問と書道の神さま」という性格をもっています。
また才能だけでなく、真面目でひたむきな人柄が多くの人の心を打ち、彼が亡くなると「天神様」として崇あがめられるようになりました。
江戸時代に入ると、子どもたちが学ぶ寺子屋が普及し、「子どもが学問に親しみますように、字の上手な子になりますように」と、天神様はますます慕われるようになっていきました。
人間を神様としてあがめる信仰を、「人神」といいます。
菅原道真は、学者の家に生まれたことより、幼いころから人並外れた才能を発揮していました。
青年になると学者としての最高位の文章博士となり、祖父や父と同じく着実に学者としての道を歩んでいました。
また、とても誠実な人柄だったことから周りからの信頼も厚く、さまざまな官職も就任し、着実に成果を上げてきた人です。
そして平安時代に認められて右大臣となった超エリート菅原道真は、このまま恵まれた人生を送るはずでした。
ところが、朝廷の政争に巻き込まれ、落とし穴にはまります。
左大臣(今でいう内閣総理大臣)藤原時平が、醍醐天皇に「道真があなたを退かせ、自分の娘婿の斉世親王を即位させようと企んでいる」と嘘の告げ口をしたのです。
この言葉を信じた醍醐天皇は、彼を都から遠い、九州の大宰府に左遷させてしまいました。
左遷とは、今までより低い役職や低い能力の業務に落とされることです。
皇位継承を巡り、醍醐天皇と時平が有能すぎる菅原道真を追放し、宇多勢力を一掃するために仕組んだとか、道真に反感(嫉妬)を持つ人々の意向があったなど、当時の貴族社会の問題が目え隠れした内容です。
ちなみにこのあとすぐに、藤原時平は妹である穏子を醍醐天皇の女御(奥さん候補)として入内させ、事実上の正妃に格上げさせています。
太宰府への移動はすべて道真の自費だったそうです。
そこではお給料も従者も与えられず、政務にあたることも禁じられ、衣食住もままならない厳しい生活を強いられました。
そして左遷から2年後の903年、失意のうちに亡くなったのです。
享年59です。
刑死ではありませんが、緩慢な死罪に等しいと言われています。
彼は、いつの日にか疑いが晴れて帰京できることを夢見て、詩を書き続け、気持ちを紛らわせていたと伝えられています。
しかしその夢もかなうことはありませんでした。
道真の死後、都では次々と異変が起こり始めました。
都で疫病が流行り、落雷、干ばつ、火災が相次ぎます。
さらに示し合わせたように、道真を陥れた政敵が次々に不審死を遂げていくのです。
左遷に追いやった藤原時平は、909年、39歳の若さで熱病にかかり悶死します。
時平と左遷に結託し、後釜として右大臣に昇進した大納言・源光みなもとのひかるも、913年、鷹狩りの最中に泥沼に転落して溺死、遺体があがらず。
923年、時平の妹と醍醐天皇の間に生まれた皇太子・保明親王やすあきらしんのうが19歳で急死します。
次の皇太子となった藤原時平の孫・慶頼王でしたが、925年、改元の甲斐なく5歳で急死します。
そしてさらに、人々を震撼させる衝撃的な事件が起きます。
930年になんと、醍醐天皇のいる宮中に大きな雷が落ち、皇族や貴族が多数死傷し、醍醐天皇の側近である藤原清貫までも焼死したのです。
醍醐天皇はその惨状を目の当たりにしたことで体調崩し、そのまま亡くなりました。享年49でした。
あまりにも衝撃的で凄惨な事件であり、『清涼殿落雷事件』として歴史上に残されています。
じつは醍醐天皇は生前の923年、相次ぐ関係者の死に恐れおののき、道真の左遷を命じた文書を燃やし、左遷そのものを取り消していたそうです。
それほど「道真の怨霊のしわざに違いない」と誰もが考え、その祟りに怯えていたということです。
不思議なことに、菅原道真の家があった桑原だけは、落雷の被害がありませんでした。
雷が鳴ったときに「くわばら、くわばら」と唱えるのは、このことが由来です。
道真の祟りを恐れていた人々は、道真の霊を神さまとして祀って、怒りを鎮めようと考えました。
そして947年、道真の祟りを解くために、京都北野にあった天神社のかたわらに、道真の霊を祀る社を造営しました。
これが「北野天満宮」のはじまりです。
こうして菅原道真は神さまとなりました。
今では学問の神様として名高い菅原道真も、「天神様」として祀られた当初は、何をやらかすかわからない怨霊として恐れられていたのです。
天神様、学問の神様と呼ばれる
怨霊とされた天神様が、「学問の神様」と言われるようになったのは、江戸時代になってからです。
学問に秀で、人々から厚い信頼を得ていた菅原道真にちなんで、自然と「学問の神様」として信仰されるようになっていきました。
寺子屋には天神様の神像が祀られ、手習いに来た子どもたちは、まず小さな手をあわせ、天読み、書き、算盤の上達を祈ったそうです。
それから現在では、全国の天満宮が学問の神さまと呼ばれるようになりました。
資料館に天神様をたくさん飾るので受験生は神社までいかなくても資料館に集合してもらいな!