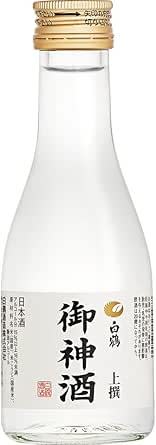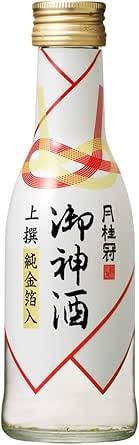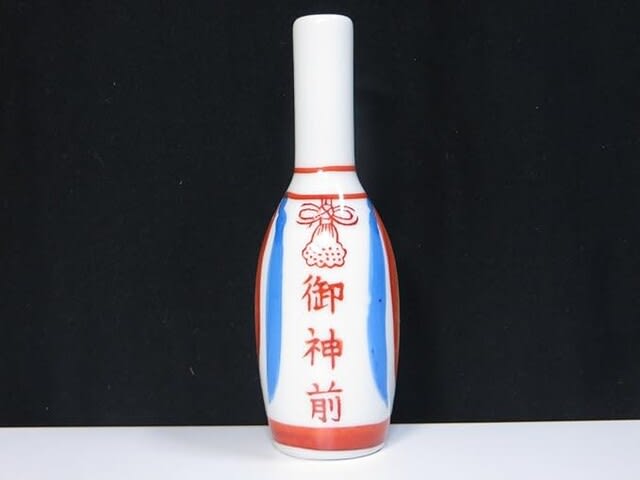先般、蔵を移転して最新鋭の設備を導入された蔵元さんとお話しししていて、こんなことを聞きました。
米の吸水率を0.1%単位で管理しています。
その時は「すごいなぁ」と感心してお聞きしていたのですが、夜、布団に入ってからその言葉が気になりました。
酒造りには携わっていませんが、米を蒸す前の吸水が重要なことは理解しているつもりです。
実際、同じ米でも水に漬けて吸水させる(浸漬)際の時間や水温、あるいはその前に米を洗う(洗米)の水温(や米との温度差)にも大きな影響があるとお聞きします(浸漬時間などはストップウオッチで計測、とか)。
実際、「久保田」の朝日酒造さんのホームページでも、そんな画像が。

逆に同じように洗米・浸漬しても、もとの米に含まれる水分の量が少しでも異なると、仕上がりの吸水率が大きく変わってしまうとも言われていて、それ故、使用予定の米が、どの程度の時間でどのくらい水を吸うのか、あらかじめテストし、その米に合わせた洗米・浸漬をするとも聞いています。
その意味でとてもデリケートな事項であるというのは判るのですが、一方で理系的な発想だと、吸水率を測るのってどうしてもサンプルをとって事後的かつ実験的にせざるを得ないのでは、とも思われます。
以前見た業界資料では、
①お米を一定量測って(Xg)
②そのお米を水に浸して
③そのお米を取り出して水を切って
④重さを測る(Yg)
という手順を踏んだうえで、「(Y-X)÷X」を吸水率と呼んでいるようです。
しかも「水を切って」というのも要注意で、遠心分離で気合を入れて水を切るようです。
つまり、リアルタイムでの計測はできないし、水切りのやり方でも誤差が出る。
そういうものを0.1%単位で管理(コントロール)するというのはどういう技なんだろう。
実際、熟練の技だと吸水の際に「米の芯の部分が水を吸っておらず透明になっている『目玉』を目視で見極める」というのもあるようですが、これで0.1%の単位での管理は無理でしょうし。
発酵させる仕込みタンク内の温度であれば、(均一性等の問題はあるにせよ)エアコンのように温度設定をして制御するということはあると思いますが、吸水率を管理というのはよく考えても判りません。
もしかしたら、
a)事前にそのロットのお米をテストして
b)データとも突き合わせて吸水率の目標を○%と設定して
c)その目標に適合するような洗米・浸漬時間や水温の組み合わせを設定して
d)実際に洗米・浸漬を行う
ということなのかもしれませんね。
(ただ、「ダイエットで体重の目標を65.065kgに設定して、それに必要な運動や食事を選んで、取り組み」というのは「体重を0.1%単位で管理」とは言わないけど)
ちなみに上掲した写真の「久保田」の「萬壽」の場合、「洗米時間は約17秒とかなり短く」「の後、約10分ぐらい浸漬します」ということで、その時間管理には気を遣っているようですね(それでも、17秒の0.1%は0.017秒なので管理不可能だし、10分=600秒あるけど0.1%は0.6秒。難しい)。
詳しそうな問屋仲間(理系)もいらっしゃるので、今度お聞きしてみましょう。
★★
お酒に関する諸事万端のご相談を承っております(商品企画/情報提供/寄稿等)★★
酒ブログランキングに再度エントリーしました。

←クリック頂けるとうれしいです。

応援の
クリックを↑↑↑↑↑
【アルバイト・契約社員募集中!】
(1)飲食部門(フロアスタッフ兼新規開店企画)
(2)酒類営業部門(倉庫管理兼営業企画)
(3)酒類営業部門(通販管理)
日時・時間はご相談。正社員登用もあり。男女問いません。詳細は当社HPまで。


 ←クリック頂けるとうれしいです。
←クリック頂けるとうれしいです。