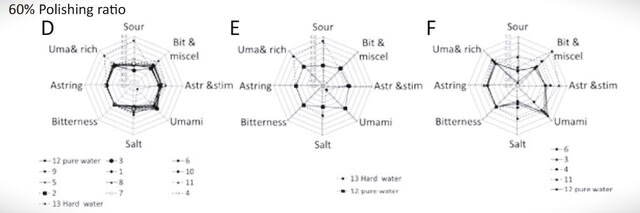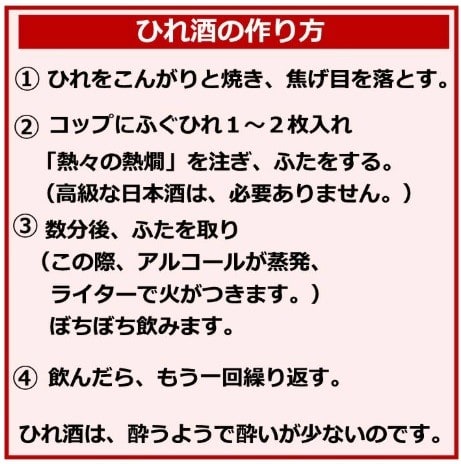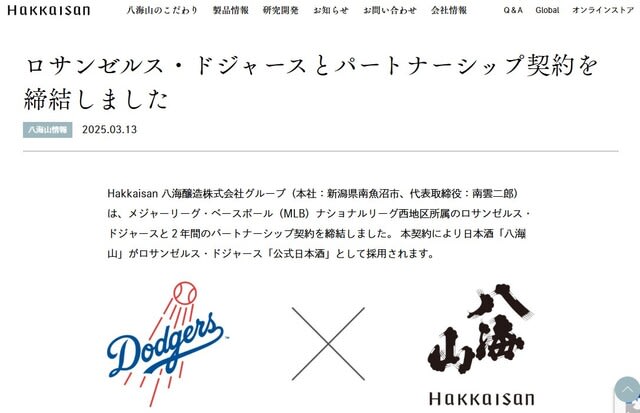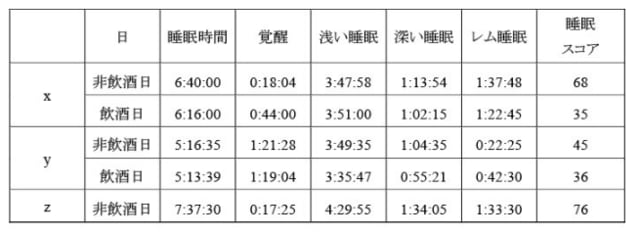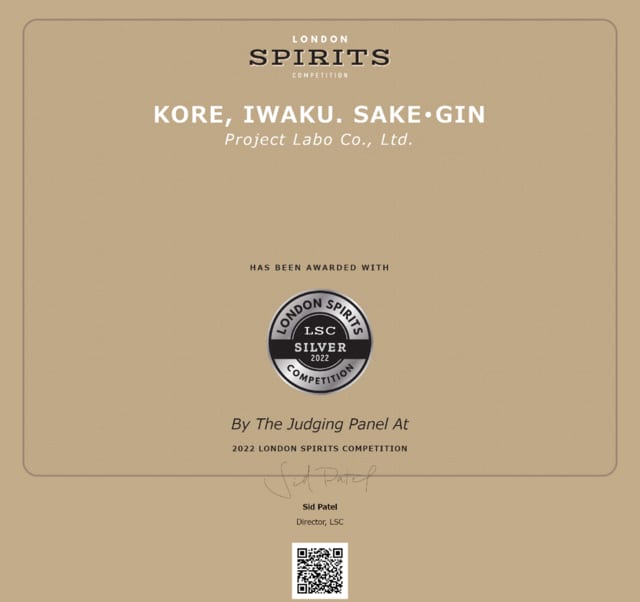一昨日、酒類総研のR6酒造年度新酒鑑評会の結果が発表されました。
メディアでは「福島県が3年ぶりに金賞蔵元数日本一を奪還」と速報が出たり、社内では「お取引の蔵元さんのうち○○さんが金賞受賞!」とか、話題になっていましたが、卸組合の寄り合いで仲間と話していて出たのは「○○さんは山廃で金賞を獲ったよ」という話。
新酒鑑評会の入賞/金賞には、いわゆる「YK35」といった、傾向と対策があると言われています。
山廃とか生酛は受賞しにくいとも言われていて、山廃/生酛主体の蔵でも出品酒は違う造り、というケースもままあるようです。
(「純米」もそうですね)
近年では山廃や生酛で受賞するケースも出てきたり、「傾向も世につれ」ということも言われますが、この辺りはあまり定量化されていないような気もしますね。
その中で、主催者の酒類総研では出品酒の種類等を整理していて、ホームページには一昨年分の結果が掲載されています。
そこでの山廃とか生酛とかの「酒母」に関する整理はこうなっていた。

全体の818点のうち、速醸と中温速醸で681点と8割を占め、一方の生酛と山廃は9点と1%。
「上位酒(入賞)」の状況はというと、速醸と中温速醸で87点で出品酒の27%、生酛と山廃は上位酒は1点!。ここまで少ないと割合を出す意味も??ですね。
審査は造りがどうかという情報もないブラインドなので、これは明確な傾向ですね。
実際、生酛で有名な大七などは金賞を受賞した後は「もう鑑評会には出しません」と撤退宣言を出したりしているし。
ただ、近年は技術革新というか設備導入革新が進んで、山廃とかでもキレイなお酒を造るところが増えてきましたので、潮目が少しは変わるのでしょうか。
久しぶりにお披露目会に行ってみようかな。
★★お酒に関する諸事万端のご相談を承っております(商品企画/情報提供/寄稿等)★★
酒ブログランキングに再度エントリーしました。
 ←クリック頂けるとうれしいです。
←クリック頂けるとうれしいです。
応援のクリックを↑↑↑↑↑

【アルバイト・契約社員募集中!】
(1)飲食部門(フロアスタッフ兼新規開店企画)
(2)酒類営業部門(倉庫管理兼営業企画)
(3)酒類営業部門(通販管理)
日時・時間はご相談。正社員登用もあり。男女問いません。詳細は当社HPまで。