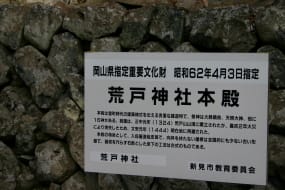| 下界の瀬戸内海の景色を見ながらノンビリ登って行くと、いきなりこんな案内板に出くわした。 何でも、柏原伝六という人が山上の観音堂に籠り、儒教・仏教・神道の三大宗教に当時禁制のキリスト教を加えた新宗教“一観教”を開いたのだと言う。 伝六さんは、布教に努めると共にこの白滝山に、五百羅漢や三尊像など約700体の石像を造ったが、お役人に一揆の疑いをかけられ、挙句の果てに怪死したらしい。 多分お役人に殺されたのだろう? |  |
こうなったのも元はと言えば母親の不用意な(?)発言だったのかもしれない!
良きにつけ悪しきにつけ、母親の影響力が極めて大きいと言う事だろう!
山門をくぐると、先ず六地蔵が立っており、次に五百羅漢、山頂には釈迦如来・文
殊菩薩・普賢菩薩の三尊像が立っていた。
この他にも伝六さんと奥さんの石像もあったらしいが、何しろ山登りが専門のグル
ープなので石像などに余り興味は無いらしく、置いて行かれそうになったので分か
らずじまいに終わった。
 |  > > |
| 山 門 | 六地蔵(→) |
 |  |
| 五百羅漢 | 普賢菩薩、釈迦如来、文殊菩薩 |
白瀧山
白瀧山は重井町善興寺の奥の院で、古くは瀧山と称し古代から霊山として頂上の岩
場を“盤境”と伝えている。
盤境(いわさか)とは神を迎え祭儀を行う場所或いは神が天から降臨される場所の
事で、そこにある大きな岩や土地、ご神木を磐座(いわくら)と呼ぶ。
六地蔵
人は死後、生前の行いを閻魔大王を筆頭にした十王によって裁かれ、49日目にこ
の世の六つの世界の内のどの世界に生まれ変わるか判決を受けるとされている。
六つの世界とは、悪行の結果として行く三悪道(地獄、餓鬼、畜生)と、善行の結
果として行く三善道(阿修羅、人、天)を言う。
六地蔵とは、この六つの世界の夫々にあって衆生の苦悩を救済する地蔵菩薩の事で、
釈迦の死後、56億7000万年後に弥勒菩薩が出現するまでの間、六道を彷徨う人々を
救済する為に自身が仏になる事を延期したとされている。
“地蔵尊”とも呼ばれ、他の菩薩が天界で救済活動をするのに対して、六道で自ら
が救済に当たる事が庶民の共感を得、地蔵信仰として広く民間で広まり、子育て地
蔵や延命地蔵などの現世利益に結びついたものもつくられ、道端などにも石像がま
つられるようになった。
石像の形は、古くは菩薩の姿をしていたが、後に頭髪を剃って墨染めの法衣を着た
僧の形で表される事が多くなった。
五百羅漢
羅漢(阿羅漢=あらはんの略)は、“修行を完成して尊敬するに値する人”を指す。
釈迦の弟子で特に優れた16人を“十六羅漢”と呼び、釈迦の死後その教えを後世
に伝える為に、初めての経典編集に集まった弟子達を“五百羅漢”と呼んだ。
因みに、最近スーパーなどで売られている羅漢果は、中国の医師の名前“羅漢”か
ら名づけられたもので仏教とは無関係。
こちらは、中国の桂林周辺にしか生育しないウリ科のつる性植物の果実で、一見
キウィのような形をしている。
味は黒砂糖に似ていて、糖度は砂糖の300倍~400倍あるが腸から吸収されずに排泄
されてしまうので、糖尿病やダイエットに役立つとされている。
その上に、活性酸素を除去する成分やビタミンE、鉄、リン、マグネシウム、カル
シウムなども豊富に含んでいるそうだ。














 >
>