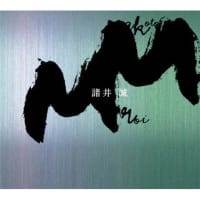相変わらず、東京には小雨が降っている。昨日に続いて、また雨の話。「雨の日の釣り師のために」という本がある。ヘミングウエイやリチャード・ブローティガン、井伏鱒二らの釣り文学を開高健が編んだもので、彼自身の作品も収載されている。書物のタイトルも、おそらく開高自身のネーミングだと思う。このタイトルの深さと奥行きは、釣り師にしか分からない。はらはらと雨が伝う窓の先に、釣り師は山女(やまめ)の美しき魚体を追うのである。
エミール・クストリッツァの「アリゾナ・ドリーム」には空を飛ぶ魚が登場するが、魚を扱った映画としては、ティム・バートンの「ビッグ・フィッシュ」に感動した。『小さな池の、大きな魚にはなりたくない』、不覚にも涙を流してしまう名品である。
雨の日の釣り師に戻ろう。私は、フライ・フィッシャー誌に連載されている柴田邦彦さんのイラストとコラムの大ファンなのだが、以前の号で印象に残っているのが、マリエル・フォスターの話。雨の中を釣りに急ぐマリエルおばさんの姿を描いた作品だ。このシリーズ「川からの釣り人の手紙」が、講談社から単行本として出版されたときも、マリエルおばさんのコラムはしっかり収載されていた。『丸いつばのついた帽子をかぶり、オイルコットンの上着、下は長いツィードのスカートに厚いソックスと革の頑丈そうな短靴。釣具はフィッシング・バッグ一つと重そうな竿を肩にかついでいる。楽しくて仕方ないという風に水を蹴散らしながら歩いている』(原文引用)。これもまた、雨の日の釣り師の肖像である。
フライ・フィッシングの虜になって10年以上の年月が流れた。試行錯誤を繰り返しながら、どうにかフライ(毛鉤)が巻けるようになったころ、アイザック・ウォルトンの「釣魚大全」に出会った。「 Study to be quiet = 静かなることを学べ」という箴言ではじまるこの書物の原題は「 The Complete Angler = 完全なる釣り師 」。だからといって、釣りに関する諸事万端が語られているわけではなく、旅人と猟師の会話(パブでエール・ビールを飲んだりするくだりが微笑ましい)によって鱒釣りを中心とした釣りの作法が人生論のように語られる。初版の発行は1653年というのだから、江戸時代から今日まで脈々と読み継がれている釣り文学の金字塔である。
釣りをはじめてしばらく経ったころ、青山にあった釣り関連の洋書専門店で、「 The Uncomplete Angler = 不完全なる釣り師」というふざけた本を見つけた。タイトルの面白さにつられて買って帰ったものの、いまだに読まずじまいだ。ただ、相変わらず静かなることを学べないでいる私にとって、The Uncomplete Angler という称号は、耳に痛いながらも、まことに共感できる。
「リバー・ランズ・スルー・イット」は、まさしくフライ・フィッシングの聖典のような映画だが、兄が弟のキャスティングを見てつぶやく場面、『弟のフライ・キャスティングは芸術の域に達した』という一言で、私はフライ・フィッシングを始める決意をしたものだった。以来、“芸術的なフライ・キャスティング”は、私自身の生涯の課題となった。
本日のコラムの結びに、開高健が喧伝した中国のことわざを紹介しよう。『一時間、幸せになりたかったら、酒を飲みなさい。三日間、幸せになりたかったら、結婚しなさい。八日間、幸せになりたかったら、豚を殺して食べなさい。永遠に幸せになりたかったら、釣りを覚えなさい』。
雨の日の釣り師は、やがて永遠の幸せを手に入れるのである。
(写真は「リバー・ランズ・スルー・イット」の舞台にもなった釣りの聖地モンタナ)