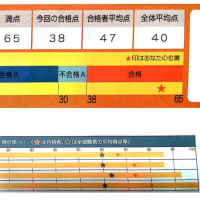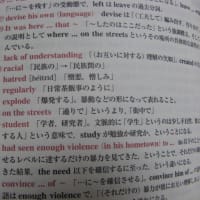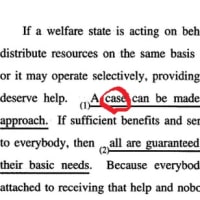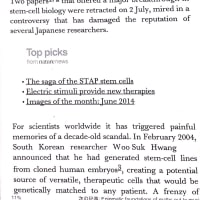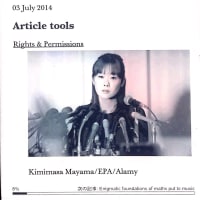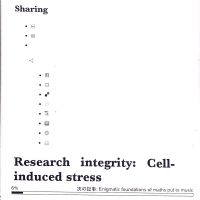(6)唱歌に頼る「二十四の瞳」の手法では、現代人には通じにくい。
前回、木下恵介監督の「二十四の瞳」は一種の群像的ドラマであり、一人一人の子供たちの境遇の違いなどを描き分けよとしていると評価した。確かにそういう意味でも貴重な映画である。しかし、実はそれ故に、致命的な弱点をも抱えているのである。
私は、子供たちの境遇には様々な違いがあり、単純な「貧困」の一言によって要約されないような描写があると書いていた。しかし、予備知識を持っていない普通の現代人にとっては、12人もの子供の境遇の状況を想像するのは、ちょっと難しすぎるのである。
当時の人にとっては、例えば、「将来嫁になることを前提に都会に働きに出される」という説明があっただけで、その意味するものは明白だったのだろう。だから、簡単な説明だけで、その女の子の厳しい境遇が想像できてしまう。あるいは、ブカブカの靴を履いている男の子の映像が出てきたとしても、説明は必要ないだろう。しかし、今の子供たちには、説明されなければぶかぶの靴の意味は意味不明である。
現代人が鑑賞するという観点から見れば、1人の子供なり1人の時代に絞って詳しく丁寧に描写してもらわなければ、ちょっと困ってしまうのである。そういう意味でも、ちょっと賞味期限が切れているというわけである。だが、それは問題の一つにすぎない。
今回の記事で書きたいのは、むしろには2番目のことである。
これも前回書いた事であるが、坪井栄原作の小説の方では、子供たちの間での優越感だとか劣等感だとか、我を貼ったり相手をバカにしたりとかするような描写があるのに、映画の方でおそれが感じられなかった。これは私の勝手な思い込みなのかと思ってインターネットで調べたところ、名古屋女子大学の荒川志津代という方の2009年の紀要論文「映画『二十四の瞳』に描かれた子ども像 -戦後における子どもイメージの原点についての検討」にも同じ趣旨の事が述べられていた。
そこで自信を持って再度述べるが、木下恵介監督の映画の方では子供たちの間の対立や葛藤が覆い隠されているのである。原作の小説における子供たちの間の対立的場面が描かれていないというだけではない。むしろ、積極的に子供たちの協調と相互扶助の精神が強調されているのである。そのためのもっとも大事な手法が、当時の日本人ならば誰でも感情的に突き動かされる小学唱歌を多用したということである。唱歌は朗々と映画全体を流れ、当時の映画鑑賞者にノスタルジックな感動を大いに喚起せざるを得ない。子供時代の懐かしい良い思い出がよみがえってくるのだ。この唱歌こそが、子供たちの協調(ハーモニー)の精神を表現するための通奏低音なのである。(おそらく木下においては、戦時中のウルトラ・ナショナリズムの精神を、健全なナショナリズムに転換しようという意図もあったに違いない)。
子供たちの間にある葛藤や対立を意図的に無視してしまう木下の映画作りについては、いろんな見解があるだろう。私としては、木下の映画よりも原作の方がより興味深いものに映ったが、その点については深入りしない。
問題は、イデオロギー的な観点がどのようなものであれ、国民唱歌に頼って子供たちの協調の精神を描くのでは現代人には通用しないことだ。現代人は、国民唱歌は知っているかもしれないが、情緒的に大きく喚起されるということはない。とすれば、唱歌に頼る映画というのは、民族主義的なイデオロギー装置としても、情緒的な感激をする映画としても、不十分だということになってしまうのである。国民唱歌は、普遍的な音楽というよりは、時代的に限定された音楽のようである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
結論的に言えば、木下恵介監督の「二十四の瞳」は、誰にでも勧められる映画というよりは、この時代を勉強したり、映画について学んだことのある大学生以上に勧められる作品のように思われる。大変興味深いが、今となっては決して子供向けではない。多くの人がブログやHPでこの映画を強く薦めている理由も、ちょっと理解しがたい。
たとえば、貧困の問題を理解してもらいたいのであるとすれば、例えば、溝口健二の「赤線地帯」(1956年)のほうが分りやすいだろう。あるいは、ブニュエル監督の「忘れられた人々」の方が良いだろう。(私が昔ゼミ学生に見せたのは、ブニュエルの方でした)。
前回、木下恵介監督の「二十四の瞳」は一種の群像的ドラマであり、一人一人の子供たちの境遇の違いなどを描き分けよとしていると評価した。確かにそういう意味でも貴重な映画である。しかし、実はそれ故に、致命的な弱点をも抱えているのである。
私は、子供たちの境遇には様々な違いがあり、単純な「貧困」の一言によって要約されないような描写があると書いていた。しかし、予備知識を持っていない普通の現代人にとっては、12人もの子供の境遇の状況を想像するのは、ちょっと難しすぎるのである。
当時の人にとっては、例えば、「将来嫁になることを前提に都会に働きに出される」という説明があっただけで、その意味するものは明白だったのだろう。だから、簡単な説明だけで、その女の子の厳しい境遇が想像できてしまう。あるいは、ブカブカの靴を履いている男の子の映像が出てきたとしても、説明は必要ないだろう。しかし、今の子供たちには、説明されなければぶかぶの靴の意味は意味不明である。
現代人が鑑賞するという観点から見れば、1人の子供なり1人の時代に絞って詳しく丁寧に描写してもらわなければ、ちょっと困ってしまうのである。そういう意味でも、ちょっと賞味期限が切れているというわけである。だが、それは問題の一つにすぎない。
今回の記事で書きたいのは、むしろには2番目のことである。
これも前回書いた事であるが、坪井栄原作の小説の方では、子供たちの間での優越感だとか劣等感だとか、我を貼ったり相手をバカにしたりとかするような描写があるのに、映画の方でおそれが感じられなかった。これは私の勝手な思い込みなのかと思ってインターネットで調べたところ、名古屋女子大学の荒川志津代という方の2009年の紀要論文「映画『二十四の瞳』に描かれた子ども像 -戦後における子どもイメージの原点についての検討」にも同じ趣旨の事が述べられていた。
そこで自信を持って再度述べるが、木下恵介監督の映画の方では子供たちの間の対立や葛藤が覆い隠されているのである。原作の小説における子供たちの間の対立的場面が描かれていないというだけではない。むしろ、積極的に子供たちの協調と相互扶助の精神が強調されているのである。そのためのもっとも大事な手法が、当時の日本人ならば誰でも感情的に突き動かされる小学唱歌を多用したということである。唱歌は朗々と映画全体を流れ、当時の映画鑑賞者にノスタルジックな感動を大いに喚起せざるを得ない。子供時代の懐かしい良い思い出がよみがえってくるのだ。この唱歌こそが、子供たちの協調(ハーモニー)の精神を表現するための通奏低音なのである。(おそらく木下においては、戦時中のウルトラ・ナショナリズムの精神を、健全なナショナリズムに転換しようという意図もあったに違いない)。
子供たちの間にある葛藤や対立を意図的に無視してしまう木下の映画作りについては、いろんな見解があるだろう。私としては、木下の映画よりも原作の方がより興味深いものに映ったが、その点については深入りしない。
問題は、イデオロギー的な観点がどのようなものであれ、国民唱歌に頼って子供たちの協調の精神を描くのでは現代人には通用しないことだ。現代人は、国民唱歌は知っているかもしれないが、情緒的に大きく喚起されるということはない。とすれば、唱歌に頼る映画というのは、民族主義的なイデオロギー装置としても、情緒的な感激をする映画としても、不十分だということになってしまうのである。国民唱歌は、普遍的な音楽というよりは、時代的に限定された音楽のようである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
結論的に言えば、木下恵介監督の「二十四の瞳」は、誰にでも勧められる映画というよりは、この時代を勉強したり、映画について学んだことのある大学生以上に勧められる作品のように思われる。大変興味深いが、今となっては決して子供向けではない。多くの人がブログやHPでこの映画を強く薦めている理由も、ちょっと理解しがたい。
たとえば、貧困の問題を理解してもらいたいのであるとすれば、例えば、溝口健二の「赤線地帯」(1956年)のほうが分りやすいだろう。あるいは、ブニュエル監督の「忘れられた人々」の方が良いだろう。(私が昔ゼミ学生に見せたのは、ブニュエルの方でした)。